Microsoftは、Windows 11向けに「人間中心(human-centric)」を理念としたスタートメニューの再設計を発表した。新UIは「呼吸する余白」と個別最適化を軸に、アプリの即時把握や作業効率の加速、アイコン文化への敬意など、4つの指針に基づいて構築された。ユーザー行動に即応する動的提案、カスタマイズ可能なグリッド、非表示制御などの機能も強化されている。
この刷新は300人超のフィードバックと非監視型調査を通じて磨かれ、Surface Goからウルトラワイドディスプレイまで幅広い環境での検証も行われた。デザインプロセスには、未採用案も含む多様な試行錯誤が盛り込まれ、開発チームは「UIは対話である」と位置づけ
再設計の柱となった4つの指針とUI機能の進化
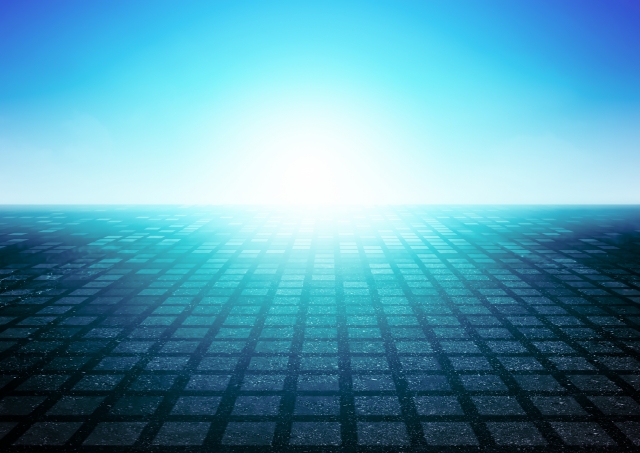
MicrosoftはWindows 11のスタートメニューに対して大規模な刷新を施し、その中心には「Apps at a Glance」「Make it Yours」「Accelerate the Day」「Honor the Icon」という4つの設計指針が据えられた。これらは、視認性と即応性、個別最適化、作業効率、そしてWindowsの象徴的要素の尊重を軸に、UIの機能性と感情的価値の両立を図るものである。
具体的には、全アプリビューが3種類に再構成され、ユーザー行動に応じてリアルタイムに内容が変化する提案機能や、使用頻度の高いアプリを強調表示するグリッド構造が導入された。また、ユーザーが不要と感じた提案を非表示にできる機能も追加され、操作性の選択肢が拡張されている。
この再設計は、300人以上のWindows 11ユーザーやファンを対象とした非監視型調査の結果を反映したものであり、Microsoftは機能重視から体験重視への転換を意図したことが明確である。ただし、いかに設計思想が明瞭でも、実際の使用における効果は依然としてユーザー側の反応に左右される。従来のスタートメニュー改変が支持を得られなかった歴史を鑑みれば、今回の試みも慎重な評価が求められるのは避けられない。
Fresh Start」に見る開発過程の透明性と実験的アプローチ
Microsoftは今回のスタートメニュー刷新に際し、「Fresh Start」と名付けたプロトタイプ群を社内外で共有し、UI開発の過程そのものをユーザーとの対話と位置づけた。提案の動的生成や、アプリ表示の整理、パフォーマンスの裏側改善といった要素を段階的に試行する姿勢が強調されている。こうした公開姿勢は、過去の閉鎖的な開発体制とは一線を画すものであり、特にMicrosoft Designの公式ブログでの詳細なプロセス共有が象徴的である。
「デザインは独り言ではなく対話である」という開発者の発言は、単なる機能追加以上に、ユーザーとの関係性そのものをUIに組み込む姿勢を示している。従来のスタートメニュー改変では、ユーザーの身体的記憶や操作習慣との齟齬が批判されてきたが、今回のアプローチはその失敗を踏まえた応答である可能性がある。
ただし、最終的なUXがユーザーにとって「優雅で使いやすい」ものとなるかは、完成された設計の精度ではなく、現実の使用文脈での検証に委ねられる。過去の設計思想の焼き直しにとどまるのか、それとも転機となるのか、依然として確定的な判断は避けるべきである。
Source:TechSpot

