人気YouTuberのTech Yes Cityが実施した検証により、ASRock製マザーボードがRyzen 9000シリーズCPUと接続された際に、SoC電圧が常時1.27V近くまで変動する特異な挙動を示すことが明らかとなった。これにより、従来からReddit上などで報告されてきたCPUの物理損傷事例が、ASRock独自の電圧制御仕様に起因する可能性が浮上している。
特にRyzen 9800X3Dや9950Xなどの高性能モデルにおいて、同社のX870Eシリーズ上で他社製品を超える高電圧が継続的に供給される事例が確認されており、SoC電圧が1.25Vを超える設計が致命的な要因となる懸念がある。一方で、SoC電圧の指示はCPU側から行われている点や、ASUS製マザーボードでも同様の電圧補正が存在することから、原因はハード単体ではなく、双方の連携不全にある可能性も否定できない。
ユーザーが自主的にリスクを抑えるには、BIOS設定におけるUncore Voltage機能の活用や、メーカーによるBIOSアップデート対応の動向を注視する必要がある。
Ryzen 9000シリーズにおけるASRock製マザーボードのSoC電圧挙動と損傷リスクの関係
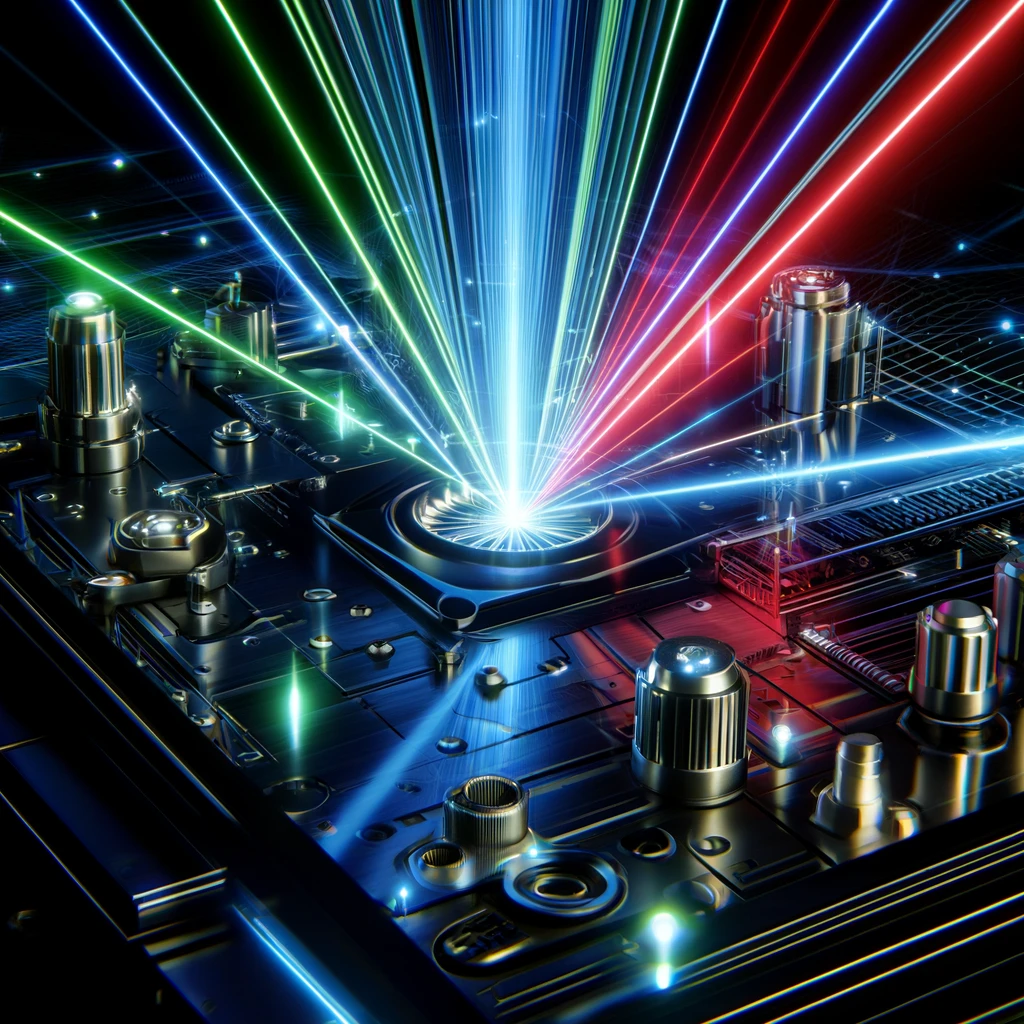
ASRock製のX870E Taichi LiteやX870 Steel Legendなどのマザーボード上で、Ryzen 9000シリーズのCPUを搭載した際にSoC電圧が1.27V近くまで上昇する事象が確認された。YouTuber Tech Yes CityのBryan氏が実施した検証では、Ryzen 7 7700やRyzen 9800X3Dの構成において、他社製よりも明確に高い電圧が継続的に記録されており、電圧変動も一定ではない。特にReddit上で報告されている約200件の故障事例の大半がASRock製マザーボード上で発生している点は、仕様的な異常を示唆している。
SoC電圧は通常、CPU内のSystem on Chip領域に対して静的に供給されるものであり、頻繁な変動や上限超過は設計上望ましくない。一般的な基準値は1.20V前後とされる中で、ASRockの挙動はこの範囲を超えている。ASUSのX870E Crosshair Heroにおいても50mVの上乗せが存在するが、これはあくまで安定性目的で静的に設定されたものであり、ASRockのような連続的変動とは異質である。
このような高電圧状態がCPU側の物理損傷を引き起こすか否かは未解明な部分も多いが、少なくともASRockの電圧制御仕様が、他社と比較して独特であることは確かである。ASRock側は今後BIOSアップデートによる対応を迫られる可能性があるが、現時点での公式な見解は示されていない。
CPUとマザーボードの相互作用が引き起こす潜在的リスクへの考察
今回の検証において明らかとなったのは、SoC電圧の値そのものよりも、その供給ロジックにある複雑な相互依存関係である。電圧の要求はCPUから発され、マザーボード側がこれに応じるという仕組みで動作している以上、問題の原因をASRock製マザーボードのみに帰することはできない。
実際、Ryzen 9000シリーズのSoCリクエスト信号自体に何らかの挙動差異が存在する可能性も否定できず、この問題はハードウェア単独ではなく、相互動作の結果と捉えるべきである。
また、電圧が高いこと自体が即座に故障につながるとは限らず、長期的な使用や高負荷時における累積的影響が鍵となる。したがって、現時点での問題は「異常値の観測」という段階にとどまっており、原因を特定するにはさらなる実測と比較検証が不可欠である。特にASRock製ボードの電圧変動が、内部回路や電源設計に起因するものなのか、もしくはBIOS設定や電圧リファレンス処理に依存するのかは、現状の情報では断定しがたい。
いずれにせよ、リスク回避の観点からユーザー側に求められるのは、ASRock製マザーボード使用時にBIOS内で「Uncore Voltage」のマニュアル設定を行い、動作電圧を制御下に置くことである。製品本来の性能を維持しつつ、潜在的な損傷リスクを低減する策が求められている。
Source:Wccftech

