AppleはAI機能の分野でライバル企業に後れを取っており、WWDC 2024で掲げた目標の多くが未達成のままとなっている。特にGoogleのNotebook LMのような多言語対応の音声要約、Anthropicが提唱するMCPによる外部アプリとの連携、そしてOpenAIのリアルタイム画面共有など、他社が先行する機能との差は拡大しつつある。
視覚インテリジェンスやSiriショートカットなど既存の基盤を活かせば、Appleも追随可能な構造は持ち合わせているが、現時点では実用化に至っていない。特にセキュリティとプライバシーを理由にAIの導入を抑制する姿勢は、ユーザーの利便性を損なう要因にもなり得る。
数週間後に迫るWWDC 2025では、これらの機能にどこまで追いつけるかがApple Intelligenceの評価を大きく左右するだろう。
Notebook LMと音声要約が示すAppleの音声インテリジェンスの課題
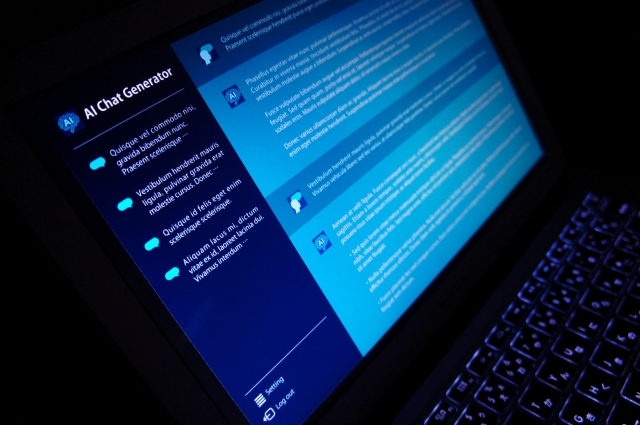
Googleが展開するNotebook LMは、カスタム指示への対応に加えて多言語の処理能力、さらに音声による記事や論文の要約機能などを備えており、日々の学習や情報収集において非常に高い実用性を実現している。特にAudio Overviewsは、専門性の高い技術文書の内容を短時間で把握する手段として有効であり、既に日常利用に組み込まれているユーザーも多い。これに対してAppleは、SafariやApple Notesにおいてこうした音声要約機能をネイティブに統合する仕組みを持たない状況が続いている。
Appleが独自に展開する視覚インテリジェンスやSiriの枠組みを踏まえると、音声による要約や通知の導入は技術的に不可能ではないと考えられる。ただし、ブラウザやノートアプリとAIとの連携において、Googleのようにプロアクティブな実装が見られないことは、日常用途の差に直結している。音声で内容を捉えることが求められる場面は今後も増えると見られ、Appleがこの領域に手を付けるか否かは、ユーザー体験の大きな分かれ目となる可能性がある。
MCPと外部ツール連携がもたらす新たなAI基盤のヒント
Anthropicが提案したMCP(Model Context Protocol)は、LLMと外部プラットフォームやツールを統一的に接続するためのオープンスタンダードである。すでにOpenAI、Google DeepMind、Microsoft、Zapierなどの企業が採用し、ClaudeがBlenderを介して3Dシーンを生成するような高度な連携も実現されつつある。この標準は、インターネットにおけるHTTPS、データベースにおけるSQLのように、AI活用の中核プロトコルとなる可能性を秘めている。
Appleは既にSiriショートカットやIntentsといった連携フレームワークを構築しており、MCPのような仕組みをゼロから構築せずとも、独自規格で同様のアプローチを取る余地があると考えられる。たとえば、Pagesで書かれた文書をKeynoteに自動展開したり、GarageBandの素材をFinal Cutに同期させるといったワークフローがAIによって完結するようになれば、Apple製品の統合価値が飛躍的に向上する。
OpenAIの画面共有との比較で浮き彫りになるインターフェースの差
OpenAIのChatGPTが提供するリアルタイム画面共有機能は、視覚情報をもとにしたインタラクションの自然さという点で大きな優位性を持つ。メニューを映して食物アレルギーの有無をAIに即座に確認したり、リアルタイムでカメラ映像に基づいてナビゲートするような体験は、従来の静的な画像識別やテキスト要約を超えた利便性をもたらしている。これに対してAppleの視覚インテリジェンスは、写真からの情報抽出にとどまり、Liveな対話を前提とした設計には至っていない。
iPhoneのカメラ性能やチップの処理能力を考えれば、こうしたリアルタイム性を取り入れる環境は整っている。しかし、Appleが慎重な姿勢を維持する背景には、プライバシー保護やローカル処理へのこだわりがあると見られる。とはいえ、用途によっては画面共有型AIとの対話に圧倒的な体感差が生まれる場面も少なくない。Appleがこれまでのインターフェース設計の延長線に留まるのか、それとも変革に踏み出すのかが今後の鍵となる。
Source:9to5Mac

