Nintendoの次世代機「Switch 2」に関して、Digital Foundryが公開した詳細な技術仕様により、その全貌が明らかになった。CPUはARM Cortex A78Cを8コア搭載し、最大1.7GHzで動作。GPUはNVIDIAのAmpereアーキテクチャを採用し、CUDAコア数は初代Switchの256から1,536へと6倍に増強された。
さらに、メモリにはLPDDR5(128-bit)を搭載し、最大帯域幅はドック接続時で102GB/s、携帯モードでも68GB/sを確保。GPUクロックも最大1.4GHzに達し、DLSSを含む複数のアップスケーリング技術もサポートする見通しである。これらの仕様は、ハンドヘルド機としては破格の処理能力を示唆している。
CPUとGPUの刷新が示す次世代モバイル性能の飛躍
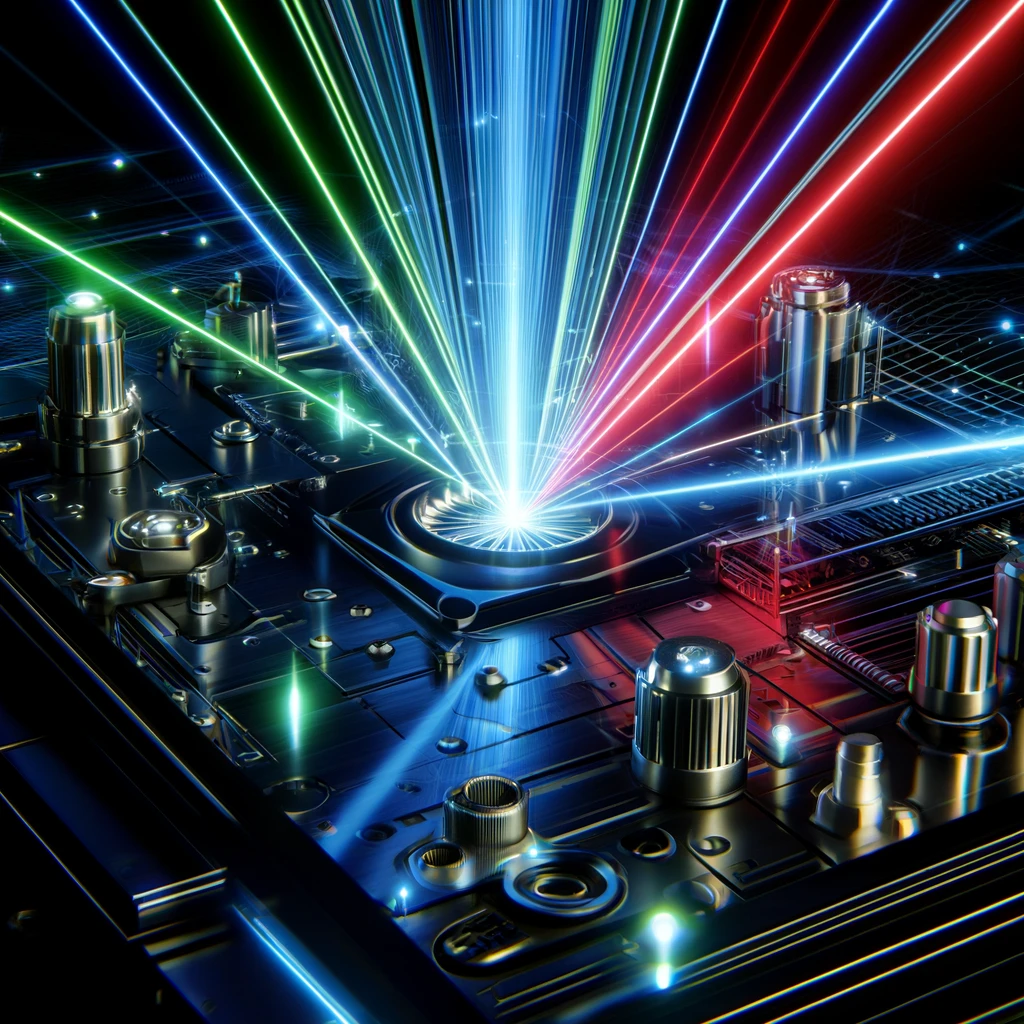
Nintendo Switch 2に搭載されるCPUは、ARM Cortex A78Cの8コア構成であり、モバイル機としては高水準の演算性能を誇る。Digital Foundryの情報によれば、クロック速度は最大1.7GHzで、ドック接続時には998MHz、携帯モードでは1,101MHzと使用状況に応じた可変制御がなされている。2コアがシステム用に確保され、開発者は6コアを自由に使用可能とされる点も特徴である。
一方GPUには、NVIDIA Ampereアーキテクチャが採用され、CUDAコアは初代Switchの256から大幅に増加した1,536を搭載。クロック速度もドック接続時で1,007MHz、携帯モードでは561MHz、最大で1.4GHzに達する。加えて、LPDDR5メモリの採用により、最大102GB/sの帯域幅が確保されており、ハンドヘルド機の常識を覆す水準である。
この構成は、従来機に対して圧倒的な性能向上を意味するが、特にGPU面での強化が際立っている。処理負荷の高いグラフィック演出やAI処理にも耐え得る設計と見られ、任天堂が携帯機における性能と電力効率の両立に挑んでいる姿勢が窺える。ただし、現時点では熱設計やバッテリー持続時間との兼ね合いについての情報は示されていないため、実機における最適化の度合いが成否の鍵となるだろう。
Ampere世代GPUとDLSS対応が拓くゲーム体験の進化可能性
Nintendo Switch 2に搭載されるGPUがAmpere世代である点は、単なる処理速度の向上に留まらず、DLSSとの連携による描画品質の飛躍的向上を示唆する要素である。Digital Foundryの報告によれば、本機はDLAA、DLSS 1x、2x、3xといった複数のアップスケーリング技術に対応する設計であり、高解像度と高フレームレートを両立させる手段が用意されている。
メモリは128-bitのLPDDR5が採用され、合計12GBの容量のうち9GBがゲームに割り当てられる。ドック接続時の帯域幅は102GB/s、携帯モードでは68GB/sとなっており、携帯機としては例外的なメモリ転送性能を持つ。これにより、オープンワールドや高度な物理シミュレーションを含むタイトルにおいても、パフォーマンス低下を抑えながらの展開が期待できる。
ただし、DLSSの適用方法やそれに伴う画質変化の具体的挙動については現時点で不明であり、実際のゲームタイトルにおける採用実績とチューニングが重要な評価基準となる。Switch 2は、旧世代の弱点であった描画解像度とフレームレートの制約を克服する可能性を持つが、それはあくまで対応ソフトと開発体制の整備次第という条件付きの前進である。
ハードウェア仕様から見える任天堂の戦略的立ち位置の変化
任天堂が新型Switchにおいて採用した構成は、従来の「性能より体験重視」路線から、一定の性能競争への意識が強まった兆候と見ることができる。特にAmpere世代GPUの採用や、LPDDR5メモリ、DLSS対応といった要素は、サードパーティ製タイトルとの互換性やマルチプラットフォーム展開の円滑化を狙ったものと解釈される。
CPUの6コア解放やメモリ9GB割当など、開発者側の制約を緩和する措置も講じられており、従来のSwitchが抱えていたパフォーマンスのボトルネック解消に配慮した姿勢が伺える。この変化は、より高度なゲーム体験を志向するユーザー層の獲得だけでなく、開発者にとっても参入障壁の低下につながる。
もっとも、PS5やXbox Series Xのような純粋な性能競争に真っ向から挑む設計ではなく、携帯性能と電力効率を維持しながら選択的に高性能要素を導入するという「差別化の中の進化」という文脈でのアプローチである。任天堂は、独自の市場領域を維持しながらも、技術面での遅れを最小限に抑える調整に入ったとみられる。
Source: Android Headlines

