Xiaomiが開発中とされる新型SoC「XRing 01」の詳細がリークされた。Arm Cortex-X925を含む10コア構成に加え、16コアのMaliベースGPU「G925-MC16」を備え、TSMCの3nmプロセスノードを採用するなど、ハイエンド向け仕様が浮上している。
削除されたGeekbenchスコアによれば、マルチコア性能でMediaTekのDimensity 9400に匹敵する可能性があるという。HuaweiやLenovo同様、自社シリコンによる脱外資依存の流れの一環と見られ、今後のモバイル戦略における鍵となる可能性がある。ただし、モデムやISPなど周辺機能の開発・調達体制は未知数であり、垂直統合の完成度が実用面での競争力を左右すると考えられる。
XRing 01の10コア構成と16コアGPUが示すXiaomiの性能志向
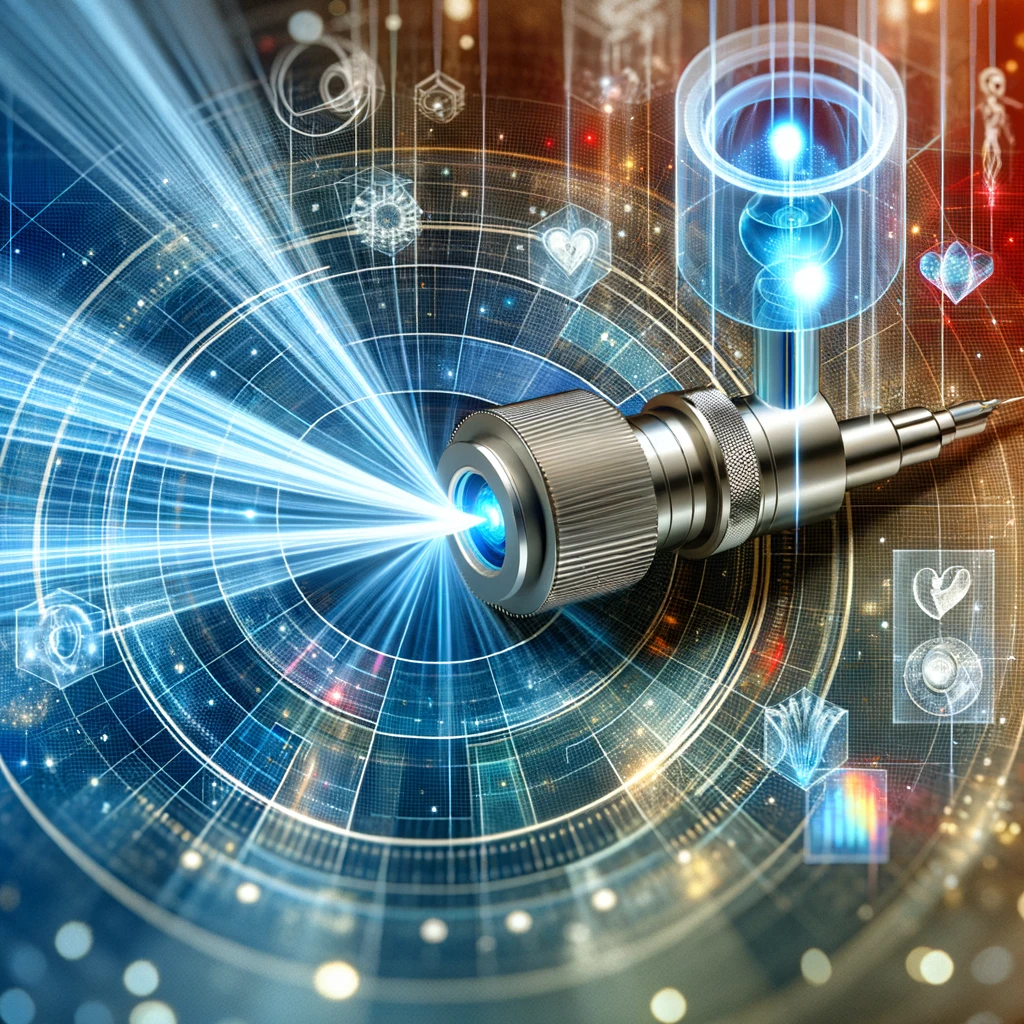
Xiaomiが独自開発を進めているとされる「XRing 01 SoC」は、10コアのCPUと16コアのMali G925 GPUという異例の構成で注目を集めている。CPUはCortex-X925を2基のプライムコアとして搭載し、最大3.9GHzで動作。これに加え、A725/X4、A720/A725、A520といった4種類のArmコアを組み合わせる複雑な構造を採用しており、SamsungのExynos 2400にも類似する構成となっている。
特に、マルチコア性能を重視した設計であることが、削除されたGeekbenchスコア(マルチ8,125)からもうかがえる。さらにGPUには、Armのハイエンド「Immortalis G925」の16コア版(G925-MC16)を採用しているとの情報があり、同GPUの12コア版を搭載するMediaTek Dimensity 9400を上回る可能性を持つ。これにより、QualcommのAdreno 830やApple A18 Proといったライバル製品との比較でも、グラフィックス性能において競争力を発揮しうる設計といえる。
Xiaomiの今回の構成は、パフォーマンス追求に明確な焦点を当てたものであり、単なるコスト削減の域を超えた試みと読み取れる。ただし、初期スコアはDimensity 9400に及ばない可能性も指摘されており、最適化の進展が性能評価に大きく影響する。今後の正式なベンチマーク結果が出揃うまでは、あくまで潜在性能の段階であり、製品としての総合力は周辺設計やチップセット全体の完成度にかかっている。
脱依存戦略としての自社開発SoCとXiaomiの垂直統合課題
XRing 01 SoCの登場は、HuaweiやLenovoと同様に、中国メーカーが海外製チップへの依存から脱却しようとする動きを象徴している。特に米国の規制強化を背景に、QualcommやMediaTekなど外資系の半導体企業に対する中国企業の調達リスクが顕在化しつつあり、自社製チップへの移行は経済的合理性と戦略的自立の両面から推進されている。Huaweiの「Kirin X90 SoC」がその好例であり、SMICの7nmプロセスを活用し、中国国内での独立開発・製造体制を実現している点は注目に値する。
ただし、SoC単体では製品の完成度は語れず、モデム、ISP、NPUといった周辺機能の整備が不可欠である。AppleですらIntelのモデム事業買収からC1モデムの自社製品化まで6年を要しており、Xiaomiが同様の水準に達するには相応の時間とリソースが必要とされる。また、GoogleのTensorがSamsung製モデムを依存するように、現時点でXiaomiがフルスタックの垂直統合を即座に実現することは困難と考えられる。XRing 01の完成度と今後の展開は、SoCに留まらない包括的な半導体戦略の成熟度に左右される可能性が高い。
Source:Tom’s Hardware

