NvidiaがゲーミングおよびAI向けGPU価格を5~15%引き上げたことで、市場関係者の注目が集まっている。背景には関税圧力、AIチップの対中輸出規制、米国への先端パッケージ移転によるコスト上昇がある。B200やH200を含むAI向けGPUは引き続き米国や中東での需要が堅調であり、同社の中核事業を支えている。
株価は過去5日で16.4%上昇し、AI関連の成長期待が再び評価されている。一方、Nvidiaは中国市場からの収益減少を55億ドルと見積もっており、地政学リスクが今後の成長性に影を落とす可能性も残る。5月28日の決算発表に向け、価格改定が利益率の改善に寄与するのか、それとも需要鈍化を招くのかが焦点となる。
全製品での価格改定が示すNvidiaの供給戦略とコスト構造の変容
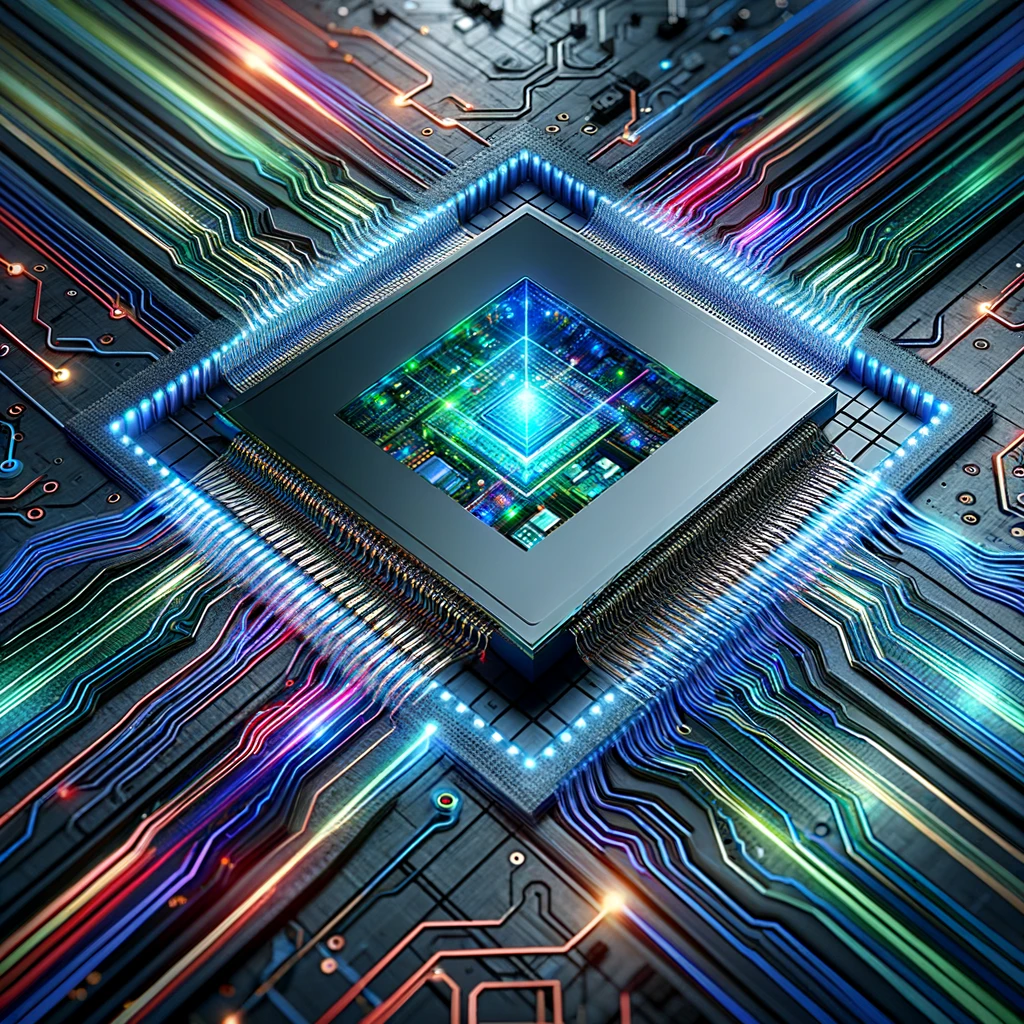
Nvidiaは、ゲーミング向けGPUの価格を5〜10%、AI向けでは最大15%引き上げた。Digitimes Taiwanの報告によれば、これは関税負担の増大、AIチップに対する米国の対中輸出制限、そして先端パッケージングの生産拠点をTSMC米国工場へ移したことによるコスト上昇に起因する。H200やB200といった高性能AIチップは、引き続き米国や中東でのインフラ構築需要に支えられており、販売価格の引き上げが許容される市場環境にある。一方で、対中制裁強化によって開発されたH20などの製品は、今後の販売に制約が生じる恐れがある。
供給網の再編と価格戦略の転換は、Nvidiaが今後の製造原価に対し高い意識を持ち続けていることを物語る。単なるコスト転嫁にとどまらず、利幅を守るための布石と見るべきである。特にAI半導体は高収益部門であり、需要が下支えされる限り価格改定が業績に与える影響はポジティブに働く可能性が高い。しかし、中国市場への依存が完全に払拭されたわけではなく、55億ドルと試算された制裁影響が利益構造に与える不確実性は無視できない。今後の決算でこの価格戦略が実際にどのように利益率へ反映されるかが注視される。
株価急騰の背景にあるAIインフラ需要と投資家の評価軸の変化
過去5営業日でNvidia株は16.4%上昇し、再び130ドルを突破した。AIインフラへの期待感が再燃しており、年初来では1%の上昇にとどまっていた株価がここにきて急伸している。市場は次回の決算発表を5月28日に控え、同社の成長持続力と価格決定力に着目している。Barchartの調査では44人中37人のアナリストが「強い買い」と評価しており、目標株価の平均は166.22ドルとされ、現在価格から約23%の上昇余地があるとの見解が示されている。
現在のPSR25.36倍、PER33.25倍という水準は割高と見られがちだが、55.9%という利益率の高さと、AI分野での圧倒的なシェアがそのプレミアムを正当化しているとの声もある。GPUの需要がハイパースケーラーや国家レベルのAI戦略に直結している点も評価されており、株価の急騰は一時的な投機にとどまらない要素を含んでいる。
ただし、投資家の期待が過度に先行している面も否定できず、次回決算での売上・利益の実数が市場の期待に届かなければ、反動も大きくなる恐れがある。価格引き上げによる短期的な業績貢献と、制裁影響による長期的リスクの間で、投資家の評価軸は繊細なバランスを要求されている。
Source:Barchart.com

