2023年、生成AIのブームを追い風に、米国NVIDIA(エヌビディア)は一躍注目を集めた。ChatGPTのような大規模AIモデルの開発・実行を支えるGPU市場で圧倒的な存在感を示し、AI、ロボティクス、デジタルツインといった先端領域でもその名が広く知られるようになった。
NVIDIAは本当に“GPUメーカー”にとどまる企業なのか。そう問い直すのが、日経BPシリコンバレー支局・島津翔氏による新著『NVIDIA大解剖』である。
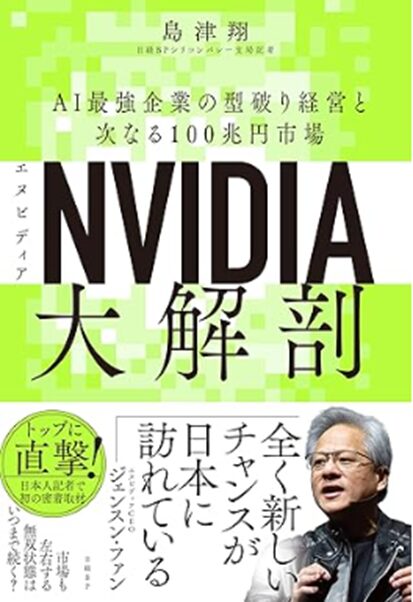
▼参考リンク▼
Amazon『NVIDIA(エヌビディア)大解剖 AI最強企業の型破り経営と次なる100兆円市場』
本書は、NVIDIAのビジネス、技術、経営、組織、そして未来への展望までを6章構成で掘り下げた一冊。Reinforz Insightでは、著者・島津氏にインタビューを実施し、執筆の背景と本書の狙い、「NVIDIA型経営」から得られる示唆を伺った。
―書籍『NVIDIA大解剖』の執筆に至ったきっかけを教えてください。
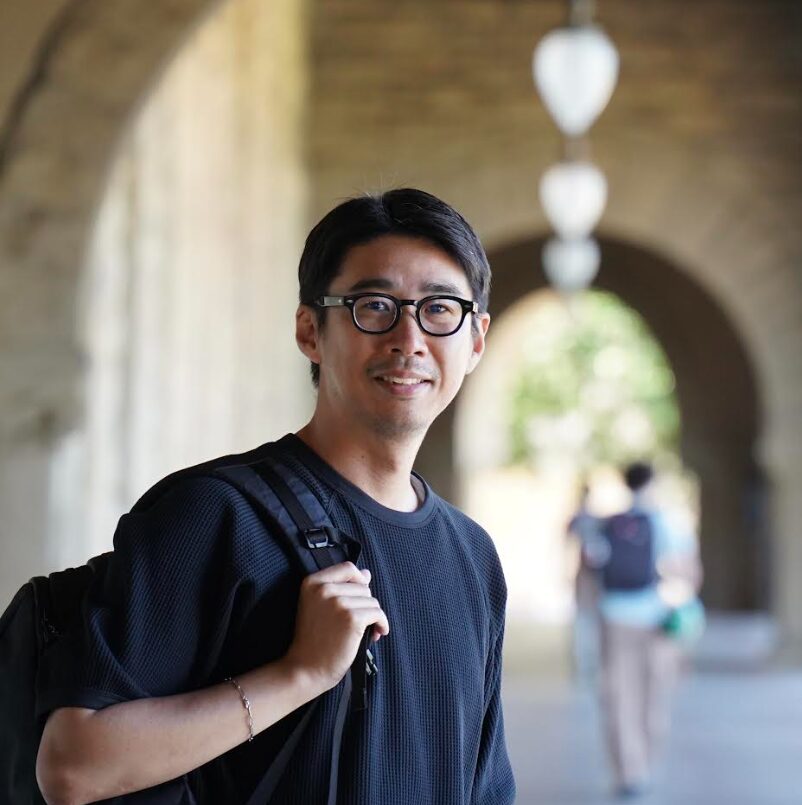
島津翔氏(以下、島津氏):実は前著『生成AI 真の勝者』でも、AI半導体を扱う章を設けており、その中でNVIDIAの重要性をあらためて実感していました。生成AIの進化には、並列処理に優れたGPUが不可欠であり、その中心にいるのがまさにNVIDIAです。
さらに言えば、私はシリコンバレー駐在になる前からNVIDIAを継続的に取材してきました。2016年当時は自動車担当の記者で、自動運転関連の取材が中心でした。その中で、「今後、クルマにもGPUが載るようになる」という話をエンジニアから繰り返し聞くようになったのが最初のきっかけです。
そして2024年、日経ビジネスでNVIDIAの「経営」に焦点を当てた特集を執筆する機会を得て、技術面だけでなく経営面に関する取材の蓄積もできた。そこから本格的に「この企業のすべてを1冊にまとめるべきだ」と確信し、執筆に着手しました。
―当時から、NVIDIAが今のように躍進することを予感していましたか?
島津氏:技術的には明確にポテンシャルを感じていました。自動運転やAIといった分野では、並列処理性能に優れたGPUが重要になるというのは、現場のエンジニアたちから一貫して聞こえてきた声です。
ただ、2016〜17年頃は「第3次AIブーム」などと呼ばれていた時期ではありましたが、実際にはその応用がまだ追いついていませんでした。自動運転も2020年に実用化されると言われていましたが、実際にはどの企業も実用化をすることができなかった。
その意味で、NVIDIAは「可能性はあるが、いつ跳ねるかわからない企業」だったと言えるでしょう。しかし、今振り返ると、あの段階でGPUの重要性を技術の側面からしっかりと理解していたことが、NVIDIAという企業の本質を見抜く第一歩だったと思います。
―書籍の中で特に読んでほしい「見どころ」はどこでしょうか?
島津氏:すべての章に読みどころはありますが、特に注目してほしいのは「経営編」です。NVIDIAのマネジメントスタイルは非常にユニークで、日本企業の常識とは真逆のアプローチが多く採られています。
たとえば、日本企業で近年重視されている「1on1ミーティング」や「月次報告」などの文化はNVIDIAには存在しません。その代わりに「トップ5」と呼ばれる情報共有のルールがあったり、組織構造自体が極めてフラットだったりで、情報がボトルネックなく流れるように設計されているのです。
これは、ただの“効率的な経営”という話ではありません。情報の流れ方こそが、企業の進化と判断のスピードを左右する――その前提に基づいた設計思想が、NVIDIAにはあるということです。
―組織構造としては、どのような印象をお持ちですか?
島津氏:コンサルティングファームに近い印象を受けました。つまり、固定的な部署ではなく、案件やプロジェクトごとに最適なチームを編成するスタイルです。専門性の高い人材が、必要に応じてアサインされる。
それぞれのメンバーは、法務やデザイン思考、ハードウェア設計など、多様なバックグラウンドを持っていて、その専門性が活かされる構造になっています。約3万人という大所帯にもかかわらず、柔軟で流動的な組織を維持できている点は驚くべきことです。
日本の伝統的な大企業では、どうしても縦割りや階層の硬直性が強くなりがちですが、NVIDIAのようにプロジェクトベースで動ける組織は、今後の企業の理想形の一つかもしれません。
―日本企業との最も大きな違いはどこにありますか?
島津氏:「根回し」などの回りくどい作法が存在しないという点は大きいと思います。日本企業では、何か新しい提案を経営会議に出す場合、まずは関係部署の執行役員や上長と個別にアポを取り、順番に合意を得ていくというプロセスが事実上求められます。最終的に経営会議に提出する段階では、すでに関係者の了承が取れている状態で、会議自体は“シャンシャン”で終わる儀式のようになりがちです。
NVIDIAはまったく逆の文化を持っていて、会議の場でこそ本当の議論がなされ、是々非々の判断がその場で行われます。事前に根回しをして“通す”ことが前提ではなく、むしろ皆がオープンな状態で集まり、フラットに意見をぶつけることが尊重されている。
これは単に意思決定が早いという話ではなく、組織としての「透明性」や「納得感」、そして「スピード感」を担保するための文化的な基盤だと思います。情報と意思決定が開かれた場で流通しているからこそ、全体が一つの方向に一気に動くことができる。そういう意味でも、日本企業とNVIDIAでは、組織の根本的な設計思想が大きく異なると感じました。
―ジェンスン・ファンCEOの「先見性」についても語られていますね。
島津氏:ファン氏は、電子工学を専門とする技術者として、深い知見を持っています。大学教授と同等の知識量があるとも言われ、技術のトレンドを感覚ではなく構造的に理解できる、稀有なタイプの経営者です。
そして重要なのは、そうした知識に基づく直感だけで動くのではなく、自らのもとに「正確かつ迅速に情報が届く組織構造」を設計していることです。階層を極力抑えたフラットな体制や、優先情報を整理して共有する「トップ5」ルールなど、経営判断の質とスピードを高める仕組みが整っています。
情報が正しく流れる環境を整えたうえで、その情報をもとに判断を下す。NVIDIAのスピード経営の本質は、まさにそこにあり、ファン氏の戦略眼が最もよく表れている部分だと思います。
―意思決定の柔軟さもNVIDIAの強みだと聞きました。
島津氏:ファン氏は、必要なときには自らの判断ミスも素直に認める人だと私は理解しています。たとえば過去にはスマートフォン事業やゲーム事業に参入しましたが、いずれも期待通りにはいかず、結果的に1年以内に撤退を決断しています。
こうした迅速な撤退判断は、実際には難しいものです。なぜなら、多くの企業ではすでに投下した資金や、社内での発言力・面子といった“心理的コスト”が撤退の障壁になるからです。
しかしNVIDIAでは過去の意思決定にとらわれず、「今やるべきこと」にすばやく舵を切る文化が根づいています。ファン氏自身が、自らの判断の誤りを受け入れる柔軟さを持っているからこそ、それが組織全体に波及し、現場の動きにもスピードが出る。
この“引き際の潔さ”と“方向転換の速さ”は、単なる失敗回避ではなく、次の成長機会を早くつかむための重要な意思決定だと思います。過去にこだわらないこのスタンスこそが、今日のNVIDIAの躍進を支えている要因の一つだと感じます。
―今後のNVIDIAの将来性についてどう見ていますか?
島津氏:現在、株価は年初来で2割ほど下落していますが、これはNVIDIA固有の問題というより、テック業界全体に対する市場の見通しが厳しくなっているためです。米中対立に伴う輸出規制や、クラウド大手によるAI関連の過剰投資懸念、新興の低コストAI開発手法の登場など、複数の要因が重なっている状況です。
とはいえ、AI分野におけるGPUの重要性は今も変わっていません。むしろ、AIの応用が広がる中で、求められる処理能力はさらに高まっていると感じます。今後は「学習」から「推論」へとフェーズが移っていきますが、この推論領域でも高性能な演算が求められるようになっており、NVIDIAはすでにその準備を進めています。
推論は一見、省電力な専用チップの方が有利に見えるかもしれませんが、最近では推論自体が高度化し、大規模なモデルをリアルタイムで動かすケースも増えています。そうした場面では、依然としてGPUの強みが活きてくる。NVIDIAが持つハードウェアとソフトウェアの総合力は、この先も十分に競争力を維持していくと考えています。
―推論用途ではNVIDIAのシェアも変わると?
島津氏:そうですね。学習用途ではNVIDIAが非常に高いシェアを持っていましたが、推論に関しては少し事情が異なってきます。というのも、推論フェーズでは活用されるシーンがより多様で、スマートフォンや自動車、ロボティクスといった「エッジ」側での活用が増えてきている。
こうした領域では、演算性能だけでなく、省電力や小型化といった要素も重要になるため、GPUだけではカバーしきれない場面が出てくる。結果として、より軽量で特化型のチップなど、他社製品の入り込む余地が広がる構造になっています。
とはいえ、NVIDIAはそうした変化を前提としつつ、自動運転やロボット、デジタルツインのような“GPUが力を発揮できる市場”を自ら創出し、先手を打っている。GPUが求められる場所をつくり、そこに自社製品を展開するという発想は、今後も変わらないと思いますし、それがNVIDIAの強さの一つだと感じています。
―最後に、読者へのメッセージをお願いします。
島津氏:本書は、あえて多面的に構成しています。投資家であれば将来性とリスク、エンジニアであれば技術の選択と進化、経営者であれば組織と意思決定のあり方。そうした多様な視点で読んでもらえるように設計しました。
NVIDIAという企業は、単なる“半導体メーカー”ではありません。その裏にある経営思想、組織戦略、そして市場の捉え方は、日本企業やビジネスパーソンにとって大いに参考になるはずです。この本が、そのヒントになれば幸いです。

