2025年8月、朝日新聞社と日本経済新聞社が米生成AIスタートアップ「Perplexity AI」を東京地裁に提訴した。請求額は計44億円。著作権侵害に加え、生成AIによる虚偽情報拡散がブランド信用を毀損したとする不正競争行為までを問う異例の二重構成である。この一件は、単なる知財紛争にとどまらず、日本の報道産業の生存戦略、さらには民主主義社会におけるジャーナリズムの位置づけをも左右する重大な局面といえる。
背景には「データ植民地主義」と呼ばれる構造がある。新聞各社が多大なコストをかけて取材・編集した記事をAIが無断利用し、検索結果からユーザーを引き離す「ゼロクリック」問題が深刻化しているのだ。広告収入や購読料に依存する報道経済モデルが根底から揺らぐ中、訴訟は業界全体の危機感の表れでもある。
国際的に見れば、米国ではフェアユースの枠組みでNYT対OpenAIの訴訟が進行中、EUではAI法やDSM著作権指令が規制を先導する。日本の司法判断は、これらと異なる「第三の道」を示す可能性を秘める。AIの利便性と報道の公共性、双方の価値をどう調和させるのか。今回の訴訟は、その均衡点を社会に問うリトマス試験紙となるだろう。
日本の報道大手が一線を画した共同提訴の背景

2025年8月26日、朝日新聞社と日本経済新聞社は、米生成AIスタートアップのPerplexity AIを東京地方裁判所に提訴した。両社が求めるのは、著作権侵害による記事コンテンツの無断利用差し止め、保存データの削除、そして合計44億円に及ぶ損害賠償である。この動きは単なる個別企業の権利主張ではなく、日本の報道界全体が直面する構造的課題に対する組織的抵抗を示すものであった。
実際、同年8月7日には読売新聞グループ3社も同じ相手を訴えており、約21億円の賠償を求めている。つまり、日本の「三大紙」がそろって同一のAI企業に法的措置を取った形であり、業界横断的な危機感の共有が鮮明になった。新聞各社は、自社記事がAIの回答生成に無断で利用され、読者が本来アクセスすべきサイトから離脱する「ゼロクリック問題」に直面している。広告収益や有料購読モデルを根幹から揺るがすこの現象は、取材・編集に多大なコストを投じる報道機関にとって、ビジネスモデルの崩壊を意味する。
さらに今回の提訴は、「データ植民地主義」への反発という象徴的意味を持つ。AI事業者が世界中の報道コンテンツを収奪的に利用し、十分な対価を支払わずに収益化する構造が広がれば、取材現場の持続可能性は失われる。日本新聞協会も繰り返し声明を出し、生成AI事業者に対して「報道コンテンツの無断利用を直ちにやめるべきだ」と警告してきた。
今回、朝日・日経が巨大IT企業ではなくスタートアップのPerplexityを提訴した背景には、同社のビジネスモデルが「ゼロクリック」を最も端的に体現しているという事情がある。報道業界にとって直接的脅威であるこのモデルを「テストケース」として法廷に持ち込み、将来的にGoogleやMicrosoftといった大手との交渉を有利に進めるための布石とみられている。
こうした一連の動きは、日本の新聞産業が「生き残りを懸けた最後の戦い」に突入したことを示すものだ。
著作権侵害と不正競争行為の二重構成

今回の訴訟が注目されるのは、原告側が著作権侵害だけでなく、不正競争行為をも同時に主張している点にある。これは日本におけるAI関連訴訟で極めて異例の戦略であり、法的論点を多角的に広げる狙いが明確に表れている。
まず著作権侵害について、原告はPerplexityが両社の記事を無断で複製・保存し、要約した形で繰り返し提供していたと主張する。これにより、複製権(著作権法21条)、公衆送信権(23条)、翻案権(27条)が侵害されたと訴えている。特に重大視されているのは、robots.txtによるアクセス拒否設定を意図的に無視してデータを収集した点と、日経電子版の有料記事を突破して利用した点である。これらは単なる偶発的行為ではなく、計画的かつ悪質な権利侵害の証拠と位置づけられている。
さらに原告は、不正競争防止法に基づき「信用毀損行為」を構成するとも主張する。Perplexityの回答には、両社の記事を出典として掲げながら実際には存在しない虚偽情報が含まれていたケースがある。これは生成AI特有の「ハルシネーション」によるものであるが、報道機関のブランド価値を直接的に損なう重大な問題だ。長年築き上げた「正確性」と「信頼性」という無形資産が毀損されることは、金銭的損害以上に深刻なダメージであり、これを不正競争行為として訴訟に盛り込む戦略的意義は大きい。
この二重構成により、争点はAIの学習行為そのものから、生成物が社会に与える具体的被害へとシフトする。著作権侵害が「資産の無断利用」を問うのに対し、不正競争行為は「積極的な加害行為」を問う枠組みであり、両者を組み合わせることで訴訟の射程は拡大する。結果として、Perplexity社の行為の違法性を多面的に立証しやすくなると考えられる。
このアプローチは、日本の司法が生成AIと報道コンテンツの関係をどう位置づけるかを示す試金石となり、他のメディア企業や海外事例にも波及する可能性が高い。
著作権法第30条の4「非享受目的」規定をめぐる攻防
今回の訴訟の最大の焦点は、日本の著作権法第30条の4、いわゆる「非享受目的」規定の解釈にある。この条文は、著作物を「自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合」に限り、著作権者の許諾なしで利用できると定めている。もともとはビッグデータ解析や研究開発を促進する目的で導入された規定だが、生成AIが普及する中で初めて本格的に司法判断が問われる局面を迎えた。
AIの学習は、プログラムが記事の内容を「味わう」わけではなく、統計的パターンを抽出するための情報解析に過ぎない。そのため業界では長らく「AI学習は非享受目的に該当する」という理解が広がっていた。しかし、今回の訴訟では事情が異なる。Perplexityのような「アンサーエンジン」は、最終的にユーザーに情報を要約して提示し、享受させることを目的としている。原告側は、このプロセス全体を見れば「享受目的」が不可分に存在すると主張し、条文の適用を否定する構えだ。
さらに、同条には「著作権者の利益を不当に害する場合は除外する」というただし書きがある。報道機関のウェブサイトへのアクセスを奪い、広告収入や購読料を侵食する行為は、この例外に該当するとされる可能性が高い。文化庁も2024年に「AIと著作権に関する考え方」を公表し、robots.txtなどのアクセス制御を回避してデータ収集を行うことは著作権者の利益を不当に害する可能性があると明言している。この見解は、裁判所にとって重要な参考資料となるだろう。
また、日本新聞協会は声明の中で、検索エンジンが果たす「道案内」と異なり、生成AIはコンテンツの中身を直接明かす「種明かし」であり、軽微利用の範囲を逸脱していると強調した。robots.txt遵守や学習用クローラーの分離を求めるなど、具体的な規制を政府や企業に対し提案している。
このように、条文の適用可否をめぐる議論は、単なる技術論争ではなく、日本が「AI開発推進」と「著作権保護」のどちらに重きを置くのかを示す判断となる。東京地裁の結論は、今後のAI開発環境やメディア産業の経済基盤に直接的な影響を与えることになる。
国際比較:米国のフェアユース、EUの規制主導、日本の選択肢

朝日・日経の提訴は日本国内にとどまらず、国際的な文脈の中で理解されるべき事案である。世界各国では同様の訴訟や規制が進んでおり、日本の司法判断はその中で「第三の道」を提示する可能性を持っている。
米国では、ニューヨーク・タイムズ(NYT)がOpenAIとMicrosoftを相手取り訴訟を提起している。NYTは、ChatGPTが自社記事をほぼそのまま再現し、有料購読サービスの代替となっていると主張。一方、OpenAIは「フェアユース」の法理を盾に、AI学習は新たな価値を生み出す変容的利用であり許諾は不要だと反論している。米国の枠組みは柔軟だが、判例依存で予測が難しいため、長期にわたる訴訟が続く可能性が高い。
一方、欧州連合(EU)は規制による先手を打った。AI法により、汎用AIモデルの開発者には学習に使った著作物の「詳細な要約」の公表義務が課される。また、DSM著作権指令では報道機関に「隣接権」を認め、記事の利用に対して報酬を請求できる仕組みを整備した。さらに、robots.txtのようなオプトアウトを法的に尊重する義務も明確に規定している。
表で整理すると次のようになる。
| 地域 | アプローチ | 主な法規・法理 | 透明性・オプトアウト |
|---|---|---|---|
| 日本 | 司法判断 | 著作権法30条の4 | robots.txtは参考基準、法的拘束力は弱い |
| 米国 | 訴訟中心 | フェアユース | オプトアウト義務なし |
| EU | 規制主導 | AI法・DSM指令 | 学習データ要約義務、オプトアウトは法的拘束力あり |
この比較から分かるのは、日本が現時点で米国型の「訴訟中心」でもなく、EU型の「規制主導」でもなく、独自の解釈を模索していることだ。今回の判決は、日本がAIと著作権の間でどのような均衡点を選ぶのか、その方向性を世界に示すシグナルとなる。
日本の新聞各社は、規制整備を待つのではなく、司法判断によって道を切り拓こうとしている。この戦略的な挑戦は、グローバルな知財戦争の中で日本がどの立ち位置を取るのかを決定づける可能性がある。
Perplexity社の対応と戦略的ジレンマ

朝日・日経の提訴を受け、被告となったPerplexity AIは圧力に直面し、迅速に対応策を打ち出した。同社は訴訟翌日に「Comet Plus」という収益分配プログラムを発表。月額5ドルの有料会員収益のうち80%を、回答生成に利用したコンテンツの提供元に分配すると公表した。一見すると報道機関に歩み寄る姿勢を示す懐柔策だが、その実効性には疑問が残る。
分配額を試算すると、例えば数十社に利用料が分配される場合、各社に入る金額はごく僅かで、日経電子版の月額購読料(4,277円)や朝日新聞デジタルの月額3,800円と比べると到底補填にはならない。批判回避のための象徴的ジェスチャーに過ぎないとの見方が強い。むしろ対価支払いの仕組みを設けたことで、コンテンツに経済的価値があることを被告自身が認めてしまった点が法廷で不利に働く可能性がある。原告側は「必要性を認識しながら無断利用を続けている」と逆手に取ることができるのだ。
さらに技術的防御として、同社はRAG(検索拡張生成)を利用しており、学習済みモデルが直接コピーを保存しているわけではなく、検索と要約の組み合わせであると主張する見込みである。しかしNYT対OpenAI訴訟では、特定プロンプトで記事がほぼ一字一句再現される事例が提出されており、AIはコピーを保存しないという説明の説得力は弱まっている。
Perplexityのジレンマはここにある。収益分配策を示せば「対価の必要性」を認めたことになる。逆に無視すれば「ただ乗り」との批判が強まる。技術的説明に依存すれば、実際の再現事例との乖離を突かれる。つまり、どの戦略を取っても法廷・世論の双方で矛盾を抱える構造に陥っているのだ。
この訴訟の展開は、Perplexity社のみならず、同様のサービスを提供するグローバルAI企業にとっても、自らの事業モデルを再構築するか否かを迫る分岐点となる。
ジャーナリズム存続の危機:ゼロクリックと信頼の侵食
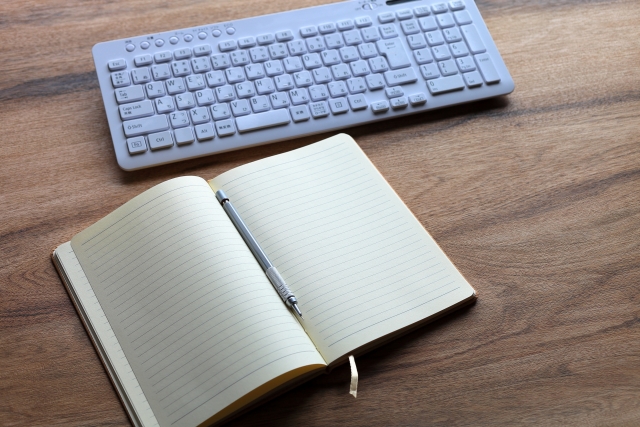
今回の訴訟は、単なる法的争点にとどまらず、報道機関の存続基盤を直撃する経済的・社会的課題を浮き彫りにした。最大の脅威は「ゼロクリック検索」である。ユーザーがAIの要約だけで満足し、元記事にアクセスしなくなる現象は、広告収入と有料購読料を基盤とするジャーナリズムに致命的な打撃を与える。
日本の新聞発行部数は1990年代末に5,300万部に達したが、2022年には3,084万部まで減少した。デジタル収益も成長しているとはいえ、紙媒体の縮小を補い切れていない。こうした中でゼロクリックが常態化すれば、読者を自社サイトに呼び込む経済的循環は完全に断たれる。報道機関が売っているのは単なる記事ではなく、検証や説明責任を伴う「信頼」だが、そのコストを負担する仕組みが失われつつある。
さらに深刻なのは「信頼性の侵食」である。生成AIは「ハルシネーション」により虚偽情報を生成するリスクを常に抱える。もしその情報が「出典:日経」「出典:朝日」と表示されれば、信頼性が毀損される。研究によれば、ニュース記事にAIが関与していると開示されただけで読者の信頼度が下がる傾向が確認されている。別の研究ではAI生成ニュースは人間よりバイアスが少ないと評価される場合もあるが、説明責任が不明確になる点が大きな懸念とされる。
つまり、経済的基盤の喪失と社会的信頼の低下が同時進行している。両者が組み合わされば、報道機関は存続可能性そのものを失い、民主主義を支えるインフラとしての役割が揺らぐ。今回の訴訟は、その危機に対する最後の防衛線ともいえる。
AIがもたらす利便性と、ジャーナリズムの信頼性をどう両立させるのか。それは産業の生存戦略であると同時に、社会全体の情報環境を守るための根源的な課題である。
まとめ
朝日新聞社と日本経済新聞社によるPerplexity AIへの提訴は、単なる企業間の紛争ではなく、生成AIの利便性とジャーナリズムの存続可能性をどう両立させるかという社会的課題を浮き彫りにした。
著作権法第30条の4の解釈をめぐる法廷闘争は、日本が「AI開発推進」と「権利保護」のどちらに軸足を置くのかを示すシグナルとなる。また、米国のフェアユースやEUの規制主導モデルとの比較から、日本が選ぶ「第三の道」は世界的にも注目される。
同時に、報道機関は「ゼロクリック」や「ハルシネーション」といったAI特有のリスクに直面し、経済基盤と信頼性の双方を揺るがされている。報道機関の知的成果を正当に評価し、持続可能な情報エコシステムを築くことが不可欠である。
この危機を乗り越えるためには、報道機関の戦略的投資、AI事業者の透明性確保と公正な契約、そして政策立案者による制度設計が三位一体で進められなければならない。今回の訴訟は、その均衡点を模索する歴史的転換点であり、日本社会の情報環境の未来を左右する重大な「データポイント」となるだろう。
出典一覧
- 共同通信「米生成AI社を朝日・日経が提訴」47NEWS
https://www.47news.jp/13065448.html - ITmedia「朝日と日経、米Perplexityを共同提訴 読売に続き『記事の無断利用』」
https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2508/26/news100.html - 日本新聞協会「生成AIにおける報道コンテンツの無断利用等に関する声明」
https://www.pressnet.or.jp/statement/broadcasting/240717_15523.html - 文化庁「AIと著作権に関する考え方について」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf - Harvard Law School「Does ChatGPT violate New York Times’ copyrights?」
https://hls.harvard.edu/today/does-chatgpt-violate-new-york-times-copyrights/ - European Parliament「EU AI Act: first regulation on artificial intelligence」
https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence - Press Gazette「News generative AI deals revealed: Who is suing, who is signing?」
https://pressgazette.co.uk/platforms/news-publisher-ai-deals-lawsuits-openai-google/ - 日本新聞協会「新聞の発行部数と世帯数の推移|調査データ」
https://www.pressnet.or.jp/data/circulation/circulation01.php - University of Kansas「Study finds readers trust news less when AI is involved, even when they don’t understand to what extent」
https://news.ku.edu/news/article/study-finds-readers-trust-news-less-when-ai-is-involved-even-when-they-dont-understand-to-what-extent

