日本の科学技術政策は、いま大きな転換点を迎えている。従来の「広く薄く」支援するスタイルから、人工知能(AI)や量子といった国家の命運を握る先端技術に資源を集中投下する「選択と集中」戦略へのシフトである。背景には、米中欧を中心に激化する技術覇権争いと、経済安全保障の重要性の高まりがある。
政府は「第6期科学技術・イノベーション基本計画」でSociety 5.0実現への道筋を描き、さらに経済安全保障重要技術育成プログラム(K Program)を通じて総額5,000億円規模の基金を投入した。量子分野では2030年に50兆円市場の創出を掲げ、理化学研究所や情報通信研究機構などが国際的な研究開発競争をリードする。AIでは生成AIや創薬・素材開発への応用が急速に進み、日本企業の強みを再び浮上させつつある。
だが、この戦略は諸刃の剣でもある。基礎研究の多様性を犠牲にするリスクや、若手研究者のキャリア不安定化、頭脳流出といった課題は深刻だ。果たして日本は、重点投資と持続的な研究基盤強化を両立し、真に競争力あるイノベーション国家として再生できるのか。その成否は、次の10年に試される。
日本の科学技術政策転換:選択と集中の必然性
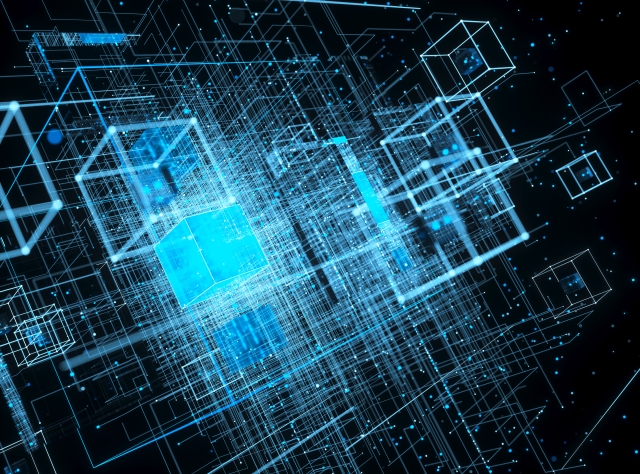
「第6期科学技術・イノベーション基本計画」が描く未来像
日本が科学技術政策の大きな舵を切ったのは、2021年度から2025年度を対象とする「第6期科学技術・イノベーション基本計画」である。この計画は、単なる研究指針ではなく、「Society 5.0」実現という国家の未来像を具体化する壮大な設計図として策定された。Society 5.0とは、サイバー空間とフィジカル空間を融合させ、経済発展と社会課題の解決を同時に達成する人間中心の社会を意味する。AIや量子は、この社会像を支える基盤技術と位置づけられている。
この政策転換の背景には、日本が直面する深刻な課題がある。まず、米中を中心に激化する技術覇権争いだ。AIや量子を巡る国際競争は単なる経済競争を超え、国家安全保障の領域に直結している。さらに、日本の研究力低下への危機感も無視できない。質の高い論文数で日本は国際的順位を落とし続けており、研究基盤の脆弱化が指摘されている。加えて、気候変動やパンデミックといった地球規模課題への対応も求められ、従来型の「広く平等な研究支援」では解決できないという認識が広がった。
広範な研究支援から重点投資への必然的移行
こうした状況下で、日本政府は研究資源をより戦略的に配分する必要に迫られた。「選択と集中」戦略は、限られた資源を最もインパクトの大きい分野に投下し、国際競争で「勝ち筋」を見出す必然的アプローチとして採用されたのである。注目すべきは、この計画が自然科学だけでなく人文・社会科学の知見も取り込み、「総合知」に基づく政策設計を掲げた点だ。これは、技術の社会的影響を多角的に評価し、倫理・法制度面にも対応する成熟した科学技術政策への移行を意味する。
政策の方向性を一言で表せば、「量より質」「広く浅くから、狭く深く」へのシフトである。従来はあらゆる分野に小規模支援を広げていたが、今後はAIや量子といった重点分野に大胆に集中し、社会実装と国際競争力確保を狙う。日本が未来を切り拓くには、この戦略が避けられない選択肢となったのである。
経済安全保障とK Program:安全保障化する科学技術政策

経済安全保障推進法とK Programの誕生
「選択と集中」を具体化する制度的枠組みが、2022年に施行された経済安全保障推進法に基づく「経済安全保障重要技術育成プログラム(K Program)」である。総額5,000億円規模の基金が創設され、科学技術振興機構(JST)と新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が研究資金を運用する。K Programは、単なる産業競争力強化ではなく、安全保障に資するデュアルユース技術の育成を目的としている点に大きな特徴がある。
政府が指定した重点領域は以下の通りである。
- 海洋分野:高性能次世代船舶、無人機による海洋監視システム
- 宇宙・航空分野:衛星コンステレーション、長期飛行可能な高高度無人機
- サイバー・横断分野:AIセキュリティ技術、量子情報通信技術、ハイブリッドクラウド基盤
- バイオ分野:合成生物学による肥料生産、人工血液(人工血小板)開発
これらはいずれも、他国依存が安全保障上のリスクとなり得る領域を網羅している点で戦略的だ。
デュアルユース技術と政策の安全保障化
従来の科学技術政策が「産業振興」に軸足を置いていたのに対し、K Programは「経済合理性」と「国家安全保障」の両立を狙う。たとえば、量子暗号通信は金融市場の安全性を担保する一方、国家安全保障インフラとしても重要な役割を果たす。また、人工血液は平時の医療だけでなく有事の医療体制にも直結する。
さらに、K Programは単に研究開発を支援するだけでなく、技術成熟度に応じて流出防止策を同時に講じるという運用も特徴的である。米中対立下での技術覇権競争を背景に、日本が技術的自律性を守るためには不可欠な仕組みといえる。
科学技術政策の「安全保障化」という転換点
K Programの始動は、日本の科学技術政策が「経済合理性」から「国家存続」に直結する安全保障の論理を取り込んだことを意味する。これは単なる研究支援ではなく、国家戦略の一部として科学技術を位置づけ直す画期的な変化である。政策の方向性は明確だ。すなわち、AIや量子といった最先端技術を「守るべき資産」として国家が主体的に育成し、国際競争力と安全保障を同時に担保する。
こうして、日本は「選択と集中」を現実の予算と制度に落とし込み、政策の実効性を大きく高めたのである。
量子技術で描く未来社会

2030年に向けた野心的な国家ビジョン
日本政府は、量子技術をAIと並ぶ国家戦略の柱と位置づけ、「量子未来社会ビジョン」を策定した。その目標は極めて野心的で、2030年までに50兆円規模の新市場を創出し、国内の利用者数を1,000万人規模に拡大するというものだ。これは、量子技術を単なる研究対象にとどめず、材料、創薬、金融、製造など幅広い分野で産業の基盤技術とすることを意味する。さらに、政府は2025年を「量子産業化元年」と宣言し、研究段階から社会実装への移行を国家として推し進めている。
研究機関が形成する「ナショナル・チャンピオン」ネットワーク
このビジョンを支えるのが、理化学研究所(理研)、情報通信研究機構(NICT)、量子科学技術研究開発機構(QST)、産業技術総合研究所(産総研)といった世界的研究機関の連携だ。
- 理研は量子コンピュータ開発の司令塔として、量子とスーパーコンピュータ「富岳」の世界初の連携を実現。誤り耐性が不十分な現行デバイスの限界を補い、材料科学や創薬での実用化を加速させている。
- NICTは、首都圏に構築した「Tokyo QKD Network」を拠点に、金融取引データの量子暗号通信実証を成功させ、さらに衛星実験で地球規模通信網を視野に入れている。
- QSTは、ダイヤモンド中の窒素空孔中心(NVセンター)を用いたナノ量子センサで世界初となる生体細胞温度の直接計測に成功し、がん研究や創薬の新手法を開拓した。
- 産総研は、量子・AI融合を進める「G-QuAT」を設立し、産業界との橋渡し役を担っている。
このネットワークは、それぞれの強みを有機的に結び付け、量子エコシステムを体系的に構築している点に大きな強みがある。
スタートアップと産業界が生み出す量子エコシステム
近年は、Yaqumo(中性原子方式)、Jij Inc.(最適化ソフトウェア)、OptQC(光量子方式)といった多様なスタートアップが登場しており、産業応用の幅を広げている。これを支えるのがトヨタやNEC、日立などが参加する「量子技術による新産業創出協議会(Q-STAR)」である。Q-STARは標準化や国際連携を推進し、Plug and Play Japanと協力してスタートアップ育成にも力を注ぐ。
世界市場の成長も追い風だ。調査会社Straits Researchは量子コンピューティング市場が2032年に約90億ドル、Fortune Business Insightsは126億ドル規模に達すると予測している。さらに、日本国内市場も同年には29億〜38億ドルに拡大すると見込まれており、金融やエネルギーなどで新たな産業機会が広がる。
このように、量子分野は基礎研究から産業化に至る明確なロードマップが描かれつつあり、政策・研究・産業界が一体となった取り組みが日本の競争力強化を牽引している。
AI戦略の核心:融合と応用

「AI戦略2022」と「統合イノベーション戦略2025」
AI分野における日本の戦略の特徴は、「単体開発」ではなく「融合」と「応用」を重視している点だ。政府は「AI戦略2022」や「統合イノベーション戦略2025」で、AIを社会課題解決の強力なツールと位置づけた。特に重視されているのは以下の4分野である。
- 科学研究そのものを革新する「AI for Science」
- 介護・物流・製造現場を対象とした「フィジカルAI」
- 社会実装に伴うリスクを評価する「AIセーフティ・インスティテュート(AISI)」の設立
- 幅広い層を対象にしたAI人材育成
国家基盤能力の強化:ABCIと国産LLM
こうした戦略を下支えするのが、産総研が運用する「AI橋渡しクラウド(ABCI)」である。世界トップクラスの計算資源を提供するABCIは、大学や企業に広く開放され、日本のAI研究の基盤を支えている。さらに、近年注目される生成AIに対応するため、産総研は1750億パラメータ規模の国産大規模言語モデル(LLM)開発に着手した。これは従来の国産モデルの10倍以上の規模で、日本語特有の文脈理解や文化的ニュアンスを反映したモデルを目指している。
また、産総研は少量データ問題に挑むべく、数式ベースで画像を自動生成しAIを事前学習させる新手法を開発。実際に医療画像9,000枚だけで専門医を上回る診断精度を実現し、希少疾患領域での応用可能性を示した。このアプローチは、AI活用が難しかった領域に大きな突破口を開いたと評価されている。
日本の強みを再強化する応用領域
AI戦略の真価が発揮されるのは、応用領域である。特に日本が強みを持つ「創薬」と「素材開発」では顕著な成果が見られる。
- AI創薬では、MOLCUREやRevolKa、ソシウムなどのベンチャーが相次ぎ登場。開発期間を数年から数ヶ月に短縮し、難病薬開発や既存薬の再活用で成果を上げている。
- マテリアルズ・インフォマティクス(MI)では、旭化成や東レが新素材開発期間を数年から半年に短縮。ENEOSは従来比1万倍以上の速度で分子シミュレーションを行う技術を実証した。
さらに、富士フイルムや村田製作所、ブリヂストンもMIを導入し、半導体材料や電子部品、タイヤ素材の開発効率を高めている。これを支えるのがPreferred NetworksやNTTデータ数理システムといった専門企業であり、産学官連携によるエコシステムが確実に形成されつつある。
AI経済の成長ポテンシャル
国内AI市場は急成長が見込まれている。富士キメラ総研は2028年度に市場規模が2兆7,780億円に達すると予測し、そのうち生成AI関連市場は1兆7,397億円と、2023年度比で12倍以上の拡大を見込む。ただし、野村総合研究所の調査によれば、実際に生成AIを利用した日本人は9%に過ぎず、一般利用はまだ限定的だ。一方で企業導入効果は高く、導入企業の85%以上が成果を実感している。
この「個人利用の低さ」と「企業効果の高さ」のギャップは、AI市場のさらなる成長余地を示しており、労働力不足を抱える日本にとって生産性向上の切り札となる可能性がある。
世界と比較する日本の戦略ポジション

米国:民間主導のダイナミズムと安全保障の両輪
米国の技術戦略は、GoogleやMicrosoft、IBMといったBig Techが牽引する民間主導モデルに特徴がある。政府は「国家量子イニシアティブ法」や「CHIPSおよび科学法」を通じて基礎研究に巨額投資を行い、民間のイノベーションを支援する。さらに、バイデン政権はAIのリスク管理や透明性確保を目的とした大統領令を発令し、安全保障とのバランスを図っている。一方でトランプ政権は規制緩和と輸出管理強化に重点を置くなど、政権による力点の違いはあるものの、「民間活力を最大限活かしつつ安全保障を担保する」という構造は一貫している。
中国:国家主導の巨額投資とスピード
中国は米国とは対照的に、国家主導のトップダウン方式で技術覇権を狙う。AIや量子を「中国製造2025」などの国家計画に組み込み、巨額の投資を集中させている。量子技術分野への投資は2023年時点で153億ドルに達し、世界最大規模だ。研究開発は「軍民融合」によって軍事と民間が密接に連携し、衛星「墨子号」の打ち上げ成功など、実用化のスピードと規模では他国を圧倒している。
EU:人権と規制を基軸とする「第三の道」
欧州連合(EU)はイノベーションの加速よりも「ルール形成」に注力している。2024年に成立した「EU AI法」は世界初の包括的AI規制であり、AIを4段階のリスクに分類し、用途に応じた規制を義務付ける。例えば、医療や採用で使われる高リスクAIには市場投入前の厳格な適合審査が求められる。EUはGDPRと同様、この規制を世界標準として浸透させる戦略を描いている。
日本の立ち位置:米中欧の中間モデル
こうした比較から、日本の「選択と集中」戦略は、米国の民間主導型と中国の国家主導型の中間に位置している。日本は「産業応用と経済安全保障を両立するハイブリッド戦略」を掲げ、民間の創薬・素材開発での強みを伸ばしつつ、国家が安全保障上不可欠な技術を主体的に育成する。一方で、EUのように国際ルール形成を主導する力は限定的であり、米国のダイナミズムや中国の実行力に比べれば規模で劣る。今後の成否は、自国の強みを最大化しつつ、国際的な役割をどう築けるかにかかっている。
選択と集中の副作用:基礎研究と人材育成の危機
基礎研究の多様性喪失リスク
「選択と集中」は効率的な投資戦略とされる一方で、科学技術政策に適用すると重大な副作用を生む可能性がある。最大の懸念は、基礎研究の多様性が失われることだ。AIや量子など「重要技術」とされた分野に資金が集中すると、選ばれなかった研究領域が衰退しかねない。実際、現在の応用研究の多くは、過去の基礎研究の蓄積に支えられており、短期的成果を優先する過度の集中は未来のブレークスルーを阻害する恐れがある。
また、資金の集中が必ずしも成果に比例しない点も指摘されている。研究資金が一定規模を超えると「収穫逓減」が生じ、投資効果が薄れる現象がある。日本では、資金が集中するはずの一部トップ大学からの論文数が減少し、結果的に国全体の研究力低下につながっているとの分析も出ている。
若手研究者のキャリア不安と頭脳流出
もう一つの深刻な課題が人材問題である。特に若手研究者は任期付きポストに依存し、安定した研究環境を確保できないケースが多い。短期成果を求められることで、独創的・挑戦的な研究に取り組みにくくなっている。これが優秀な人材の研究離れや海外流出(ブレイン・ドレイン)を招いている。
大学の財政基盤が脆弱化する中で、若手が自立的に研究を始められるスタートアップ支援制度も限定的だ。AIや量子分野は国際的な人材獲得競争が激しく、国内育成だけでは不足している。世界中の才能を引きつけるには、魅力的な研究環境や長期的インセンティブが不可欠である。
イノベーション・エコシステムの持続性確保が課題
選択と集中戦略のもとで、理研や産総研といった中核機関は強化される一方で、地方大学や中小研究機関は資金難に直面している。結果として、エリート研究機関は富み、周辺は痩せ細る「マタイ効果」が進行するリスクがある。これは日本全体のイノベーション・エコシステムをトップヘビーかつ脆弱なものにしかねない。
したがって、日本が持続的な競争力を確保するためには、重点投資と同時に基礎研究や若手人材への底上げ施策を拡充し、裾野から峰へとつながる健全な研究パイプラインを維持することが不可欠である。
まとめ
日本の科学技術政策は、AIや量子といった先端分野に資源を集中させる「選択と集中」戦略によって、大きな転換期を迎えている。経済安全保障を基盤に、国家が自らの技術的自律性を確保しようとする姿勢は必然的な選択である。理研や産総研などの研究機関、Q-STARのような産業プラットフォーム、スタートアップ群が一体となり、産業化への道筋を描きつつある点は大きな強みだ。
一方で、この戦略は基礎研究の多様性を損なう危険や、若手研究者のキャリア不安、頭脳流出といった課題も抱えている。「峰」を高くするための集中投資と、裾野を支える基礎研究・人材育成とのバランスをどう取るかが、今後の日本の成否を決める。
米国の民間主導、中国の国家主導、EUの規制主導という異なるモデルが並立するなかで、日本はその中間に位置する独自戦略を模索している。国際競争の荒波を乗り越えるには、重点投資だけでなく、研究エコシステム全体の持続可能性を高める視点が欠かせない。選択と集中の光と影をいかにマネジメントするか――それこそが日本が未来に向けて果たすべき最大の課題である。
出典一覧
- 文部科学省「第6期科学技術・イノベーション基本計画について」 https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kihon/main5_a4.htm
- 経済産業省「経済安全保障と日本の対応」 https://www.hkd.meti.go.jp/hokia/20221226/data01.pdf
- 内閣府「経済安全保障重要技術育成プログラム」 https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/kprogram.html
- 理化学研究所「量子コンピュータ研究センター (RQC)」 https://www.riken.jp/research/labs/rqc/
- 情報通信研究機構(NICT)「量子暗号・物理レイヤ暗号の研究開発」 https://www.nict.go.jp/quantum/about/crypt.html
- 量子科学技術研究開発機構(QST)「ナノ量子センサによる哺乳類生体内の細胞温度計測に世界で初めて成功」 https://www.qst.go.jp/site/press/20240919.html
- 一般社団法人Q-STAR「量子技術による新産業創出協議会」 https://qstar.jp/
- 富士キメラ総研「生成AI関連の国内市場を調査」 https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=24114
- 野村総合研究所「生成AIを使用したことのある日本人はわずか9%」 https://times.gesher.co.jp/article/only-9-of-japanese-people-have-used-generative-ai-survey-by-nomura-research-institute
- JETRO「バイデン米政権、連邦政府機関のAI利用指針を発表」 https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/03/df301210e8a51dfd.html
- JETRO「トランプ米政権、AI行動計画を発表」 https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/07/795a9288d3eb6871.html
- 欧州委員会「EU Artificial Intelligence Act」 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

