現代日本において「小中学生の学力低下」は、保護者や教育現場で繰り返し語られる不安の象徴となっている。子どもがスマートフォンや動画に夢中になる姿を見て、「集中力が続かない」「昔より学力が下がっているのではないか」と感じる人は少なくない。しかし、OECDのPISAやIEAのTIMSSといった国際学力調査では、日本の児童生徒は依然として世界トップ水準の成績を維持している。特にパンデミック後、他国の成績が軒並み下がる中でも、日本は安定あるいは向上を見せている。
この矛盾は、「学力低下」という言葉が示す意味を問い直す契機となる。もし学力をテストの点数や順位に限定するなら、危機は存在しない。しかし国内調査では、知識を記述で説明する力や読解力の欠如が深刻に表れている。つまり、日本の子どもたちは「答えを知っていても説明できない」という構造的な課題に直面しているのだ。
本稿では、国際データと国内の警鐘を突き合わせながら、スマートフォン依存や読書習慣の崩壊、教育DXの光と影を分析する。その上で、海外の先進事例を交えつつ、家庭・学校・政策が一体となった再生の道を探る。未来を担う世代の知性をいかに守り育むか——それは日本社会全体の持続可能性を左右する喫緊の課題である。
学力低下は本当か:国際調査が映す日本の位置
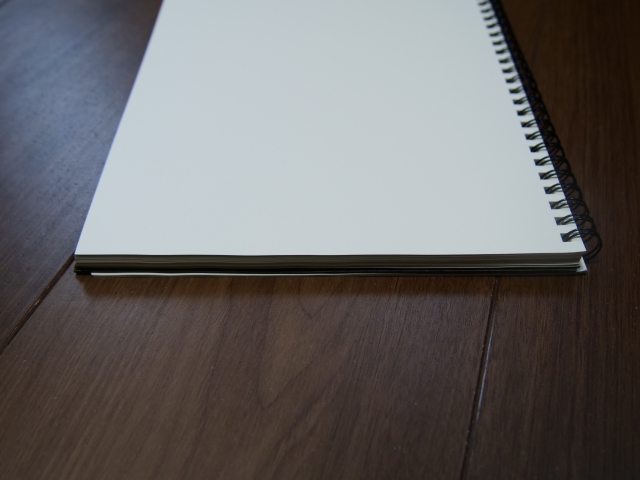
「日本の子どもの学力は下がっているのではないか」という懸念は社会で繰り返し語られてきた。しかし、OECDの国際学力調査「PISA」やIEAの「TIMSS」の結果を見ると、そのイメージとは対照的な現実が浮かび上がる。
PISA2022の結果によれば、日本の15歳は数学的リテラシーで世界5位(OECD加盟国中1位)、読解力で3位、科学的リテラシーで2位と、いずれもトップクラスに位置している。特に注目すべきは、新型コロナ禍で多くの国が大幅な得点低下を記録する中、日本はむしろ安定あるいは向上を示した点である。背景には、休校期間の短さや教員の努力による学習機会確保があったとされ、日本の教育システムの強靭さが裏付けられた。
さらにPISAのデータを分布で見ると、高得点層が多く低得点層が少ないという「質と公平性の両立」が際立つ。OECD平均と比較しても、学力のばらつきが小さく、教育機会の格差が比較的抑えられていることが確認できる。
同様にTIMSS2023でも、小学4年生が算数で5位、理科で6位、中学2年生が数学で4位、理科で3位と安定した結果を示した。特に数学は前回調査と同水準を維持し、日本の基礎教育の底堅さを証明したといえる。ただし理科に関しては一部の分野で平均点が低下しており、問題傾向の変化や生活環境との親和性の低さが影響している可能性が指摘されている。
一方で、国際調査においても課題は存在する。TIMSSの質問紙調査では、理科を「楽しい」と答えた中学2年生の割合が70%で国際平均の79%を下回り、「理科を使う職業につきたい」と答えた生徒は27%にとどまった。これは高い得点の裏で学習意欲や好奇心が十分に育まれていないことを示しており、学力の外的成果と内的動機の間にギャップがあることを浮き彫りにする。
つまり、テストスコアだけを見れば「学力低下」の懸念は誤解に過ぎない。しかし、子どもたちが学問を楽しみ、自ら探究する姿勢をどこまで獲得できているかという視点では、日本の教育は課題を抱えているのである。
国内調査が突きつける“説明できない子どもたち”
国際的には高い評価を得る一方で、国内の「全国学力・学習状況調査」が示す実態は異なる様相を呈している。特に顕著なのは、知識を活用して説明する力や、論理を言語化する力の弱さである。
令和6年度の調査では、中学3年生の国語の平均正答率が前年度の70.1%から58.4%へ急落した。出題内容の変化も影響しているが、知識をただ再生するのではなく、自らの言葉で説明する問題に対する脆弱さが浮かび上がっている。
データを詳しく見ると、短答式や選択式では正答率が70%を超える一方、記述式は大幅に低い。例えば国語では記述式問題の正答率が25.6%にとどまり、数学でも「式の意味を言語で説明する問題」が26.4%、「証明を完成させる問題」が33.8%という結果が示された。
この結果は、「答えはわかるが、なぜそうなるのか説明できない」子どもが多数存在することを意味する。つまり、知識を持っていても、それを活用し、論理的に組み立てて他者に伝える力が欠如しているのだ。
表:全国学力調査に見る記述式の弱さ
| 分野 | 記述式問題の正答率 | 傾向 |
|---|---|---|
| 国語(中3) | 25.6% | 要約や複数情報の統合に弱さ |
| 数学(中3) | 26.4% | 式の意味を説明できない |
| 数学(中3・証明問題) | 33.8% | 論理展開を記述できない |
この背景には基礎的読解力の不足があると考えられる。国立情報学研究所の新井紀子教授が提唱するリーディングスキルテストでも、子どもたちが中学教科書レベルの文章の構造を正確に理解できていない事例が多数報告されている。
国際調査で問われる「構造化された問題解決」と、国内調査で問われる「自由度の高い言語化」との間には大きな乖離が存在する。ここにこそ、日本の教育が直面する“見えにくい学力低下”の正体があると言えるだろう。
このように、点数や順位だけでは把握できない「説明できない子どもたち」の存在は、教育現場に深刻な課題を突きつけている。今後は、知識の獲得から一歩進んで、それをどう使いこなし、他者に伝えるかという力を育むことが求められている。
スマートフォン依存が脳と学習習慣に与える深刻な影響

現代の小中学生にとって、スマートフォンは単なる通信手段を超え、生活の中心にある存在となった。しかし、長時間利用が子どもの脳や学習に深刻な影響を及ぼすことが、脳科学や教育学の研究によって明らかになりつつある。
東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授らの調査によれば、スマホやゲームを長時間利用する子どもは「前頭前野」の発達が遅れる可能性があるという。前頭前野は思考・判断・感情の制御といった高度な認知機能を担う領域であり、特に9歳から18歳にかけて急速に発達する。この時期にスマホ漬けの生活を送ると、脳の発達そのものが阻害されるリスクがあると報告されている。
加えて、学力との逆転現象も注目に値する。川島教授らの研究では、スマホ利用時間が1日1時間を超えると成績が低下傾向を示し、1日3時間以上では「毎日2時間以上勉強する生徒が、勉強しないがスマホを使わない生徒より成績が低い」という結果すら確認された。つまり、学習時間の「量」を確保しても、「質」がスマホによって損なわれているのである。
この背景には「メディア・マルチタスキング」の問題がある。通知音やSNSチェックといった小さな中断が繰り返されるだけで、脳は集中を維持できなくなる。実験では、作業中にLINEの通知音を鳴らすだけで、注意力と作業効率が大幅に低下することが示された。スマホはそばにあるだけで集中を奪う「認知的負債」を生むのだ。
さらに「スマホ認知症」と呼ばれる現象も指摘されている。過度な利用は記憶力や段取り力を衰えさせ、思考の持続性を失わせる。これは学力だけでなく、将来の労働生産性や社会的自立にも影響しかねない。
つまり、スマホ問題の本質は「時間の浪費」ではなく「思考習慣の変容」である。短時間で刺激的な情報に慣れた脳は、長文読解や数学の証明といった粘り強い学習に耐えられなくなる。学力低下の陰には、スマートフォンが静かに進行させる知性の劣化が潜んでいるのである。
読解力の崩壊:活字離れが招く思考力の断絶
スマホ依存と並行して進むのが、子どもたちの「活字離れ」である。読書習慣の減少は、思考力や表現力の基盤である読解力を根底から揺るがしている。
国立情報学研究所の新井紀子教授は『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』で、中学生ですら教科書レベルの文章を正確に理解できない現状を指摘した。新井氏が開発したリーディングスキルテストでは、単語の意味は理解できても、文の係り受けや同義文判定でつまずくケースが多数確認されている。これは「読める」と「わかる」の断絶を如実に示している。
背景には読書習慣の衰退がある。全国学校図書館協議会の調査によれば、1か月に1冊も本を読まない「不読者」の割合は学年が上がるほど増え、高校生では約半数に達する。さらに読書内容はマンガ中心で、論理的・複雑な文章に触れる機会が極端に減少している。
この状況は学力調査の記述式問題にも反映されている。数学の証明ができないのは計算力不足ではなく、問題文を正確に理解できていないからである。国語の要約問題でつまずくのも、論理の流れを読み解く力が欠けていることが大きい。
また、SNSやショート動画など断片的で視覚的な情報に慣れた脳は、論理的に構成された文章を読むことを「苦痛」と感じやすい。結果として、深い読解に必要な神経回路が使われず、能力が劣化する。スマホ利用と読解力低下は別問題ではなく、相互作用して「思考力の空洞化」という負のスパイラルを生んでいるのだ。
表:読解力危機の実態
| 項目 | データ | 傾向 |
|---|---|---|
| 不読者率(高校生) | 約50% | 活字離れの深刻化 |
| 記述式国語問題正答率 | 25.6% | 論理統合の弱さ |
| 数学証明問題正答率 | 33.8% | 論理展開の表現力不足 |
このように、活字離れは単なる趣味の問題ではない。「読む力」を失うことは「考える力」を失うことに直結する。デジタル時代においても、人間がAIに代替されないために必要なのは、文脈を理解し、批判的に読み解く力である。教育現場がこの基盤を取り戻せなければ、学力低下は不可逆的に進行してしまうだろう。
GIGAスクール構想の功罪:教育DXの期待と落とし穴

日本の教育現場では「GIGAスクール構想」が国家プロジェクトとして推進され、1人1台端末と高速ネットワーク環境の整備が急速に進んだ。導入スピードは世界的にも類を見ず、デジタル教育の先進事例として注目を集めている。しかし、成果と同時に多くの課題も浮上している。
調査によれば、校長の多くは「個別最適な学び」や「協働的な学び」が促進されたと評価している。また、不登校児や特別支援が必要な生徒に学習機会を保障する点でICT活用が役立っていると報告される。ICT端末の利用を通じて、生徒のデジタルスキルが向上した事例も報告されており、教育機会の拡大という意味では一定の成果が確認できる。
しかし一方で、現場からは深刻な課題が指摘されている。まずインフラ面では、校内ネットワークが不安定で動画再生が滞るケースが多く、学習活動に支障をきたす例が後を絶たない。また、自治体ごとに異なるソフトウェアやプラットフォームを導入しているため、転校時に学習履歴が引き継げないといった「教育データの断絶」が生じている。
加えて教員の負担も大きい。ICT活用に積極的な一部の教員に業務が集中し、多忙な現場では研修を受ける時間も不足している。「端末を配布するだけでは学びは変わらない」という現場の声は強く、教育哲学や指導法の変革が追いついていない現実がある。
さらに、生徒側の課題も無視できない。家庭の経済格差によるデジタルデバイドや、端末を用いたネットいじめ、不適切サイトへのアクセスなどリスクは拡大している。ICT教育を推進した川島隆太教授も「エビデンスの多くがネガティブな影響を示している」と警鐘を鳴らす。
結局のところ、GIGAスクール構想は「導入」から「活用」への質的転換が求められている。今後はハード整備ではなく、教員研修・教育コンテンツ・情報モラル教育の充実という“ソフト面”への投資が不可欠である。デジタルが学びを支える武器になるのか、それとも格差を拡大する刃となるのか、岐路に立っているのが現在の教育現場だ。
海外に学ぶ教育改革:フランス・フィンランド・韓国の実践
日本が直面する「学びの危機」を乗り越えるヒントは、海外の先進的な取り組みにも見出せる。特にフランス・フィンランド・韓国の事例は、それぞれ異なるアプローチで教育の質を高めようとしており、日本にとって有益な示唆を与える。
フランスは2018年、世界で初めて幼稚園から中学校までの校内でスマートフォン使用を法律で原則禁止した。狙いは授業集中度の確保、スマホ依存の抑制、ネットいじめ対策である。導入後、一部の学校ではネットいじめの件数が減少するなどの効果が見られた。デジタル機器を「制限」することで環境を整える発想が特徴的だが、学校外の利用や子どもの自主的判断力育成には限界もある。
一方、フィンランドは「読解教育」を徹底してきた国として知られる。PISAで世界トップを誇った背景には、幼少期から文章を批判的に読み解く訓練を体系的に施す教育法があった。しかし近年は順位を落とし、国内では改めて「学びの質」への回帰が進んでいる。ここから学べるのは、教育の根幹は一貫して「読む力」を育むことにあるという普遍的な教訓である。
韓国は世界有数のIT先進国でありながら、スマホ依存やネットいじめの深刻さも際立つ。これに対し、政府は専門相談窓口の設置、サイバーパトロールの強化、加害者への法的対応などを推進。同時に学校での情報モラル教育や家庭でのルール作りも推奨し、社会全体でリスクに立ち向かう「総合対策モデル」を築いている。
これらの事例は、日本が取るべき道を単一化するものではない。むしろ重要なのは、フランスの「制限」、フィンランドの「教育内容への回帰」、韓国の「総合対策」を組み合わせ、日本の文脈に即したハイブリッド戦略を構築することだ。
つまり、デジタル社会における教育改革は、テクノロジーを盲信するのでも、排除するのでもなく、現実的なバランスを取ることが肝要である。海外の実践はその道筋を示しており、日本の教育政策にとって強力な羅針盤となるだろう。
「禁止」から「共生」へ:デジタル・シティズンシップ教育の可能性
スマートフォンやタブレットを完全に排除することは、現代社会では現実的ではない。むしろ、テクノロジーとどう向き合い、主体的に使いこなすかが教育の核心となっている。その鍵を握るのが「デジタル・シティズンシップ教育」である。
従来の情報モラル教育は「危険だからやらない」という禁止型の指導に偏りがちだった。しかし、それでは子どもたちは抜け道を探すだけで、根本的な自律性は育たない。これに対しデジタル・シティズンシップ教育は、「デジタル社会の善き市民」としてテクノロジーを安全・責任・倫理的に使う力を養うことを目的とする。
例えば、愛媛県四国中央市では、各学級に「ICT係」を設置し、生徒自らが端末の適切な使い方を考え、ルールを発信する仕組みを導入した。福井県ではSNSでの表現方法やメディアリテラシーを国語や社会などに組み込み、教科横断的に教育を行っている。これらの事例に共通するのは、子どもたち自身の主体性を尊重し、現実的な課題について対話を通じて学ばせる点である。
家庭においても、単なる使用制限ではなく「なぜそのルールが必要か」を話し合い、納得の上でルールを決めることが効果的とされる。実際に「夜9時以降は使用禁止」「アプリのダウンロードは親の承認制」といったルールを親子で合意した家庭では、スマホ利用のトラブルが減少したという報告もある。
重要なのは、子どもが自分の中に判断基準を持つことだ。「禁止」から「共生」への転換は、テクノロジー社会を生き抜くためのリテラシー育成に直結する。日本の教育がデジタル・シティズンシップ教育を本格的に導入できるかどうかは、未来の学力を左右する分岐点となるだろう。
政策・学校・家庭に求められる三位一体の対応策
子どもたちの学力低下の実態は単純ではない。テストの点数に表れるものではなく、思考力や読解力、そしてデジタル社会で自律的に生きる力の欠如に根ざしている。この課題に立ち向かうには、政策・学校・家庭が三位一体となった取り組みが不可欠である。
まず政策レベルでは、全国学力・学習状況調査の評価方法を再設計する必要がある。単なる知識再生型の問題を減らし、記述式やプロジェクト型の課題を重視すべきだ。これにより、教育現場も「知識をどう使うか」に焦点を移すことが可能になる。また、GIGAスクール構想もハード整備からソフト整備へと移行し、教員研修や質の高い教育コンテンツ開発に重点を置く「2.0」への進化が求められる。
学校においては、全教科を横断して「読む力」を育成する取り組みが必要だ。例えば数学の授業でも問題文を論理的に分解させ、根拠を明示させる練習を取り入れる。さらに「ノーメディアデー」や「読書週間」といった取り組みを導入し、デジタルから距離を置く体験を意図的に設けることも効果的である。
家庭では、親子でルールを話し合い、明文化することが重要だ。例えば以下のような形で合意形成する家庭も増えている。
- スマホ使用はリビングのみ
- 夜9時以降は利用禁止
- ルール違反時のペナルティを事前に設定
また、親自身が模範を示すことも不可欠である。食事中にスマホを見ない、読書する習慣を共有するなど、行動で示すことが最も効果的な教育となる。
結局のところ、学力の再生には「社会全体で学びを支える文化」を取り戻すことが必要である。点数至上主義に終始せず、深く読む力、論理的に考える力、テクノロジーを賢明に使いこなす力を育む。そのために、政策・学校・家庭がそれぞれの役割を担い、連携することが未来の知性を守る唯一の道である。
まとめ
日本の小中学生をめぐる「学力低下」論は、必ずしも国際調査の結果と一致していない。むしろPISAやTIMSSのデータは、依然として日本の学力が世界トップ水準であることを示している。しかし同時に、国内調査が明らかにする「説明できない子どもたち」の存在、スマートフォン依存による脳への影響、読解力の低下など、テストでは測りきれない“知性の質の変容”が深刻化している。
GIGAスクール構想は教育の未来を切り拓く可能性を持つ一方で、現場の混乱や格差拡大という副作用も露呈している。こうした状況を克服するには、政策・学校・家庭が一体となり、読解力や思考力を再び教育の中心に据える必要がある。
海外の事例が示すように、単なる「禁止」ではなく「共生」を基盤としたデジタル・シティズンシップ教育の導入が不可欠である。子どもたちがテクノロジーを自律的に使いこなし、批判的に物事を考える力を身につけることができれば、日本の教育は“点数主義”を超えた新たな学びの地平へと進むことができるだろう。
出典一覧
- OECD/国立教育政策研究所「PISA2022のポイント」 https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2022/01_point_2.pdf
- 文部科学省「OECD生徒の学習到達度調査(PISA2022)」 https://www.mext.go.jp/content/20240312-mxt_kokusai-000020406_3.pdf
- 国際教育到達度評価学会(IEA)「TIMSS2023結果概要」 https://www.mext.go.jp/content/20241223-mxt_chousa02-000039290-8.pdf
- 文部科学省「令和6年度全国学力・学習状況調査」 https://school-security.jp/news/2024/08/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9C%81%E3%80%8C%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%AD%A6%E5%8A%9B%E3%83%BB%E5%AD%A6%E7%BF%92%E7%8A%B6%E6%B3%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE/
- 新井紀子『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』/リーディングスキルテスト調査 https://www.flierinc.com/summary/1489
- 全国学校図書館協議会「学校読書調査」 https://www.j-sla.or.jp/material/research/dokusyotyousa.html
- 東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授ほか「スマホ利用と脳発達に関する研究」 https://toyokeizai.net/articles/-/587902
- 文部科学省「GIGAスクール構想の成果と課題」 https://www.mext.go.jp/content/20230612-mxt_jogai01-000030057_005.pdf
- 総務省「家庭で学ぶデジタル・シティズンシップ~実践ガイドブック」 https://www.soumu.go.jp/main_content/000874784.pdf
- UNESCO/フランス教育省「スマートフォン校内禁止に関する政策」 https://globe.asahi.com/article/15065022

