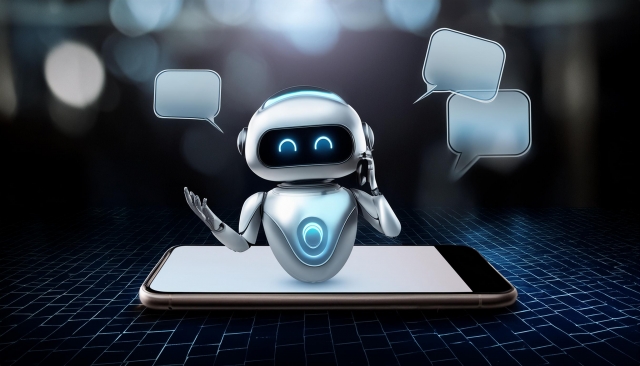ダイキン工業は2025年、歴史的な転換点を迎えている。2021年に始動した中期経営計画「FUSION25」は、売上高目標を大きく上回る勢いを見せる一方、営業利益では計画未達が確実視される状況となった。欧州のヒートポンプ需要減速や中国不動産市場の停滞といった外部要因が収益を直撃し、規模拡大と収益確保という二律背反に直面しているのである。
こうした環境下で、同社は戦略の大転換を進めている。北米では競合に奪われたシェアを取り戻す「ウィンバック」戦略を推進し、同時にAIデータセンター冷却市場へのM&A参入という新たな成長領域を切り開いた。さらに、脱炭素ソリューションへの投資やデジタル人材育成など、従来の製造業モデルを超えた事業革新にも取り組んでいる。
しかし、最大の懸念はPFAS(有機フッ素化合物)問題である。従業員から国平均の数百倍に及ぶ濃度が検出された事実は、同社の垂直統合型モデルを揺るがしかねない深刻なリスクとなっている。今後の持続的成長は、これらの課題にいかに対応しつつ、新たな市場機会を確実に捉えられるかにかかっている。
FUSION25の審判:売上拡大と収益圧力の二律背反

ダイキン工業の中期経営計画「FUSION25」は、2021年の策定以来、同社の成長戦略の指針であり続けてきた。売上規模の拡大においては計画を上回る成果を示し、2026年3月期の売上高は4兆8,400億円と修正目標の4兆5,500億円すら超過する見通しとなっている。しかし、営業利益については当初目標5,000億円に対し4,350億円にとどまる見込みであり、明確な未達が示されている。この二律背反は、外部環境の変化と事業構造上の課題を浮き彫りにしている。
具体的には、欧州のヒートポンプ暖房市場が補助金削減や天然ガス価格の安定化により急減速し、中国の住宅市場も長期的な不況に直面した。これらの市場はダイキンにとって成長ドライバーであったが、政策主導の特性が裏目に出た形である。ポーランドに建設した新工場が低稼働率に陥っている事実は、過剰な楽観シナリオに基づいた投資判断のリスクを示している。
一方で、経営陣は収益性改善に向けた戦略転換を進めている。コスト削減の徹底、高付加価値商品の拡販、価格政策の強化を通じて営業利益率を9%に維持し、厳しい環境下でも利益の下支えを図っている。ここには、短期的な市場逆風を吸収し、長期的な収益基盤を再構築しようとする強い意思が表れている。
表:FUSION25目標と最新業績見通し(2026年3月期)
| 項目 | 当初目標(2021年) | 修正目標(2023年) | 最新予想(2025年9月) |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3兆6,000億円 | 4兆5,500億円 | 4兆8,400億円 |
| 営業利益 | 4,300億円 | 5,000億円 | 4,350億円 |
| 営業利益率 | 約12% | 11% | 9% |
この乖離は、成長市場への過度な依存がもたらした結果であり、今後の投資判断における教訓といえる。ダイキンの持続的成長は、規模追求から利益構造の強化へと軸足を移すことにかかっている。
財務パフォーマンスが示す底堅さと課題
2026年3月期第1四半期の決算は、売上高が前年同期比3%減となったものの、営業利益は1,213億円と前年同期比5.1%増を達成し過去最高を更新した。この結果は、米国の新関税による75億円規模の逆風を価格転嫁とコストダウンで吸収し、オペレーション能力の高さを証明したものである。特に、空調・冷凍機事業が全社売上の9割を占める中で営業利益を二桁成長させた点は注目に値する。
一方で、化学事業は深刻な不振に直面した。半導体需要の低迷や自動車市場の回復遅れが直撃し、営業利益は前年同期比58%と半減した。高収益源である化学事業の失速は、収益全体に大きな穴を開けており、経営陣は空調事業での収益補填を余儀なくされている。
表:2026年3月期第1四半期セグメント別業績(前年同期比)
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 空調・冷凍機事業 | 97% | 110% | 10.1% |
| 化学事業 | 96% | 58% | 10.9% |
| その他 | 98% | 10% | 0.5% |
株価動向も財務パフォーマンスの反映となっている。2025年9月時点の株価は17,720円前後で推移し、時価総額は約5.2兆円を維持している。アナリストの多くは「買い」を推奨しており、目標株価は現状より11〜12%高い19,817円前後とされているが、欧州需要の不透明感を理由に慎重な見方も存在する。
ダイキンの財務は底堅さを示す一方、短期的な外部環境に依存する脆弱性も露呈した。今後の課題は、空調事業の収益力を維持しつつ、化学事業の景気循環リスクをいかに克服し、新たな成長柱を確立できるかにかかっている。
北米・欧州・インド・中国にみる地域戦略の行方
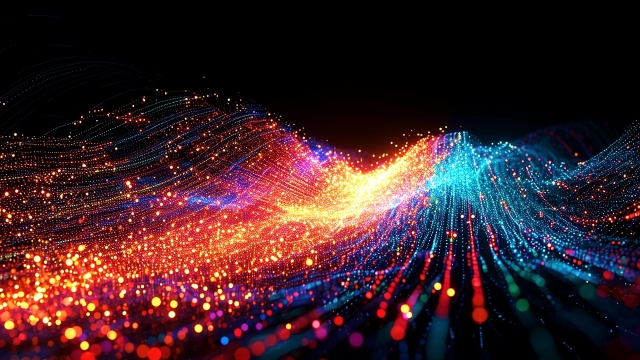
ダイキン工業の成長を支える根幹は、各地域市場での適応力と戦略遂行力にある。特に北米と欧州は収益基盤、インドは未来投資、中国・アジアは高付加価値戦略という役割を担い、複合的な戦略が展開されている。
北米:シェア奪還とサービス化への転換
北米市場は世界最大の空調需要地であり、ダイキンの最重要戦略地域である。住宅用ユニタリー市場でのシェア奪還を目指す「ウィンバック」戦略は当初出遅れたが、2026年3月期第1四半期には目標の45%まで回復した。新冷媒R32搭載製品を前面に押し出し、競合製品との差別化を図る姿勢が奏功しつつある。
さらに業務用事業では、サービス・ソリューション比率を50%以上へ高める方針を掲げている。AIデータセンター冷却を強みとする米DDCS社買収は、その具体的な布石であり、販売からライフサイクル管理までを一体化する事業モデルを加速させている。
欧州:ヒートポンプ市場の踊り場と次の一手
欧州市場では、補助金削減や天然ガス価格の下落により、急成長を続けていたヒートポンプ需要が減速した。ポーランド新工場は稼働率低下に直面し、短期的には逆風が強い。
しかしダイキンは自然冷媒R290を活用した新商品投入や、複雑化する補助金申請支援を強化することで競争力を維持している。2025年までに生産能力を4倍に拡大する計画を継続しており、短期の停滞を超えた長期的な電動化シフトを見据えている。
インド:一大拠点化への巨額投資
インド市場はFUSION25後半で最重要戦略地域に格上げされ、約200億円を投じた新工場が稼働を開始した。圧縮機まで一貫生産する体制を構築し、2025年度には売上高2,000億円を目指す。
販売網も「ソリューション・プラザ」を350店舗まで拡大予定であり、研究開発拠点の新設も進んでいる。2026年3月期第1四半期は天候不順で業績が低迷したが、中長期的にはインドをアフリカ・中東への輸出拠点とする戦略は大きな潜在力を持つ。
中国・アジア:高付加価値集中戦略
中国市場は住宅不況で需要が冷え込む中、ダイキンは高付加価値型マルチエアコンに集中し、直接販売を強化して高利益率を維持している。ASEANでは住宅需要の低迷を業務用市場で補完し、販売店網の拡充によってインフラ案件を着実に獲得している。
このように、地域ごとに「市場シェアの奪還」「次世代市場の創出」「高付加価値集中」を組み合わせた戦略を展開しており、複雑なグローバル戦略がダイキンの将来を左右している。
空調・化学という二大事業の進化と競争環境
ダイキン工業の事業基盤を支えるのは、空調事業と化学事業という二大エンジンである。両事業は異なる成長性とリスクを抱えながら、グローバル市場での競争優位を形成している。
空調事業:モノ売りからコト売りへ
空調事業は売上の約9割を占める中核であり、今や単なる製品販売からサービス・ソリューション提供へと転換している。遠隔監視データを活用したクラウド型プラットフォーム「DK-CONNECT」は、予知保全やエネルギー管理を可能にし、継続収益モデルを構築する中心的存在である。
さらに、欧州では冷媒の循環利用を進め、廃棄物削減と同時に新たなサービスビジネスを創出している。こうした循環型経済への対応は、環境規制が強化される市場で競争力を高める手段となっている。
化学事業:フッ素材料の両義性
ダイキンは1,800種類以上のフッ素化合物を手がけ、半導体やEVバッテリー向けに不可欠な素材を供給してきた。しかし2025年には半導体需要低迷の影響を受け、営業利益は前年同期比58%に落ち込んだ。
一方で、EV市場向けフッ素材料は次世代成長領域として期待されている。リチウムイオン電池の性能を左右するバインダーやガスケット分野での技術投資は、今後の化学事業の柱となる可能性を秘めている。
グローバル競争環境と優位性
世界の空調市場は、中国の美的集団や格力、米国のキャリアやトレーン、日本の三菱電機などが激しく競合している。各社は脱炭素化やサービス化を戦略の柱とし、方向性は収斂してきている。
この中でダイキンの独自性は、空調機器と冷媒を一貫開発できる垂直統合モデルにある。冷媒規制強化の流れの中で、新冷媒開発からシステム設計までを一体で進められる能力は他社にない強みである。ただし、PFAS問題がこの優位性を揺るがすリスクも存在し、最大の強みと最大のリスクが背中合わせになっている点が特徴的である。
空調と化学という二大事業は、収益とリスクを補完しあう存在でありながら、グローバル競争環境と規制強化に直面することで新たな進化を求められている。
AIデータセンター冷却と脱炭素ソリューションの新展開

ダイキン工業は既存事業の成長停滞を打開するため、新たな市場機会を積極的に開拓している。その象徴が、AIデータセンター冷却事業と脱炭素ソリューション事業である。これらは単なる周辺ビジネスではなく、今後の収益構造を根底から変革しうる戦略的投資として位置づけられている。
AIデータセンター冷却:次世代インフラへの参入
2025年8月、ダイキンは米Dynamic Data Centers Solutions(DDCS)の買収に合意した。DDCSはサーバーラック単位や半導体チップ単位での個別冷却技術に強みを持ち、AI用途に不可欠な高効率冷却を実現する。同社の大型空調技術と組み合わせることで、施設全体からチップ単位までを包括的に冷却できる体制が整う。
生成AIの普及により、データセンターの電力消費量は今後10年で2倍以上に膨らむと予測される。冷却効率の優劣が運営コストを大きく左右するため、この市場は急成長が見込まれている。ダイキンにとっては、北米市場を足掛かりにグローバル展開を加速させる絶好の機会である。
脱炭素ソリューション:社会課題を収益機会に
ダイキンは単なるCSR活動ではなく、脱炭素を事業モデルとして取り込む姿勢を鮮明にしている。2025年6月にはCO2排出量可視化サービスを手がけるアスエネに出資し、省エネ機器やエネルギー管理システムと組み合わせて企業向け脱炭素支援サービスを展開する。
さらに、日本政府のGXリーグに参画し、政策形成にも積極的に関与している。これは同社の技術が優位に働く事業環境を創出するための戦略的活動であり、単なる省エネ機器メーカーから社会的課題解決型企業への進化を示すものだ。
成長シナジーの可能性
AIデータセンター冷却と脱炭素ソリューションは独立した事業ではなく、互いに補完し合う関係にある。データセンターの冷却効率化は脱炭素にも直結し、両事業を組み合わせることで顧客に包括的な価値を提供できる。この統合戦略は、ダイキンが「空気と環境」を軸に新しい成長領域を切り拓いている証左である。
PFAS問題が突きつける事業リスクとブランドへの影響
ダイキン工業にとって最大のリスク要因は、フッ素化学製品に不可欠なPFAS(有機フッ素化合物)である。高い収益を生み出してきた一方、その環境残留性と健康リスクから「永遠の化学物質」と呼ばれ、規制強化と訴訟リスクの波が押し寄せている。
深刻化する実態と乖離
2025年には大阪府淀川製作所の周辺環境から高濃度のPFASが検出され、元従業員においても血中濃度が国平均の500倍から5万倍に達するケースが確認された。企業は公式には健康被害を否定してきたが、内部資料や住民説明会での発言から現実との乖離が浮き彫りとなった。
この矛盾は企業倫理とガバナンスに対する信頼を大きく損ない、社会的非難を集めている。米国では同様の問題で化学大手3Mが事業撤退を決断しており、ダイキンも同様のリスクに直面している。
財務・ブランドへの影響
PFAS問題がもたらすリスクは、罰金や浄化費用だけにとどまらない。住民や従業員からの集団訴訟、グローバルブランドとしての信頼失墜、さらには冷媒技術の開発遅延による競争優位性の喪失が懸念される。特にダイキンの最大の強みである垂直統合モデルは、冷媒開発に依存しているため、PFAS規制が進めば根本的な事業基盤を揺るがしかねない。
今後の対応と展望
同社は既に3億ドルを投じて排出削減技術を導入し、PFAS代替技術の研究開発を進めている。フッ素ゴムは2025年まで、その他の高分子も2030年頃までに代替へ移行する計画を公表している。
しかし、規制のスピードが開発を上回れば、競合他社の特許技術に依存せざるを得ず、独自性を失うリスクがある。投資家にとっては四半期決算以上に、代替技術開発の進捗を注視することが求められる状況である。
PFAS問題は、成長戦略の裏側に潜む最大のアキレス腱であり、環境規制の波をどう乗り越えるかが、ダイキンの未来を左右する決定的な分岐点となる。
ガバナンス改革と企業文化の持続性

ダイキン工業は、売上高5兆円規模へと成長した今もなお、独自の企業文化を維持し続けることを最大の強みとしてきた。しかし、経営トップの交代やグローバル化の加速に伴い、ガバナンス体制と文化の持続性がかつてないほど注目されている。特に、ポスト井上礼之時代における経営スタイルの変化は、同社の未来像を占う上で不可欠な論点である。
経営トップ交代がもたらす変化
2024年、長年にわたりダイキンをグローバルリーダーへと導いた井上礼之氏が会長職を退任した。後任として竹中直文社長と十河政則会長が舵を取る体制となり、経営の継続性は確保されている。しかし、世界市場の変化スピードは加速しており、従来の「人を基軸におく経営」理念をどのように発展させるかが試されている。
新体制の課題は、短期的な収益回復と長期的な文化維持を両立させることである。特に北米や欧州での収益改善と同時に、PFAS問題や市場リスクへの対応を迫られる中、意思決定の迅速性と透明性が問われている。
多様性の欠如とグローバル対応力
ダイキンの経営陣は依然として日本人男性が中心であり、外国人や女性役員は極めて少ない。この状況は、海外売上比率が8割を超えるグローバル企業としては明らかな弱点である。
米キャリアや中国美的集団など競合は多国籍人材を積極的に登用し、現地市場の動向を迅速に経営へ反映させている。ダイキンも持続的に競争力を保つためには、ガバナンス体制に多様性を取り込み、国際的な視野を持つ意思決定を実現する必要がある。
独自文化の持続性
ダイキンの最大の強みは、現場の自主性と挑戦を許容する文化にある。社員が上司の意向に逆らってでも提案を貫く「野人」の存在は、革新的な製品やサービスの源泉となってきた。
一方で、企業規模の拡大は官僚主義やリスク回避といった大企業病を招きかねない。特に売上規模が拡大した今、効率性を重視するあまり現場の活力を削ぐ危険性が指摘されている。経営陣が文化を維持するためには、制度よりも日々のマネジメントや人材育成に重点を置く必要がある。
今後の課題と展望
ガバナンス改革と企業文化の持続は、収益改善や新規事業開発以上にダイキンの未来を左右する要素である。多様性の欠如は組織の盲点を生み、文化の形骸化は競争力の源泉を失わせる。
今後2~3年は、新経営体制が迅速な意思決定と現場文化の維持を両立できるかどうかが焦点となる。もしこのバランスを崩せば、ダイキンは規模は大きいが革新性に欠ける「普通の優良企業」へと変質しかねない。逆に、この課題を克服できれば、世界の空調・環境ソリューション市場で揺るぎない地位を確立できるだろう。