ファーストリテイリングは2025年、売上収益2兆6,167億円、営業利益4,509億円という過去最高の業績を更新し、世界的アパレル企業としての存在感を改めて示した。しかし、決算発表直後に株価が急落した事実は、市場が単なる好業績に酔わされることなく、将来のリスクに強い警戒感を抱いていることを浮き彫りにした。円安や原材料費の高騰、さらに北米市場で見込まれる高関税適用は、今後の収益性を大きく左右する要因となり得る。
同社の成長を支えているのは、依然として海外ユニクロ事業である。欧米市場を中心に積極的な出店を進め、現地消費者に「LifeWear」という普遍的価値を浸透させている。一方で、第二の柱とされるジーユー事業は収益改善に苦戦し、ブランド再構築とグローバル化という難題に直面している。
また、サプライチェーンを革新する「有明プロジェクト」や、全員が経営者意識を持つ「グローバルワン・全員経営」といった独自の経営哲学が、10兆円企業を目指す同社の野心を支える。だが、サステナビリティや人的資本への投資といった社会的要請を満たしつつ、激化するZARAやH&Mとの競争を勝ち抜く必要がある。ファーストリテイリングの挑戦は、成長とリスクが交錯する複雑な局面に差し掛かっている。
過去最高業績と市場の冷ややかな視線

2025年8月期第3四半期までのファーストリテイリングの業績は、売上収益2兆6,167億円、営業利益4,509億円と、いずれも過去最高を記録した。前年同期比で売上は10.6%増、営業利益は12.2%増と力強い成長を見せており、同社のグローバル展開戦略が成果を挙げていることは明らかである。特に、欧米市場での新規出店やインバウンド需要の回復が業績を押し上げた。
また、国内事業においても売上収益は8,014億円と前年同期比11.0%増となり、成熟市場でありながら底堅い成長を示した。Eコマースの売上は1,217億円に達し、オンラインとオフラインを融合させる戦略が実を結んでいる。
主要な財務指標は以下の通りである。
| 項目 | 2025年8月期第3四半期累計 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上収益 | 2兆6,167億円 | +10.6% |
| 営業利益 | 4,509億円 | +12.2% |
| 純利益 | 3,390億円 | +8.4% |
しかし、この華々しい実績にもかかわらず、市場の反応は冷ややかであった。2025年7月10日の決算発表翌日、株価は前日比3,240円安の43,500円へ急落し、日経平均株価を260円以上押し下げる要因となった。
市場が注目したのは過去の好業績ではなく、将来的なリスクであった。円安や原材料費高騰によるコスト増、3〜5月期における粗利益率低下、さらに2026年以降北米で適用される高関税リスクなどが投資家心理を冷やした。ベトナム製品に20%、バングラデシュ製品に35%の関税が課されれば、年間約300億円のコスト増になると試算されている。
一方で、証券アナリストの評価は依然として「買い」が優勢であり、平均目標株価は53,617円と現状より上昇余地があるとの見解を示す。短期的なリスクを重視する個人投資家と、長期的な成長戦略を評価する専門家の間で、明確な認識の差が浮き彫りになったのである。
つまり、ファーストリテイリングは業績の頂点に立ちながらも、利益率の頭打ちや外部リスクを背景に「成功のパラドックス」に直面しているといえる。過去最高益の裏で生じた市場の不信感は、10兆円企業を目指す同社の未来を試す試金石となっている。
海外ユニクロ事業が牽引する成長と依存リスク
ファーストリテイリングの成長を支えているのは、依然として海外ユニクロ事業である。2025年8月期第3四半期までに1,642億円の増収を記録し、全体の増収額の過半を占めた。欧州、北米、東南アジア市場での積極的な出店と現地顧客への浸透が、業績を押し上げている。
特に欧州ではローマやワルシャワなどへの新規出店が好調に推移し、2025年には15店舗、2026年には20店舗以上の追加出店が予定されている。2027年までに売上収益5,000億円を目指す計画も進行中であり、欧州は次なる成長の柱として期待されている。
北米市場でもテキサス州をはじめとする新規店舗が堅調な滑り出しを見せ、長期的には売上収益3兆円規模の成長が見込まれている。さらに東南アジアやインドといった人口大国でも事業拡大を加速させており、海外事業は名実ともにグループ成長の原動力となっている。
海外ユニクロ事業の現状を整理すると以下のようになる。
- 欧州:2027年までに売上収益5,000億円を目標
- 北米:将来的に売上収益3兆円規模を視野
- 東南アジア・インド:積極的な店舗拡大を継続
- グレーターチャイナ:消費低迷により減益傾向
ただし、この成功には大きな依存リスクが伴う。グレーターチャイナ市場では消費意欲の低下によって減益を記録し、地政学的リスクの影響も顕在化している。また、北米市場では前述の関税問題が利益構造を直撃する可能性が高い。
欧米市場のポテンシャルは依然として大きいものの、ファーストリテイリングが海外ユニクロに依存しすぎれば、特定地域の景気後退や政治的リスクに直撃される脆弱性を抱えることになる。
成長の主役である海外ユニクロ事業は、同時に最大のリスク要因でもある。ここで持続可能な成長モデルを確立できるか否かが、10兆円企業という壮大な目標の成否を左右するのである。
国内ユニクロ事業:成熟市場における持続的成長モデル
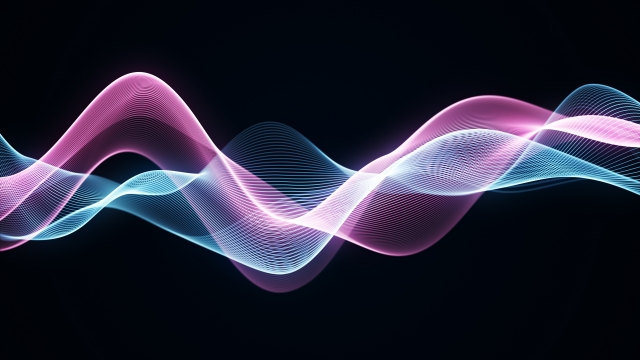
国内ユニクロ事業は、日本市場の成熟度を背景に大幅な成長は難しいと見られていたが、2025年に入っても堅調な伸びを示し、グループ全体の安定収益源として機能している。2025年8月期第3四半期までの売上収益は8,014億円で前年同期比11.0%増を記録した。インバウンド需要の回復に加え、Eコマースの拡大がその成長を支えている。
国内ユニクロの成長要因を整理すると以下のようになる。
- Eコマースの急拡大
- インバウンド需要の増加
- 事業運営効率の改善
- ブランド力の浸透
特にEコマースは、オンラインと実店舗をシームレスに結びつけるO2O戦略の中核を担っている。2025年3Q累計でのEC売上は1,217億円に達し、前年同期から2ケタの伸びを確保した。顧客はオンラインで商品を確認し、店舗で試着や購入を行うという購買行動をとるケースが増加しており、ユニクロが打ち出す「どこでも買える」戦略が定着しつつある。
また、訪日外国人観光客の回復も収益に大きく寄与している。特に都市型店舗では、インバウンド需要が売上全体の押し上げ要因となり、ブランドの国際的な認知度向上にもつながっている。
さらに、販売効率の向上が経営数値にも表れている。販売好調により売上高販管費率が改善し、営業利益率の維持に貢献した。国内ユニクロは既に市場の飽和段階にあるが、このような効率経営の徹底によって、成熟市場における持続的な利益創出モデルを構築している。
しかし課題も残る。特に地方店舗では需要の伸び悩みが見られ、人口減少や購買力低下の影響を受けやすい。また、国内消費者の低価格志向が続く中で、原材料費や物流費の上昇分をどこまで吸収できるかは不透明である。
つまり、国内ユニクロ事業は成長余地こそ限られているが、Eコマース拡大とインバウンド需要の取り込みにより安定的に収益を確保する役割を果たしている。これは、海外事業に依存するグループ全体にとって、リスク分散と経営の安定性を担保する重要な存在である。
ジーユー事業の再建とグローバル挑戦
ジーユー事業は、ファーストリテイリングが掲げる「10兆円企業」構想の実現に向けて、第二の成長の柱として期待されている。しかし現状では粗利益率の低下やヒット商品の不足による減益が課題となっている。2025年3〜5月期には単独で減益を記録しており、収益性改善は急務である。
同社はジーユーの再建に向け、複数の戦略的施策を打ち出している。
- 商品開発拠点をニューヨークに移転
- 「GU USグローバル本部」を設立し、企画から販売まで統括
- 世界市場を前提としたトレンド商品開発を推進
- ブランドの再定義による「トレンド×低価格」の確立
ニューヨークに拠点を移すことで、世界のファッションの中心地から直接トレンドを吸収し、企画・デザインに反映させる体制を整えた。従来の日本中心の商品開発からの脱却は、グローバルブランドとして成長するための必然的な改革である。
ジーユーのブランド・アイデンティティは「誰もが手に入れやすいトレンドファッション」である。ユニクロが機能的なベーシックウェアを軸とするのに対し、ジーユーは流行をいち早く取り入れ、若年層を中心に共感を得ることを目指している。この住み分けが明確化すれば、グループ全体のポートフォリオ効果も高まる。
直近では、ニューヨーク・ソーホー地区に旗艦店を開業し、ブランドの存在感を高める取り組みを進めている。これは単なる店舗展開ではなく、ブランド価値を国際市場で確立するための戦略的投資である。
一方で、ジーユー事業は依然としてリスクを抱える。グローバル化の過程で供給網の効率化、現地ニーズへの対応、価格競争力の維持など、多岐にわたる課題が存在する。加えて、ZARAやH&Mといった既存のグローバルファストファッションとの競争は激しく、ジーユー独自のポジションを築けなければ淘汰される可能性もある。
ジーユー事業の成否は、ファーストリテイリング全体の成長戦略に直結する。第二の柱として本格的に立ち上げることができれば、ユニクロに依存する収益構造の改善につながり、10兆円構想の実現可能性は一段と高まるだろう。逆に失敗すれば、海外ユニクロ事業への依存度が高まり、グループ全体のリスクを増幅させる結果となる。
有明プロジェクトとDXが変えるサプライチェーンの未来

ファーストリテイリングの競争力の源泉は、サプライチェーン全体を変革する「有明プロジェクト」と、それを支えるデジタルトランスフォーメーション(DX)にある。同社は従来のSPAモデルから「情報製造小売業」へと転換し、無駄を徹底的に排除する仕組みを構築している。
この改革の中心にあるのがRFID(無線自動識別)タグの導入である。全商品にRFIDを搭載することで、工場から倉庫、店舗までの在庫がリアルタイムで可視化され、需要予測の精度が飛躍的に高まった。結果として在庫回転率は2.5回から3.1回に改善し、過剰在庫の削減によって値引き販売の比率も縮小した。これはアパレル業界に共通する長年の課題に対する、先進的かつ実効性のある解決策である。
さらに、大阪府茨木市をはじめとする自動倉庫への投資により、検品や棚卸といった作業の効率が大幅に向上した。顧客がセルフレジで会計する際にもRFIDが活用され、人件費削減と利便性向上を同時に実現している。AIを活用した需要予測も導入されており、生産計画の最適化や欠品リスクの軽減が進んでいる。
サプライチェーンの進化は、単なるコスト削減ではなく、事業全体のスピードを加速させる役割を担っている。生産リードタイム短縮や直送比率拡大が進めば、トレンドを捉えた商品の市場投入までの時間が短縮され、競争力が一層高まるだろう。
つまり、高度に効率化されたサプライチェーンは、ユニクロのビジネスモデルを成立させる経済的基盤そのものである。ここで削減されたコストは素材や縫製の品質向上に再投資され、最終的に「LifeWear」という高品質かつ低価格の製品哲学を支えている。他社が容易に模倣できない規模と複雑性を備えた有明プロジェクトは、グローバル市場でのユニクロの優位性を長期的に保証する存在となっている。
サステナビリティ経営と人的資本戦略の真価
ファーストリテイリングはサステナビリティをCSRの枠を超えた経営戦略の中核と位置付けている。その取り組みは環境(Environment)と社会(Social)の両面で明確に数値目標を設定し、実行へと移されている。
環境面では、2030年度までに自社事業での温室効果ガス排出量を90%削減するという野心的な目標を掲げている。すでに2022年度時点で45.7%削減を達成しており、再生可能エネルギーへの切り替えも欧州、北米、ベトナムでは100%に到達している。一方で、サプライチェーン全体での排出量削減(スコープ3)は増加傾向にあり、この領域が最大の課題である。
加えて「RE.UNIQLO」プログラムによる衣類の回収・再利用、ダウンリサイクルや店舗でのリペアサービスといった取り組みは、循環型経済の実現に向けた具体的なアクションとして注目されている。これらは廃棄物削減だけでなく、顧客にブランドへの共感を促す効果も持つ。
社会面では、ILO基準に基づく人権デューデリジェンスを徹底し、生産パートナーへの監査や労働環境改善を進めている。また、2030年度までにグローバルでの女性管理職比率を50%とする目標を掲げ、ダイバーシティ経営を推進している。LGBTQ+への配慮や障がい者雇用の拡大など、多様性を尊重する制度整備も進む。
人的資本戦略の側面では、「全員経営」を支える人材育成機関FR-MICを設立し、次世代リーダー育成に投資している。従業員のエンゲージメント調査や相談ホットラインの整備も進められ、従業員の働きやすさと成長環境を両立させる仕組みを整えている。
サステナビリティ経営と人的資本戦略は、環境負荷削減や人権尊重といった社会的要請に応えるだけでなく、企業の長期的な成長を支える競争力そのものである。ただし、サプライチェーン全体の脱炭素化という難題を克服できるかどうかが、2030年目標の成否を分ける最大の鍵となる。
ZARA・H&Mとの比較で見える競争優位性

グローバルSPA市場では、ファーストリテイリングはInditex(ZARA)、H&Mといった巨大競合と激しい競争を繰り広げている。ZARAは「トレンドを数週間で商品化するスピード」を武器とし、H&Mは「低価格とトレンド性の両立」に強みを持つ。これに対してユニクロは、トレンドではなく「LifeWear」という普遍的なベーシックウェアを軸に据えることで、差別化を図っている。
主要指標を比較すると以下の通りである。
| 項目 | ファーストリテイリング (2024年8月期) | Inditex (2025年1月期) | H&M (2025年11月期第2四半期) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3.1兆円 | 約6.1兆円 | 微減収 |
| 営業利益 | 5,009億円 | 約1.2兆円 | 減益 |
| 営業利益率 | 16.2% | 19.6% | N/A |
| オンライン売上比率 | N/A | 26.4% | N/A |
| 店舗数 | N/A | 5,563店 | N/A |
ZARAの売上規模は依然としてユニクロの倍近くに達しているが、ユニクロの利益率は高水準を維持している。これは、RFIDやAIを活用したサプライチェーン改革により、在庫効率とコスト管理を徹底していることの成果である。トレンド依存型のZARAや価格依存型のH&Mと異なり、ユニクロは品質と機能性を基盤にするため、値引きに頼らず収益性を確保できる点が際立つ。
さらに、ZARAがオンライン比率を高めてデジタルシフトを進める一方で、ユニクロはオンラインと店舗を融合させたO2O戦略を深化させている。顧客がオンラインで情報収集し、店舗で体験する購買行動を設計することで、オムニチャネルの利便性を最大化しているのである。
H&Mはサステナビリティを前面に押し出しているが、ファーストリテイリングも「RE.UNIQLO」やリサイクル素材の導入を進めており、その実効性は高い。ユニクロの強みは、トレンドや価格に左右されない普遍的な価値提供と、それを支える高度に効率化されたオペレーションにある。この構造的な競争優位は、長期的にZARAやH&Mとの差別化を可能にする。
10兆円企業への挑戦と待ち受けるリスク
柳井正会長兼社長が掲げる「売上収益10兆円」という目標は、ファーストリテイリングの成長戦略の象徴である。中間目標として2028年に5兆円を達成し、その先に10兆円を見据えるロードマップが描かれている。しかし、この挑戦の過程には多くのリスクが潜んでいる。
第一に地政学的リスクである。グレーターチャイナ市場は依然として重要だが、消費マインドの低迷や国際関係の緊張が収益を直撃する可能性がある。特に中国依存が高い構造は、経営上の大きな不安定要素となっている。
第二に収益性の圧迫だ。2025年3〜5月期には国内ユニクロで2.1ポイント、海外ユニクロで1.5ポイントの粗利益率低下が確認された。円安による原価上昇、物流費高騰、在庫処分のための値引き販売強化など、複合的要因が影響している。
第三に関税リスクである。北米市場では2026年以降、ベトナム製品に20%、バングラデシュ製品に35%の高関税が適用される見通しで、年間約300億円のコスト増が試算されている。価格転嫁が進めば販売減速の恐れがあり、戦略修正を迫られる可能性が高い。
さらに、第二の柱として期待されるジーユー事業の成否が成長戦略全体を左右する。ニューヨーク本部設立など大規模な投資が進められているが、収益性の回復とグローバル展開が計画通り進まなければ、10兆円構想そのものが危うくなる。
とはいえ、欧米市場のアパレル市場規模は約120兆円と推定されており、ユニクロのシェアは依然として小さい。未開拓市場での成長余地は極めて大きく、挑戦が成功すれば10兆円企業は決して夢物語ではない。その成否を決めるのは、外部環境の逆風をどう克服し、内部の改革をどこまで徹底できるかにかかっている。

