2025年、日本経済は「金利のある世界」への移行とともに、大きなパラダイムシフトを迎えている。東京証券取引所によるPBR改善要請やカーボンニュートラルの潮流、さらには生成AIの急速な普及など、金融機関を取り巻く環境はかつてない変化の連続である。この激動期において、みずほフィナンシャルグループ(以下、みずほ)は過去の危機や停滞を脱し、成長軌道への再浮上を鮮明にしている。
同社が掲げるパーパス「ともに挑む。ともに実る。」は、単なる標語ではなく、顧客や社会との共創を基盤に未来を切り拓く意思表明である。中期経営計画においては、資産所得倍増への取り組み、顧客体験の徹底強化、日本企業の競争力支援、サステナビリティ推進、グローバルCIB事業の拡大という5つの成長エンジンを明確に掲げた。さらに、ソフトバンクや楽天といった異業種との提携、AI・DXを核とするデジタル戦略、人的資本改革を通じ、従来の「金融機関」の枠を超えた「価値共創プラットフォーム」への変貌を加速させている。
本記事では、みずほが描く未来像を多角的に分析する。財務パフォーマンス、事業戦略、外部環境への適応、そしてアライアンスや技術革新の進展をもとに、同社がどのように日本の金融業界を再定義し、競争優位を確立しようとしているのかを解き明かす。市場が「新しいみずほ」に抱く期待と懸念を俯瞰しながら、2026年以降の持続的成長への展望を提示する。
経営戦略の核心:5つの成長エンジンと中期計画の全貌

みずほフィナンシャルグループが掲げる中期経営計画(2023〜2025年度)は、過去の守勢を脱し、攻めの姿勢を鮮明にした成長戦略である。その特徴は、バックキャスティング手法を用いて10年後の理想像から逆算し、今取り組むべき課題を明確化した点にある。単なる短期的な改善ではなく、非連続的な成長を志向する姿勢が随所に見られる。
計画の中核には、5つの成長エンジンが位置づけられている。資産所得倍増に向けた取り組み、顧客利便性の徹底追求、日本企業の競争力強化、サステナビリティとイノベーションの推進、そしてグローバルCIBビジネスの深化である。これらは相互補完的に作用し、全体で一つのエコシステムを構築することを狙う。
例えば、資産形成支援では新NISAを契機に楽天証券との提携を深め、デジタルと対面を融合したハイブリッド型サービスを展開している。一方で、法人分野ではPBR1倍割れ企業の経営改善を支援し、スタートアップとの接点拡大によって新しいビジネス機会を創出している。
以下は中期計画における主要目標の一部である。
| 財務目標(2025年度) | 数値目標 |
|---|---|
| 連結ROE | 8%以上 |
| 連結業務純益 | 1兆〜1.1兆円 |
この数値目標は、資本効率と収益性の大幅な改善を示すものであり、従来の規模依存型モデルから手数料・ソリューション提供型への転換を加速させる指標となっている。経営陣の強いコミットメントを裏付けるこれらの目標は、市場関係者からも高い注目を集めている。
<strong>5つの成長エンジンはそれぞれが独立した戦略ではなく、全体として自己増殖的な成長モデルを描く仕組みである</strong>。個人投資支援は法人の成長を通じて資産形成ニーズを拡大させ、CIBビジネスがその企業活動を支え、サステナビリティが方向性を定める。この相互連関性こそが、みずほの新しい競争力の根幹となっている。
財務実績と市場評価:ROE改善と株価上昇の裏側
戦略の実効性は最終的に財務成果と市場評価によって測られる。みずほは近年、安定的な収益改善を実現し、投資家からの信頼を取り戻しつつある。2026年3月期第1四半期(2025年4〜6月)決算では売上高が前年同期比11%減少した一方、純利益は0.4%増の2,905億円と過去最高を更新した。これを受けて通期純利益予想は1兆200億円へ上方修正され、2期連続で過去最高益を狙う姿勢を鮮明にした。
ROEの推移を見ると、2022年3月期の5.79%から2025年3月期には8.57%へ上昇している。低採算資産の整理や政策保有株式の売却といった構造改革が、資本効率の改善として結実した形である。さらに経営陣は、2027年度にROE10%超、業務純益1.4〜1.6兆円という新たな高みを目指す目標を掲げている。
株式市場もこれに呼応している。2025年9月時点の株価は4,861円前後で推移し、アナリストの平均目標株価は5,035円と上昇余地が見込まれている。さらに、2026年3月期の当期利益予想は1兆678億円と会社予想を上回り、市場がより楽観的な成長シナリオを織り込んでいることがうかがえる。
表に示すと次の通りである。
| 指標 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期会社予想 | 2026年3月期アナリスト予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 5,555億円 | 6,790億円 | 8,854億円 | 1兆200億円 | 1兆678億円 |
| ROE | 6.10% | 7.01% | 8.57% | 8%以上 | — |
格付機関も好意的に評価している。S&Pグローバル・レーティングはスタンドアローン評価を「a」へ引き上げ、JCRも「AA」を付与するなど、財務基盤の安定性が確認されている。
<strong>市場の期待が会社の予想を上回る状況は、戦略が投資家に強い説得力を持っている証左である</strong>。だが同時に、その期待を裏切らない実行力が問われるフェーズに入ったとも言える。財務実績の改善と株価上昇の背景には、確かな改革の成果と、市場が託す未来への信認が重なり合っている。
リテール事業の逆襲:楽天との提携がもたらす新展開
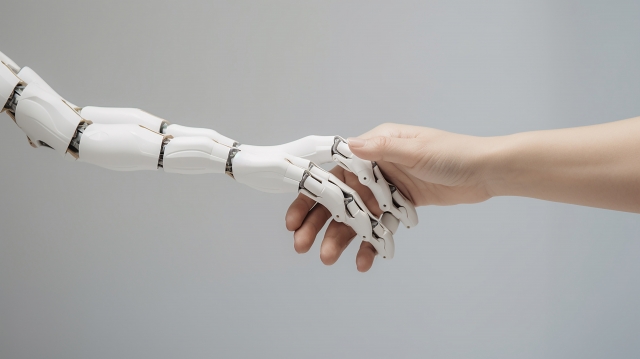
みずほフィナンシャルグループにとってリテール事業は過去において競合メガバンクに後れを取った分野であり、その再生は最大の課題とされてきた。木原社長が掲げる「もう一度リテールで旗を立てる」という言葉は、その決意を端的に示すものである。現在、同社は楽天グループとの戦略的提携を通じて、デジタルとリアルを融合した新しいリテールモデルを構築しようとしている。
注目すべきは、楽天証券との協業である。みずほの強みである対面コンサルティングと、楽天の優れたオンラインプラットフォームを掛け合わせることで、顧客は利便性と専門性を同時に享受できる。金利競争が激化する中、単に預金金利で勝負するのではなく、楽天経済圏を活用したポイントプログラムやデジタル連携を武器に、ロイヤルティの高い預金基盤を築く戦略を描いている。
店舗戦略も大きく変化している。従来のフルサービス型から脱却し、資産形成相談に特化した店舗や口座開設専用店舗など、顧客ニーズに合わせた専門型店舗を展開している。これにより、デジタルで完結できない複雑な相談や長期的な資産戦略の設計に応えることが可能となる。さらに、コンタクトセンターを高度化し、AIを活用したプロアクティブな営業提案を強化することで、デジタルとリアルをつなぐハイブリッドチャネルを実現している。
リテール事業の逆襲を支える要素を整理すると以下の通りである。
- 楽天証券との提携によるオンラインと対面の融合
- 楽天経済圏を活用した非価格競争力の強化
- 専門型店舗の展開による顧客体験の高度化
- AIとデータ活用による提案型営業の実現
<strong>リテール戦略の最大の狙いは、価格競争から脱却し、顧客との関係性を深化させることで安定した収益基盤を確立することにある</strong>。日本の金利環境が変化する中で、付加価値型サービスによる差別化こそが長期的な勝敗を分ける鍵となる。
グローバルCIB戦略:M&Aで拡張する米州・欧州ビジネス
みずほの成長を牽引するもう一つの柱が、グローバルCIB(コーポレート&インベストメントバンキング)戦略である。銀行と証券を一体化させたビジネスモデルを米州市場で深化させるとともに、M&Aを通じて非連続的な成長を実現している。
2023年12月に完了した米国のM&Aアドバイザリー会社Greenhillの買収は象徴的である。この買収により、従来のデットビジネスに加え、M&Aアドバイザリーという企業の最上流に位置する意思決定プロセスへの関与が可能となった。結果として、買収ファイナンスや債券発行、デリバティブ取引など後続の収益機会を総取りできる「フライホイール効果」が期待されている。
さらに2025年7月には、欧州の再生可能エネルギー分野に特化したM&AブティックAugusta & Coを買収した。これにより、エネルギートランジションという巨大市場における存在感を一気に高め、欧州における専門的な案件対応力を確保した。単なる規模の拡大ではなく、自社に不足していた専門性を補完する戦略的なM&Aである点が特徴である。
以下の表は主なM&A案件を示したものである。
| 年月 | 買収先 | 特徴 | 狙い |
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | Greenhill(米国) | M&Aアドバイザリー大手 | 米州CIBの上流機能強化 |
| 2025年7月 | Augusta & Co(欧州) | 再エネ特化M&Aブティック | 欧州エネルギートランジション市場への参入 |
こうした取り組みは、みずほを資金提供者から戦略パートナーへと進化させている。顧客企業にとって単なる金融支援にとどまらず、成長戦略そのものを伴走する存在へと変貌しつつある。
<strong>グローバルCIB戦略の核心は、専門性の高いM&A機能を取り込み、米州と欧州の両市場で存在感を拡大することにある</strong>。アジア市場でのトランザクション拡大と合わせ、みずほは世界的な資本市場におけるプレゼンスを着実に高めている。
サステナビリティとイノベーション:産業変革の共創パートナーへ

みずほフィナンシャルグループは、サステナビリティを単なる社会的責任の枠にとどめず、事業成長の中核へと位置づけている。その姿勢は「Sustainability Progress 2025」に示された「ポジティブインパクトの最大化」と「ネガティブインパクトの抑制」という二本柱に表れている。環境規制や産業構造転換が加速する中で、金融機関がいかに新しい産業の立ち上げに寄与できるかが問われている。
特筆すべきは、みずほが独自に策定した「グランドデザイン」である。これは2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、日本の主要産業ごとに必要なエネルギー転換や排出削減のロードマップを描き出したものである。電力や鉄鋼など基幹産業単位での定量的シナリオを提示することで、顧客企業や政策当局とより戦略的な対話を実現し、産業変革の共創パートナーとしての存在感を高めている。
具体的なファイナンス分野では、水素関連で2030年までに2兆円の資金供給を目標に掲げ、カーボンクレジット市場形成にも積極的に関与している。シンガポール取引所Climate Impact Xや政府系ファンドTemasek傘下のGenZeroと連携し、国際的なカーボン市場の発展を支える役割も担っている。
革新的な商品開発も進む。「Mizuho自然資本インパクトファイナンス」や「Mizuhoインパクト預金」といったサービスは、融資先のサステナビリティ評価を条件に反映させ、金融取引を通じて顧客行動の変革を促す仕組みを備えている。これは単なる資金提供ではなく、持続可能性への具体的な誘導を可能とする仕組みである。
箇条書きで整理すると以下の通りである。
- 「グランドデザイン」による産業横断的な未来図の提示
- 水素・カーボンクレジット分野での大型ファイナンス実行
- インパクトファイナンス商品の開発と普及
- 政策当局や国際機関との連携による新市場創出
<strong>サステナビリティ戦略の本質は、金融の力で産業全体を変革に導き、自らを新産業創造のオーガナイザーとして位置づけることにある</strong>。環境対応が競争力の源泉となる時代において、このアプローチは長期的に持続可能な収益モデルを確立する鍵となる。
AI・DXの双子エンジン:ソフトバンク提携と内製改革の融合
みずほの未来戦略を支えるもう一つの大きな柱がAIとデジタル変革(DX)である。2025年7月、ソフトバンクとの戦略的包括提携を発表し、AGI(汎用人工知能)時代を見据えた新たな成長ステージに入った。この提携の目的は、顧客体験の向上と業務効率化を同時に実現することであり、2030年度までに3,000億円規模の効果創出を掲げている。
法人向けサービスの分野では、AIが24時間365日融資や経営アドバイスを提供する体制を整えようとしている。営業活動の生産性を2倍以上に引き上げ、低付加価値業務を最大50%削減することが目標とされている。これにより、行員はより付加価値の高いコンサルティングに注力できる体制が実現する。
一方で、みずほは内製によるAI開発にも力を注いでいる。「デジタル・AI推進室」が中心となり、業務現場で直接役立つツールを次々と開発している。議事録作成時間を7割以上短縮する「Wiz Create」、膨大な情報収集を数時間から数分に短縮する「みずほDeepResearch」、社内手続き検索を効率化する「Wiz Search」などはその成果である。
加えて、システム面では過去の障害経験を踏まえ、AWS、GCP、Azureといった複数クラウドを組み合わせたマルチクラウド環境への移行を進めている。2026年にはみずほ銀行とみずほリサーチ&テクノロジーズの統合を検討し、発注と受注の関係性を超えたアジャイル開発体制を構築する計画もある。
ポイントをまとめると次の通りである。
- ソフトバンクとの提携でAI活用を飛躍的に拡大
- 法人顧客向けにAIが24時間365日対応する新サービス構想
- 内製ツールによる現場の即効性ある効率化
- マルチクラウド化と組織統合で俊敏性を強化
<strong>AIとDXは、みずほが競争優位を築くための「双子のエンジン」であり、大規模提携と現場主導の開発を両輪として推進されている</strong>。これにより、顧客接点の質を高めると同時に、組織のレジリエンスと俊敏性を兼ね備えた新しい金融機関像が形作られている。
人的資本戦略「かなで」:組織文化の刷新と挑戦する人材育成

みずほフィナンシャルグループが進める改革の中で、人材戦略は最も重要な柱の一つである。新たに導入された人事制度「かなで」は、年功序列から実力主義への転換を象徴する取り組みであり、企業文化そのものを変革しようとしている。経営陣は「人の成長こそがビジネスの源泉」と位置づけ、社員の挑戦を後押しする体制を整えている。
この制度は、公正な評価と透明性を重視し、成果に基づいた登用を徹底することを目的としている。従来のように年次や在籍年数が重視される仕組みから脱却し、意欲と能力を持つ人材が早期に活躍できる環境を整備している。特に若手社員のモチベーション向上につながり、組織全体の活力を引き出す効果が期待されている。
また、非財務目標として「社員エンゲージメントスコア65%」「インクルージョンスコア65%」という数値を掲げ、働きがいと多様性の両立を追求している。単なる理念ではなく、数値目標に落とし込むことで、経営戦略と人事改革を一体化させている点が特徴的である。
以下の要素が「かなで」の核心である。
- 公正で透明性の高い評価制度
- 成果に基づく登用の徹底
- エンゲージメントと多様性の数値目標化
- 自律的なキャリア形成の支援
<strong>人的資本戦略の真価は、社員一人ひとりの挑戦が組織の成長へと直結する仕組みを確立することにある</strong>。過去に硬直的な文化がシステム障害や組織の停滞を招いたことを踏まえれば、文化変革と人材育成は技術投資と並ぶ重要な競争力の源泉となる。
外部環境と競争地図:MUFG・SMFGとの比較から見るポジション
みずほを取り巻く環境は、金利上昇、異業種参入、そして競合メガバンクとの熾烈な競争が重なる複雑な状況である。その中で、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)との比較は不可欠である。
MUFGはアジアでの成長戦略と総合金融プラットフォーム「エムット」を柱に据え、幅広い顧客基盤を取り込む動きを強めている。SMFGは「Olive」を中心に若年層への浸透を図り、米ジェフリーズとの提携を軸にグローバルCIB事業を拡張している。両社ともデジタル戦略とグローバル展開を巧みに組み合わせ、収益機会を拡大している。
一方、みずほの独自性は非金融領域との戦略的アライアンスにある。楽天との協業による1億人規模の顧客接点や、ソフトバンクとの提携による最先端AI技術へのアクセスは、他行が模倣しにくいエコシステムを形成している。金融と非金融を融合させた取り組みは、顧客の日常生活や企業活動に深く入り込み、エンベデッド・ファイナンスの先駆けとなりつつある。
比較を整理すると以下のようになる。
| 項目 | MUFG | SMFG | みずほ |
|---|---|---|---|
| 主戦略 | アジア展開・「エムット」 | 若年層獲得・米ジェフリーズ | 楽天・ソフトバンクとのアライアンス |
| デジタル戦略 | プラットフォーム型 | デジタル口座「Olive」 | ハイブリッド型サービス |
| 強み | 資本力・国際展開 | 若年層・CIB強化 | 非金融連携・独自エコシステム |
<strong>みずほのポジションは、金融機関の枠を超えたアライアンスを軸に独自の競争優位を築くことにある</strong>。MUFGやSMFGが既存の金融機能強化を進める中で、みずほは異分野との連携を通じた差別化に挑む。この戦略が奏功すれば、次世代の金融サービスにおいて独自の存在感を確立できる可能性が高い。

