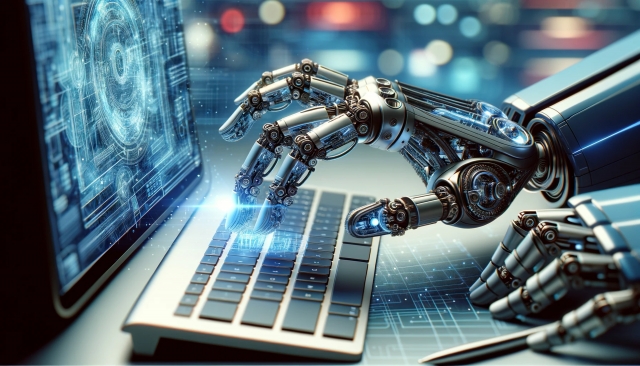三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、現在まさに歴史的な転換点に立っている。2024年度から2026年度までの中期経営計画に基づき、グループ全体が「成長戦略の進化」「社会課題解決への貢献」「企業変革の加速」という三本柱を軸に大規模な変革を進めている。その背景には、世界的な地政学リスクの高まり、AI時代の幕開け、そして日本経済におけるゼロ金利政策からの転換といった外部環境の激変がある。
MUFGはこうした逆風を単なるリスクと捉えるのではなく、むしろ成長機会とみなしている。2025年5月には新ブランド「エムット(emutto)」を立ち上げ、国内リテール市場でのデジタル攻勢を本格化させた。また、AI分野ではSakana AIやSalesforceとの連携を通じて「AI Native」組織への転換を目指しており、人的資本や企業文化の刷新も進められている。さらに、100兆円規模のサステナブルファイナンス目標を掲げ、環境・社会課題の解決を収益機会と結びつける戦略を打ち出している。
財務的にはROE12%、時価総額30兆円という野心的な長期目標を掲げ、世界のトップ金融機関に肩を並べることを視野に入れている。しかし、その実現には15万人規模の従業員を変革に巻き込み、迅速かつ確実に戦略を実行する力が求められる。果たしてMUFGは、この「覚醒」の物語を成功へと導くことができるのか。本記事では、その戦略的青写真と実行状況、競争環境、そして将来展望を詳細に分析する。
MUFGが直面する歴史的転換点と亀澤CEOのビジョン

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、2025年現在、従来の銀行モデルを超える抜本的な変革に踏み出している。背景には、AI技術の急速な進展、地政学的リスクの高まり、そして日本経済のゼロ金利政策からの脱却という大きな潮流がある。これらは金融業界に新たな競争環境を生み出し、MUFGにとってはリスクであると同時に飛躍のチャンスでもある。
亀澤宏規CEOは、こうした状況を「歴史的な転換点」と位置づけ、自らのメッセージで「未来は過去の延長線上にはない」と強調している。彼のリーダーシップの中心的なキーワードは「覚醒」であり、組織全体が従来の枠組みを超えて新時代に適応するための意識改革を促している。単なる効率化ではなく、金融の枠を超えた社会的使命を果たす存在へと変貌することを目指している点に特徴がある。
また亀澤CEOは、トランプ政権の政策転換やAIの台頭を「世界秩序を破壊する二大要因」とし、不確実性を生み出す一方で新たな収益機会も提供すると分析している。この視点は、リスクを受動的に回避するのではなく、積極的に活用する戦略思考の表れである。
強調すべきは、MUFGが「金融機関としての存在意義」を問い直している点である。従業員一人ひとりが自らのパーパスを持ち、社会とともに成長する姿勢を求められている。これは日本のメガバンクにおいて極めて異例なリーダーシップの在り方であり、組織文化の深い変革を示唆している。
具体的な財務目標としては、2026年度までにROE9%、長期的には12%を掲げ、時価総額30兆円を目指す野心的な計画を打ち出している。これらは単なる数値目標ではなく、変革の実効性を測る試金石としての意味を持つ。市場関係者は、このビジョンが現実的な成果につながるかどうかを注視している。
MUFGは今、国内外の金融市場において「伝統から革新へのシフト」を体現する存在となりつつある。亀澤CEOが語る「覚醒」は、単なる経営スローガンではなく、企業全体の方向性を決定づける戦略的メッセージなのである。
三本柱で描く中期経営計画の全体像
MUFGの2024年度から2026年度までの中期経営計画は、「成長戦略の進化」「社会課題の解決」「企業変革の加速」という三本柱で構成されている。これらは独立した施策ではなく、相互に補完し合う統合的な枠組みである。
三本柱の概要
| 柱の名称 | 主な内容 | 目標指標 |
|---|---|---|
| 成長戦略の進化 | 金利上昇の恩恵獲得、新規ビジネスモデル構築 | 営業純益2.1兆円以上 |
| 社会課題の解決 | ESG統合、カーボンニュートラル推進 | サステナブルファイナンス100兆円 |
| 企業変革の加速 | AI・データ基盤強化、文化改革、人的資本拡充 | ROE9%(中期)、12%(長期) |
第1の柱である「成長戦略の進化」では、既存ビジネスの強化とともに新しい事業領域の開拓を進める。具体例として、2025年に開始した新ブランド「エムット」によるデジタルリテール戦略や、法人×ウェルスマネジメントの統合による事業承継市場の開拓が挙げられる。
第2の柱「社会課題の解決」は、CSRの延長ではなく経営の中核にサステナビリティを組み込む点が特徴である。環境・社会への貢献を「先義後利」の考え方で捉え、カーボンニュートラルやトランジション・ファイナンスに積極的に関与する姿勢を示している。100兆円規模のサステナブルファイナンス目標はその象徴である。
第3の柱「企業変革の加速」は、前二つの柱を実現するための基盤整備である。AI・データ基盤の強化、コンプライアンス体制の強化、リスキリングやダイバーシティ推進といった人的資本投資が含まれる。特に「挑戦とスピード」を浸透させる文化改革は、15万人規模の組織全体における最大の挑戦である。
この三本柱は単なる目標の羅列ではなく、相互に結びつく戦略構造を持つ。例えば、サステナブルファイナンスを展開するにはAIとデータ基盤によるリスク管理が不可欠であり、文化改革なくして新たな成長戦略は機能しない。この一体的な設計こそが、MUFGの中期経営計画の最大の特徴である。
MUFGはこの三本柱を通じて、単なる金融機関を超えた社会的インフラとしての存在を確立しようとしている。市場や投資家にとっては、これが持続的な株主価値の向上につながるかどうかが最大の注目点である。
国内リテール強化:「エムット」が挑むデジタル金融の新時代

MUFGのリテール戦略における最大の目玉は、2025年5月に始動した新ブランド「エムット(emutto)」である。人口減少やフィンテック企業との競争激化といった逆風を受け、顧客との長期的な関係性を重視する方向へ大きく舵を切ったことが背景にある。狙いは単なる口座開設数の増加ではなく、顧客生涯価値(LTV)と顧客基盤の最大化である。
エムットの特徴は、銀行アプリ、クレジットカード、ポイントプログラムをグループ全体でシームレスに統合する点にある。従来の「口座+カード」の単発的サービスから脱却し、顧客の日常生活全体をカバーする金融プラットフォームへと進化している。例えば、新アプリでは資産管理、支出分析、金融商品の購入までワンストップで完結でき、さらにマネーツリーの買収によってパーソナライズされたサービス提供が可能となった。
具体的な施策としては、以下が挙げられる。
- 銀行アプリの全面リニューアルと直感的なUI設計
- 家計消費と連動したポイントアッププログラムの導入
- 相談特化型のキャッシュレス新店舗「エムットスクエア高輪」の開設
- 外部パートナーとの連携による金融サービスの拡充
これにより、MUFGはアプリの月間アクティブユーザー数(MAU)1,000万人、金融預かり資産残高100兆円という具体的な目標を掲げている。これは単なる数値ではなく、金融生活の「インフラ」としての地位確立を意味している。
競合の三井住友フィナンシャルグループが「Olive」を先行投入したのに対し、エムットは後発として市場に参入した。だがその強みは、銀行口座を中心に据えた包括性と、ファミリー層を重視するパートナー戦略にある。スーパーマーケット30ブランドとの連携は、日常消費のシーンに深く入り込み、より幅広い顧客層を取り込むための布石である。
顧客が日々の買い物や資産形成を通じてMUFGと接点を持つ仕組みが構築されつつあり、この循環が確立すれば国内デジタル金融市場における強力な基盤となる。エムットは単なる新サービスではなく、MUFGのリテール戦略そのものを象徴する存在なのである。
法人×ウェルスマネジメント統合による事業承継・資産承継ビジネスの拡大
国内の法人金融において、最大の課題は中小企業オーナーの高齢化と事業承継問題である。東京商工リサーチの調査によれば、2025年時点で全国160万社以上が事業承継課題を抱えており、日本経済全体にとっても深刻なテーマとなっている。MUFGはこの巨大なニーズを成長機会と捉え、法人ビジネスとウェルスマネジメント(WM)を統合した新しいモデルを打ち出している。
法人×WMモデルの強みは、企業オーナーの事業承継と個人資産承継を一体的に扱える点にある。従来は法人部門と個人部門が分断されていたが、統合することで資本政策から相続対策までを一貫して支援できる。これにより、オーナー企業に対する総合的なソリューション提供が可能となった。
具体的な取り組みとしては以下が挙げられる。
- M&Aアドバイザリーチームの拡充による外部承継支援
- 「事業・資産承継プロチーム」の設立による親族内承継のサポート
- 富裕層向けデジタルプラットフォームの強化
- ウェルスマネジメント顧客向けの情報発信メディアの立ち上げ
目標として、事業承継関連融資1兆円、法人×WM分野での営業純益880億円を掲げている。これらは単なる収益機会ではなく、日本経済の構造的課題を解決する社会的使命とも重なる。
また、この分野では外資系プライベートバンクや証券会社も競合として存在する。しかし、MUFGが有する強みは、銀行・証券・信託といった総合金融グループとしての機能を統合できる点にある。金融商品の提供にとどまらず、資本政策や相続設計までカバーする包括性は国内随一である。
加えて、テクノロジーを活用した情報発信やデータ分析も競争力の源泉となっている。AIによる顧客ニーズ分析やデジタルチャネルを活用した非対面型アドバイスの普及は、法人・富裕層顧客にとって利便性を高めると同時に、MUFGのサービス効率化を支えている。
法人×WM統合戦略は、日本経済の「大廃業時代」を乗り越えるための金融インフラ構築とも言える。MUFGがこの分野で確固たる地位を築ければ、単なる収益増強にとどまらず、持続可能な経済基盤を支える存在としての役割を果たすことになる。
グローバル戦略の進化:モルガン・スタンレーとの協業とアジア市場の強化

MUFGはグローバル戦略の中核として、モルガン・スタンレーとの戦略的協業とアジア市場の拡大を掲げている。これにより、世界的な競争環境で優位性を確立する狙いがある。特にコーポレート&インベストメントバンキング(GCIB)部門と市場部門の統合は、収益力と資本効率の向上を両立させる重要な取り組みとなっている。
モルガン・スタンレーとの協業深化
モルガン・スタンレーとの協業は単なる資本提携を超え、リサーチや商品開発などの実務レベルに及んでいる。代表例として、日本株リサーチ部門の統合により、モルガン・スタンレーMUFG証券がリサーチランキングで9位から3位へと急上昇したことは象徴的である。これは国際的な投資家への情報発信力強化を意味し、国内外の顧客基盤拡大に直結している。
また、「MUFGモルガン・スタンレー・クレジットソリューションズ」の設立により、グローバル債券市場での共同商品開発が加速している。これにより、発行市場(プライマリー)から流通市場(セカンダリー)まで一体的なバリューチェーンを構築し、競争力を高めている。
アジア市場の強化
MUFGはアジアを「第2のマザーマーケット」と位置付け、積極的に現地銀行への出資と経営統合を進めている。タイのアユタヤ銀行、インドネシアのバンク・ダナモン、ベトナムのヴィエティンバンクなどへの戦略的投資は、地域に根ざしたネットワーク形成を支えている。さらに、インドではDMI Financeへの出資や証券子会社の設立などにより、成長著しい市場を取り込む動きを加速している。
成果指標と展望
- GCIB・市場部門ROE:8.3%
- アジアプラットフォームROE:10%超
- 営業純益:6,000億円
これらの目標達成は、世界の金融機関との競争における存在感を高める上で不可欠である。アジア市場での拡大とモルガン・スタンレーとの協業は、MUFGを「日本発のグローバルバンク」として位置付け直す戦略的布石であり、長期的な収益基盤の強化に直結している。
「資産運用立国」実現に向けたMUFGの取り組みと新NISA効果
日本政府が推進する「資産運用立国」構想は、家計の金融資産2,000兆円超を「貯蓄から投資へ」動かす国家的戦略である。MUFGはこの潮流を取り込み、資産運用(アセットマネジメント=AM)と資産管理(インベストメントサービス=IS)の両分野で国内No.1を目指している。
新NISAと投資ブームの追い風
2024年から開始された新NISAは、非課税枠の拡大により投資初心者層の参入を加速させた。これにより、証券口座の開設数は過去最高水準を記録し、資産運用市場は拡大基調にある。MUFGはウェルスナビや三菱UFJ eスマート証券の完全子会社化を通じて、デジタルチャネルを強化し、若年層から富裕層まで幅広い顧客をカバーしている。
MUFGの戦略的施策
- デジタル証券口座の利便性向上
- ロボアドバイザーによる自動運用提案
- 金融リテラシー教育の推進(学校・地域社会でのセミナー)
- BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)サービスによる外部運用会社支援
特にBPOサービスは、他の運用会社にバックオフィス業務を提供することで業界全体の効率化を支援し、残高100兆円の受託を目指している。
成果目標と意義
| 項目 | 2029年度目標 |
|---|---|
| 運用資産残高(AUM) | 200兆円 |
| BPO受託残高 | 100兆円 |
これらの目標は単なる収益拡大ではなく、日本経済全体の資産形成力強化に資する取り組みである。高齢化が進む日本において、資産運用は老後資金の確保や経済循環の活性化に直結する。
MUFGが掲げる「資産運用立国」戦略は、政府方針との整合性が高く、同時に社会的意義を伴う。AIやデータ分析を活用した運用提案は、顧客ごとの最適解を提供し、長期的な信頼構築にもつながる。結果として、MUFGは国内外の資産運用市場における確固たる地位を確立し、持続的な成長の基盤を築くことになる。
サステナブルファイナンス100兆円目標とGX支援の現状

MUFGが中期経営計画で掲げた最も注目すべきコミットメントの一つが、サステナブルファイナンス100兆円の目標である。これは従来の環境金融にとどまらず、社会課題解決型の投融資を通じて企業や社会の持続可能性を支援する包括的な取り組みである。背景には、日本が掲げる2050年カーボンニュートラル目標と、それに伴う産業構造転換がある。
GX支援の具体的な取り組み
MUFGは単なる「グリーンローン」ではなく、バリューチェーン全体を支援する姿勢を鮮明にしている。電力や海運といった高排出セクターに対し、トランジション・ローンやトランジション・ボンドを積極的に組成し、顧客企業の移行プロセスを後押ししている。さらに、水素・アンモニアといった新技術への資金供給や、新興国におけるブレンデッドファイナンスの導入など、幅広い手法を用いている。
また、顧客向けに「トランジション白書」を発行し、産業ごとに脱炭素への道筋を明確化することで、金融と実業の橋渡し役を果たしている。このような情報提供は、企業が自らのESG戦略を設計する上で大きな指針となっている。
成果目標と影響
- サステナブルファイナンス目標:2030年までに100兆円
- GXプロジェクト共創件数:50件
- 高排出産業に対する移行支援案件の拡大
これらの成果は単なる数値目標ではなく、日本経済全体の脱炭素化を進める社会的責任と直結している。特に高排出産業が多い日本において、金融機関が主導的にトランジションを支援することは不可欠である。
市場における位置付け
MUFGの100兆円目標は、国内の他メガバンクと比べても規模が大きく、グローバル基準でも高い水準にある。これは単なる競争優位性の確保ではなく、日本経済全体をGXに適応させる牽引力としての役割を担うことを意味する。市場や投資家は、この大規模ファイナンスが具体的な成果につながるかを注視しており、今後の進捗が株価や企業評価に影響を与える可能性は高い。
「AI Native」組織への変革と人材・文化改革の挑戦
MUFGの変革戦略を支える基盤が、「AI Native」な組織づくりである。これは単なるAIツールの導入にとどまらず、人間とAIがシームレスに協働する新しい企業文化を構築する試みである。亀澤CEOは、AIを「人間の思考を拡張する存在」と位置づけ、短期的効率化ではなく長期的な競争優位性の確立を狙っている。
AI投資とパートナーシップ
MUFGは2027年度までに600億円をAI関連に投資し、デジタル戦略統括部を300人体制へ拡充する計画を示している。特徴的なのは、アプリケーション開発よりもまずデータ基盤の整備を優先している点である。これは「生成AIの派手さ」に流されず、持続可能なインフラを重視する姿勢を表している。
加えて、Sakana AIとの提携により金融特化型の大規模言語モデルを共同開発し、コンプライアンスや説明責任を担保できるAI活用を目指している。さらに、Salesforceと連携してAIエージェント「Agentforce」を導入し、営業活動の効率化と顧客インサイトの高度化を実現している。
人材と文化改革
AI戦略と並行して、人材育成と文化変革も進められている。リスキリングプログラムの拡充やダイバーシティ推進、従業員エンゲージメントの強化は、その一例である。亀澤CEOは「従業員こそが会社そのもの」と強調し、技術投資と人材投資を両輪とする姿勢を明確にしている。
MUFGが掲げる文化のキーワードは「挑戦とスピード」である。従来の大企業特有の意思決定の遅さを克服し、スタートアップ的なアジリティを取り入れることが求められている。これは15万人規模の組織にとって容易ではないが、成功すればメガバンクの常識を覆す存在となる。
今後の展望
- 2027年度までのAI投資総額:600億円
- デジタル戦略統括部の拡充:300名体制
- Human Capital Reportの発行による人的資本経営の透明化
AIによる業務効率化だけでなく、人材や文化の刷新を通じて真の意味での「AI Native」な組織に進化できるかが最大の試金石となる。MUFGがこの挑戦に成功すれば、単なる金融機関の枠を超え、21世紀の新しい経営モデルを提示する存在となるであろう。
財務パフォーマンスとアナリスト評価:市場が注視する成長の持続性

MUFGの財務状況は、戦略的な変革の進捗を測る重要なバロメーターである。2025年3月期の通期では、親会社株主に帰属する純利益は2兆円を目標としており、中期経営計画の実効性を裏付けるものとなっている。しかし、2026年3月期第1四半期(2025年6月末時点)の純利益は5,461億円で前年同期比1.8%減となり、外部環境の影響を受けやすい構造が浮き彫りとなった。
セグメント別の業績動向
- リテール・デジタル部門:新ブランド「エムット」の浸透度が成長の鍵を握る。アプリのMAUや預かり資産の増加が進むかどうかが、業績に直結する。
- 法人・WM部門:事業承継関連融資1兆円や営業純益880億円といった数値目標の達成度合いが焦点となる。
- グローバル部門(GCIB・市場・アジア):GCIB・市場部門でのROE8.3%、アジア市場でのROE10%超が重要な達成基準となっている。
証券事業は堅調であり、2025年3月期には旺盛なM&Aや引受業務により純利益が前年同期比16%増となった。これは国内外での資本市場の活性化を反映した結果である。
アナリスト評価と株価の見通し
2025年9月時点のアナリスト評価は「買い」が優勢で、コンセンサスは強気買い3名、買い3名、中立5名という内訳となっている。平均目標株価は2,335円で、緩やかな上昇余地が示唆されている。市場関係者が注視しているのは、MUFGが掲げるROE9%という中期目標を安定的に達成できるかどうかであり、さらに長期目標であるROE12%を実現できれば、株価評価は大きく変わる可能性がある。
MUFGの財務パフォーマンスは、単なる短期利益ではなく、戦略実行力と持続的成長性を投資家に示す指標となっている。今後の市場評価は、これらの指標に沿った一貫した成果が示されるかどうかに大きく左右されるだろう。
メガバンク間競争と差別化戦略:SMFG・みずほとの比較から見える未来
日本のメガバンク業界は、MUFG・三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)・みずほフィナンシャルグループの三強体制が続いている。しかし、各社の戦略には明確な違いがあり、それぞれが異なる方向性で競争を展開している。MUFGは「AI・サステナビリティ・グローバル」を軸に掲げる一方、SMFGは「Olive」に象徴されるデジタル決済強化、みずほは「One MIZUHO」によるグループ内連携に注力している。
主要戦略の比較
| 銀行名 | 戦略の特徴 | 主な施策 |
|---|---|---|
| MUFG | AIとサステナブルファイナンスで差別化 | エムット、100兆円GXファイナンス、AI Native化 |
| SMFG | 国内デジタル顧客基盤の拡大 | Olive、キャッシュレス連携、DX推進 |
| みずほ | 組織文化改革と基盤強化 | システム安定化、グループ連携強化、信頼回復 |
MUFGの優位性と課題
MUFGは、アジア市場での株式出資を伴う戦略的展開や、モルガン・スタンレーとの協業による国際競争力の強化で他社と一線を画している。さらに、100兆円規模のGXファイナンスやAIを軸とした組織変革は、長期的に見れば国内市場を超えた差別化要因となる。一方で、組織文化改革という内部課題が成果に直結するかどうかは依然として最大のリスクである。
業界全体の展望
日本のメガバンクは国内低金利環境と人口減少に直面しており、成長の軸を海外や新規事業に求めざるを得ない状況にある。その中でMUFGは、AIやサステナビリティを武器に国際的な地位を高める戦略を描き、SMFGは国内デジタル分野で攻勢を強め、みずほは信頼回復と基盤強化に注力している。
この構図は、短期的には国内競争の差異を際立たせるが、長期的にはグローバル市場での地位確立を左右する要素となる。MUFGが他行との差別化を実行力で裏付けられるかどうかが、日本の金融業界全体の未来像をも左右すると言えるだろう。