三菱重工業(MHI)は、日本の産業界を代表する重工メーカーとして長らく知られてきたが、2025年現在、その存在意義は単なる製造業を超えている。新中期経営計画「2024事業計画」のもと、同社は「エナジートランジション」と「国家安全保障」という二つの巨大潮流を捉え、世界的構造変化の中で新たな役割を果たす国家戦略企業へと変貌を遂げつつある。
エネルギー分野では、ガスタービン・コンバインドサイクル(GTCC)発電における世界トップシェアを武器に、水素・アンモニア燃焼技術や次世代原子炉の開発を加速し、脱炭素化社会の実現に貢献している。一方、防衛・宇宙分野では、日本政府の防衛力強化政策に呼応し、次期戦闘機「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)」やAI搭載無人機、H3ロケット商業化など、最先端技術を核とした事業展開を推進している。
2025年度第1四半期には売上収益1兆1,936億円(前年同期比7.4%増)、事業利益1,041億円(同24.7%増)と大幅な増収増益を達成し、受注残高は10.7兆円超と過去最高水準を維持した。これは、戦略の実効性が市場に認知されつつある証左であり、今後の安定的成長の土台を示すものである。
本記事では、三菱重工の「2024事業計画」の全貌と、その最新動向を多角的に分析し、競合との比較や市場評価を踏まえながら、日本経済と世界秩序の変化の中でどのように位置づけられるのかを探る。
三菱重工の戦略転換:「守り」から「攻め」への大胆なシフト

三菱重工業は、2021年度からの中期経営計画において「収益力の回復と強化」を掲げ、不採算事業の整理やコスト構造改革を断行してきた。その結果、2020年度比で事業利益を5倍に拡大し、純有利子負債を55%削減するなど、財務基盤を大幅に改善した。この守りのフェーズを経て、2024年度からの新中期経営計画「2024事業計画」では、いよいよ本格的な攻めの成長戦略へと舵を切った。
新計画では、売上収益5.7兆円以上、事業利益4,500億円以上、ROE12%以上という極めて野心的な数値目標を設定している。これは2023年度実績と比較して事業利益が約60%増という水準であり、従来の守り重視の経営姿勢から大きく転換した姿勢を示すものだ。
さらに、経営資源の重点配分を明確にした点も注目に値する。従来の「全方位戦略」から脱却し、GTCCや原子力、防衛といった伸長事業に加え、水素・アンモニアやCCUSなどの成長領域に資金と人材を集中させるポートフォリオ経営を採用した。これは、政府のGX基本方針や防衛力整備計画といった国家戦略と強く連動しており、事業の先行きの確度を高めている。
加えて、投資規模も大幅に拡大した。2024事業計画では総額1.2兆円の投資を予定しており、前中計から60%以上の増加である。そのうち成長領域への投資は6,500億円に達し、従来の倍近い規模となる。株主還元についても配当を拡大し、投資と還元の両立を実現している点は、三菱重工のキャッシュフロー創出力の強さを示す。
この戦略転換は、単に成長市場を狙うだけではなく、国家政策に沿った形での産業実行主体としての役割を明確にした点にある。守りから攻めへと転換した三菱重工は、今後の日本経済の安全保障とエネルギー戦略に直結する存在として、その地位をさらに固めていくことになる。
財務基盤の強化と野心的な数値目標の実像
三菱重工が攻めの経営へ転換できた背景には、盤石な財務基盤の確立がある。2021年度からの計画期間で同社は収益力を飛躍的に改善させ、2023年度の事業利益は2,825億円に達した。この成果が、次なる飛躍のための資金的余力を生み出した。
新中期経営計画で掲げられた主要な数値目標は以下の通りである。
| 指標 | 2023年度実績 | 2026年度目標 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益(兆円) | 4.7 | 5.7以上 | +1.0以上 |
| 事業利益(億円) | 2,825 | 4,500以上 | +1,675以上 |
| 事業利益率(%) | 6.0 | 8.0以上 | +2.0pt以上 |
| ROE(%) | 11.0 | 12.0以上 | +1.0pt以上 |
| 1株当たり配当金(円) | 20 | 26 | +6 |
この表からも分かるように、三菱重工は利益率の改善と資本効率の向上を明確に意識している。特にROE12%以上という目標は、日本の重工業分野においては高水準であり、投資家にとっても魅力的な指標となる。
さらに、自己資本比率は35%を維持しており、財務健全性は高い。2025年度第1四半期時点で受注残高は10兆7,729億円に達しており、将来数年間にわたる安定収益の確保が見込まれている。潤沢な受注残高を背景に、利益拡大を伴う持続的成長が現実味を帯びているのである。
この強固な財務基盤の上に、三菱重工は投資と還元の両立を図る。前述の通り、成長領域への投資を倍増させる一方で、株主還元額も1,500億円から2,800億円へと拡大した。これは、事業拡大と株主利益を同時に実現できる自信の表れであり、経営陣が自社のキャッシュフロー創出力に強い確信を持っている証拠である。
野心的な数値目標の設定とその裏付けとなる財務基盤は、三菱重工が単なる重工業メーカーから、国家戦略を担う企業へと進化する上で不可欠な要素となっている。
エネルギー事業の成長軌道:GTCC・水素・原子力の三本柱

三菱重工業の成長戦略の第一の柱は、エネルギー事業におけるリーダーシップ強化である。既存の強みを基盤にしつつ、水素や原子力といった次世代技術へのシフトを加速させ、脱炭素社会の実現を事業機会へと変えている。
エネルギー事業の中核を担うのは、ガスタービン・コンバインドサイクル(GTCC)である。MHIはこの分野で世界トップシェアを誇り、台湾電力向け総額約7,600億円の大型案件やベトナムでの発電設備受注など、アジア市場を中心に存在感を高めている。GTCCは再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、系統安定化のための調整電源として需要が増大しており、今後も安定した収益源となる見通しだ。
水素・アンモニア燃焼技術の開発も急速に進んでいる。高砂水素パークでは大型ガスタービンでの30%水素混焼に成功し、今後は50%混焼や100%専焼へと段階的に移行する計画を掲げる。これは、既存のGTCC技術を脱炭素時代に適応させると同時に、将来の水素需要を自ら創出する戦略的取り組みである。
さらに、原子力分野でも国家方針と歩調を合わせた復権戦略を進めている。次世代の革新軽水炉「SRZ-1200」の設計開発を推進するほか、高速炉や高温ガス炉といった新技術でも主導的な役割を担う。2025年には、原子力分野の品質マネジメント国際規格「ISO 19443」を国内で初めて取得し、技術力と信頼性を国際的に証明した。
この三本柱のシナジーによって、三菱重工は短期的な収益確保と長期的な技術革新を両立している。GTCCが稼ぐキャッシュフローを水素や次世代炉の研究開発に投資し、同時にGTCC自体にも新技術を組み込むことで、現在と未来をつなぐ強靭な成長モデルを確立しているのである。
防衛・宇宙分野の拡大と国家安全保障への貢献
三菱重工のもう一つの成長エンジンが、防衛・宇宙分野である。地政学的リスクの高まりと日本政府の防衛力強化方針を背景に、この事業は安定収益源から高成長事業へと進化している。
防衛事業では、2025年4月に防衛省と契約金323億円の新型長射程ミサイル開発契約を締結した。これはスタンド・オフ防衛能力や反撃能力を具体化する国家プロジェクトであり、2032年度の完成を目指している。また、英国・イタリアと共同開発する次期戦闘機「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)」でも、日本側の主契約企業として中心的な役割を担っている。さらに、戦闘機と連携するAI搭載無人機の開発も進行中で、2025年中の飛行試験が予定されている。
宇宙分野においては、新型H3ロケットの商業化が進展している。フランスのユーテルサット社との複数回打ち上げ契約を獲得し、国際市場での信頼を高めた。H3は信頼性とコスト効率を両立させた次世代基幹ロケットであり、商業衛星打ち上げ市場における競争力を強化する役割を担う。
制度改革もMHIの追い風となっている。防衛省は装備品契約の利益率上限を従来の約8%から最大15%へと引き上げ、国内防衛産業の基盤強化を図った。これにより、三菱重工の防衛事業は「量の拡大」と「質の改善」を同時に実現し、利益成長の源泉となっている。
2025年度第1四半期の「航空・防衛・宇宙」セグメントの売上収益は3,027億円、事業利益は151億円と堅調に推移しており、将来的には売上高1兆円超への成長も期待されている。
このように、防衛・宇宙分野は単なる企業収益の柱ではなく、日本の国家安全保障そのものを支える基盤である。三菱重工は、防衛装備と宇宙技術の両面で、産業界を超えて国家の安全を支える存在へと進化している。
GXセグメント創設と次世代エネルギー経済の構築
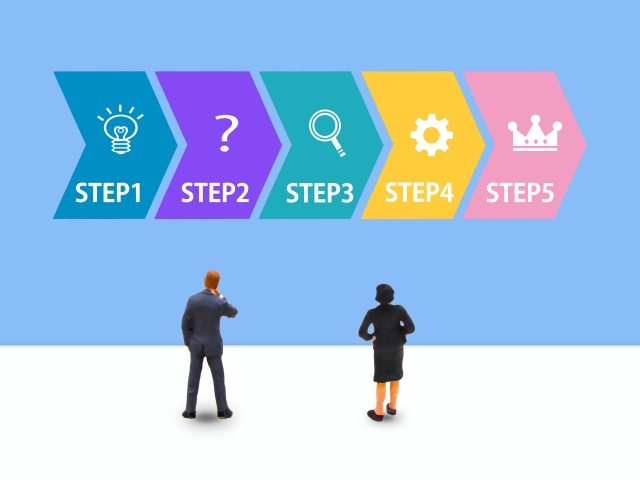
三菱重工業は2024年4月、脱炭素事業の推進を目的に「GXセグメント」を新設した。従来は水素、アンモニア、CCUSといった機能が部門ごとに分散していたが、これを統合することで、効率的なプロジェクトマネジメントとエンジニアリング体制を構築した。これにより、顧客へのワンストップ提供が可能となり、成長領域の事業化を加速する狙いがある。
GXセグメントの役割は単なる組織改革にとどまらない。水素やアンモニアの燃料供給インフラ構築、CO2回収・利用・貯留の実用化といった分野を包括的に推進することで、未来のエネルギー経済全体をデザインする役割を担う。
具体例として、MHIは米国ユタ州で計画されている世界最大級のグリーン水素製造・貯蔵・供給プロジェクトに参画している。また、シンガポールでのアンモニアバンカリング事業や、ExxonMobilとの提携によるCCUSソリューションの提供体制強化など、グローバルに多角的な事業展開を進めている。
さらに、小型CO₂回収装置「CO₂MPACT」の開発により、これまで大規模設備でしか導入できなかった分野への適用拡大も可能となった。これにより、産業界全体における脱炭素の裾野を広げる効果が期待される。
GXセグメント創設の背景には、政府のGX実現に向けた基本方針がある。原子力の活用や水素・アンモニアの導入促進、CCUSの商用化といった政策課題は、三菱重工の戦略と完全に同期している。国家方針と連動することで、事業の予見可能性が高まり、投資家にとっての政策リスクが低減する点も大きな強みである。
このように、GXセグメントは単なる新設部署ではなく、三菱重工の未来戦略を象徴する存在であり、同社が脱炭素時代のエネルギー経済をリードする中心的役割を果たすとみられる。
最新動向:アジア市場での大型受注と国際連携の深化
三菱重工は2025年に入り、アジア市場を中心に大型案件を相次いで獲得している。2025年9月には台湾電力から総額約7,600億円規模のGTCC発電設備を受注、さらにベトナムでも同種の大型案件を獲得した。これにより、同社はアジアの電力インフラ市場において圧倒的な存在感を示している。
また、2025年8月には中国・前海エネルギー科技発展有限公司と戦略的提携を結び、「三菱重工大湾区デジタル低炭素運営センター」を設立した。これにより、グレーターベイエリアにおけるグリーンエネルギー事業への本格参入を果たし、現地政府や企業との連携を強化している。
さらに、新興国との協業も進んでいる。2025年5月にはウズベキスタンエネルギー省と脱炭素化分野での協力に関するMOUを締結した。こうした取り組みは、途上国におけるエネルギー転換を技術面から支援するものであり、国際社会における日本の存在感を高める役割も担っている。
一方、防衛・安全保障分野でも進展が見られる。同年9月には海上保安庁向けの大型巡視船「ひろしま」の進水式を実施し、海洋安全保障への貢献を示した。また、AI搭載無人機の初飛行試験計画を発表し、次期戦闘機「GCAP」と連携する先端防衛技術の開発を本格化させている。
宇宙分野では、H3ロケットの商業契約が拡大している。2024年9月にはユーテルサット社との複数回打ち上げ契約を獲得し、商業衛星打ち上げ市場への本格参入を実現した。
このように、アジア市場での大型受注と国際連携の深化は、三菱重工のグローバル戦略を象徴する動きである。エネルギーから防衛、宇宙まで多岐にわたる分野で成果を上げており、同社が単なる製造業を超えて世界的な政策実行プレイヤーへ進化していることを物語っている。
市場評価と競合分析:川崎重工・IHIとの比較優位性

三菱重工業の戦略と業績は、国内競合である川崎重工業やIHIとの比較において際立っている。2025年度第1四半期の決算において、三菱重工が前年同期比で売上収益7.4%増、事業利益24.7%増という堅調な成長を示した一方で、川崎重工は親会社株主利益が72%減益、IHIも為替影響などから減収減益に陥った。
この格差は一時的な景気変動ではなく、事業ポートフォリオ戦略の違いに由来している。三菱重工がエネルギー転換と防衛という二大成長分野に資源を集中させたのに対し、川崎重工やIHIは事業構成が分散し、外部環境の逆風に脆弱な構造が残っている。
競合3社の四半期業績比較
| 企業 | 2025年度Q1売上収益 | 前年同期比 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 三菱重工 | 1兆1,936億円 | +7.4% | エネルギー・防衛が牽引 |
| 川崎重工 | 減収 | -72%(最終利益) | 為替影響と需要低迷 |
| IHI | 減収減益 | 不明確 | 外部環境の影響 |
証券アナリストの評価も三菱重工に軍配が上がる。2025年9月時点で17名中14名が「買い」または「強気買い」のレーティングを付与しており、2026年売上収益のコンセンサスは5.42兆円と、会社予想を上回る見通しである。
さらに、防衛省の契約制度改革により装備品契約の利益率上限が最大15%へ引き上げられたことは、三菱重工に直接的な追い風となっている。競合企業に比べ、防衛・宇宙分野での事業規模と技術力において優位に立つ同社は、政策面からも恩恵を享受できる立場にある。
このように、三菱重工は市場からの高評価に加え、競合との差別化を実際の数値で示しており、その優位性は戦略的選択と実行力の結果として明確に現れている。
将来への課題と展望:受注残高の遂行と成長領域の収益化
三菱重工が国家戦略企業としての地位を確立しつつある一方で、今後の課題は戦略の実行力に集約される。最大の焦点は、10兆円を超える受注残高をいかに確実に遂行し、想定利益率で収益化できるかである。大規模プロジェクトの増加に伴い、プロジェクトマネジメント力やサプライチェーンの安定確保が企業価値を左右する要素となる。
特に防衛分野では、国際共同開発プロジェクトの成否が重要だ。次期戦闘機「GCAP」のような複雑かつ長期にわたる開発案件は、パートナー国との調整や技術標準化におけるリスクが大きい。国際協調と技術主導権のバランスを取りながら、商業的成功へつなげる必要がある。
成長領域の収益化も大きな課題である。水素、アンモニア、CCUSといった新技術は現時点では研究開発段階にとどまる部分が多く、本格的な事業収益化には時間を要する。これらを「伸長事業」へと育成できるかが、長期的な企業価値向上の分水嶺となる。
課題の整理
- 受注残高10兆円超の確実な遂行
- 国際共同開発(特にGCAP)の成功
- 水素・アンモニア・CCUSの収益化加速
- サプライチェーンの安定確保
とはいえ、三菱重工の位置づけは極めて有利である。エナジートランジションと安全保障という二大メガトレンドを事業の柱とし、国家方針と緊密に連動することで需要の安定性を確保している。
今後数年間は、日本産業界における三菱重工の成功が、脱炭素と安全保障という二大課題における日本の技術的リーダーシップを占うバロメーターとなるだろう。

