2025年の大塚ホールディングスは、まさに「成長の頂点」に立ちながらも、次なる大きな挑戦に直面している。2024年12月期決算では売上収益2兆3,299億円、営業利益3,236億円と過去最高を更新し、株価も8,500円台に達するなど、財務基盤はかつてないほどの強固さを誇っている。しかし、その足元では主力製品「ジンアーク/サムスカ」の特許切れが迫り、2026年以降に約3,100億円規模の減収インパクトが見込まれる。いかにこの逆風を乗り越え、持続的な成長へとつなげるかが、同社の未来を左右する最大の課題となっている。
大塚HDはこの局面において、第4次中期経営計画(2024-2028年)を推進し、従来の「単品ブロックバスター依存」から「プラットフォーム戦略」への転換を鮮明にしている。自己免疫疾患やがん領域への研究開発投資、Araris社買収によるADC技術の獲得、さらに「エクエル」やBonafide社ブランド群を核としたフェムテック市場開拓など、次世代の成長源を多角的に構築している。好調な財務実績は安住の証ではなく、未来の成長を切り拓くための軍資金である。この「ピーク利益」をいかに次の成長曲線へと転換できるか、大塚HDの戦略執行力が問われている。
大塚HDの現状:過去最高益と迫るパテントクリフ
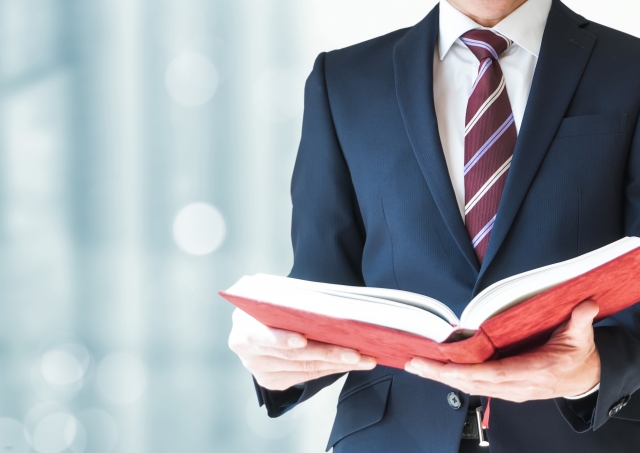
大塚ホールディングスは2024年12月期において、売上収益2兆3,299億円(前期比15.4%増)、営業利益3,236億円(同131.8%増)を計上し、過去最高の業績を達成した。2025年に入っても勢いは衰えず、第2四半期累計では売上収益1兆1,808億円(前年同期比6.5%増)、営業利益2,421億円(同91.7%増)と、依然として高成長を維持している。市場はこれを好感し、株価は8,500円台の高値を記録し、時価総額は4兆6,000億円を超える水準で推移している。
特に注目すべきは、抗精神病薬「レキサルティ」や「エビリファイ」フランチャイズの貢献である。レキサルティはアルツハイマー型認知症に伴うアジテーション治療で米国シェアを25%に迫る勢いで拡大し、エビリファイの長期持続性注射剤も堅調な成長を遂げている。これらが潤沢なキャッシュフローを生み出し、研究開発やM&Aに再投資できる体力を生んでいる。
一方で、最大のリスクは主力製品「ジンアーク/サムスカ」(一般名トルバプタン)の特許切れである。同製品は2024年に2,814億円を売り上げたが、2026年以降の米国での特許失効によって、約3,100億円のマイナス影響が見込まれている。経営陣はこの局面を「調整期」と位置づけ、最小限かつ短期的に収める方針を掲げている。
表:大塚HDの主要財務指標(2024年実績・2025年予想)
| 指標 | 2024年12月期 | 2025年12月期予想 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2兆3,299億円 | 2兆3,800億円 | +2.2% |
| 営業利益 | 3,236億円 | 4,500億円 | +39.1% |
| 当期利益 | 3,431億円 | 3,300億円 | -3.8% |
| 配当金 | 120円 | 140円 | +20円 |
このように、大塚HDは過去最高益を享受しながらも、特許切れという不可避のリスクに直面している。好調な業績は安住の証ではなく、むしろ次なる戦略を加速させるための軍資金であることが強調される。
第4次中期経営計画の核心:「プラットフォーム戦略」への転換
2024年から始動した第4次中期経営計画(2024〜2028年)は、従来の単一ブロックバスター依存から脱却し、持続可能な成長を支える「プラットフォーム戦略」へと舵を切った点に大きな特徴がある。目標は2028年に売上収益2兆5,000億円を達成し、ROIC9.5%以上、ROE10%以上を実現することである。
この計画の柱は以下の3点に整理できる。
- Well-beingにつながる新たな価値創造
- 「グローバル10プラス2」製品群を軸とした進化した事業成長ステージ
- 資本コストを意識した積極的な財務戦略
特に注目されるのは、自己免疫疾患領域の研究開発プラットフォームである。2018年のVisterra社買収以降、2024年のJnana Therapeutics社買収、2025年のHarbour BioMed社との契約、さらにCantargia社資産買収などを通じて、複数の新規モダリティを獲得している。その成果として、APRIL中和抗体「シベプレンリマブ」が米国で承認申請中であり、今後の成長エンジンとして期待される。
さらに2025年3月にはスイスのAraris Biotech社を買収し、ADC(抗体薬物複合体)技術という次世代のがん治療分野に参入した。この買収は単一製品の確保ではなく、将来複数の製品を生み出し得る「技術プラットフォーム」そのものを獲得した点に戦略的意義がある。
また、ニュートラシューティカルズ事業では「女性の健康」をキーワードに市場再定義を進め、「エクエル」や米国Bonafide社のブランド群を基盤としたフェムテック市場開拓を加速させている。これは社会課題解決型の成長戦略として、医療関連事業のリスク分散を支える役割を担う。
このように第4次中期経営計画は、短期的な特許切れリスクを超え、長期的に安定した収益基盤を築くための戦略的転換点である。単発的な成功に依存せず、研究開発、M&A、ニュートラ事業の三本柱を連動させることで、強靭な成長モデルの構築を目指している。
医療関連事業の成長エンジン:レキサルティとエビリファイの戦略的役割

大塚HDの収益構造において、医療関連事業は依然として最大の成長エンジンである。2024年12月期には売上収益1兆6,290億円(前期比17.1%増)、事業利益3,906億円(同38.5%増)を記録し、グループ全体の業績を大きく押し上げた。2025年上期も好調を維持し、売上収益8,367億円を達成している。この背景には、「レキサルティ」や「エビリファイLAI」など中枢神経領域のフランチャイズが存在する。
レキサルティ:アルツハイマー型認知症市場を牽引
レキサルティ(ブレクスピプラゾール)は2024年に2,674億円(前期比25.8%増)を売り上げ、中枢神経領域における成長を強力に牽引した。特に米国ではアルツハイマー型認知症に伴うアジテーション治療で承認を獲得し、市場シェアは2025年4月時点で21.7%、直近では25%に迫る水準に達している。この新適応は巨大な未充足ニーズ市場であり、今後数年の持続的成長が期待される。
一方でPTSDへの適応拡大はFDA諮問委員会で否定的見解が示されており、ライフサイクルマネジメントにおけるリスクが浮き彫りになった。これにより、同社の研究開発力や他パイプラインへの期待度が一層高まっている。
エビリファイLAI:持続型注射剤で市場を防衛
エビリファイの持続型注射剤(LAI)も強固な収益源である。1ヵ月製剤の「エビリファイメンテナ」は2024年に2,190億円を売り上げ、安定した成長を続けている。さらに利便性を高めた2ヵ月製剤「エビリファイアシムトファイ」は286.8%増の189億円と急拡大し、既存患者の切り替えや新規患者獲得を通じてフランチャイズ全体を強化している。
戦略的意義
レキサルティとエビリファイLAIの収益力は、「ジンアーク」の特許切れによる減収を補う戦略的役割を担っている。特にアルツハイマー型認知症市場からのキャッシュフローは、自己免疫疾患やADCといった次世代パイプラインが成熟するまでの時間を稼ぐ「架け橋」となる。現行ブロックバスターの成長維持が、未来の投資に直結する構図が鮮明になっている。
ニュートラシューティカルズ事業の拡大とフェムテック市場での先手
大塚HDのニュートラシューティカルズ(NC)事業は、医薬品事業の高リスク性を補完する安定的な収益源として重要性を増している。2024年には売上収益5,570億円(前期比15.2%増)を記録し、グループ全体のポートフォリオにおけるバランサーの役割を果たした。
グローバルブランドの強化
ポカリスエットは「気候・環境リスク」カテゴリーを代表するブランドとして、ベトナムでの新工場建設やインド市場参入を進めており、新興国市場でのシェア拡大を狙う。同時に国内ではアクエリアスとの競争が続き、スポーツ飲料市場の覇権争いが熾烈化している。
ネイチャーメイドは日米のサプリメント市場で強固な地位を築き、米国オハイオ州でのグミタイプ製品専用工場を新設するなど製造能力を拡大。製薬会社が手掛けるという品質保証が、消費者からの強い信頼につながっている。
フェムテック市場での先手
エクエルは2024年に前年比52.3%増の驚異的な成長を遂げ、フェムケア市場の代表製品として存在感を示した。さらに米国Bonafide Health社を買収したことで、更年期ケアを中心とした女性向け健康食品のグローバル展開を加速させている。日本国内ではフェムケア市場規模が2023年に750億円に達し、今後も拡大が見込まれる中、大塚HDは早期にポジションを確立した格好である。
戦略的価値
NC事業の意義は単なる収益多角化にとどまらない。安定したキャッシュフローは研究開発投資の原資となり、また「ポカリスエット」や「ネイチャーメイド」といったブランドは世界中の消費者と直結する無形資産を形成している。これにより、医薬品だけでは得られないブランド力と消費者接点を武器に、企業全体の競争優位性を高めている。
大塚HDは医療と生活の両輪を強化することで、特許切れリスクを乗り越え、より強靭で多角的な成長モデルを構築しつつある。
自己免疫疾患とADC:次世代パイプライン構築の最前線

大塚HDは、ジンアーク特許切れという巨大な逆風に対処するため、自己免疫疾患とがん領域に注力し、次世代パイプラインを構築している。研究開発費は年間3,000億円以上、5年間で総額1兆5,000億円と過去最大規模に達しており、その重点投資先が自己免疫疾患領域とADC(抗体薬物複合体)である。
自己免疫疾患領域での戦略的拡大
大塚HDは2018年にVisterra社を買収し、APRIL中和抗体「シベプレンリマブ」を獲得。これはIgA腎症を対象とし、米国で申請済み、日欧中ではP3段階にある。さらに2024年にはJnana Therapeuticsを買収し、SLCトランスポーターを標的とする低分子創薬基盤を獲得。2025年にはHarbour BioMed社から二重特異性T細胞エンゲージャー「HBM7020」、Cantargia社からIL-1RAP抗体「CAN10」資産を取得し、パイプラインを拡充した。現在、自己免疫疾患関連のパイプラインは8つの候補品で構成され、2030年以降の成長を見据えた次世代収益基盤となっている。
ADC技術でがん領域へ本格参入
がん領域では大鵬薬品を軸に強化を進め、2025年3月にはスイスのAraris Biotechを最大11.4億ドルで買収した。Araris社の独自リンカー技術を獲得したことで、自社でADCの臨床候補を創出できる基盤を手に入れた。競合の第一三共がADC分野で先行する中、大塚HDは後発ながらもプラットフォームを基礎から構築する戦略をとり、長期的な競争優位性を目指す姿勢を鮮明にしている。
パイプラインの期待値
- シベプレンリマブ:2025年米国承認取得見込み
- HBM7020:2030年頃のPOC取得
- CAN10:2030年頃のPOC取得
- zipalertinib(EGFR阻害剤):2025年下期に迅速承認申請予定
これらの進捗は、特許切れ後の売上を補完するだけでなく、次の成長曲線を描くための試金石となる。
成長を加速させるM&A戦略と資本効率の追求
大塚HDは潤沢なキャッシュフローを背景に、積極的なM&Aを展開している。直近のディールは既存事業の強化と新規領域への進出という明確な意図に基づいており、資本コストを意識した効率的な投資判断が特徴である。
主なM&Aの動き
| 対象企業/パートナー | 発表時期 | 獲得資産/技術 | 戦略的意図 |
|---|---|---|---|
| Araris Biotech AG | 2025年3月 | 次世代ADCリンカー技術 | がん領域での基盤強化 |
| Jnana Therapeutics | 2024年8月 | 低分子創薬基盤 | 自己免疫疾患領域強化 |
| Cantargia AB | 2025年7月 | IL-1RAP抗体「CAN10」 | パイプライン拡充 |
| Harbour BioMed | 2025年6月 | T細胞エンゲージャー「HBM7020」 | 新規モダリティ獲得 |
| Bonafide Health | 2023年12月 | 女性向け健康食品ブランド | フェムテック市場開拓 |
財務戦略との一体化
これらのM&Aは単なる事業拡大ではなく、第4次中期経営計画の「ROIC9.5%以上」「ROE10%以上」という財務目標と結びついている。経営陣は資本効率を重視し、投資回収の見通しを前提にディールを決定している点が特徴である。過去の「エビリファイ」依存から脱却するため、収益源の多様化とリスクヘッジを同時に進めている。
成長触媒としての位置づけ
Bonafide社の買収によって米国のフェムケア市場に足場を築き、Araris社買収でがん領域における競争力を高めるなど、M&Aは医薬とニュートラシューティカルズの両輪を補強する役割を担う。さらに自己免疫疾患分野への一連の投資は、長期的な成長と資本効率を両立させる戦略的布石となっている。
大塚HDは、短期的な収益確保だけでなく、持続可能な成長を実現するために、M&Aを成長触媒として位置づけている。資本効率を追求しつつ、プラットフォーム型の事業モデルを構築する姿勢は、同社が世界的な競争環境で優位を保つための核心戦略である。
ESGとグローバル展開:企業価値を高める非財務戦略

大塚HDは、財務面での成長に加え、非財務領域における取り組みを強化し、企業価値の最大化を図っている。特にサステナビリティやESG戦略は、グローバル企業としての信頼性と持続可能性を高める上で中核的な要素となっている。
環境領域での高評価
同社は国際的な環境評価機関CDPから、気候変動への取り組みにおいて3年連続で最高評価「Aリスト」に認定されている。国内でも消費者庁主催の「消費者志向経営優良事例表彰」で長官表彰を受賞し、環境や社会に配慮した事業運営が高く評価されている。また、有価証券報告書においてTCFD提言に基づく気候関連リスク・機会の情報開示を開始し、投資家との透明性ある対話を強化している。
グローバルサプライチェーン強化
生産・供給体制の拡充も積極的である。ベトナムにポカリスエット新工場を建設し、インド市場での販売を開始するなど、アジア新興国での基盤を拡大した。さらに米国ではグミサプリメント専用工場を稼働させ、サプリメント需要の高まりに対応している。こうした設備投資は、需要の多様化や地政学リスクへの耐性を高め、グローバル市場での供給安定性を確保する戦略的布石である。
デジタルトランスフォーメーションと人材育成
大塚HDは「大塚デジタルアカデミー」を開設し、研究開発から販売、サプライチェーンまでデータ活用を推進するデジタル人材育成に取り組んでいる。これにより、事業効率の向上だけでなく、新しい価値創造を可能にする組織変革を進めている。
これらのESGとグローバル展開の両輪は、財務的成果を支えると同時に、投資家や消費者からの信頼を獲得し続ける基盤として機能している。非財務戦略の充実が、結果的に中長期的な株主価値向上につながっているのである。
国内外競合との比較から見る大塚HDの競争優位性
大塚HDの位置づけを明確にするためには、国内外の競合他社との比較が不可欠である。特に製薬大手である武田薬品工業、第一三共、アステラス製薬との関係性は戦略分析において重要な視点を提供する。
医薬品分野での比較
国内製薬売上高ランキングでは、武田薬品工業が4.3兆円規模で首位に立ち、大塚HDは2兆円超で第2位に位置している。アステラス製薬や第一三共がこれを追随するが、大塚HDの特徴は「医薬品+ニュートラシューティカルズ」の二本柱によるリスク分散である。特に第一三共がADC領域で先行する中、大塚HDはAraris社の買収で競合に肉薄しつつある。後発ながらも技術プラットフォームを基盤から構築する戦略は、長期的競争力につながる可能性が高い。
消費者市場における競争
ニュートラシューティカルズ事業では、食品・飲料大手が競合相手となる。国内では「ポカリスエット」と「アクエリアス」が長年にわたり市場シェアを争っており、消費者認知度ではポカリが優位に立つ一方、流通網ではアクエリアスが強みを持つ。この競争構造の中で、大塚HDは海外展開を強化し、新興国市場の拡大で差別化を進めている。
市場環境要因と対応力
2025年の薬価改定に伴い、業界全体で2,466億円規模の薬剤費削減が見込まれる中、大塚HDはNC事業のキャッシュフローを研究開発投資に振り向け、薬価下落圧力を吸収している。医薬と消費者向け事業を両輪とするポートフォリオ構造が、競合に対する優位性を生み出している。
競合分析の視点から見ると、大塚HDは規模で武田薬品には及ばないものの、事業多角化による安定性と次世代パイプラインへの積極投資によって、独自の競争優位性を築いている。特許切れという大きな試練を抱えつつも、同社の強みはリスクを成長機会へと転換する柔軟性にある。
SWOT分析で読み解く将来の成長可能性とリスク

大塚HDの将来展望を整理する上で、SWOT分析は有効なフレームワークとなる。強みと弱み、機会と脅威を具体的に見ていくことで、同社がどのようにして持続的な成長を確保できるかが浮かび上がる。
強み:多角的な事業モデルとブランド力
大塚HDの最大の強みは、医薬品とニュートラシューティカルズ(NC)の二本柱を持つ多角的事業モデルである。医薬品領域では「エビリファイ」や「レキサルティ」など中枢神経領域の強固なフランチャイズが収益を支え、NC事業では「ポカリスエット」「ネイチャーメイド」「エクエル」といったブランドが世界的に認知されている。これにより、単一製品依存リスクを分散し、安定したキャッシュフローを生み出す構造を確立している。
また、2024年度の営業利益は3,236億円と過去最高を更新し、株価も時価総額4兆6,000億円超に達するなど、財務的な強固さも他社に対する競争優位性の源泉となっている。
弱み:主力製品依存と後発参入のリスク
一方で、収益の多くを「ジンアーク」「レキサルティ」「エビリファイ」に依存している点は明確な弱みである。特にジンアークは2026年以降に特許切れを迎え、約3,100億円の減収影響が見込まれている。さらにADC領域など新規分野では後発参入であり、第一三共のような先行企業と比較して開発リスクが大きい。研究開発の進捗遅延や承認失敗は、成長戦略に深刻な影響を与える可能性がある。
機会:新市場と技術革新
成長機会としては、自己免疫疾患やフェムテック市場が挙げられる。シベプレンリマブをはじめとするパイプラインは2030年以降の収益基盤を形成する可能性を秘めており、さらにエクエルやBonafide社ブランド群は女性の健康市場拡大において強い成長余地を持つ。加えて、デジタルトランスフォーメーションやAI活用による創薬効率化も、新たな競争優位性を生み出す要素となる。
脅威:規制と競争環境
脅威としては、日本国内における薬価改定が継続的に収益を圧迫するリスクがある。2025年の薬価改定では業界全体で2,466億円規模の薬剤費削減が見込まれており、どの製品が対象になるかによって収益影響が変動する。また、ADC領域では第一三共、免疫分野ではアステラスや海外大手との激しい競争が続き、後発参入の大塚HDにとっては厳しい環境となる。
総括:成長シナリオの鍵
以上を踏まえると、大塚HDの将来成長の成否は以下の3点に集約される。
- シベプレンリマブを筆頭とする自己免疫疾患パイプラインの着実な進展
- ADC技術の早期実用化と臨床候補品創出による競争力強化
- NC事業の持続的拡大とグローバルブランド戦略の深化
ジンアーク特許切れという試練をいかに乗り越え、次世代の収益基盤を確立できるかが最大の焦点である。強みを最大化し、弱みを補う戦略遂行力が問われる数年間になるだろう。

