第一三共は、かつて国内市場を主戦場とする製薬大手であったが、今や世界的なオンコロジーのリーダーとしての地位を確立した。その原動力となったのは、抗体薬物複合体(ADC)技術における比類なき優位性である。特にエンハーツは、従来の標準治療を凌駕する臨床成績を示し、乳がんや肺がん領域における治療パラダイムを根底から書き換えた。
また、TROP2標的ADCであるダトロウェイをはじめとする「5DXd」フランチャイズは、エンハーツに続く成長の柱として期待され、同社の成長を持続的に牽引する見込みである。さらに、メルクやアストラゼネカといった世界的製薬大手との戦略的提携は、開発リスクの分散とグローバル展開の加速を同時に実現し、競争優位を強固なものとした。
加えて、6,000億円規模に及ぶ製造能力拡充投資や、グローバル人事制度の導入といった組織改革は、国際的競争力の強化に直結している。第一三共の挑戦は、単なる業績向上にとどまらず、世界の製薬産業全体に新たなモデルを提示するものである。
第一三共の戦略転換:国内大手から世界的オンコロジー企業への変貌
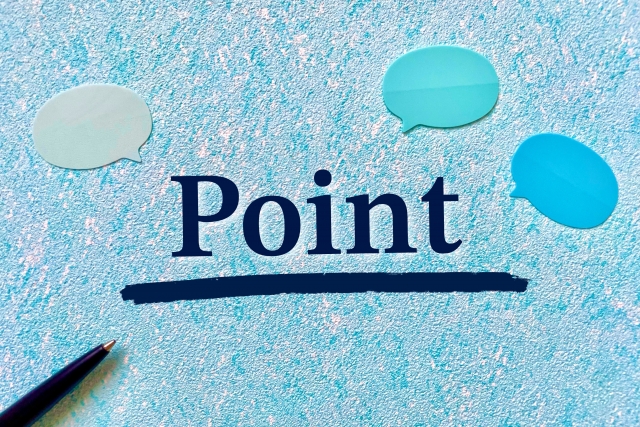
第一三共は、2020年代前半まで国内市場を中心に展開する製薬大手であったが、2025年現在では世界的なオンコロジーリーダーとしての存在感を確立した。その変革の象徴が、第5期中期経営計画に掲げられた「がんに強みを持つ先進的グローバル創薬企業」というビジョンである。当初、2025年度の売上収益目標は1兆6000億円と設定されていたが、直近の見通しでは2兆円を突破する勢いを見せている。これは当初計画を25%上回り、さらにオンコロジー領域の売上は9000億円超と目標の1.5倍に達する見込みである。
この成長を牽引したのが、抗体薬物複合体(ADC)プラットフォームの強みである。エンハーツを筆頭に、ダトロウェイやHER3、B7-H3、CDH6を標的とする後続品が次々と後期開発に進んだことにより、同社は単一製品依存からポートフォリオによる持続的成長へと移行した。これにより、第一三共は単なる製薬企業から、がん治療の未来をリードするイノベーターへと進化を遂げている。
2026年3月期第1四半期決算では、売上収益が前年同期比8.8%増の4746億円、コア営業利益が32.1%増の963億円と、収益性の改善が明確に示された。特に売上原価率の改善は、高利益率のADC製品比率が拡大した結果であり、財務基盤を一層強固にした。
表:第一三共の業績ハイライト(2026年3月期第1四半期)
| 指標 | 実績(億円) | 前年同期比 | 主因 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4746 | +8.8% | エンハーツ、ダトロウェイの成長 |
| コア営業利益 | 963 | +32.1% | 製品構成の変化 |
| 親会社所有者帰属利益 | 855 | +0.1% | 金融収支悪化の影響を吸収 |
第一三共が築いた財務の好循環は、研究開発投資や設備拡張、株主還元を同時に実現する力を持つ。これは単なる数字の拡大ではなく、グローバル製薬企業としての競争優位性の基盤を形成しているのである。
エンハーツがもたらす治療パラダイムの再定義と市場創造
第一三共の成長を象徴するのが、ADC「エンハーツ」の成功である。2025年の米国臨床腫瘍学会(ASCO)で発表されたDESTINY-Breast09試験は、HER2陽性転移性乳がんの一次治療において、従来のTHP療法に比べて病勢進行または死亡のリスクを44%低減するという圧倒的な成果を示した。無増悪生存期間は40.7ヶ月と、標準治療群の26.9ヶ月を大きく上回った。
この結果は、化学療法を含まない新しい治療レジメンが標準治療を凌駕することを示し、治療パラダイムを根本から書き換えるものである。米国FDAが画期的治療薬指定を与えたことも、その臨床的意義の大きさを裏付けている。
さらに注目すべきは、エンハーツがHER2低発現・超低発現乳がんにも適応を拡大した点である。従来HER2陰性とされ治療選択肢が限られていた患者群に対しても有効性が示されたことで、新たな市場が創出された。これにより、エンハーツは単なる製品にとどまらず「パイプラインそのもの」としての地位を確立している。
表:DESTINY-Breast09試験主要データ
| 項目 | エンハーツ群 | 標準治療群 |
|---|---|---|
| PFS中央値 | 40.7ヶ月 | 26.9ヶ月 |
| ハザード比 | 0.56 | – |
| 奏効率(ORR) | 85.1% | 78.6% |
| 完全奏効率(CR) | 15.1% | 8.5% |
2024年度のエンハーツ売上は5528億円、2025年度は6621億円に達する見込みであり、今後も指数関数的な成長が期待されている。アナリストの間では、史上最大級のがん治療薬になるとの予測も出ている。
エンハーツの進化は、単に競合を上回るのではなく、新たな治療対象を生み出す点にこそ意義がある。第一三共はエンハーツを通じて、がん治療の常識を覆し、患者に新たな選択肢を提供する革新企業としての地位を固めたのである。
ダトロウェイと「5DXd」フランチャイズが拓く次の成長曲線

エンハーツに続く第二の成長ドライバーとして注目されているのが、TROP2標的ADC「ダトロウェイ(Dato-DXd)」である。米国食品医薬品局(FDA)は2025年7月を目標に承認審査を進めており、優先審査指定を受けている。この承認が下りれば、非小細胞肺がんにおいて初めてのTROP2標的ADCとなり、巨大な市場を切り拓くことになる。
第一三共の強みは、個別製品の成功にとどまらず、ADC全体を体系的に展開する「5DXd」フランチャイズ戦略にある。HER2、TROP2、HER3、B7-H3、CDH6といった多様な標的を対象に、5つのADCを並行して開発することで、リスク分散と持続的成長を両立させている。これらは単独のブロックバスターに依存するのではなく、複数の薬剤群が相互補完的に成長を支えるポートフォリオ型の発展モデルである。
表:5DXdフランチャイズ主要開発状況
| 製品名 | 標的抗原 | 主な適応症 | 開発段階 | 提携先 |
|---|---|---|---|---|
| エンハーツ | HER2 | 乳がん、肺がん、胃がん | 承認済み | アストラゼネカ |
| ダトロウェイ | TROP2 | 肺がん、乳がん | 承認審査中 | アストラゼネカ |
| パトリツマブ | HER3 | 肺がん、乳がん | 第3相 | メルク |
| イフィナタマブ | B7-H3 | 肺がん、前立腺がん | 第2/3相 | メルク |
| ラルドタツグ | CDH6 | 卵巣がん、腎細胞がん | 第1/2相 | メルク |
このように、第一三共のADC戦略は単なる製品の積み上げではなく、知見を横展開するプラットフォーム型の発想である。エンハーツで得られた臨床経験や製造ノウハウは、そのまま後続品の開発効率化に活かされている。特に毒性管理や製造工程の精緻化は、複数製品の同時開発を加速させる原動力となっている。
アナリストの間では、このフランチャイズ戦略が第一三共を「ADC市場の覇者」へと押し上げるとの見方が強い。今後は、免疫チェックポイント阻害剤などとの併用療法が普及することで、各ADCの適応範囲がさらに拡大し、市場規模は指数関数的に拡大する可能性がある。
メルク・アストラゼネカとのメガアライアンスが生む競争優位性
第一三共の飛躍を可能にした最大の要因の一つが、世界的製薬大手との戦略的アライアンスである。2019年のアストラゼネカとの提携は、エンハーツの臨床開発と商業化を加速させる成功モデルとなった。この経験を踏まえ、2023年にはメルクと総額最大220億ドル規模の超大型提携を締結し、HER3、B7-H3、CDH6を標的とする3つのADCの共同開発に踏み出した。
この提携では、メルクが最初の20億ドルの研究開発費のうち75%を負担する仕組みが盛り込まれており、第一三共にとって財務的リスクを最小化しつつグローバル開発を推進できる極めて有利な条件である。さらに、日本を除く全世界での利益を50%ずつ分配する形となっており、単独開発では到達できなかった規模の臨床試験や適応拡大を現実化させている。
箇条書きで整理すると、このアライアンスの優位性は以下に集約される。
- 開発費用の大部分をパートナーが負担することで、財務リスクを軽減
- 世界市場での販売網と臨床開発力を共有し、上市スピードを加速
- 多様な適応症に同時並行で挑戦できるスケールメリットを獲得
- 研究開発から商業化までを共同で進めることで、成功確率を最大化
一方で、提携には課題も存在する。例えば、2025年5月にはパトリツマブ デルクステカンの米国申請を自主的に取り下げる事態があった。全生存期間で統計的有意差を示せなかったためである。しかし、このリスクもメルクが大部分を吸収したことで、第一三共にとっては致命的な打撃にはならなかった。むしろ、提携の有効性を逆説的に証明する事例となった。
アストラゼネカとメルクという業界最大手2社と同時にメガアライアンスを展開し、かつそれを運営できる製薬企業は極めて稀である。第一三共は、このパートナーシップを通じてグローバルでの競争優位性を確固たるものにしつつある。アライアンスマネジメント自体が同社の新たなコア・コンピタンスとして浮上しており、今後の持続的成長を支える無形資産となるだろう。
6,000億円規模の設備投資が支えるグローバル供給体制とリスクヘッジ

第一三共は、急拡大するADC需要に対応するため、6,000億円規模の巨額投資による製造能力強化を進めている。日本国内の館林、小名浜、平塚の3工場に加え、ドイツのプファッフェンホーフェンでは10億ドルを投じた新施設、米国オハイオ州ニューアルバニーでは3億5,000万ドルの拡張、中国・上海では1億5,400万ドルの新工場建設を実施中である。これにより、2030年までに年間40万人規模の患者に「5DXd」ポートフォリオを届ける体制を構築しようとしている。
ADCの製造は、抗体と高活性ペイロードを別々に生産し、その後に精密なコンジュゲーション工程で結合させる極めて複雑なプロセスを要する。生産過程の難易度の高さから、供給網の遅延や不具合は数千億円規模の機会損失につながりかねない。したがって、冗長性を持つ多拠点化と地理的分散は事業継続性を確保するための不可欠な戦略である。
表:第一三共の主要製造拠点と投資額
| 地域 | 主な拠点 | 投資額 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 館林・小名浜・平塚 | 数千億円 | 国内生産基盤強化 |
| ドイツ | プファッフェンホーフェン | 約10億ドル | 欧州市場供給 |
| 米国 | オハイオ州ニューアルバニー | 約3.5億ドル | 北米需要対応 |
| 中国 | 上海 | 約1.54億ドル | アジア市場強化 |
特に、米中間の地政学的リスクが高まる中で、日欧米中にバランスよく配置された製造拠点は、貿易摩擦やパンデミックといった不測の事態にも対応できる柔軟性を備える。この「サプライチェーン主権」こそが、グローバル市場で安定的に製品を供給するための強力なリスクヘッジとなっている。
第一三共が巨額投資を敢行する背景には、エンハーツやダトロウェイといったADC製品群が急速に需要を拡大し、単なるブロックバスターを超えて複数領域で治療の柱となりつつある現実がある。サプライチェーンの整備は、競合に先んじて市場を獲得し続けるための戦略的布石であり、企業価値の持続的成長を支える基盤となる。
人的資本改革とジョブ型雇用がもたらす国際競争力の強化
グローバル企業としての成長を実現するため、第一三共は2025年度から人事制度を大きく刷新し、従来の年功序列型の「メンバーシップ型」から「ジョブ型」雇用へと転換した。これにより、評価・等級・報酬体系を全世界で統一し、国際的人材市場での競争力を確保している。
この改革の成果はすでに現れつつある。30代社員が幹部職に登用され年収が約40%増加した事例、新卒初任給が修士卒で37万円へ大幅引き上げられた事例などが報告されている。職務価値と成果に基づいた報酬体系は、優秀な人材を引き付け、モチベーションを高める効果を発揮している。
箇条書きで整理すると、ジョブ型導入の意義は以下の通りである。
- グローバル共通基準に基づく人材評価で、国際市場における人材確保を容易にする
- 成果主義的な報酬体系により、若手人材や専門職の登用が加速
- 社員の当事者意識を高め、組織のパフォーマンス文化を強化
- 従来制度の硬直性を解消し、迅速な意思決定を可能にする
奥澤CEOは「アカウンタブル・マインドセット」、すなわち従業員が責任感を持ち主体的に行動する姿勢の重要性を強調している。この意識改革こそが、複雑でスピードが求められるグローバル市場で競争するための土台となる。
表:人的資本改革の具体的成果
| 項目 | 改革前 | 改革後 |
|---|---|---|
| 雇用形態 | 年功序列型 | ジョブ型(職務価値基準) |
| 幹部登用 | 主に40代以降 | 30代社員も積極登用 |
| 新卒初任給(修士卒) | 約25〜27万円 | 37万円 |
| 報酬水準 | 年功連動 | 成果・貢献度重視 |
この制度改革は単なる人事施策ではなく、企業文化そのものを変革する取り組みである。グローバル製薬企業として持続的に成長するためには、研究開発力や製造力に加え、人材競争力を高めることが不可欠である。第一三共の人的資本改革は、企業の未来を左右する戦略的投資にほかならない。
ESGとDXが長期的企業価値の基盤となる理由

第一三共は、製薬企業としての収益拡大だけでなく、ESG(環境・社会・ガバナンス)とDX(デジタルトランスフォーメーション)を戦略の中心に据えている。2025年には3年連続で「DX銘柄」に選定され、また2年連続で「SX銘柄」にも選ばれるなど、外部評価機関からの高い評価を得ている。さらに、FTSE Blossom Japan IndexやMSCI Japan ESG Select Leaders Indexといった主要なESG指標にも組み入れられており、長期的な投資対象としての魅力を強化している。
DXの取り組みは多岐にわたり、コールセンターでのAI活用、翻訳支援ツールの導入に加え、研究開発におけるビッグデータ解析や臨床試験の効率化にまで及んでいる。また、ヘルスケアをサービスとして提供する「Healthcare as a Service(HaaS)」モデルの導入も進んでおり、単なる創薬企業から包括的なヘルスケア提供企業への進化が視野に入っている。
一方、ESG活動においては環境負荷低減や医薬品アクセス向上が重視されている。温室効果ガス排出削減に向けた環境マネジメントシステムの構築や、低中所得国への医薬品供給強化などがその代表例である。これらは単なる社会貢献ではなく、薬価交渉や規制当局との関係においても有利に働き、事業の継続性を担保する重要な要素となっている。
箇条書きで整理すると、ESGとDXの効果は以下の通りである。
- 投資家や機関からの信頼性向上による資本コスト低下
- サプライチェーン強靭化によるリスク管理強化
- AI・データ活用による研究開発効率の飛躍的改善
- 医薬品アクセス向上による社会的評価の確立
このように、ESGとDXは短期的利益のための施策ではなく、長期的な競争優位性と企業価値向上を支える基盤である。第一三共にとって、これらは研究開発力や財務力と並ぶ第三の成長エンジンとなっている。
激化するADC市場競争と薬価圧力への戦略的対応
第一三共が世界的に成功を収めつつある一方で、ADC市場は急速に競争が激化している。TROP2領域では、ギリアド・サイエンシズのトロデルヴィが既に乳がん領域で存在感を示し、免疫チェックポイント阻害剤との併用療法も進んでいる。さらに、ファイザーがシーゲンを430億ドルで買収し、豊富なADCポートフォリオを手にしたことは市場勢力図を大きく塗り替えた。アストラゼネカも独自のADC開発を強化しており、第一三共にとっては協業先でありながら競合でもある複雑な関係が存在する。
競争の焦点は単剤効果だけではなく、免疫チェックポイント阻害剤やPARP阻害剤との併用療法に移りつつある。最適な組み合わせを見極められるかどうかが、次世代ADCの成功を左右する。第一三共もエンハーツの併用試験を複数進めており、安全性と有効性のバランスが市場競争の勝敗を決定づける要因となる。
また、安全性リスクの管理も重要である。特にDXdプラットフォームは間質性肺疾患(ILD)という重篤な副作用のリスクを抱えており、臨床現場では厳格なモニタリングが求められる。第一三共は教育プログラムや管理ガイドラインを通じ、このリスクを「管理可能なもの」として扱う戦略を展開している。
さらに、薬価圧力も大きな課題である。日本では2025年度の薬価改定が収益に影響し、欧州では英国NICEやドイツのG-BAなどが厳格な費用対効果評価を行っている。その結果、米国市場の収益性が相対的に高まっており、第一三共がアストラゼネカやメルクといった米国強者と組む理由の一つともなっている。
表:第一三共を取り巻く主要リスク
| リスク領域 | 内容 | 企業対応策 |
|---|---|---|
| 競合 | ギリアド、ファイザー、AZなどが参入 | 5DXdフランチャイズ構築 |
| 安全性 | ILDなど重篤な副作用 | 教育・ガイドライン整備 |
| 特許 | リンカー技術訴訟など | 広範な特許網構築 |
| 薬価 | 日本・欧州での引き下げ圧力 | 米国市場での収益確保 |
このように、第一三共の成功は決して安泰ではなく、多層的なリスクと直面している。しかし、プラットフォーム技術の優位性、強力な提携戦略、そして市場適応力によって、同社は逆風を成長機会へと変える潜在力を持っている。競争と規制の板挟みの中で、いかに優位性を維持できるかが今後の最大の焦点である。

