2025年、中外製薬は創業100周年を迎え、日本を代表する製薬企業から「世界のヘルスケア産業におけるトップイノベーター」へと進化するための大転換点に立っている。同社はスイス・ロシュ社との強固なアライアンスを基盤に、2002年比で営業利益を21倍に伸長させるなど、国内製薬業界において稀有な成功を収めてきた。その潤沢な経営資源を原動力として策定された長期成長戦略「TOP I 2030」は、研究開発、デジタル、組織改革を三本柱とし、単なる事業規模の拡大ではなく、イノベーションの仕組みそのものを再構築することを目的としている。
特に、抗体エンジニアリングや中分子創薬といった独自技術を深化させ、AI創薬やリアルワールドデータ(RWD)を駆使するデジタル戦略を推進する姿勢は、同社が「守り」ではなく「攻め」に徹していることを鮮明に示している。また、全社員にジョブ型人事を適用し、年齢上限を撤廃するという日本的慣行を超えた人事制度改革は、挑戦と自律を促す文化を育む大胆な試みである。
一方で、ロシュ社への高依存という収益構造の課題、国内薬価改定による収益圧迫、グローバル市場での新薬開発競争の激化など、直面するリスクも少なくない。中外製薬がこれらの課題をいかに克服し、研究開発成果を持続的な成長へとつなげられるかが、今後の成否を決定づける。本稿では、財務、研究開発、DX、人事改革、ESG、事業環境といった多角的な観点から中外製薬の最新戦略を徹底分析し、その将来展望を描き出す。
中外製薬を導く羅針盤「TOP I 2030」の全貌と進捗

中外製薬が2021年に策定した「TOP I 2030」は、単なる中期経営計画ではなく、10年先を見据えた包括的な変革戦略である。この戦略は、前計画「IBI 21」が目標を2年前倒しで達成した成功体験を踏まえ、さらに野心的な目標を掲げてスタートした。ビジョンは「世界最高水準の創薬の実現」と「先進的事業モデルの構築」という二本柱で構成され、日本国内にとどまらず、世界的なトップイノベーターを目指す方向性を明確に示している。
特に注目すべきは、この戦略が外部環境の変化に対する受動的な対応ではなく、能動的な価値創造を志向している点である。日本の医薬品市場は薬価抑制や少子高齢化による成長鈍化という逆風に直面している。だが中外製薬は守りに回るのではなく、むしろ攻めの姿勢を取り、アンメットメディカルニーズに応える新たな治療法を次々と市場に送り出す体制を築こうとしている。
この戦略の実行を支えるのが「5つの改革」である。創薬改革、開発改革、製薬改革、Value Delivery改革、成長基盤改革という五つの領域が相互に作用し合い、エコシステムを形成している点に特徴がある。例えば、中分子創薬のような高度な技術は製造難易度が高く、それを実用化するにはスマートファクトリー化を推進する製薬改革が不可欠である。さらに、得られた革新的な医薬品を医療現場に適切に届けるには、リアルとデジタルを融合させた新たな情報提供モデルが求められる。こうした一連の連鎖が企業全体の変革を加速させている。
2025年時点での進捗を見ると、特に創薬と開発の分野で大胆な判断が実行されている。科学的根拠に基づく厳格なGo/No-Go判断の徹底は、2025年7月に早期開発5品目を一括中止する決断に表れている。これは一見すると後退のように見えるが、実際には資源を真に革新的なプロジェクトに集中させるための合理的な戦略的撤退である。これにより、同社は高い成功確率を持つプロジェクトに経営資源を投下できるようになり、成果の最大化を狙う体制を整えている。
<strong>「TOP I 2030」の最大の特徴は、全体最適を意識した改革の連動性にある</strong>。一つの改革が次の改革を加速させる仕組みを内包しており、それが中外製薬の競争力を飛躍的に高めているのである。このビジョンが実現すれば、中外製薬は単なる日本企業の枠を超え、世界の製薬業界で独自の存在感を放つことになるだろう。
財務分析:ロシュ依存と自立への道筋
中外製薬の2025年上半期(1〜6月)の業績は、売上収益5,785億円、Core営業利益2,720億円と前年同期比でそれぞれ4.6%増、3.5%増を記録し、堅調な成長を示した。特に海外製商品売上が2,881億円と前年同期比7.3%増となり、業績を力強く牽引している。一方、国内製商品売上は2,197億円と横ばいに近く、薬価改定や後発医薬品の影響を受けて成長余地が限定されている。
以下の数値は2025年上半期実績をまとめたものである。
| 項目 | 2025年上半期 | 2024年上半期 | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5,785億円 | 5,530億円 | +4.6% |
| Core営業利益 | 2,720億円 | 2,628億円 | +3.5% |
| Core当期利益 | 1,935億円 | 1,895億円 | +2.1% |
| 国内製商品売上 | 2,197億円 | 2,178億円 | +0.9% |
| 海外製商品売上 | 2,881億円 | 2,684億円 | +7.3% |
| 研究開発費 | 832億円 | 823億円 | +1.1% |
この業績の構造を分析すると、ロシュ社向け輸出の寄与度が極めて高いことが浮き彫りになる。血友病治療薬「ヘムライブラ」や関節リウマチ治療薬「アクテムラ」が輸出の柱となり、円安効果も相まって大きな収益源となっている。しかし、裏を返せば収益の大部分がロシュ社への依存に偏っている状況であり、これが「ロシュ・アライアンスのジレンマ」と呼べる課題を生んでいる。
<strong>安定とリスクは表裏一体である</strong>。ロシュ社との強力な提携は短期的な財務安定を保証する一方で、依存度が高まりすぎれば中長期的には自立性を損なう危険性がある。国内市場が薬価制度の厳しさで伸び悩む中、同社はこの「助走期間」を活かし、自社創製のグローバル品を育成する必要がある。
その一環として、2025年7月には800億円を投じて東京都北区浮間事業所に新研究棟「UKX」の建設を決定した。これは製薬改革の一環であり、製法開発の強化と環境配慮を両立する施設として期待される。利益を短期的に追求するのではなく、長期的な競争力の源泉となる研究基盤への投資を進める姿勢は、将来の自立を見据えた戦略である。
株式市場の評価もおおむね好意的であり、2025年9月時点の株価は6,699円と堅調に推移している。アナリスト予想では目標株価を8,100円台に設定する見方もあり、R&Dパイプラインの将来性が市場の期待を支えている。中外製薬がこの期待に応え、ロシュ依存からの脱却を果たせるかが、今後の企業価値を決定する最大の分岐点となる。
研究開発パイプライン徹底解剖:革新的新薬への挑戦
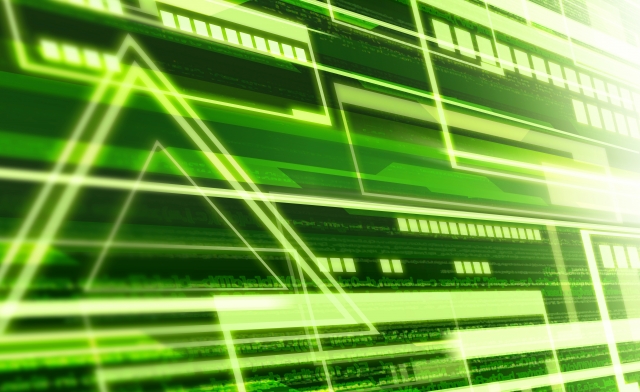
中外製薬の持続的成長の生命線は研究開発パイプラインにある。2025年7月時点で同社はがん、免疫疾患、血液疾患、神経疾患、眼科など、多岐にわたる領域で開発を進めており、いずれもアンメットメディカルニーズの高い分野に焦点を当てている点が特徴である。
近年の成果として、デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対する遺伝子治療薬「エレビジス」、発作性夜間ヘモグロビン尿症に対する初の皮下投与薬「ピアスカイ」が承認を取得した。これらは従来の治療法では不十分だった患者に新たな選択肢を提供するものであり、中外製薬の高い創薬能力を象徴する存在である。
現在進行中の注目プロジェクトを整理すると以下のようになる。
| プロジェクト | 対象疾患 | 開発段階 | モダリティ | 注目点 |
|---|---|---|---|---|
| AUBE00 | 固形がん | 第I相 | 中分子 | KRAS遺伝子変異がんへの画期的新薬候補 |
| NXT007 | 血友病A | 第I/II相 | – | 正常レベルの凝固能回復を目指す次世代薬 |
| GYM329 | フォン・ヴィレブランド病 | 第III相 | 抗体 | 新規作用機序でQOL向上に寄与 |
| エレビジス | デュシェンヌ型筋ジストロフィー | 承認済 | 遺伝子治療 | 根本原因にアプローチする革新性 |
| ピアスカイ | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 承認済 | 抗体 | 高い利便性を誇る皮下投与製剤 |
これらの開発は、従来困難とされた治療領域に踏み込み、既存薬では対応できない患者層に治療を提供することを目的としている。特に、KRAS変異がんは従来「ドラッガブルではない標的」とされてきたが、AUBE00はその壁を突破する可能性を秘めている。
専門家の間でも「中外製薬は単なるパイプラインの数ではなく、質で勝負している」という評価が強い。創薬の成功確率は3万分の1とも言われるが、その中でリスクを取って革新的モダリティに挑む姿勢は、世界市場での差別化に直結する。今後、これらのプロジェクトが上市に結びつくかどうかが、中外製薬がグローバル製薬大手と伍して戦うための試金石となるだろう。
戦略的撤退が示す成熟したR&Dマネジメント
2025年7月、中外製薬は早期開発段階にあった14プロジェクトのうち5品目の自社開発を一括中止すると発表した。この決断は一見すると失敗や後退と受け止められかねないが、実際には研究開発戦略の成熟を示す重要なシグナルである。
奥田修社長CEOはこの判断について「競合状況を勘案し、開発の優先順位を付けた結果」と説明している。つまり、成功確率が低い、あるいは差別化が難しいプロジェクトに固執するのではなく、経営資源を有望な案件に集中させるための合理的な撤退である。このような資源配分の徹底こそ、長期的にイノベーションを実現するための必須条件である。
具体的には、競合他社に先行されていた固形がん領域の一部プロジェクトなどが対象となった。その一方で、AUBE00やNXT007といった革新性の高いパイプラインには資金・人材・時間を厚く投下している。この動きは「TOP I 2030」で掲げる「適切・迅速なGo/No-Go判断」の実践例であり、スローガンにとどまらない実効性を裏付けている。
R&Dの効率性を高めるには、勇気ある撤退が不可欠である。米国大手製薬企業でも、パイプラインの3割程度を常時見直し、成功確率が低い案件から撤退するのは一般的である。中外製薬の今回の決断も、国際的な標準に沿ったリスクマネジメントの一環と位置づけられる。
<strong>重要なのは「失敗を避ける」のではなく、「成功確率を最大化する」ことにある</strong>。限られた資源を革新的でインパクトの大きい領域に集中させることで、最終的には企業全体の競争力が高まる。この戦略的撤退の姿勢は、研究開発における経営規律の高さを示すものであり、将来の成長に直結する合理的な判断である。
DX戦略の核心:AI創薬とソフトバンク協業の衝撃

中外製薬は「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」を掲げ、デジタル変革を全社戦略の中核に位置づけている。その目的は単なる業務効率化ではなく、創薬から開発、販売に至るまでのバリューチェーンを革新し、新薬開発の成功確率とスピードを飛躍的に高めることにある。
注目すべき取り組みの一つが、独自のAI技術「MALEXA」による抗体創薬支援である。従来は研究者の経験や勘に頼っていた抗体設計を、機械学習によりデータ駆動型へと変革することで、候補物質の創出効率を大幅に向上させている。この技術は既に複数のプロジェクトで活用され、研究の初期段階における時間短縮と成功率向上に寄与している。
さらに同社はリアルワールドデータ(RWD)の活用にも積極的である。電子カルテやレセプト情報を統合的に分析することで、臨床試験の効率化や市販後調査に役立てている。これにより、医薬品の真の価値を実臨床で証明できる仕組みを構築しつつある。
そして2025年1月、ソフトバンクおよびSB Intuitionsとの間で、生成AIを活用した共同研究の基本合意を締結した。臨床開発業務は膨大な文書作成やデータ解析を伴うが、AIエージェントや大規模言語モデルを導入することで、これらの作業を劇的に効率化できる可能性がある。この取り組みは単なるツール導入ではなく、製薬業界特有の高度に専門的なデータに最適化された垂直統合型AIを構築する点で独自性が高い。
専門家の間では「この協業が実現すれば、開発期間を数年単位で短縮し、治験成功率を向上させる可能性がある」との評価が出ている。中外製薬は自社の長年の臨床データを、ソフトバンクの計算基盤と融合させることで、他社が模倣しにくい競争優位性を築こうとしている。
強固なAI基盤とRWD活用を両輪とするDX戦略は、単なるコスト削減ではなく、創薬のゲームチェンジャーとなる可能性を秘めている。これが実用化されれば、中外製薬はグローバル製薬業界で際立った存在となるだろう。
人的資本経営への転換:ジョブ型人事と文化革命
中外製薬のもう一つの大きな変革が、2025年1月から本格導入された新人事制度である。従来の年功序列や会社主導の異動に依存する仕組みを改め、社員が自らキャリアを選択する「ポスティング制」を全社員に展開した点に革新性がある。さらに2026年には雇用上限年齢を撤廃し、能力と意欲次第で誰もが活躍し続けられる環境を整備する予定である。
新制度導入の狙いは、社員一人ひとりの主体性を引き出し、挑戦を促すことでイノベーションを加速させることにある。奥田修社長は「主体性の連鎖が新しい発想を生む」と語り、この改革を単なる制度変更ではなく文化変革の一環と位置づけている。
導入から半年の成果も顕著である。2025年上半期には全社員の約2割がポスティングに応募し、異動者の約7割が制度を利用した。管理職の間でも部下を自ら選ぶ意識改革が進み、モチベーションや組織活性化につながっている。数字だけでは見えない効果として、社員のキャリア形成に対する意識が大きく変化している点が注目される。
加えて、この制度はダイバーシティ推進にも寄与している。女性マネジャー比率は17.6%、男性の育児休業取得率は98.2%と、国内でもトップレベルの水準を達成しており、多様な人材が活躍できる基盤が整いつつある。
まとめると、この改革には以下の特徴がある。
- 年齢や社歴に依存しないジョブ型人事制度
- 社員主導のキャリア形成を可能にするポスティング制
- 雇用上限年齢の撤廃による長期的なキャリア支援
- 多様な人材の活躍を促進するDE&Iとの連動
<strong>この人事改革は企業文化のOSを入れ替える「文化革命」である</strong>。世界のトップイノベーターと伍するためには、世界標準の人材マネジメントが不可欠であり、中外製薬はその実現に踏み出したといえる。挑戦を恐れず自律的に行動する社員が増えれば、組織は持続的にイノベーションを生み出すエコシステムへと進化するだろう。
ESG戦略と社会的価値創造:持続可能な成長の基盤

中外製薬は経済的価値の追求にとどまらず、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の三要素を重視した経営を成長戦略の中心に据えている。これは法令遵守やリスク管理の枠を超え、イノベーションを促進し、企業価値を長期的に高める「攻めのESG経営」として位置づけられている点に特徴がある。
外部評価も高く、日本の公的年金を運用するGPIFが採用する国内6つすべてのESG指数に選定されており、また国際的な評価指標である「DJSI World」にも継続的に選出されている。これにより、同社の取り組みが国内外で認められていることがわかる。
環境分野では「中期環境目標2030」を掲げ、全事業所で再生可能エネルギー由来の電力を100%導入済みである。さらに新研究棟「UKX」においてはCO2削減やフロン使用削減を前提とした設計が導入されており、製造プロセス全体での環境負荷軽減を実現している。
社会分野では「患者中心」を経営理念に掲げ、研究開発や販売活動のすべてに反映している。また、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)の推進にも注力し、女性マネジャー比率は17.6%、男性育児休業取得率は98.2%と国内製薬企業の中でも高水準にある。これにより、多様な人材の視点を経営に取り込み、イノベーションの基盤を広げている。
ガバナンスにおいても、IR活動の充実により「ディスクロージャー優良企業」に選ばれるなど、投資家や市場からの信頼を確立している。経営の透明性を重視する姿勢は、長期的な企業価値の維持に直結する。
<strong>中外製薬のESG戦略は、単なる社会貢献ではなく、持続的成長を支える経営の中核に位置づけられている</strong>。環境対応によるコスト削減、多様な人材の活躍によるイノベーション創出、透明性の高いガバナンスによる市場からの信頼。この三位一体の取り組みこそが、同社を次世代のトップイノベーターへと押し上げる原動力となっている。
国内外の事業環境と競合分析:規制改革が迫る選択
中外製薬を取り巻く事業環境は、国内外で大きな変化を迎えている。特に国内市場では、超高齢化社会の進展に伴い医療費抑制圧力が強まっている。2025年は団塊の世代がすべて75歳以上となる節目であり、薬価制度の毎年改定によって製薬企業の収益性はますます厳しくなっている。
2025年6月に閣議決定された「骨太方針2025」は、ジェネリック医薬品やバイオシミラーの使用促進と同時に、創薬力の強化とイノベーションの適切な評価を強調している。つまり、製薬企業は低価格医薬品に依存するのではなく、高付加価値かつ科学的に有効性が証明された新薬に資源を集中することが求められている。中外製薬の研究開発集中戦略は、この政策の方向性と合致している。
業界全体を見渡すと、新薬開発には数千億円の投資が必要とされ、その成功確率は3万分の1とも言われる。リスクが極めて高い領域であるがゆえに、オープンイノベーションの重要性が増している。実際、大学やバイオベンチャーとの連携、M&Aを通じた技術獲得が加速しており、中外製薬も同様に外部知見を積極的に取り込んでいる。
競合環境も激化している。武田薬品工業は大型買収により確立したグローバル基盤を強みに成長を維持しており、第一三共はADC(抗体薬物複合体)を核にがん領域で急成長を遂げている。これに対し中外製薬は、独自の抗体エンジニアリング技術や中分子創薬、そしてロシュ社との強固なアライアンスというユニークな優位性を活かし、競争力を発揮している。
<strong>国内市場の規制強化とグローバル競争の激化という二重の圧力の中で、企業は「低価格競争」か「高付加価値創薬」かの選択を迫られている</strong>。中外製薬は後者を選び、リスクを取ってでも革新的な新薬開発に挑む道を進んでいる。この戦略が実を結ぶかどうかは、今後数年の研究開発成果と市場投入の成否にかかっている。
成功の条件:トップイノベーターに不可欠な二つの要素

中外製薬が掲げる「世界のトップイノベーター」というビジョンは、単なるスローガンではなく、極めて具体的な条件を満たさなければ実現できない目標である。その条件は大きく二つに集約される。第一は、研究開発から確実に成果を生み出すことであり、第二は、DXと人事制度改革を通じて組織能力を高め、持続的にイノベーションを生み出す仕組みを構築することである。
研究開発の観点では、「NXT007」や「AUBE00」といった次世代の有力候補品を計画通りに上市できるかが試金石となる。特にAUBE00は、KRAS遺伝子変異がんという従来治療が困難であった領域をターゲットとしており、成功すれば世界的なブロックバスターとなる可能性を秘めている。一方で、研究開発の成功確率は極めて低く、巨額の投資を要するため、経営資源の集中と撤退判断のバランスが問われる。早期開発プロジェクト5品目の一括中止という決断は、この戦略的柔軟性を示す好例である。
次に組織能力の強化である。中外製薬はDXと人事制度改革を両輪として、組織全体のパフォーマンスを高めようとしている。DXにおいてはソフトバンクとの協業により、臨床開発に特化した生成AIプラットフォームを構築中である。この仕組みが完成すれば、治験の効率化と成功確率向上に直結し、業界の競争ルールを変える可能性がある。さらにAI創薬支援技術「MALEXA」やリアルワールドデータの活用は、創薬から市販後に至るまでの一連のプロセスを高度化している。
一方の人事改革は、社員が自律的にキャリアを形成できるポスティング制度や、雇用上限年齢の撤廃など、従来の日本型雇用慣行を覆す内容である。すでに全社員の約2割がポスティングに応募し、組織の活性化が数字として表れている。これは単なる人事制度の変更ではなく、挑戦と自律を促す文化変革の始まりである。
これら二つの条件を満たせるかどうかが、中外製薬が真に世界的なトップイノベーターとして認められるかを決定づける。研究開発の成果は市場での競争力を生み出し、組織能力の進化はそれを継続的に生み出す力となる。両者の相乗効果を発揮できるかが、未来を切り拓く最大の鍵である。
<strong>トップイノベーターの称号は、単に革新的な薬を生み出すことではなく、それを継続的に生み出し続ける仕組みを持つ企業に与えられる</strong>。中外製薬はその条件を満たすための挑戦を続けており、今後数年がその真価を問われる決定的な期間となるだろう。

