東京エレクトロン(TEL)は、世界の半導体製造装置市場における圧倒的な存在感を誇る企業である。2025年3月期には売上高2兆4,315億円を記録し、AIや高帯域幅メモリ(HBM)を中心とした旺盛な需要を背景に過去最高の業績を達成した。しかし、2026年3月期第1四半期には減収減益へと転じ、市場の急速な変調が鮮明になった。特に中国向け売上が全体の42%を占めるという突出した依存度は、TELにとって最大の成長機会である一方、米中対立による輸出規制強化という重大なリスクを内包している。
同社が掲げる中期経営計画は、2027年3月期までに売上高3兆円、営業利益率35%、ROE30%以上を実現するという野心的なものであり、その実現には5年間で1.5兆円超の研究開発投資を行う計画だ。リソグラフィ用コータ/デベロッパ市場で89%という世界シェアを握る技術的優位性と、2万件を超える特許群が強固な競争の壁を形成しているが、その一方で地政学的リスクが経営の不確実性を高めている。AI革命という巨大な追い風を受けつつも、荒波を航海するTELの戦略実行力が、今後の企業価値を左右する決定的な要素となる。
東京エレクトロンの現状と戦略的岐路

東京エレクトロン(以下、TEL)は2025年3月期において売上高2兆4,315億円を記録し、過去最高業績を達成した。生成AIの普及を背景に広帯域幅メモリ(HBM)や先端ロジック半導体への投資が急拡大し、それが業績を大きく押し上げた結果である。しかし、2026年3月期の第1四半期には減収減益に転じ、市場は調整局面に入った。TELはまさに「成長の追い風」と「地政学リスク」という二つの大きな力の狭間に立たされている。
特に注目されるのが中国市場依存度の高さである。2025年3月期の売上の約42%が中国向けであり、これは同業他社を大きく上回る水準である。この構造はTELに大きな成長機会をもたらすと同時に、米国による輸出規制強化という重大なリスクをも内包する。米中関係の行方がTELの将来を大きく左右する要因であることは間違いない。
TELは同時に、2027年3月期までに売上高3兆円を目指す中期経営計画を掲げている。この目標達成には5年間で1.5兆円を超える研究開発投資が予定されており、技術的優位性の維持と拡大を最優先課題としている。AIや自動運転といったメガトレンドが半導体需要を押し上げる中で、この戦略が功を奏すか否かが同社の未来を決定づける。
表に示すように、TELは記録的な業績と調整局面を短期間で経験し、その不安定さこそが戦略的岐路を象徴している。
| 指標 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期Q1 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.83兆円 | 2.43兆円 | 5,495億円(▲1.0% YoY) |
| 営業利益 | 4,553億円 | 6,973億円 | 1,446億円(▲12.7% YoY) |
| ROE | 21.8% | 30.3% | ー |
このように、TELはAI革命を追い風に飛躍する力を持ちながらも、地政学リスクによる急激な揺れ動きに直面している。その舵取りが、次の成長ステージを決定づける最大の課題である。
中期経営計画:3兆円企業への挑戦と投資戦略
TELの中期経営計画は、2027年3月期に売上高3兆円、営業利益率35%、ROE30%以上という極めて野心的な目標を掲げている。これは2025年3月期実績からさらに24%以上の成長を求められる水準であり、収益性の抜本的な改善を意味する。単なる拡大ではなく、高付加価値製品の比率を高め、事業ポートフォリオの最適化を進める必要がある。
その実現を支えるのが研究開発と設備投資である。同社は今後5年間で1.5兆円超の研究開発投資と7,000億円超の設備投資を行う計画を打ち出した。宮城の「技術革新センター」や九州の新開発棟は、2nm世代以降のGAAトランジスタやBSPDNといった新技術に対応する最前線の拠点となる。これにより、次世代半導体に不可欠な装置の供給を確保し、顧客企業との関係を一層強化することが狙いである。
投資の意義は単なる技術開発にとどまらない。TELは顧客の研究段階から深く関与する「Shift Left」戦略を採用し、課題解決を共同で進めることで、自社装置を量産プロセスの必須インフラとして位置づける。この戦略は顧客のロックイン効果を高め、長期的な安定収益につながる。
また、資本政策の側面でも配当性向50%を目安とした還元方針を掲げ、株主への利益還元と成長投資のバランスを取っている。自己株式取得も機動的に実施しており、投資家に対する信頼を確保している。
箇条書きで整理すると、TELの中期計画の特徴は以下の通りである。
- 売上高3兆円、営業利益率35%以上、ROE30%以上という高い財務目標
- 研究開発投資1.5兆円超、設備投資7,000億円超の大型投資計画
- Shift Left戦略による顧客研究段階からの関与強化
- 配当性向50%、自己株式取得による株主還元方針
TELはAIやIoT、自動運転といったメガトレンドを追い風に、次世代半導体製造における覇権を確立しようとしている。壮大な目標を掲げる同社に求められるのは、戦略を計画通りに実行する能力であり、その成否が2027年以降の成長軌道を決定づける。
業績の山と谷:2025年度の好調と2026年度の調整局面
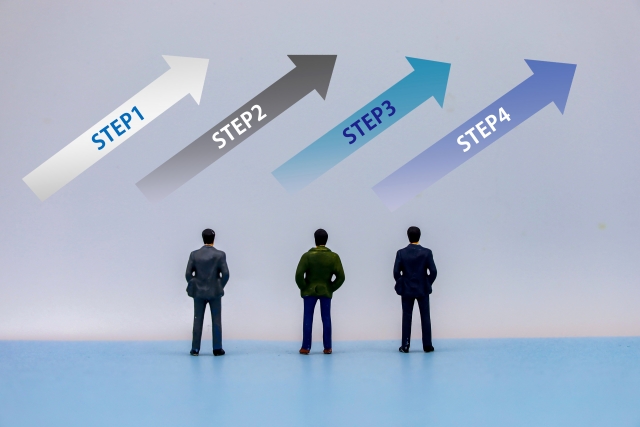
東京エレクトロン(TEL)の業績は、半導体市場のサイクルを映し出す鏡のようである。2025年3月期には売上高2兆4,315億円、営業利益6,973億円、ROE30.3%という過去最高水準を記録した。AIやクラウド需要を背景にDRAMやロジック向け設備投資が急増し、特にHBM(広帯域幅メモリ)の拡大が大きな成長をけん引した。まさに歴史的な快進撃であった。
しかし、2026年3月期第1四半期には売上高5,495億円、営業利益1,446億円と前年同期比で減収減益となり、市場は急速な調整局面を迎えた。減益幅は営業利益で12.7%に達し、研究開発費の増加と中国の成熟ノード向け投資の一服が要因として挙げられる。この展開はTEL自身が示していた「上期は減収減益、下期から回復」というシナリオと一致しており、必ずしも想定外ではなかった。
財務データの推移を整理すると以下のようになる。
| 期 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2兆4,315億円 | 6,973億円 | 28.7% |
| 2026年3月期Q1 | 5,495億円 | 1,446億円 | 26.3% |
この数字が示すのは、TELの収益が外部環境に大きく左右される一方で、高い収益率を維持できる競争力を備えているという二面性である。AIや自動運転の普及によって長期的な需要は強固であるが、短期的には地域やアプリケーションごとの需要変動が収益に直結する。
特にHBM需要が急伸したDRAM分野では全売上の31%を占めるまでに拡大したが、ロジック/ファウンドリ分野では中国の成熟ノード投資が鈍化し、成長の足かせとなった。TELの事業構造はまさに「山と谷」を同時に抱え込むものであり、これをどう平準化していくかが今後の課題である。
中国依存度42%がもたらす機会とリスク
TELを語る上で避けて通れないのが中国市場への依存度である。2025年3月期における中国向け売上比率は約42%に達し、同業他社であるアドバンテストの約22%、NVIDIAの約13%と比較しても突出して高い。この数字は巨大市場としての魅力と同時に、米中対立というリスクの影を色濃く映し出している。
中国市場はTELの成長を強力にけん引してきた。2024年から2025年にかけては、米国の輸出規制強化を見越した「駆け込み需要」や「戦略的在庫積み増し」が急増し、記録的な売上の源泉となった。しかし、この前倒し需要が2026年3月期に一服し、業績の減速を引き起こしたのである。
地域別売上構成を見ると、TELのリスクと機会が明確に浮かび上がる。
| 地域 | 売上比率(2025年3月期) |
|---|---|
| 中国 | 約42% |
| 韓国 | 22.4% |
| 台湾 | 20.7% |
| その他 | 約14.9% |
この構造は「ハイリスク・ハイリターン」の典型である。中国市場におけるプレゼンスの高さは長期的なシェア獲得に有利である一方、米国の規制や中国国内政策による変動リスクは極めて大きい。特に、米国が先端半導体製造装置の輸出制限を段階的に強化する中で、日本企業であるTELも例外ではなく、今後さらに規制の影響を受ける可能性が高い。
投資家やアナリストが注視するのもこの点であり、TELの株価は中国関連のニュースに敏感に反応している。つまり、中国依存はTELにとって最大の成長エンジンでありながら、最大のリスクファクターでもある。この「中国の方程式」をどう解くかが、同社の未来を左右する最大の試金石となる。
技術的優位性と知財ポートフォリオの強固な壁

東京エレクトロン(TEL)の競争力の根幹を成すのは、長年にわたり蓄積された技術的優位性と、それを支える圧倒的な知的財産ポートフォリオである。リソグラフィ工程に不可欠なコータ/デベロッパにおいて世界シェア89%を誇り、この独占的地位は先端半導体の製造においてTELを不可欠な存在にしている。装置の選択肢が限られる顧客にとって、TEL製品は事実上の標準インフラとなっている。
特に注目すべきは、成膜、エッチング、洗浄といった複数の重要工程をカバーする広範なポートフォリオである。この統合力により、顧客はプロセス全体を最適化するソリューションを一括して導入できる。技術的課題の早期解決と工程間の整合性確保は、半導体の微細化や高積層化が進む現代において極めて重要である。
また、知財の厚みは競合他社の参入障壁を高める。2024年3月末時点でTELが保有する有効特許は23,249件に達し、これは業界最大規模である。2025年に入ってからもプラズマ処理や基板接合、EUV関連技術などで新規特許を次々と取得し続けており、研究開発活動の活発さを裏付けている。さらに、Clarivateが選出する「Top 100 Global Innovators」に名を連ねるなど、外部からの評価も高い。
箇条書きで整理すると、TELの優位性は以下の3点に集約される。
- コータ/デベロッパでの圧倒的シェア(世界89%)
- 成膜・エッチング・洗浄を含む工程全体をカバーする広範なポートフォリオ
- 2万件超の特許に裏打ちされた知財力と外部評価の高さ
この「情報と技術革新の好循環」によって、TELは顧客の研究開発段階から課題解決に深く関与できる。得られた知見は他部門の技術開発にフィードバックされ、競争優位が自己強化される構造を形成しているのである。
競合環境とグローバル市場におけるポジション
TELの戦略を評価するには、グローバルな競合環境と市場動向を理解する必要がある。半導体製造装置(SPE)市場は、ASML(オランダ)、Applied Materials(米国)、Lam Research(米国)、そしてTELが主要プレーヤーとして寡占する構造となっている。ASMLが露光装置で独占的地位を築く一方、TELはプロセス装置でApplied MaterialsやLam Researchと激しく競い合っている。
世界の半導体市場規模は2025年に7,009億ドルを突破し、2年連続の2桁成長が見込まれている。それに伴い、SPE市場も2025年には1,255億〜1,330億ドル規模に拡大すると予測されており、TELにとって強力な追い風が吹いている。特にAI関連需要はDRAMやロジック向け投資を押し上げ、TELの主力装置に対する需要を長期的に支える。
直近の業績を比較すると、TELは売上高2兆4,315億円、Applied Materialsは約292億ドル、Lam Researchは184億ドル規模であり、成長率ではTELが32.8%と他社を上回った。営業利益率ではApplied Materialsが30.7%と優位に立つが、TELも投資拡大期にあることを考慮すれば十分に競争力を示している。
競合3社の比較を整理すると以下の通りである。
| 企業 | 売上高(直近期) | 成長率(YoY) | 主力分野 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 2兆4,315億円 | +32.8% | コータ/デベロッパ、エッチング |
| Applied Materials | 約292億ドル | +8% | 成膜、エッチング |
| Lam Research | 184億ドル | +24% | エッチング、成膜 |
このデータから分かるように、TELは売上成長率で競合を上回り、技術力と投資規模の両面で存在感を高めている。一方で、利益率の改善は今後の課題であり、研究開発投資を収益に結びつける実行力が問われる局面にある。
AI革命がもたらす半導体需要の拡大は、SPE業界全体に成長の機会を提供している。TELはその中心で競合としのぎを削りつつ、独自の強みを武器にグローバル市場での存在感をさらに拡大しようとしている。
米中対立と国家戦略がもたらす地政学リスク

東京エレクトロン(TEL)の最大の外部リスクは、米中対立を背景とした輸出規制強化にある。米国はCHIPS and Science Actを通じて520億ドル以上の補助金を投じ、国内半導体製造能力の拡大を進める一方、中国への先端半導体製造装置の輸出を段階的に制限している。この動きは、安全保障と経済覇権の両面から進められており、世界の半導体サプライチェーンを地政学的な駆け引きの舞台へと変貌させている。
TELは日本企業であるが、その装置には米国製の部品や技術が含まれるため、米国の規制対象に組み込まれる可能性が高い。売上高の42%を中国に依存する同社にとって、米国の政策変更は事業基盤を根底から揺るがす脅威である。さらに、中国市場では規制強化を見越した「駆け込み需要」が一時的に業績を押し上げたが、その反動として2026年3月期第1四半期には投資の一服感が鮮明になった。
地政学リスクの構造を整理すると以下のようになる。
| 要素 | 内容 | TELへの影響 |
|---|---|---|
| 米国政策 | CHIPS法による補助金、輸出規制強化 | 中国依存度が高いため規制影響大 |
| 中国政策 | 自給率向上戦略、在庫積み増し | 駆け込み需要による一時的業績押上 |
| 日本政策 | Rapidus・TSMC熊本への巨額補助金 | 国内市場での新たな商機創出 |
TELに求められるのは、中国市場依存を戦略的に緩和しつつ、新興市場や国内外の補助金政策を成長機会として取り込む柔軟性である。米国大統領選挙など政治イベントの行方もリスク要因となるため、不確実性は高いが、地政学を単なるリスクではなく成長戦略の文脈に組み込む姿勢が鍵を握る。
ESG経営と持続可能性への取り組み
TELは技術力や市場シェアだけでなく、ESG(環境・社会・ガバナンス)経営においても先進的な姿勢を示している。同社は「E-COMPASS」という独自イニシアチブを掲げ、サステナビリティ委員会を設置するなど全社的な推進体制を整備している。これにより、ESGを単なるCSR活動ではなく、企業戦略の中心に据えている点が特徴的である。
特に環境分野での取り組みは野心的である。2050年としていたネットゼロ目標を2040年に前倒しし、2031年3月期までにスコープ1・2排出量を2019年比で85%削減する計画を打ち出した。また、使用電力を100%再生可能エネルギー由来とする方針を掲げ、サプライチェーン全体での環境負荷低減を進めている。
TELのサステナビリティ戦略の要点は以下の通りである。
- 2040年までのネットゼロ達成目標
- 2031年までにスコープ1・2排出量を85%削減
- 再生可能エネルギー由来電力の100%化
- ERM(エンタープライズリスクマネジメント)への気候リスク統合
気候変動リスクをERMに統合している点は特筆に値する。台風や洪水によるサプライチェーン寸断といった物理的リスクと、炭素税導入による移行リスクを同時に分析し、具体的な対応策をBCP(事業継続計画)や省エネ技術開発に落とし込んでいる。この取り組みはESGをコスト要因としてではなく、事業レジリエンスを高める投資と位置づけている証左である。
投資家にとっても、ESGに基づく透明性の高い経営は長期的な信頼性を担保する。TELの取り組みは、国際的な投資資金の流れを取り込み、持続可能な成長と企業価値向上を両立させる重要な戦略となっている。
2026年に向けた主要課題と成長シナリオ

東京エレクトロン(TEL)は、AI革命の追い風を受けて中長期的な成長ポテンシャルを備えている一方、2026年に向けて複数の重要課題を克服しなければならない局面にある。業績回復への期待は高いが、その道筋は単純ではなく、外部環境と内部の戦略実行力の双方に左右される。
まず最も大きなテーマは「売上高3兆円への道筋」である。HBMやGAAトランジスタ、先進パッケージングといった次世代技術の需要は構造的に拡大しており、TELが強みを持つ分野と重なる。特にDRAMやロジックの先端投資は今後も続く見通しであり、TELの多様な製品ポートフォリオは需要を幅広く取り込む可能性を持つ。しかし、この需要を確実に売上に転換するには、研究開発投資と製造拠点の立ち上げを計画通り遂行する実行力が不可欠である。
次に注目されるのが「地政学リスクの克服」である。売上の42%を占める中国依存をいかに調整し、他地域への分散を進めるかが課題となる。米国による輸出規制強化は今後も続く可能性が高く、規制に適応しながら市場シェアを維持する戦略が求められる。韓国や台湾の半導体メーカーとの連携強化、日本国内でのRapidusやTSMC熊本工場向けの装置供給は、依存度を是正する有力な選択肢である。
さらに「投資計画の実行性」も重要である。TELは2025年から5年間で1.5兆円超の研究開発投資と7,000億円超の設備投資を計画している。宮城や九州の新拠点が予定通り稼働し、2nm世代以降の技術に対応する装置をタイムリーに市場投入できるかどうかが、競争優位の持続を左右する。少しでも遅れが生じれば、競合にシェアを奪われるリスクがある。
最後に「投資家との信頼関係維持」も欠かせない。配当性向50%を目安に安定した株主還元を続けつつ、巨額投資を正当化するだけの成果を示さなければならない。特に2026年の下期以降に想定される業績回復が実現しなければ、市場からの信頼は揺らぎかねない。
箇条書きで整理すると、TELの2026年に向けた主要課題は以下の通りである。
- 売上高3兆円達成に向けた投資計画の遂行
- 中国依存度42%の戦略的是正
- 宮城・九州拠点を含む新開発プロジェクトの確実な立ち上げ
- 投資家への還元と成長のバランス確保
総じて、TELの未来は「実行力」と「リスクマネジメント」にかかっている。AI革命がもたらす需要拡大は確かに追い風であるが、その風を帆に受けて進むためには、外部環境に翻弄されない強靭な戦略遂行力が求められる。2026年はその真価が試される年になるだろう。

