東京海上ホールディングスは今、かつてない大転換期を迎えている。長年の信頼を揺るがしたガバナンス不全を契機に、監督当局からの厳しい視線にさらされる一方で、従来の保険ビジネスの枠を超えた成長モデルを模索しているからである。同社は新中期経営計画「Re-New 2026」を掲げ、補償中心の事後対応型モデルから、リスク予防やウェルビーイングにまで踏み込む「保険+α」戦略へと舵を切った。
その具体策として、防災・レジリエンス分野を担うID&Eホールディングスの子会社化、AIやSalesforceを活用した顧客体験の高度化、さらには政策保有株式の全廃という歴史的決断を下した。これらは単なる改善ではなく、企業アイデンティティを「保険会社」から「総合リスクソリューション企業」へ転換する試みである。
加えて、北米スペシャルティ保険事業の高収益性や新興国市場への布石など、グローバル戦略も一段と鮮明化している。2025年3月期決算では経常収益8兆円超を記録し、直近四半期では前年比113%増の経常利益を叩き出すなど、業績も追い風にある。一方で、文化変革の定着やガバナンス改革の実効性、マクロ経済リスクといった課題も山積しており、変革の道のりは決して容易ではない。
本稿では、東京海上HDの変革の全貌を、戦略・財務・グローバル展開・ガバナンス改革・競合比較の観点から多角的に分析する。そこから浮かび上がるのは、日本発グローバル保険グループが次なる時代のリーダーとなれるかを占う試金石である。
東京海上HDの新中期経営計画「Re-New 2026」と「保険+α」戦略の核心
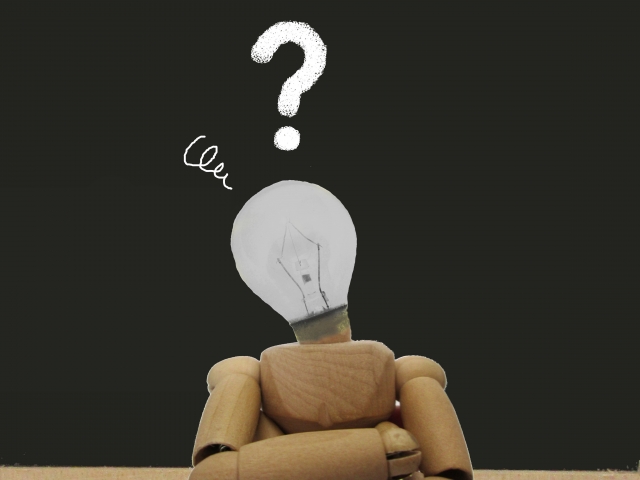
東京海上ホールディングスは、2024年度から始動した新中期経営計画「Re-New 2026」を通じて、従来型の保険会社から総合的なリスクソリューション企業へと転換を図っている。この計画の中心にあるのが「保険+α」という概念であり、単なる補償提供から一歩踏み込み、リスクの未然防止や生活の質向上までを含めた包括的な価値提供を目指すものである。
従来の損害保険事業は、事故や災害といった「事後」の対応を主軸としてきた。しかし、顧客ニーズや社会環境が大きく変化する中で、この枠組みでは差別化が困難になりつつある。そこで東京海上は「事故が起きる前」にリスクを減らすコンサルティングや、「平常時」におけるウェルビーイング支援といった領域に進出し、顧客との関係性を再定義しているのである。
特に注力分野として掲げられているのが、GX(グリーン・トランスフォーメーション)、ヘルスケア、中小企業支援(SME)、サイバーリスク、レジリエンスの5領域である。これらは環境問題や高齢化、デジタル化といった社会課題と直結しており、保険業界が新たな成長機会を見いだす余地が大きい分野とされる。たとえばサイバー保険市場は今後も年率2桁の成長が見込まれており、国内外の企業にとって急務のリスク対応となっている。
この戦略において重要な役割を果たすのが、2025年に完全子会社化したID&Eホールディングスである。同社の持つ防災・インフラコンサルティング能力と東京海上の保険引受力を組み合わせることで、災害予防から補償、復旧までを一気通貫でカバーできる体制が整う。これは「保険+レジリエンス」という新市場の創出に直結する試みであり、同社の変革を象徴する一手といえる。
さらに、競合との差別化の観点からも「保険+α」戦略は意義が大きい。従来の保険商品は価格競争に陥りやすく、収益性の維持が困難だった。しかし、防災コンサルやAIを駆使したリスク予測サービスなどは容易に模倣されにくく、独自の付加価値を生み出す。これにより、顧客は単なる契約者ではなく長期的なパートナーへと変化し、企業の持続的成長を支える基盤となる。
<strong>東京海上HDの「保険+α」戦略は、保険業界が直面するコモディティ化の壁を突破し、価値競争へとステージを移行させる挑戦である。</strong>それは単なる企業の戦略ではなく、社会の持続可能性を支える新しい金融モデルの試金石としての意味を帯びている。
EPS成長率・ROE改善に見る財務戦略と株主還元方針
「Re-New 2026」は理念面だけでなく、極めて野心的な財務目標を掲げている点でも注目される。東京海上HDは、修正EPS(1株当たり利益)を年率8%以上、政策株式の売却益を含めれば16%以上という世界トップクラスの成長を目標に定めた。さらに、2026年度までに修正ROEを14%以上(売却益込みで20%以上)に引き上げる方針を示しており、資本効率の向上を明確に打ち出している。
この強気の目標設定を可能にするのが、政策保有株式の大幅削減である。2024年3月末時点で3.5兆円に達していた株式を2026年度までに半減し、2029年度にはゼロにする計画を公表した。これはガバナンス不全の背景にあった「もたれ合い構造」を断ち切るとともに、巨額の資本を解放して成長投資と株主還元に振り向ける意図がある。
株主還元策としても、東京海上HDは明確なシグナルを発している。2024年度の配当金は前期比29%増の159円を予定し、2025年度は210円への増配を見込んでいる。加えて、自己株式取得の拡充も検討されており、資本循環のスピードを加速させている。これにより、変革期にあっても投資家の信頼を確保し、株価の安定と上昇を両立させる狙いがある。
表:東京海上HDの財務目標(2026年度まで)
| 指標 | 目標値 |
|---|---|
| EPS成長率(ベース) | 年率+8%以上 |
| EPS成長率(株式売却益込み) | 年率+16%以上 |
| 修正ROE | 14%以上 |
| 修正ROE(売却益込み) | 20%以上 |
| 2025年度配当予想 | 210円 |
こうした株主重視の姿勢は、国際的な投資家からも評価されている。大手格付機関は同社に対しAAA(JCR)、A+(S&P)、Aa3(ムーディーズ)といった高格付けを付与し、アナリストのコンセンサスも「買い」推奨が大半を占める。特に目標株価は6,700円台から一部証券会社では8,100円まで引き上げられており、財務戦略が市場に好意的に受け止められていることがわかる。
<strong>EPSとROEの改善に資本政策を直結させる手法は、株主価値創造を最優先に据えた大胆なアプローチである。</strong>それは単に数字上の改善ではなく、改革の成果を投資家へ即時に還元することで、長期的な戦略遂行への支持を取り付ける仕組みといえる。東京海上HDは、この循環モデルを武器にガバナンス改革と成長戦略を同時に進め、国内外の市場で存在感を一層強めようとしている。
政策保有株式全廃という歴史的決断とガバナンス改革の意義

東京海上ホールディングスは、2024年3月末時点で時価3.5兆円に上る政策保有株式を2026年度までに半減、2029年度にはゼロにする方針を打ち出した。この決断は、日本の保険業界における「もたれ合い」構造を断ち切る歴史的な試みであり、ガバナンス改革の核心をなすものである。従来、政策保有株式は取引先企業との関係維持や安定株主確保の役割を果たしてきたが、同時に競争の公正性を損なう要因ともなっていた。
金融庁による業務改善命令や顧客情報漏洩問題を受けて、同社は信頼回復を最優先課題と位置づけている。その象徴的な一手が、株式保有関係の全廃である。この改革は単なる財務戦略にとどまらず、企業文化や営業慣行に深く根付いた構造改革の一環として評価されている。
また、株式売却によって得られる巨額の資金は、株主還元や成長投資に活用される。2025年度の1株当たり配当金は210円を予定し、増配基調を明確に打ち出している。これにより、投資家に対して「ガバナンス改革が直接的に株主価値を高める」というメッセージを送ることが可能となる。
箇条書きで整理すると以下のようになる。
- 政策保有株式の3年間で半減、2029年度までに全廃
- 不祥事の背景とされた「もたれ合い構造」を断絶
- 売却益を成長投資と株主還元に充当
- ガバナンス改革と財務健全性の両立を実現
この動きはMS&ADやSOMPOといった競合他社にも影響を与え、業界全体での資本政策見直しを加速させる可能性が高い。さらに国際的な投資家の視点から見ても、透明性と資本効率を高める姿勢は企業評価の向上に直結する。東京海上HDの政策株式全廃は、ガバナンス改革の完成度を示す試金石であり、同社の信頼回復戦略の中核といえる。
ID&E買収とレジリエンスコンサルティング参入の衝撃
2025年5月、東京海上ホールディングスは建設コンサルティング最大手のID&Eホールディングスを約978億円で完全子会社化した。これは「保険+α」戦略の中でも最も大胆かつ象徴的な動きであり、同社がリスクマネジメント企業へと進化するうえで重要な転機となる。
ID&Eは防災やインフラ分野で国内トップクラスの実績を持ち、国土強靭化や脱炭素化といった国家的課題に対応する専門性を有している。東京海上はこの買収により、保険引受やリスクファイナンスに加え、防災コンサルティングや都市設計、エネルギーマネジメントといった領域にまで事業を拡張できる。補償だけでなく「リスクの予防」までカバーする一気通貫の価値提供が可能になった点は大きな転換である。
表:ID&E買収によるシナジー領域
| 領域 | 期待される効果 |
|---|---|
| 防災コンサルティング | 企業や自治体へのリスク予防サービス拡充 |
| 国土強靭化 | 公共事業との連携による新市場参入 |
| 脱炭素・GX | 蓄電池・再生可能エネルギー事業との統合 |
| 都市設計 | 災害対応を織り込んだ次世代都市モデル構築 |
自然災害リスクが高い日本において、防災やレジリエンスは社会的なニーズが極めて大きい。政府も国土強靭化政策に巨額の予算を投じており、その市場規模は数兆円規模と推計される。この分野に保険会社が本格参入することは前例が少なく、業界全体に与えるインパクトは大きい。
さらに、この動きは東京海上HDが「金融×非金融」の融合を加速させる象徴的事例である。保険事業の収益と相関性の低い分野を取り込むことで、事業ポートフォリオの安定性を高めるとともに、新たな収益源を確立することができる。ID&E買収は、国内事業の変革をけん引するだけでなく、日本の国土政策やエネルギー転換とも直結した、極めて戦略的な投資といえる。
Salesforce提携とAIガバナンスによるデジタル変革

東京海上ホールディングスは2025年8月、顧客関係管理で世界をリードするSalesforceとの戦略的提携を発表した。目的はAIを前提とした業務プロセスの再設計であり、抜本的な生産性向上と顧客体験の高度化を同時に実現することである。保険業務の効率化と顧客接点の強化を両立させる取り組みは、国内金融業界におけるDXの新たなベンチマークとなりつつある。
この提携によって、同社は営業活動やリスク分析を自動化し、顧客ごとに最適化された提案を行える体制を構築する。AIを活用したチャットボットや自動査定システムは、従来数日かかっていた業務を数時間に短縮できる可能性がある。さらに、Salesforceの顧客データ基盤を利用することで、膨大な契約者データを横断的に活用し、新たな商品開発やクロスセル戦略に結びつける狙いもある。
一方で、AI活用に伴うリスク管理も同時に進めている。2025年6月には「東京海上グループAIガバナンス基本方針」を策定し、透明性・公正性・セキュリティを担保する枠組みを整備した。特に、AIが意思決定に関与する際には「最終判断は人間が行う」という原則を明文化し、バイアスや過剰依存を防ぐ仕組みを構築している。NTTデータと連携し、AIガバナンスを実効的に担保するツールの導入も進めている。
箇条書きで整理すると以下の通りである。
- Salesforceとの提携で顧客接点のデジタル化を推進
- AI活用により査定・顧客対応を高速化し効率性を大幅に改善
- データ活用による新商品開発・クロスセル機会の創出
- AIガバナンス基本方針を策定し透明性・安全性を確保
**デジタル変革とガバナンスの両立は、東京海上HDが単なる効率化にとどまらず、顧客起点の金融サービスを再構築することを意味する。**これは、他の国内金融機関に先駆けて「次世代保険ビジネス」の姿を示す重要な一歩である。
北米スペシャルティ保険と新興国市場に見るグローバル成長戦略
東京海上HDの海外事業は今やグループ利益の6割超を占めるまでに成長し、その中心にあるのが北米スペシャルティ保険市場である。ここでは100以上の専門領域にわたる商品ポートフォリオを展開し、特定の市場リスクに依存しない分散型の収益モデルを築いている。コンバインド・レシオ(損害率と事業費率の合計)は90%前後と世界トップ水準を維持し、安定した高収益を生み出している点が強みである。
北米市場の特徴は、航空・海上輸送、サイバー、環境リスクといった高付加価値分野に特化している点にある。こうした領域は専門知識と高度なアンダーライティング能力を必要とするため参入障壁が高く、東京海上が築いた優位性は容易に揺らがない。この北米事業は国内改革を財務的に支える「キャッシュカウ」として機能している。
同時に、同社は新興国市場への布石も強化している。ブラジルではDXを駆使したコスト削減とデータ分析に基づく引受管理で、業界平均を大きく上回る成長を実現している。また、アフリカ市場においても2050年に向けた人口爆発を見据え、現地有力企業への出資を進めている。これらは2030年代以降の新たな成長エンジンとして期待されている。
表:東京海上HDのグローバル戦略の軸
| 地域 | 主な特徴 | 戦略的意義 |
|---|---|---|
| 北米 | スペシャルティ保険、コンバインド・レシオ90%前後 | 安定的高収益源 |
| ブラジル | DXによる効率化、データ活用 | コスト競争力と成長加速 |
| アフリカ | 将来的な人口増加市場 | 長期的な新市場開拓 |
このように、東京海上HDは成熟市場と新興市場を組み合わせた巧みなポートフォリオ経営を行っている。短期的には北米事業が変革の原資を供給し、長期的には新興市場が次世代の成長を担う二段構えの戦略が特徴である。
国内のガバナンス改革や事業変革を進めながら、海外で安定収益と成長余地を確保する姿勢は、同社が真にグローバル保険グループへと進化するための不可欠な条件といえる。
最新決算データが示す業績の実力と市場評価

東京海上ホールディングスの2025年3月期決算は、経常収益8兆4,401億円、経常利益1兆4,600億円、純利益1兆553億円という堅調な結果となった。これは過去最高水準に近い収益力を示し、ガバナンス改革や事業変革の途上にありながらも業績基盤の強さを証明したといえる。特に、2026年3月期第1四半期(2025年4~6月)では経常収益が前年同期比17.9%増の2兆2,685億円、経常利益は同113.3%増の5,652億円と大幅な増益を記録した。わずか3カ月で通期経常利益予想の44.5%を達成しており、上方修正への期待も高まっている。
この好調の背景には、北米スペシャルティ保険事業の堅調さと、国内における成長投資の効果がある。保険引受の精緻化、データ活用によるリスク管理強化が収益性を押し上げた。さらに、政策保有株式売却による資金確保が株主還元と投資に振り向けられ、資本効率の改善にもつながっている。
表:東京海上HDの直近期業績
| 期間 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月期(通期) | 8.44兆円 | 1.46兆円 | 1.05兆円 |
| 2026年3月期 Q1 | 2.27兆円(+17.9%) | 5,652億円(+113.3%) | N/A |
市場の評価も高い。日本格付研究所(JCR)は「AAA」、S&Pは「A+」、ムーディーズは「Aa3」、格付投資情報センター(R&I)は「AA+」と、国内外の主要格付機関から高い評価を獲得している。これらは国際的な保険取引において不可欠な信用力を示す指標である。
アナリストの評価もおおむね強気である。2025年9月時点でのコンセンサスは「買い」が優勢で、平均目標株価は6,699円と現在株価を上回る水準に設定されている。一部証券会社は目標株価を8,100円に引き上げており、改革と成長の両立が市場から支持されていることが明確である。短期的な業績改善と長期的な成長戦略が同時に評価されている点は、東京海上HDの競争優位を示す証左である。
MS&AD・SOMPOとの戦略比較から読み解く業界地図の行方
日本の損害保険業界は東京海上、MS&AD、SOMPOの3大グループによる寡占市場であるが、各社の戦略は明確に分かれ始めている。東京海上は「保険+α」を掲げ、ID&Eの買収によるレジリエンスコンサルティングやSalesforceとの提携を通じ、保険を超えた総合リスクソリューション企業への転換を進めている。
MS&ADホールディングスは「ビジネススタイルの大変革」を打ち出し、グループ内の共通基盤を活用する「1プラットフォーム戦略」を推進している。これは業務効率化と国内損保事業の収益性改善に重点を置く戦略であり、2025年度のIFRSベース純利益目標を4,500億円に設定している。MS&ADは効率性とグループシナジーによる安定成長を狙う路線にある。
一方、SOMPOホールディングスは「安心・安全・健康」を軸にした新中期経営計画を進め、事業ポートフォリオを「損害保険」と「ウェルビーイング」の2本柱に再編した。特に介護事業を核とするウェルビーイング領域を長期的な成長エンジンと位置づけ、2026年度には修正連結ROE13~15%を目指す。これは高齢化社会に対応したユニークな戦略であり、他社との差別化要素となっている。
表:3メガ損保の成長戦略比較
| 企業 | 中核戦略 | 特徴 | 目標ROE |
|---|---|---|---|
| 東京海上HD | 保険+α(リスクソリューション・レジリエンス) | ID&E買収、Salesforce提携 | 14%以上 |
| MS&AD | 1プラットフォーム戦略 | グループ統合・効率化 | 約12% |
| SOMPO | ウェルビーイング重視 | 介護・健康事業への注力 | 13〜15% |
この比較から明らかなように、東京海上はリスクソリューション、MS&ADは効率性、SOMPOはウェルビーイングと、各社は異なる成長領域に賭けている。今後の業界地図は、これらの戦略の成否によって大きく塗り替えられる可能性が高い。
特に東京海上が「保険+α」によって市場の枠を広げ、グローバル展開と組み合わせて独自の地位を築けるかが注目される。国内3メガ損保は共通してガバナンス改革とDX推進を迫られているが、その先の成長モデルで各社がいかに差別化を実現できるかが、2030年代に向けた競争の鍵となる。

