2025年、日本企業におけるデータ基盤の役割は劇的に変化している。かつては情報の保存や分析のための基盤に過ぎなかったデータプラットフォームが、いまやAI、特に生成AIの浸透によって経営そのものを左右する「戦略的インフラ」へと進化しているのである。IDC Japanの調査によれば、国内データプラットフォーム市場は2025年に7,371億円規模に達する見込みであり、この成長を牽引するのは前年比56.6%増で拡大したAIシステム市場である。さらに、2029年にはAI市場が4兆円を突破し、その中心を生成AIが占めると予測されている。
こうした潮流は、単なる技術導入を超えて、企業文化や業務プロセスの変革を迫っている。リアルタイム性を担保するLakehouse、ガバナンスを強化するアクティブメタデータ、民主化を推進するノーコードETL、そしてAIによる自動化が進むデータクレンジング――これらのツール群は、もはや選択肢ではなく競争優位を確立するための必須要素である。本記事では、最新の市場データと具体的な企業事例をもとに、AI駆動型データ基盤の全貌と日本企業が取るべき戦略的アクションを徹底的に解説する。
日本のデータ基盤市場を動かすAI革命の全貌

2025年、日本のデータ基盤市場はAIの進化によって歴史的な転換点を迎えている。IDC Japanの予測によれば、国内データプラットフォーム市場は7,371億円規模に達するとされ、AIシステム市場は前年比56.6%増の1兆3,412億円に拡大した。さらに2029年には4兆1,873億円規模に成長すると見込まれており、その中心に生成AIが存在している。この潮流は単なる技術革新ではなく、企業の競争力を左右する経営課題へと変貌している。
AIによる変革は、データ基盤の5つの領域に及んでいる。DWH/LakehouseではDatabricksが提供するLakebaseのように、従来分離されていたトランザクション処理と分析処理の境界を解消し、リアルタイムデータの活用を加速させている。ETL/ELTはノーコード化と生成AIの組込みによって民主化が進み、セキュリティを担保したデータ統合が可能となった。データカタログはアクティブメタデータを活用し、ガバナンスやアクセス制御を動的に管理する「頭脳」へ進化している。
特に注目すべきはデータクレンジングの進展である。MatrixFlowのように自然言語で操作可能なツールが登場し、これまで専門家に依存していた品質管理がビジネスユーザーにも開放されつつある。また、Feature Storeは従来の特徴量管理に留まらず、ベクトル埋め込みを扱う基盤として生成AI時代の中核インフラに成長している。こうした進化は、企業がAIを実装するうえで避けて通れない要素となっている。
表:AIが変革するデータ基盤の主要領域
| 領域 | 主な変化 | 代表的ツール |
|---|---|---|
| DWH/Lakehouse | OLTPとOLAPの融合、リアルタイム処理 | Databricks Lakebase |
| ETL/ELT | ノーコード化とAI組込み、セキュリティ重視 | TROCCO、Waha! Transformer |
| データカタログ | アクティブメタデータによるガバナンス強化 | Quollio、Informatica |
| データクレンジング | 自然言語指示での操作、精度向上 | MatrixFlow、dotData Insight |
| Feature Store | ベクトル埋め込み管理、RAG基盤 | Vertex AI Feature Store |
このようにAIは、従来のデータ処理や統合を超え、組織文化や業務プロセスそのものを変革する力を持っている。企業が競争優位を確立するためには、ツール導入にとどまらず、全社的なデータ戦略と連動した活用が不可欠である。
生成AIとデータ基盤:2025年の市場規模と成長予測
市場調査機関の分析によれば、日本におけるデータとAI市場は未曾有の成長軌道に乗っている。国内のデータプラットフォーム市場は2025年に7,371億円に達するとされ、その成長を牽引するのは生成AI関連の投資である。富士キメラ総研のレポートでは、生成AI市場は2028年度に1兆7,394億円に拡大し、2023年度比で12.3倍という驚異的な伸びを示すと予測されている。この時点でAI市場全体の6割を生成AIが占める見通しであり、もはや単なる技術ではなく産業構造を変革する基盤技術となっている。
この拡大は、企業がデータ基盤に投じる資金の使途にも大きな影響を与えている。従来はストレージや処理速度の強化が中心であったが、現在では「AI-Ready」なデータ整備が最重要課題となっている。信頼性の高いデータ、厳格に統制されたアクセス、そしてビジネスコンテキストを持つデータが不可欠となり、データクレンジングやカタログ、ガバナンス分野への投資が急速に拡大している。
箇条書きで整理すると、2025年以降の市場の注目点は以下の通りである。
- データプラットフォーム市場は2025年に7,371億円規模へ拡大
- AIシステム市場は2024年に前年比56.6%成長、今後も年平均2桁成長を継続
- 生成AI市場は2028年度に1兆7,394億円規模、AI市場全体の6割を占有
- 投資の焦点は「量」から「質」へ移行し、データ品質とガバナンスが優先課題に
この背景には、AIエージェントの普及も存在する。AIは単なるツールから自律的な業務執行者へと進化しつつあり、データ基盤に対する要求は従来の人間依存型からリアルタイム性と堅牢性を前提とするものへと変わっている。わずかな品質の乱れや遅延が重大なリスクに直結するため、企業はデータ基盤を「業務基盤」として再定義する必要に迫られている。
このように2025年は、日本企業にとってデータとAIを軸にした成長戦略を加速させる転換点であり、適切な投資判断とツール選定が競争優位を分ける決定的要因となる。
AIエージェントの台頭がもたらすデータ基盤への新要求

2025年のデータ基盤において無視できないのがAIエージェントの台頭である。従来の生成AIは、与えられたプロンプトに対して単一のタスクを実行する存在であった。しかし現在は、人間の指示を起点に複数のタスクを自律的に計画・実行する「エージェンティックワークフロー」へ進化している。この変化は、企業のデータ基盤に対して従来とは全く異なる要件を突きつけている。
IDC Japanの分析では、AIエージェントが組織内で実用化される際には「ガードレール」と呼ばれる仕組みが不可欠になると指摘されている。これは、不適切な動作や危険な業務実行を未然に防ぐための制御機能であり、従来のBIツール連携や単なるデータ可視化ではカバーできない領域である。AIエージェントは膨大なデータにミリ秒単位でアクセスするため、品質のわずかな乱れやレイテンシの遅延がシステム全体の誤作動に直結するリスクを孕んでいる。
箇条書きで整理すると、AIエージェント時代のデータ基盤が求める要件は以下の通りである。
- リアルタイム性の確保(ミリ秒単位の遅延も致命的リスクとなる)
- 厳格なガバナンスと透明性(不正確なデータ利用を防止)
- 高度な堅牢性(自律的システムに耐える安定性)
- プログラムによる検証可能性(人間ではなくAIが利用する前提での設計)
この新しい要件は、データ基盤の役割を根本的に変える。従来の「人間の分析を支援するツール」から、「企業の業務を自律的に遂行する基盤」へと進化しつつあるのである。今後の企業戦略においては、単にAIを導入するのではなく、AIエージェントが安全かつ効率的に機能するデータ環境を整備することが不可欠になる。
コアプラットフォームの進化:LakehouseとFeature Storeの戦略的役割
データ基盤の中心に位置するのがDWHやLakehouseといったコアプラットフォームである。近年はAI/MLワークロードに最適化された設計が進み、特にDatabricksの「Lakebase」は大きな注目を集めている。Lakebaseはレイクハウス上でオンライントランザクション処理(OLTP)を直接実行可能にした世界初のサービスであり、従来分離されていた分析処理(OLAP)と統合することで、リアルタイムAIアプリケーション開発のボトルネックを解消した。
この技術革新により、従来は開発時間の約30%を占めていたデータ複製や整合性確保の作業が不要になり、開発効率は飛躍的に向上している。さらに、Zero-Copy Clone機能によって巨大な本番データベースのコピーを瞬時に生成し、実験やテストを低コストで行える点は、AI開発サイクルの短縮に直結している。
一方で、Feature Storeも戦略的役割を担う存在として進化している。従来は機械学習の特徴量を一元管理する仕組みとして注目されたが、生成AI時代においてはベクトル埋め込みの管理が主役となっている。Google Cloud Vertex AI Feature Storeは、BigQueryに格納されたデータを複製せず直接オンラインサービングに利用可能とし、効率的かつ低コストでベクトル検索を実現する。
表:主要コアプラットフォームの進化
| プラットフォーム | 特徴 | 主なAI対応機能 |
|---|---|---|
| Databricks Lakebase | OLTPとOLAPの融合 | Zero-Copy Cloneによる迅速な実験環境構築 |
| AWS SageMaker Lakehouse | 複数ソース統合 | ゼロETLによるデータ取り込み自動化 |
| Google Vertex AI Feature Store | BigQuery連携 | ベクトル検索とEmbedding管理 |
このように、LakehouseとFeature StoreはAI活用を前提とした新世代アーキテクチャの中核を担い、リアルタイム性と信頼性を兼ね備えた基盤として企業の競争力を支えている。経営層にとって、これらの導入はもはや技術選択ではなく、AI戦略そのものと密接に結びついた経営判断となっている。
データカタログとアクティブメタデータが変える企業の情報管理

データカタログは、かつて単なる「データの台帳」としての役割に留まっていた。しかし2025年の現在、その役割は大きく変貌している。AIの活用とアクティブメタデータの登場により、データカタログは企業全体のデータガバナンスを支える「頭脳」へと進化しているのである。
アクティブメタデータとは、データに関する情報を収集・表示するだけでなく、その情報を基に自動的にアクセス制御やデータマスキングを実行する仕組みを指す。例えば、あるデータに「個人情報」というタグが付与されれば、アクセス権限が即時に制限され、関連するガバナンス処理が自動化される。この動的な仕組みは、従来の受動的なカタログ運用とは一線を画す。
特に日本市場では、Quollio Technologiesが提供する国産ツール「Quollio Data Intelligence Cloud」が注目されている。NTTデータとの連携を強みに、日本特有のビジネス慣習や文化に適したUI/UXを実現しており、富士薬品などの導入事例では属人的だったデータ管理が「見える化」され、マーケティング施策の高度化につながった。グローバルではAtlanやCollibraがAIを駆使した第3世代カタログとして台頭しており、自然言語検索や詳細なリネージ機能で企業のデータ活用を支援している。
表:主要データカタログの特徴
| 製品名 | 特徴 | 導入メリット |
|---|---|---|
| Quollio Data Intelligence Cloud | 日本文化に適したビジネスメタデータ管理 | 属人化解消、データ民主化 |
| Atlan | AIによる自然言語検索、アクティブガバナンス | データ探索効率化、ガバナンス自動化 |
| Collibra | エンタープライズレベルのコネクタ群、データリネージ | 全社的ガバナンス強化、説明責任担保 |
このように、データカタログは単なるIT資産管理を超え、AI時代の企業経営を支える基盤へと変化している。特に重要なのは、データを探すための利便性だけでなく、AIエージェントの精度や信頼性を高めるために不可欠な役割を果たしている点である。企業は、自社のデータ戦略を推進するうえで、アクティブメタデータを中心に据えたカタログ活用を不可欠とすべきである。
ETL/ELTの最前線:民主化・統治・セキュリティの三極化
データ統合を担うETL/ELT領域は、2025年においてかつてない変革を遂げている。従来はバッチ処理が中心で静的な仕組みであったが、AIの登場によりリアルタイム性と柔軟性が格段に向上し、その進化の方向性は「民主化」「統治」「セキュリティ」という三極に分かれつつある。
まず「民主化」の代表例が、スリーシェイクのReckonerやprimeNumberのTROCCOである。これらはノーコード操作により、非エンジニアでも簡単にデータパイプラインを構築できる。Reckoner導入企業では、kintoneとSalesforce間のデータ転記を完全自動化し、工数を90%削減する成果を上げている。TROCCOでは「Connector Builder」にAIサポート機能を搭載し、標準外のシステムとの接続も容易に実現している。
次に「統治」を体現するのがInformaticaのIntelligent Data Management Cloud (IDMC)である。同社のAIエンジン「CLAIRE」は、データ統合から品質管理までをインテリジェントに自動化し、分類やマッピング、異常検知を高精度で実行する。大規模なエンタープライズ環境において、全社的なガバナンスを維持しながら運用効率を高める点で大きな価値を持つ。
最後に「セキュリティ」を軸に据えるのがユニリタのWaha! Transformerである。同社が追加した生成AI連携オプションはRAGアーキテクチャを採用し、機密データを外部に出さずに社内ナレッジを安全に活用可能にする。この仕組みは情報漏洩リスクを原理的に回避するため、金融や製造など高セキュリティが求められる業界で高い評価を得ている。
箇条書きで整理すると、ETL/ELT進化の方向性は以下の通りである。
- 民主化:現場主導のデータ活用を可能にするノーコード化
- 統治:AIエンジンによるライフサイクル全体の自動化
- セキュリティ:情報漏洩を防ぐ閉域環境での生成AI連携
このようにETL/ELTは単なる技術選定を超え、企業がどのようなAI戦略を志向するかを映し出す鏡となっている。民主化を推進するのか、統治を強化するのか、それともセキュリティを最優先するのか。その選択は、経営層が描くAI活用の方向性そのものを意味している。
データクレンジングの革新とAIによる品質保証の新常識
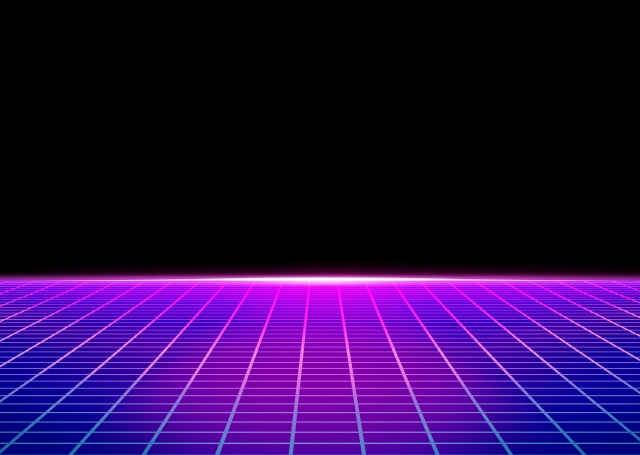
AI活用が企業の競争力を左右する時代において、データ品質は最も重要な基盤要素である。機械学習や生成AIモデルの精度は、投入されるデータの正確性に依存しており、「Garbage In, Garbage Out」という原則は今も変わらない。2025年には、この課題に対してAIを活用した革新的なデータクレンジングが実用化され、従来の属人的で手間のかかる作業を一変させている。
特に注目されるのがMatrixFlowの生成AI搭載クレンジング機能である。ユーザーが「〇〇という文字列を含む行を削除して」といった自然言語で指示するだけで、AIが意図を解釈し自動的に不要なデータを処理する。これにより、SQLや専門知識が不要となり、現場担当者でもデータ整理が可能になった。既に導入企業では、日常的なクレンジング工数が大幅に削減され、分析やAI予測の精度向上につながっている。
また、dotData InsightはAIによる品質問題の自動検出と修正提案を実現している。表記揺れや欠損値、異常値を自動で洗い出し、最適な修正案を提示することで、ユーザーは検証と承認に集中できる。さらに、NTTタウンページとアグレックスが提供するデータクレンジングサービスは、約560万件の企業情報データベースを活用し、顧客リストの正規化や属性補完まで実現している。これにより、CRMやSFAの基盤強化に直結する成果が得られている。
箇条書きで整理すると、最新のクレンジングの特徴は以下の通りである。
- 自然言語での指示による操作性の向上
- AIによるエラー検出と修正提案の自動化
- 名寄せや属性補完によるデータ資産価値の向上
- 人間の工数を9割以上削減し、検証に特化できる新たな役割分担
学術研究でも、LLMは行単位のエラー検出に強みを持つ一方、統計的バイアスや分布の偏りには限界があると報告されている。この知見は、AIツールが万能ではなく、人間の専門知識との協働が不可欠であることを示している。企業はAIを単なる自動化ツールとしてではなく、人間の判断を支えるパートナーとして位置づけることで、真に高品質なデータ基盤を構築できるのである。
国内企業の導入事例から学ぶAI駆動型データ基盤の実践的成果
AI駆動型データ基盤の導入は、単なる概念検証の段階を超え、日本企業において具体的な成果を生み出している。特にETL/ELTやAI分析、データカタログの活用は、工数削減や売上向上といった明確なインパクトを示している。
D2C事業を展開するWaqoo社は、広告データの集計に月60時間を費やしていたが、TROCCOを導入することで完全自動化を実現した。工数はゼロとなり、担当者は分析や施策改善といった付加価値業務に集中できるようになった。同様に、NTTデータビジネスブレインズではReckonerを活用し、kintoneとSalesforce間のデータ転記を自動化。これにより工数は90%削減、体制も50%縮小する成果を上げた。
さらに、dotDataの活用は多様な業界で成果を示している。横浜ゴムは需要予測モデルの精度向上により、10数億円規模の在庫コスト削減を達成。日本ゼオンでは化学プラントのセンサー解析工数を100分の1に短縮し、品質改善に直結した成果を得ている。マーケティング領域では、商品購入率を12倍に高めた事例や、保険成約率を3倍に引き上げた事例も報告されている。
表:国内企業のAI駆動型基盤導入成果
| 企業名 | 課題 | 導入ツール | 成果 |
|---|---|---|---|
| Waqoo | 広告データ集計に月60時間 | TROCCO | 工数100%削減 |
| NTTデータビジネスブレインズ | kintone-Salesforce連携の手作業 | Reckoner | 工数90%削減、体制50%縮小 |
| 横浜ゴム | 在庫予測精度不足 | dotData | 在庫コスト10数億円削減 |
| 日本ゼオン | センサーデータ解析の膨大工数 | dotData | 工数99%削減 |
これらの事例は、AI駆動型データ基盤がコスト削減、業務効率化、新たな収益創出に直結する経営資産であることを物語っている。導入効果を最大化するためには、ツール選定だけでなく、業務プロセスの見直しやデータ文化の醸成が不可欠である。企業は単なる技術導入に留まらず、経営戦略の一環として全社的にデータ基盤を位置づける必要がある。
2026年に向けた自律型データプラットフォームの展望と経営層への提言

2025年のデータ基盤市場は、AIと生成AIの進展によって大きな進化を遂げてきた。しかし、その流れはまだ序章に過ぎない。2026年以降に本格化すると予測されるのが「自律型データプラットフォーム」である。これは単にデータを保管・処理するだけでなく、AIが主体となってデータ収集、クレンジング、統合、提供までを自動で最適化し続ける仕組みであり、企業に新たな競争力をもたらす基盤となる。
調査会社の分析では、2026年以降の成長のカギは、データプラットフォームが人間の介在を最小化し、AIエージェントや生成AIと直接連動する点にある。特にアクティブメタデータとAIによるガバナンス強化は、膨大なデータが常時流通する環境において不可欠であり、リアルタイムでアクセス権限やセキュリティ設定を動的に制御する仕組みが標準となるだろう。
表:自律型データプラットフォームの特徴
| 領域 | 現在の機能 | 自律型プラットフォームでの進化 |
|---|---|---|
| データ収集 | API連携やETLによる取り込み | AIが自動的に最適な収集経路を選択 |
| データクレンジング | 自然言語での指示やAI補助 | 異常値をリアルタイム検知し自動修正 |
| ガバナンス | メタデータ管理と権限設定 | アクティブメタデータによる自動制御 |
| AI連携 | Feature Storeによる特徴量提供 | AIエージェントが直接利用する基盤化 |
このような仕組みが普及する背景には、AIエージェントの業務実装がある。営業支援やカスタマーサポートにおいて、AIが人間の補助を超えて自律的にタスクを遂行するためには、基盤となるデータの正確性と即応性が必須である。わずかな誤差や遅延が顧客体験や経営判断に致命的な影響を与えるため、データプラットフォームが自ら品質を担保する必要が生じている。
経営層に求められるのは、この変化を単なるIT部門の課題と捉えず、企業戦略の核心に位置づける視点である。AI駆動型基盤の整備はコスト削減だけでなく、新規事業創出や意思決定の高速化を可能にする。実際、国内大手企業ではAI基盤の刷新により、在庫コスト削減や成約率向上といった定量的成果が報告されている。
箇条書きで整理すると、経営層への提言は以下の通りである。
- 自律型データプラットフォームを「競争優位の源泉」として位置づける
- 部門横断的に投資を行い、ガバナンスとAI活用を両立させる
- AIエージェントとの連動を前提にしたリアルタイム性を確保する
- 人材育成とデータ文化の醸成を経営課題として推進する
2026年は、データ基盤が「人が管理するもの」から「AIが管理し続けるもの」へと転換する節目となる。この潮流を見越した経営判断を下せる企業こそが、次世代の市場で主導権を握る存在となるだろう。

