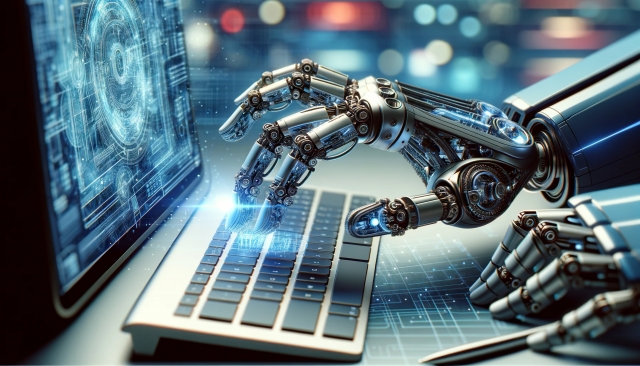日本企業は今、経済産業省が指摘する「2025年の崖」という深刻な課題に直面している。老朽化したレガシーシステムの維持コスト、セキュリティリスク、そして人材不足が重なれば、年間最大12兆円もの経済損失が発生すると警鐘が鳴らされている。同時に、国際競争の激化や労働人口の減少など、外部環境の圧力も企業の生産性向上を強く求めている。
こうした背景の下、プロセスマイニングやタスクマイニングといった技術にAIを融合させた「プロセスインテリジェンス」は、単なる業務改善ツールを超えて、経営戦略の中核へと進化しつつある。事実、国内市場は急成長を遂げており、2028年度には75億円規模に達する見通しが示されている。さらに生成AIやエージェントAIといった新潮流が加わり、プロセスが自律的に監視・診断・最適化を行う未来像も現実味を帯びてきた。
本記事では、最新の市場データと国内外の導入事例をもとに、日本企業が持続的成長と競争優位を確立するための道筋を探る。
日本企業を取り巻く「2025年の崖」とプロセスインテリジェンスの必然性

経済産業省のDXレポートで提起された「2025年の崖」は、日本企業にとって避けて通れない経営課題である。老朽化した基幹システムがブラックボックス化し、刷新できなければ2025年以降に年間最大12兆円の経済損失が発生する可能性が指摘されている。この数字は単なる警告ではなく、既に企業の財務と競争力を直撃する現実的なリスクとなりつつある。
具体的な問題は多岐にわたる。第一に、レガシーシステムの維持・運用コストが増大し、経営資源を圧迫する。第二に、セキュリティパッチが適用できないことによるサイバー攻撃リスクが高まる。第三に、クラウドやAIといった最新技術の導入が困難となり、市場競争力が低下する点である。さらに深刻なのは、これらシステムを維持できる熟練エンジニアが高齢化・退職し、企業内に技術知が失われることである。
この課題は単に企業内部の問題にとどまらない。人口減少による労働力不足、頻発する自然災害、グローバル市場でのデジタル競争など、日本社会全体の構造的課題と密接に結びついている。つまり、生産性向上は企業の存続を超え、日本経済全体の持続可能性を左右する国家的責務となっている。
このような状況下で注目されるのがプロセスインテリジェンスである。プロセスマイニングやタスクマイニングを通じて業務を客観的に可視化し、ボトルネックや無駄を特定することで、企業は短期間で改善効果を得ることができる。ブラックボックス化したシステムの実態を明らかにすることこそ、2025年の崖を乗り越える第一歩である。
表:2025年の崖がもたらす主要リスクと影響
| リスク要因 | 影響 |
|---|---|
| 老朽化システムの維持コスト増 | 経営資源の圧迫 |
| セキュリティパッチ未適用 | サイバー攻撃リスク増大 |
| 最新技術導入の阻害 | 競争力低下 |
| IT人材の高齢化・退職 | システム維持困難 |
プロセスインテリジェンスは単なる業務効率化の枠を超え、事業継続と将来の競争力確保を同時に達成する戦略的投資として位置づけられる。日本企業にとってその導入は不可避であり、もはや待ったなしの状況にある。
プロセスマイニングとタスクマイニングの核心技術と相互補完関係
従来の業務改革は担当者へのヒアリングやワークショップに依存していたが、この方法は主観に左右されやすく、業務の全体像を正確に把握できないという限界があった。これを根本から変革するのがプロセスマイニングとタスクマイニングである。
プロセスマイニングはERPやCRMといった基幹システムに記録されたイベントログを分析し、業務プロセスを事実に基づいて可視化する。たとえば、どの工程で手戻りが発生しているか、どの承認フローで時間が滞留しているかを、客観的データに基づいて特定できる。これは業務改革におけるMRI検査のような役割を果たし、隠れた非効率を浮かび上がらせる。
一方、タスクマイニングは従業員がPC上で行うクリックや入力、アプリケーション利用状況を収集・分析する技術である。これにより、繰り返し発生するコピー&ペーストや定型入力作業など、自動化可能なタスクを抽出できる。さらに、ハイパフォーマーの作業手順を標準化し、組織全体の生産性向上に活用することも可能である。
両者は異なるレイヤーを分析対象としながらも、互いを補完する関係にある。プロセスマイニングが企業全体のフローを示す地図なら、タスクマイニングは現場の細部を記録するドライブレコーダーに例えられる。両者を統合することで初めて、企業はマクロとミクロ双方の視点から業務を360度把握できる。
箇条書きで整理すると次の通りである。
- プロセスマイニング:基幹システムのイベントログを分析し、全社的プロセスを可視化
- タスクマイニング:従業員PC操作を分析し、非効率や自動化対象を特定
- 相互補完:戦略的改善領域の特定(プロセスマイニング)と、具体的施策の実行(タスクマイニング)
UiPathやMicrosoftが両方の機能を統合して提供しているのは、この相乗効果の重要性を理解しているからである。戦略(プロセスマイニング)と戦術(タスクマイニング)の両輪を回すことこそが、真の業務改革とハイパーオートメーションの実現につながる。
AIが加速するプロセスインテリジェンスの進化:予測・根本原因分析・シミュレーション

プロセスマイニングが従来提供してきた価値は、過去の業務実態を可視化し、非効率な流れを明らかにする「記述的分析」にあった。しかしAIの融合は、その役割を大きく拡張し、未来を予測し最適な打ち手を提示する「予測的・処方的分析」へと進化させている。これにより、企業はデータの事後分析に留まらず、将来の課題を先回りして解決できる体制を築きつつある。
AIが提供する具体的な機能は以下の3点に集約される。
- 予測モニタリング:進行中の案件が遅延する確率やリスクを事前に算出し、未然対応を可能にする
- 自動根本原因分析:特定の担当者、サプライヤー、時間帯など複数要因を関連付け、真因を特定する
- デジタルツイン・シミュレーション:仮想環境で改善策を検証し、ROIを定量的に予測する
例えば、ある大手製造業ではAIを活用したプロセスマイニングにより、請求処理の遅延案件の85%を事前に特定できた。その結果、従来は発生後に対応していたトラブルを未然に防ぐことが可能となり、年間数億円規模の損失回避につながった。
また、デジタルツインを活用することで「人員を2名追加した場合」や「承認フローをRPAで自動化した場合」といったシナリオを検証できる。現場に大きな影響を与える前に、定量的なシミュレーションを実行できる点は、従来の改善活動にはなかった大きな強みである。
表:AIがもたらすプロセスインテリジェンスの進化
| 機能 | 具体例 | 効果 |
|---|---|---|
| 予測モニタリング | 納期遅延確率をリアルタイム算出 | 事前対応による損失回避 |
| 根本原因分析 | 特定要因を自動特定 | 表面的対処から本質的改善へ |
| デジタルツイン | 人員配置や自動化の効果を検証 | 投資判断の精度向上 |
AIの導入により、意思決定は経験則からデータドリブンへとシフトする。問題が顕在化してから動くのではなく、事前に兆候を捉えて最適解を提示する姿勢が、次世代の業務改革に不可欠となる。
生成AIとエージェントAIがもたらす自律型企業への道筋
AIの進化は予測や分析にとどまらず、企業の業務そのものを自律的に運営する未来像を描きつつある。その中心にあるのが生成AIとエージェントAIの登場である。これらは従来の人間中心の業務フローを根底から変える可能性を秘めている。
生成AIの代表的な活用例は「コパイロット」である。経営者やマネージャーは「先月最も手戻りが多かった業務は何か」と自然言語で質問するだけで、AIが膨大なデータを解析し、わかりやすい答えとグラフを提示する。これにより、従来はデータサイエンティストを介さなければ得られなかった洞察を、誰もが瞬時に入手できるようになった。データ活用の民主化は、企業全体の意思決定スピードを飛躍的に高める。
さらに進んだ形がエージェントAIである。例えば、Celonisの「AgentC」は遅延を検知すると自律的に関係者へ通知を送り、RPAを起動して修正処理を実行する。これは単なるアシストを超え、AIが自律的にアクションを取る段階に到達したことを意味する。
エージェントAIの有効性を支えるのが「プロセスインテリジェンスグラフ」である。業務全体の文脈を理解しているからこそ、AIは誤った判断を回避し、適切な対応を実行できる。この仕組みにより、企業は人間の監督を最小限にしながら、業務の最適化を継続的に進められる。
箇条書きで整理すると以下の通りである。
- 生成AI:自然言語による質問に即座に答えるコパイロットとして活用
- エージェントAI:課題を検知し、自律的に修正アクションを実行
- プロセスインテリジェンスグラフ:AIが文脈を理解し、誤りのない判断を支える基盤
この流れの先にあるのが「自律型企業」である。業務が自らを監視し、診断し、最適化していく未来では、人間は戦略的判断や創造的業務に専念できる。生成AIとエージェントAIの融合は、企業経営の在り方を根本から変革する歴史的転換点となるだろう。
日本市場の成長軌道とハイパーオートメーションの台頭
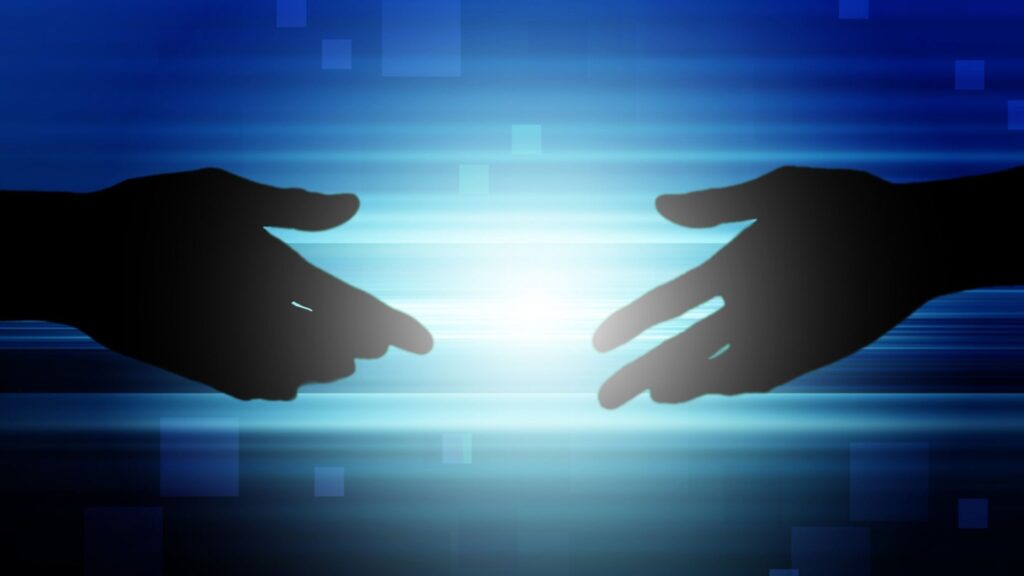
日本のプロセスマイニング市場は急速に拡大している。ITRの調査によれば、2023年度の市場規模は25.7億円で前年から約47%増加し、2024年度も約39%の成長が見込まれている。さらに2028年度には75億円規模に達する予測が示されており、年平均成長率(CAGR)は23.9%と極めて高水準である。これは当初の予測を上回るペースであり、企業の需要が急速に高まっていることを示している。
この背景には、原材料費高騰や国際情勢の変化によるコスト圧力がある。特に調達・購買分野での活用が進み、効率化とコスト最適化の両立が喫緊の経営課題となっている。IDC Japanはさらに広い視点で、国内AI市場全体が2024年に1兆3,412億円、2029年には4兆1,873億円に達すると予測している。AI市場全体の成長が、プロセスインテリジェンスの拡大を強力に後押ししている。
表:日本市場の成長予測(ITR/IDC Japan)
| 年度 | プロセスマイニング市場規模 | 国内AI市場規模 | 主な成長要因 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 25.7億円 | – | 大企業導入本格化 |
| 2024年度 | 35.7億円 | 1兆3,412億円 | 生成AI搭載、認知拡大 |
| 2028年度 | 75億円 | – | ハイパーオートメーション浸透 |
| 2029年度 | – | 4兆1,873億円 | 自律型企業基盤の確立 |
次なるトレンドが「ハイパーオートメーション」である。これはRPAやAI、プロセスマイニング、iPaaSなど複数の技術を統合し、業務の断片的自動化ではなくエンドツーエンドでの最適化を実現するアプローチである。プロセスマイニングは、この戦略において自動化すべき領域を特定する羅針盤としての役割を担う。
日本のRPA市場は2033年までに50億米ドル規模に成長すると予測されており、RPA拡大と連動してプロセスマイニング需要も急速に高まる。効率化の次のステージは、自動化対象を正確に特定し、全体最適を実現する統合戦略に移りつつある。
国内主要ベンダーと導入事例:Celonis、UiPath、Microsoft、SAP、IBM
市場の成長を支えるのはグローバルベンダーと国内SI企業の連携である。特に日本企業が選択肢とする主要ベンダーには以下の特徴がある。
- Celonis:ドイツ発のプロセスマイニングのパイオニアで、NECやKDDI、豊田通商など国内大手に導入実績を持つ。生成AIを搭載した「Process Copilot」や自律型エージェント「AgentC」で差別化を図っている。
- UiPath:RPAで知られる同社は、プロセスマイニングを自社プラットフォームに統合。リコーや大和ハウス工業が導入し、RPA導入後の最適化を加速させている。
- Microsoft Power Automate:Minitの買収でプロセスマイニング機能を強化。トヨタ自動車や愛媛銀行が活用しており、既存のMicrosoft製品との親和性が強みである。
- SAP Signavio:SAPユーザーに特化したソリューションで、AJSが販売管理プロセス改善に導入した事例がある。SAP S/4HANAとの連携力が際立つ。
- IBM Process Mining:Watsonを活用したAI機能に強みを持ち、IHIが導入。myInvenio買収による国内展開実績も豊富である。
表:国内主要ベンダー比較
| ベンダー | 主な強み | 国内導入事例 | AI差別化要素 |
|---|---|---|---|
| Celonis | グローバルNo.1シェア、生成AI搭載 | NEC、KDDI、JT | Copilot、AgentC |
| UiPath | RPAとの統合力 | リコー、大和ハウス | エージェントオートメーション |
| Microsoft | 365/Dynamics連携 | トヨタ、愛媛銀行 | Minit買収、AI Builder |
| SAP Signavio | ERP連携最適化 | AJS | 適合性チェック |
| IBM | AI分析、デジタルツイン | IHI | Watson連携 |
これらのベンダーが共通しているのは、単なる業務分析を超えて自動化とAIを組み合わせた「業務変革の実行基盤」を提供している点である。特にCelonisやUiPathは日本市場に強い投資を行い、NECやリコーのような大手企業での成果を積み上げている。
**日本企業にとって重要なのは、ベンダー単体の導入ではなく、SI企業との協業による最適な活用である。**国内の富士通、NEC、日立といったSIはグローバル製品を顧客に合わせて導入・カスタマイズしており、実践的成果を支えている。
導入を成功させるための共通要因と実践的アプローチ

プロセスインテリジェンスを導入する日本企業は増加しているが、全てのプロジェクトが成功するわけではない。成功の背後には共通する要因が存在し、それを理解し体系的に実践することが極めて重要である。NECやIHI、リコーなどの先行企業の事例を分析すると、明確なKPI設定、データドリブン文化の醸成、スモールスタートと継続改善の仕組みが鍵を握っている。
明確な目的とKPI設定
成功する企業は「可視化そのもの」を目的にしていない。例えば「リードタイムを20%短縮する」「手作業ミスを半減させる」といった具体的な数値目標を事前に設定している。IHIではプロセスマイニングを活用し、部門ごとの処理スピードや業務負荷を定量化。その結果、押印プロセスの廃止など明確な改善アクションにつながり、大幅なリードタイム短縮を実現した。
データドリブン文化の醸成
従来の業務改善は担当者の声や経験則に依存していたが、これでは改善活動が属人的になりやすい。NECはCelonis導入時に「データを共通言語とする文化」を徹底し、部門間の合意形成を加速させた。データが示す事実に基づいて意思決定を行う姿勢は、プロセス改善を継続的に根付かせる基盤となる。
スモールスタートと成功事例の横展開
リコーはまず人事や経理といった限定的なプロセスにプロセスマイニングを導入し、短期間で年間200時間以上の削減効果を算出した。この成果を社内に共有し、他部門の関心と協力を得ることで全社展開へとつなげている。小規模なPoCでクイックウィンを出すことが、全社的変革の触媒となる。
継続的改善サイクルの確立
プロセスマイニングは一度導入して終わりではない。改善後もプロセスを監視し、新たな逸脱やボトルネックを発見して改善を繰り返すことが不可欠である。継続的なPDCAサイクルを業務に組み込み、改善を常態化する仕組みが成功を左右する。
表:導入成功の4要因
| 成功要因 | 具体例 | 効果 |
|---|---|---|
| KPI設定 | リードタイム短縮20%など数値目標 | 改善効果を定量的に可視化 |
| データドリブン文化 | データを共通言語化 | 合意形成と納得感の向上 |
| スモールスタート | 限定部門でPoC実施 | クイックウィンの獲得 |
| 継続改善 | 定期的なモニタリング | 改善の持続と最適化 |
プロセスインテリジェンスの価値は単なるツール導入ではなく、組織の文化と仕組みに定着させることにある。小さな成功を積み重ね、データドリブンな改善文化を根付かせた企業こそ、長期的な競争優位を築くことができる。