2025年、日本企業の経営企画部門は大きな転換点に直面している。AI活用は単なる実験段階を超え、事業の中核に統合し具体的な成果を追求するフェーズへと移行した。IDC Japanによれば国内AI市場は2024年に前年比56.5%増となり、2029年には4兆円規模へ拡大する見通しである。一方で、矢野経済研究所の調査では生成AIを導入している企業は25.8%に達したものの、その約4割が無料プランに留まっており、投資対効果の明確化が課題となっている。
こうした状況の中で注目されるのが、複雑な業務を自律的に遂行するAIエージェントや、Perplexity AI・Similarweb・Franca AIといった特化型ツールの台頭である。パナソニックやソフトバンクなど先進企業の事例が示すように、AIは単なる効率化手段にとどまらず、経営戦略そのものを変革する力を持つ。本稿では、市場・競合リサーチ、要約・示唆生成、事業計画ドラフトといった経営企画の主要領域ごとに最新ツールと事例を徹底分析し、2026年以降の日本企業が取るべき戦略的アプローチを提示する。
経営企画におけるAI活用の現在地と課題
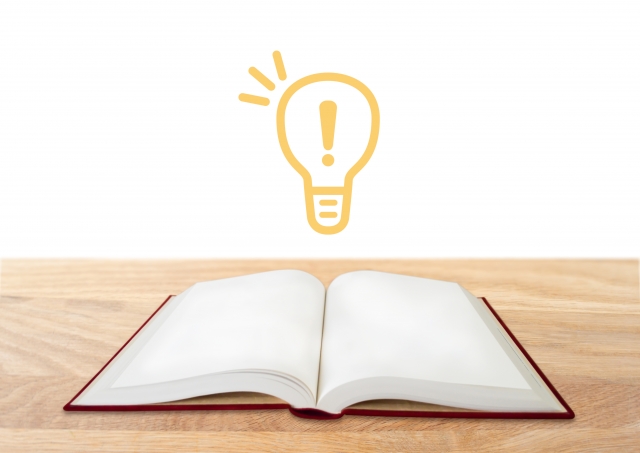
日本企業におけるAI活用は、実験段階から本格導入フェーズへと移行しつつある。IDC Japanの調査によれば、国内AI市場は2024年に前年比56.5%増の1兆3,412億円に達し、2029年には4兆1,873億円へ拡大する見通しである。この成長率は、AIが一過性のブームではなく、経営基盤を支える中核技術へと定着していることを示している。
しかし、導入企業の内実を見ると課題も多い。矢野経済研究所の2025年調査では、生成AIを何らかの形で導入している企業は25.8%に達したものの、その約4割は無料プランの利用に留まっている。つまり、AIを戦略的に活用する先進企業と、表面的な試用にとどまる企業の間で大きな格差が生じている。この「二極化」は、企業競争力に回復困難な差をもたらしかねない。
代表的な成功事例として、パナソニックコネクトは社内AIアシスタント導入により年間18.6万時間もの業務時間を削減した。削減時間を金額換算して効果を可視化した点は、経営層を納得させ全社的展開を後押しする要因となった。同様に、ソフトバンクはAIとRPAを組み合わせることで4,500人月相当の業務時間を創出し、新規事業開発へ再投資している。
一方で、多くの企業は「PoC疲れ」に直面している。PoCとは概念実証のことだが、繰り返し実験を行うもののROIが不明確で、本格的な業務統合に至らない状況が続いている。PwCの国際調査によれば、AI導入によって期待を上回る効果を実感している日本企業の割合は米国や英国の4分の1、ドイツや中国の半分に過ぎない。これは、日本企業が技術導入そのものではなく、成果創出と測定の仕組みを欠いていることを示唆している。
要するに、AIは導入すること自体が目的ではなく、明確な事業課題を設定し、その解決にどう貢献するかを定量的に測定できる体制がなければ意味を持たない。経営企画部門にとって重要なのは、無料ツールの利用にとどまらず、戦略的投資を通じてAIを企業成長の推進力へと転換することである。
爆発的に拡大する日本のAI市場と投資の二極化
日本のAI市場は急拡大を続ける一方で、その投資姿勢は明確に二極化している。IDC Japanによると2024年の国内AI市場規模は1兆3,412億円であり、2029年には約3.1倍の4兆1,873億円に到達する見込みである。矢野経済研究所や富士キメラ総研も同様の成長予測を示しており、AIは今後の産業競争力を左右する中核分野と位置づけられている。
市場拡大の裏側では、AIに積極的に投資する企業と、無料ツールに依存する企業の格差が顕著になっている。矢野経済研究所のアンケート調査では、生成AIを導入済みの企業25.8%のうち、約40%が年間利用料0円の無料プランを使用している。この数字は、AIを単なる便利ツールとして扱う層と、経営の中核戦略に位置づける層の明確な分断を物語る。
具体的な成果を上げているのは、戦略的にAIを導入した先進企業である。パナソニックコネクトは年間18.6万時間の削減を達成し、ソフトバンクはAI活用で創出したリソースを新規事業に投資することで成長を加速させた。これらの事例に共通するのは、導入効果を時間やコストといった定量的な指標で測定し、経営戦略と直結させている点である。
一方で、無料ツールの試用に終始する企業は、生産性向上や新規事業創出といった本質的な成果を得られない。これが「二極化の罠」である。AIを基盤とする次世代事業環境において、この差は企業間競争力を決定的に左右する。
まとめると、AI市場の拡大は全企業に平等な機会を与えるわけではない。むしろ、戦略的に投資し活用できる企業のみが競争優位を築き、そうでない企業は淘汰される可能性が高い。経営企画部門に求められるのは、場当たり的な導入ではなく、ROIを徹底的に測定し、事業成果と直結させる明確な投資戦略である。
| 指標 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 2024年国内AI市場規模 | 1兆3,412億円 | IDC Japan |
| 2029年国内AI市場規模予測 | 4兆1,873億円 | IDC Japan |
| 生成AI導入企業割合 | 25.8% | 矢野経済研究所 |
| 無料プラン利用率 | 約40% | 矢野経済研究所 |
このように、日本のAI市場は拡大と二極化という二つの顔を持ち、経営企画の在り方を根本から問い直している。
AIエージェント台頭が企画業務を再定義する

2025年、経営企画部門におけるAIの役割は従来の「支援ツール」から「自律的に業務を遂行するエージェント」へと質的に転換している。ガートナーや富士キメラ総研は、この「エージェンティックAI」を最重要技術トレンドと位置づけており、今後数年で標準的な存在になると予測している。従来型のAIチャットボットが受動的に質問へ答えるのに対し、AIエージェントは目標を与えられるとタスクを分解し、情報収集・分析・レポート作成までを自律的に遂行する。この進化は企画業務を根底から再定義するものである。
具体的な利用シーンとして、競合戦略の調査を挙げられる。従来はアナリストが数週間かけて調査していた業務を、AIエージェントは数時間で完了させることが可能である。さらに複数のAIエージェントを組み合わせれば、市場動向分析、財務シミュレーション、リスク評価といったタスクを同時並行で実行できる。経営企画担当者は、情報収集に時間を費やすのではなく、AIエージェントが生成したアウトプットを評価し、意思決定に直結する洞察を抽出することに集中できる。
この変化を支えるのは、マルチモーダルAIの進化である。最新の基盤モデルであるGPT-4oやGeminiはテキストだけでなく、画像や音声、表データを統合的に処理できる。例えば会議の録画データから議事録を生成し、その要約を提示すると同時に、発言内容のセンチメントを解析することも可能である。これにより、従来は分断されていたデータソースが統合され、意思決定の速度と精度が飛躍的に向上する。
さらに、PoC疲れの克服も重要なテーマである。PwCの調査では、日本企業でAI導入に期待以上の効果を実感している割合は米国の4分の1、欧州主要国の半分に過ぎない。この背景には、実験に終始してROIを可視化できていないことがある。AIエージェントは、その成果を削減時間やコスト削減額といった具体的な数値に直結させやすく、経営層を納得させる材料となりうる。
要するに、AIエージェントの台頭は企画業務を「実務の遂行」から「AIを指揮する監督」へと変える。今後の企画担当者に求められるスキルは、良質なプロンプト設計、AIの成果を批判的に評価する能力、そして複数のAIをオーケストレーションする力である。
市場・競合リサーチを革新するAIツール群
市場と競合の動向を把握するスピードと精度は、経営企画部門の競争力を左右する。AIの進化により、この領域のリサーチは従来の手作業中心から、リアルタイムかつ自動化されたプロセスへと進化している。
代表的なツールの一つがPerplexity AIである。ユーザーが自然言語で質問を入力すると、Web上の信頼性ある情報源を横断的に検索し、根拠付きの回答を提示する。各情報の出典が明示されるため、リサーチの信頼性を担保しつつ時間を大幅に削減できる点が強みである。法人向けプランではセキュリティ機能も強化されており、企業利用に適している。
また、競合分析の定番であるSimilarwebやSemrushもAIとの連携で進化している。Similarwebは競合サイトの流入経路、滞在時間、検索キーワードを詳細に把握でき、月額125ドルから利用可能である。SemrushはSEO、広告、SNSを横断的に分析するオールインワンプラットフォームであり、コンテンツ戦略や広告予算の最適化に不可欠なツールとして広く導入されている。
さらに、日本発のFeloは検索結果からスライドやマインドマップを自動生成する独自機能を備える。リサーチから資料作成までのプロセスをシームレスに結びつけ、企画担当者の作業時間を大幅に削減する。
以下の表は主要リサーチツールの特徴をまとめたものである。
| ツール名 | 主な機能 | 価格帯 | 日本語対応 | 活用シーン |
|---|---|---|---|---|
| Perplexity AI | 出典明示付き対話型検索 | $40/月 | 高精度 | 高信頼の一次情報収集 |
| Similarweb | トラフィック・キーワード分析 | $125/月〜 | 完全対応 | 競合ベンチマーク |
| Semrush | SEO・広告・SNS統合分析 | $139.95/月〜 | 完全対応 | コンテンツ戦略立案 |
| Felo | 検索から自動スライド生成 | 無料〜 | 完全対応 | レポート作成効率化 |
これらのツールは単体でも有用だが、生成AIとの組み合わせで真価を発揮する。例えば、Semrushで得たキーワードデータをClaudeに入力し「競合の戦略的優先事項を推定せよ」と指示すれば、単なるデータ列挙から具体的な示唆を導き出せる。
市場・競合リサーチは今後、AIエージェントと専門ツールを組み合わせることで「アナリスト・コパイロット」としての環境を実現する。つまり、AIは人間の分析作業を補助する段階を超え、戦略的示唆を共に創出するパートナーとなりつつあるのである。
要約・示唆生成で意思決定を加速させる最新技術

経営企画部門が日々直面する最大の課題の一つは、膨大な情報を短時間で処理し、経営に直結する意思決定を支えることである。市場調査レポートや学術論文、社内議事録といった非構造化データを人手で分析することは限界があり、ここにAIによる要約・示唆生成技術が大きな価値をもたらす。
代表的な事例として東京大学松尾研究室発のELYZA DIGESTがある。このツールは自然で論理的な三行要約を瞬時に生成する能力を持ち、日本語の文脈を正確に把握する点で評価が高い。さらに、Nottaのような会議録支援ツールは音声を自動で文字起こしし、要約を作成することで議事録作成の負担を劇的に軽減している。
加えて、Anthropic社のClaudeは20万トークンを超える大規模コンテキスト処理が可能であり、数十ページに及ぶ事業計画書や市場調査を丸ごと解析し、要約や分析を提示できる。これにより従来は数日を要した分析が数時間に短縮される。
以下は代表的な要約・示唆生成ツールの比較である。
| ツール名 | 主な特徴 | 活用領域 |
|---|---|---|
| ELYZA DIGEST | 高精度三行要約、日本語特化 | ニュース・レポート要約 |
| Notta | 音声文字起こしと要約 | 会議・インタビュー記録 |
| Claude | 長文解析、広大なコンテキスト処理 | 事業計画・研究資料 |
重要なのは、これらの技術が単なる要約に留まらず、示唆生成を通じて戦略的意思決定を加速させる点である。例えば、競合レポートの要約から「次の四半期で市場シェア拡大を狙う分野」を推定し、投資判断に直結させることが可能になる。
つまり、要約・示唆生成ツールは経営企画担当者を情報処理の作業から解放し、より創造的かつ戦略的な業務に集中させる。今後の競争環境において、これらの技術の活用度合いが意思決定スピードと企業の成長力を左右することは間違いない。
事業計画立案を効率化する特化型AIと汎用LLMの役割
経営企画の中核業務である事業計画立案においても、AIは強力な支援者となっている。近年は目的特化型AIと汎用LLMがそれぞれの強みを発揮し、相互補完的に活用されるケースが増えている。
Franca AIはその代表例であり、日本国内の補助金・融資申請に特化した事業計画書作成支援SaaSである。市場・競合・リスク分析を半自動で行い、実務に即した計画書を生成する。専門家監修による高精度な構成と文章は、資金調達の現場で高い評価を受けている。
一方、GammaやNotion AIはプレゼン資料やドキュメント作成を効率化する。Gammaはデザイン性の高いスライドを自動生成し、Notion AIはブレインストーミングから文書化までを一気通貫で支援する。これにより企画担当者は内容構築に集中できる環境を得られる。
さらに、ChatGPTやClaude、Geminiといった汎用LLMは、幅広い場面で戦略的パートナーとして機能する。ChatGPTはアイデア創出や市場予測のドラフトに強みを持ち、Claudeは長文処理や比較分析に適する。GeminiはGoogle検索やWorkspaceとの連携により、最新データに基づいた計画立案を支援する。
| AI種別 | 代表ツール | 強み | 活用領域 |
|---|---|---|---|
| 特化型AI | Franca AI | 資金調達計画、補助金申請 | 中小企業・新規事業 |
| 汎用LLM | ChatGPT、Claude、Gemini | 幅広い企画支援 | 戦略立案、データ分析 |
| 資料作成支援 | Gamma、Notion AI | デザイン性、共同編集 | 提案資料・会議資料 |
特化型AIは実務ニーズに即した高精度な支援を提供し、汎用LLMは企画全般に柔軟性をもたらす。この両者を組み合わせることで、事業計画立案のスピードと質を大幅に向上できる。
要するに、事業計画立案においては「特化型AIで基盤を固め、汎用LLMで広がりを持たせる」ことが最適解である。こうしたハイブリッド活用こそが、AI時代の経営企画部門に求められる新しい戦略である。
大企業から中小企業まで広がる導入実践事例

AI活用は一部の先進的な大企業だけでなく、中堅・中小企業やスタートアップにまで浸透している。そのアプローチは企業規模や目的によって異なるが、共通しているのは業務効率化と新規価値創出の両立である。
大企業の代表例としてパナソニックコネクトが挙げられる。同社は全社員約1.2万人に社内AIアシスタントを展開し、年間18.6万時間の業務時間を削減した。これは単なる効率化にとどまらず、削減時間を金額換算することで経営層にROIを明確に示し、全社的な導入を推進した点が注目される。ソフトバンクはAIとRPAを組み合わせ、約4,500人月相当の業務時間を創出し、そのリソースを新規事業開発に再投資することで、成長戦略の中核にAIを位置づけた。
一方、中堅・中小企業も補助金を活用してAIを導入している。飲食業ではセルフオーダーシステムを導入し、注文データ分析を基にメニュー改善を実現した事例がある。建設業では複数のシステムを統合するAI対応クラウドソリューションを採用し、年間120万円のコスト削減と利益率の改善を達成した。
スタートアップはさらに先鋭的である。ELYZAは日本語特化型の大規模言語モデルを開発し、国内外の研究・実務に広く活用されている。Laboro.AIは産業別のカスタムAIを開発し、製造業や医療業界の課題解決に寄与している。また、世界的に注目を集めるSakana AIは独自のモデル構築で国際競争力を高めている。
こうした多様な事例に共通するのは、AI導入を技術的チャレンジとしてではなく、具体的な経営課題の解決手段として活用している点である。特に「削減時間」「コスト削減額」「新規売上」などの定量的指標を設定し、その成果を組織全体で共有することが導入成功の鍵となっている。
2026年以降の展望と日本企業への具体的提言
AI活用は2025年に実証段階を脱し、2026年以降は本格的な事業変革の局面を迎える。ガートナーの予測によれば、生成AIソリューションの40%がマルチモーダル化し、複雑な戦略立案を支援するAIエージェントが普及するとされている。日本企業が国際競争で優位を築くためには、この流れを的確に捉える必要がある。
特に注目すべきは、自律型AIエージェントの役割である。今後の経営企画担当者はデータ収集や資料作成を担うのではなく、複数のAIエージェントをオーケストレーションする指揮者へと変化する。そのためには、AIに与えるべき目標を的確に設定し、成果を評価・監督するスキルが求められる。
また、ROI最大化のためには段階的なフレームワークが不可欠である。まずは議事録自動要約など短期的に成果が見込める領域で投資を正当化し、次に財務モデリングや需要予測といった中核機能にAIを統合する。最終的には業界固有の課題解決に特化した独自AIを構築し、模倣困難な競争優位を確立する必要がある。
加えて、日本企業にとってAIリテラシー教育は避けて通れない。全社員が良質なプロンプト作成やAI成果の評価方法を理解することが、組織全体のAI活用レベルを底上げする。さらに、社内にCoE(Center of Excellence)を設立し、成功事例や倫理ガイドラインを集約・横展開することで、ガバナンスとスピードの両立を図るべきである。
最後に、AI戦略の基盤は「ハイブリッドAIスタック」である。汎用LLMを基盤としつつ、SimilarwebやFranca AIのような特化型ツールを組み合わせ、さらにAIエージェントで全体を連携させる。この多層的構成こそが、日本企業が次世代の知的生産性を最大化し、世界市場で優位を築くための道筋である。

