2025年、日本企業の広報・IR業務はAIツールの浸透によって大きな転換期を迎えている。従来、プレスリリースの作成や決算要約、株主総会の想定問答集作成、さらにはSNS運用といった業務は、担当者の経験や勘、膨大な時間に依存してきた。しかし現在では、AIが文章を生成し、掲載可能性をスコア化し、投資家の質問傾向を分析するなど、業務を定量的かつ戦略的に支援する段階に入っている。
市場調査によれば、国内広報部門における生成AIの導入率は37.2%に留まる一方、大企業を中心に活用は拡大傾向にある。リソース不足を補う「一人広報」にとってはAIが創造性の壁打ち相手となり、大企業にとってはグローバル展開や投資家対応を支える戦略的インフラとなりつつある。
一方で、AI導入には「正確性」「機密性」「知財リスク」といった課題も伴い、パートナー企業の経営不祥事によるツール提供中止といったリスクも現実化している。今後の成長を見据えるならば、単なる効率化を超え、AIを戦略的パートナーとしてどう組み込むかが、広報・IR部門の競争力を左右する重要なテーマとなる。
広報・IR領域におけるAI活用の急拡大と市場背景

2025年、日本企業の広報・IR業務におけるAI導入は急速に拡大している。従来は文章生成や情報整理に限定されていたが、現在ではプレスリリースのメディア掲載可能性をスコア化する機能や、投資家との対話データを戦略インテリジェンスに変換する機能が登場し、企業コミュニケーションを定量的に最適化する時代に突入している。
市場規模の明確な統計は存在しないものの、関連する広告市場やグローバルな広報ツール市場の動向から潜在成長力を測ることができる。矢野経済研究所の試算によれば、国内インターネット広告市場は2027年度に4兆円を突破すると予測されている。また、Grand View Researchは世界の広報ツール市場が2030年までに133億3,000万ドル規模へ拡大し、年平均成長率は10.9%に達すると示している。これらの数値は、広報・IR分野においてもAI関連投資が加速することを裏付けている。
さらに注目すべきは、広報・IRにおけるAI導入が「自動化(Automation)」から「戦略的拡張(Augmentation)」へと移行している点である。初期のAIは単純に文章を生成するのみであったが、現在のツールはニュース価値やメディアに取り上げられる確率を考慮した高品質な原稿生成を実現している。
この背景を理解するうえで、日本広報学会の調査は重要である。同調査によれば、国内の広報部門における生成AIの導入率は37.2%にとどまり、特に資本金1億円以上の企業で44.8%、1億円未満では31.6%と企業規模で差が出ている。大企業ではグローバル展開や多様な投資家対応にAIを活用する動きが目立つ一方で、中小企業では「一人広報」が創造性補助のためにAIを利用するケースが多い。実際、一人広報の72.5%が生成AIをアイデア出しや壁打ち相手として活用していることが明らかになっている。
このように、AIは企業規模や目的に応じて異なる形で導入されているが、共通するのは人的リソース不足を補い、成果を最大化する戦略的パートナーとしての役割を担いつつある点である。今後もこの潮流は続き、2026年以降はより高度に統合されたAIプラットフォームが市場を席巻することが予想される。
プレスリリース作成を変えるAIの進化と主要プレイヤー
広報業務の中心であるプレスリリース作成は、AI活用が最も進んでいる分野である。近年は、従来の「文章を早く書く」だけでなく、メディア掲載を科学的に高めることを目的とした高度な機能を持つツールが登場している。
代表的なプレイヤーの一つが、株式会社メタリアルの「広報AI」である。このツールは特許取得済みの「プレスリリース採点機能」を備え、作成したリリースがメディアに掲載される可能性を6つの基準で評価する。導入企業の報告によれば、従来3時間かかっていたリリース作成が15分で完了し、工数を92%削減する成果を上げた。さらに、複数のAIエージェントが「仮想的な雑談」を行い、共感性や多角的視点を盛り込んだ自然な文章を生成するアーキテクチャを採用している点も特徴的である。
一方で、効率化を最優先する企業向けには、JAPAN AI社の「プレスリリース作成エージェント」が存在する。このツールは作業時間を従来の10時間から2〜3時間に短縮するなど、大幅な効率化を実現している。また、Toolpodsが提供する「AIプレスリリース作成支援」は、ブラウザ内で完結し外部にデータを送信しない設計を特徴とし、セキュリティを重視する企業から支持を集めている。
さらに、無料で利用できる「プレスくん」や「AIプレスリリースX」などのフリーミアムツールも登場し、NPOや自治体、スタートアップなど予算が限られる組織にもAI活用の裾野を広げている。
以下は主要ツールの比較である。
| ツール名 | 提供元 | 主な機能 | 差別化要因 | 対象ユーザー |
|---|---|---|---|---|
| 広報AI | 株式会社メタリアル | 高品質生成、掲載可能性スコア化 | 特許取得済み採点機能、人間らしい文章生成 | 中小〜大企業 |
| プレスリリース作成エージェント | JAPAN AI株式会社 | 作業時間の大幅削減 | 自律型エージェントによる遂行 | 効率重視企業 |
| AIプレスリリース作成支援 | Toolpods | ブラウザ内処理 | 外部送信なしの高セキュリティ | 情報保護重視企業 |
| プレスくん | 日本DX地域創生応援団 | 無料で基本リリース生成 | 公共性・低コスト | NPO、自治体 |
| AIプレスリリースX | 不明 | 雛形生成 | 無料・軽量性 | 小規模チーム |
このように、プレスリリース作成AIは「成果最大化」「効率化」「セキュリティ」「アクセシビリティ」といった切り口で多様に進化している。企業は自社の目的や体制に合わせ、最適なツールを選び組み合わせることが競争力強化の鍵となる。特に2025年以降は、生成から配信、効果測定までを統合するプラットフォームが拡大し、単一機能型ツールとの差別化がさらに進むと考えられる。
重要局面を支えるIRコミュニケーションAIの最新事例

企業の将来を左右するIR活動において、AIの活用は加速度的に広がっている。特に株主総会や決算説明会といった重要局面では、正確性とスピードを兼ね備えたAIツールが担当者を支える存在となっている。
代表的な事例として、エクサウィザーズが提供する「exaBase IRアシスタント」が挙げられる。このツールは、投資家との面談議事録を自動生成し、従来1時間以上を要した業務を5分程度に短縮した実績を持つ。さらに、投資家ごとの質問傾向を蓄積・分析するデータベース機能を備え、従来は属人的に管理されていた情報を組織的な資産に変換している。光フードサービスやGENDAといった導入企業は、作業の効率化にとどまらず、本質的な投資家対応に時間を割けるようになったと評価している。
一方で、AIツール導入のリスクを示す事例も存在する。オルツとイー・アソシエイツが共同開発した「smartQA」は、株主総会の想定問答作成に特化していたが、開発パートナー企業の粉飾決算疑惑を受けて販売が中止された。この事例は、技術的な優秀さだけでなく、ベンダーの経営健全性やガバナンスがサービス継続性に直結することを市場に強く認識させた。
さらに、MUTUAL社が開発した「IR QA bot(β版)」は、投資家が企業ウェブサイト上で直接質問できる仕組みを導入している。これにより、従来は人手が必要であった問い合わせ対応が大幅に効率化され、担当者は戦略的な業務に集中できるようになった。
AI導入により、IR部門は単なる情報開示の窓口から、投資家インサイトを経営陣へフィードバックする戦略的インテリジェンス部門へと進化している。ただし、誤情報生成やベンダーリスクといった課題がある以上、導入には徹底したデューデリジェンスとリスク管理が欠かせない。
決算要約と情報発信におけるAI活用の可能性と限界
決算情報は正確性が最優先される領域であるが、ここでもAIの活用が進んでいる。2025年2月、Yahoo!ファイナンスは決算短信を生成AIで要約する機能をβ版として導入した。AIは「主な事業セグメント」「業績見通し」「株主還元」などの重要項目を抽出し、個人投資家が短時間で理解できるように支援する。基盤にはAWSの「Amazon Bedrock」を通じたAnthropic社のClaudeモデルが採用され、商用サービスとしての信頼性が重視されている。
しかし、このサービスは同時に免責事項を強調している。生成AIの性質上、誤情報を含む可能性があるため、利用者は必ず決算短信全文を確認する必要があると明記されている。訂正開示が要約に反映されない点も注意点であり、AIが「補助ツール」に留まっている現状を示している。
一方で、企業側もAIを活用した新しい決算コミュニケーションに挑戦している。バトンズはAI-OCRを用いて最大10期分の決算書を自動読み取りし、比較資料を生成する機能を提供開始した。非構造化データを分析可能な形式に変換することで、投資家にとって理解しやすい情報提供を実現している。また、キャスターは決算短信と代表者の顔写真を活用し、AIが音声と映像を合成した「94秒間の決算説明動画」を制作する試みを行った。これは、従来のテキスト中心の開示から、動画を活用したリッチコンテンツによる多層的な情報伝達への移行を示すものである。
海外ではさらに進んだ活用が進んでいる。KoyfinやAlphaSenseといったツールは決算説明会の書き起こしをもとに、経営陣の発言を感情分析し、投資家が注目すべき質問や回答を自動で抽出する機能を持つ。こうした機能は、将来的に日本市場でも導入される可能性が高い。
ただし、現状のAIには依然として「ハルシネーション」のリスクが存在する。決算要約は最終的に人間が確認するプロセスを必ず組み込まなければならない。AIは情報を整理し可視化する強力な手段であるが、最終的な責任を担うのは人間であるという基本を忘れてはならない。
SNS運用支援AIによるエンゲージメント強化の新潮流

企業が消費者や投資家とつながるために、SNSは不可欠なチャネルとなった。その一方で、投稿内容の企画から作成、効果測定、さらにはユーザーとの対話までを一貫して担うことは膨大な負担を伴う。ここにAIが導入されることで、エンゲージメントを高めながら効率化を実現する新たな潮流が広がっている。
中小企業や地方団体向けには、株式会社meguruが提供する「投稿つくるさん」が注目を集めている。キーワードやURLを入力するだけで投稿文を自動生成し、さらに「やさしい」「親しみやすい」といったトーン設定や効果的なハッシュタグ提案まで可能である。価格は月額2,200円と低く、初回は1投稿無料という仕組みも導入障壁を下げている。地域の小規模事業者にとって、SNS運用の民主化を進める存在となりつつある。
一方で、グローバル展開を視野に入れる大企業は、より高度な分析・統合機能を備えたプラットフォームを求めている。Statusbrewはその代表格であり、16種類以上のチャネルを一元管理できるだけでなく、AIがブランドトーンに合わせた投稿文生成、コメント返信案、センチメント分析まで担う。さらに、炎上リスクやスパムを検知する機能を備え、24時間体制のリスク管理を可能にしている。
加えて、Moribus NaviはInstagram特化型ツールとして、最適なハッシュタグ選定をAIが自動で行う機能を提供し、リーチ拡大を科学的に支援する。EmbedSocialはUGC(ユーザー生成コンテンツ)をAIが分析し、数値的指標だけでなく「映え」といったビジュアル的魅力を考慮したコンテンツ選別を可能にしている。
このように、SNS支援AI市場はユーザー規模や目的ごとにセグメント化されている。小規模事業者には低コストかつ直感的なツール、大企業にはリスク管理と戦略立案を含む統合型プラットフォームが求められる。企業が最適なAIスタックを組み合わせることこそが、エンゲージメント強化の実効性を高める鍵となる。
AI導入におけるリスク管理とベンダーデューデリジェンスの重要性
AI導入が急速に進む一方で、その裏側には見過ごせないリスクが存在する。特に広報・IR領域では情報の正確性や機密性が最重要であり、適切なリスク管理を怠れば企業価値そのものを揺るがす事態につながりかねない。
日本広報学会の調査によれば、AI導入を妨げる最大の要因は「正確性への不安」(52.1%)であり、次いで「機密性への不安」(44.6%)、「知財侵害への不安」(43.8%)が続く。こうした不安を解消するには、ツール選定時にセキュリティ仕様を徹底的に確認することが不可欠である。例えば、Toolpodsの「AIプレスリリース作成支援」はブラウザ内で処理を完結させ、外部サーバーにデータを送信しない設計を採用しており、機密性を重視する企業に評価されている。
また、AIツールそのものの品質だけではなく、提供企業の経営基盤も重要である。実際に「smartQA」は高機能なIR支援ツールとして注目を浴びたが、開発パートナーの粉飾決算疑惑により販売中止となった。この出来事は、ベンダーの財務健全性やガバナンスがサービス継続性に直結することを如実に示している。
リスク管理の枠組みとしては以下の観点が求められる。
- 正確性の担保:AI生成内容は必ず人間が最終確認を行う
- 機密性の確保:データの保存・処理方法を精査する
- 知財リスクへの備え:生成物の権利関係を明確化する
- ベンダーリスクの評価:財務、ガバナンス、開発パートナー体制を確認する
加えて、投資対効果を測定することも欠かせない。例えば、「広報AI」が達成した92%の工数削減や、「exaBase IRアシスタント」が1時間の作業を5分に短縮したといった成果は、導入判断の明確なベンチマークとなる。
最終的に企業がAI導入で成功するか否かは、技術選定以上にリスク管理とデューデリジェンスの徹底度に左右される。華々しい機能の裏に潜むリスクを正しく見極めることが、AI時代の広報・IR戦略を安定的に運営するための必須条件である。
2026年に向けた広報・IR戦略の展望とAIエージェントの台頭
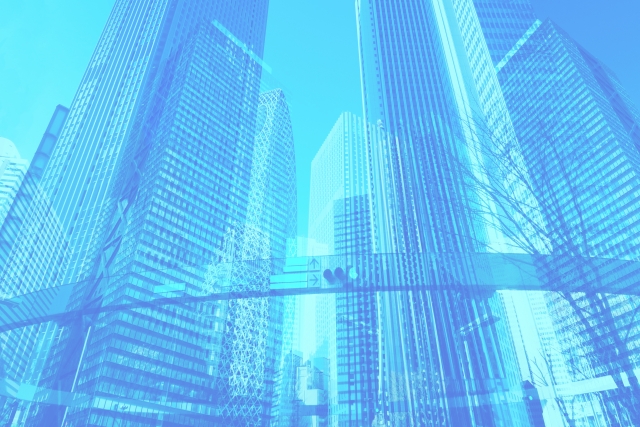
2025年は広報・IR領域におけるAI活用が加速した一年であり、その進化は2026年以降にさらに大きな変革をもたらすことが予測されている。特に注目すべきは、AIが「アシスタント」から「エージェント」へと進化し、自律的に業務を遂行する時代が始まろうとしている点である。
これまでのAIは人間の指示を受け、文章生成やデータ整理といった補助的な役割にとどまってきた。しかし次世代AIエージェントは、複数ステップから成る業務を自動で遂行する能力を持ち始めている。例えば、プレスリリースの内容を分析し、ターゲットメディアのリストを抽出したうえで、それぞれのメディアの論調に応じた個別ピッチメールを生成し送信する、といった一連のプロセスを一気通貫で処理できる可能性が高まっている。
同様に、SNS運用においてもAIエージェントは人間の介在を大幅に減らすことが期待される。投稿コンテンツの自動生成だけでなく、リアルタイムのエンゲージメント分析を行い、最も効果的な時間帯に投稿を自動最適化することが現実化しつつある。これにより、担当者は個別のタスク遂行から解放され、AIの戦略設定や監督、成果検証といったより高度なマネジメント業務に集中できる。
2026年に向けた展望として、広報・IR戦略の鍵は以下の3点に集約される。
- 自律的AIエージェントの活用範囲拡大:単純作業の自動化を超え、戦略的業務の一部を担うようになる
- ヒューマン・イン・ザ・ループの再定義:正確性が求められる決算要約やIR回答では、最終確認としての人間の役割が不可欠であり、その責任範囲を再整理する必要がある
- ガバナンスと倫理の強化:AIが戦略的意思決定に近づくほど、情報の透明性と責任所在を明確にする体制が求められる
AIエージェント時代の到来は、広報・IR担当者の役割を大きく変える。従来の「手を動かす人材」から、「AIを監督し成果を最大化する戦略マネージャー」への転換が求められるのである。この変化に対応できるか否かが、2026年以降の企業競争力を左右する決定的要素になるだろう。

