2025年、日本の企業データ戦略は大きな転換点を迎えている。生成AIの急速な普及に伴い、AIモデルが要求する膨大で多様なデータをいかに確保するかが喫緊の課題となる一方で、改正個人情報保護法の施行により、個人情報を含むデータ活用にはこれまで以上に厳格な規制が求められる。この二つの潮流が交差する中、合成データ生成とPII(個人識別情報)除去という二つの技術が、日本企業にとって新たな武器として注目を集めている。
合成データは実世界のデータ特性を保持しつつ、個人情報を含まない人工データを生成することで、AI開発に必要なデータ不足や偏りの課題を解決する。一方、PII除去は匿名化や差分プライバシーといった技術を駆使し、安全なデータ共有や外部連携を可能にする。両者を組み合わせることで、プライバシーを守りながらイノベーションを加速する強力な「データバリューチェーン」が形成されるのである。
本記事では、合成データとPII除去の最新技術、日本市場の成長予測、主要ベンダーの比較分析、そして金融・医療・自動車・小売といった産業における具体的な活用事例を詳しく解説する。さらに2026年以降を見据えた国家戦略と企業への提言を提示し、日本がデータ駆動型経済で競争優位を確立するための道筋を探る。
日本のデータ戦略転換点:生成AI需要とプライバシー規制の交差点
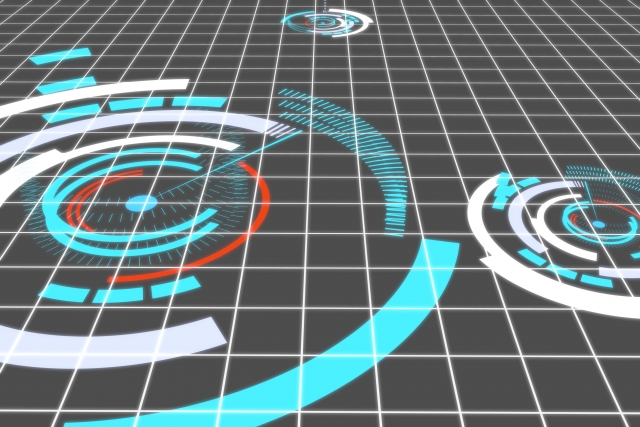
2025年、日本企業はAI活用の加速と個人情報保護の厳格化という二つの潮流に直面している。生成AIの進化に伴い、大規模で多様なデータがかつてないほど必要とされる一方で、改正個人情報保護法によりデータ利用の規制は強まっている。この矛盾の中で企業は、データを攻めの武器として使いこなす戦略的転換を迫られている。
富士キメラ総研によれば、国内の生成AI市場は2024年度に4,291億円へと成長し、2028年度には1兆7,394億円に達する見通しである。これは2023年度比で12.3倍に相当し、市場の主役が生成AIに移りつつあることを示している。一方で、個人情報保護委員会が主導する2025年改正では、統計やAI開発目的であれば一定条件下で本人同意なしに利用可能とする制度が検討されている。ただし、この制度を利用するには企業側に高度なデータガバナンスが求められる。
こうした環境下で浮上するのが、合成データとPII除去技術である。合成データは個人情報を含まない人工データを生成し、実世界データの制約を克服する。一方、PII除去は匿名化や差分プライバシーを活用し、法的リスクを抑えながらデータを共有できる基盤を構築する。両者は補完関係にあり、組み合わせることで強固なデータ戦略が形成される。
- AIモデルに必要な大量データの確保
- 厳格化する法規制との両立
- 合成データとPII除去の相乗効果
この三つを柱に据えた企業戦略こそが、生成AI時代における競争優位の源泉となる。今やデータ戦略は防御から攻めへと変革し、法規制を遵守しながらイノベーションを加速させる実行力が問われている。
AIデータジレンマを解決する合成データの可能性
AI開発の現場では「AIデータジレンマ」と呼ばれる課題が存在する。AIは学習に膨大なデータを必要とするが、そのデータは収集が困難であり、個人情報を含む場合には利用に制約が課される。この二律背反を解決する最も有望な手段が合成データである。
合成データは、実世界のデータの統計的特徴を保持しつつ、個人を特定する情報を含まない人工データである。特に希少な事例や不均衡なデータ分布を補正する「データバランシング」に強みを発揮する。例えば、金融分野では不正取引のデータが全体のわずか数%しか存在しないため、AIモデルは正常取引に偏った学習をしがちである。合成データを活用すれば、不正取引に似たケースを大量に生成し、モデルの検知精度を大幅に高められる。
また、自動運転分野では危険な走行シナリオを実際に収集することは現実的に不可能である。そこでシミュレーション環境を用いて、悪天候や突発的な歩行者の飛び出しなど無数のシナリオを合成データとして作成することで、AIを強靭に訓練できる。
表に整理すると以下のようになる。
| 課題 | 合成データによる解決策 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| データ不足 | オンデマンド生成 | コスト削減、開発スピード向上 |
| データ偏り | 希少ケースの増強 | モデルの公平性と精度向上 |
| プライバシーリスク | 個人情報を含まない生成 | 法規制遵守と安心な活用 |
**合成データの最大の価値は、実世界で入手困難な「未知のデータ」を創造できる点にある。**これは、AIが過去だけでなく未来の可能性からも学習できることを意味する。生成AIの普及と法規制の強化が進む今、合成データは単なる代替ではなく、企業の競争戦略を根底から変革する中核技術となっている。
PII除去技術がもたらす信頼とデータ連携の基盤

AIやデータ活用を推進する上で、最も大きな障壁となるのが個人識別情報(PII)の取り扱いである。近年はデータ漏洩事件が頻発し、企業の信頼性を揺るがす事例が後を絶たない。そのためPIIの適切な除去は、単なる法的義務ではなく、企業価値を守るための根幹的要素となっている。
PII除去技術は、単純なマスキングにとどまらず、匿名化、仮名化、トークン化、さらには差分プライバシーなどの高度な手法が導入されている。例えば日立ソリューションズやNECの製品は「k-匿名性」に基づき、同じ属性を持つ複数人のデータを統合して個人を特定できない状態を保証する。この仕組みにより、特定の個人がデータから再識別されるリスクを1/k以下に抑えられる。
またGoogle CloudのDLP(Data Loss Prevention)は、テキストや画像から機密情報を自動的に検出し、適切に匿名化する機能を備えている。これにより金融や医療といった厳格な業界規制を受ける分野でも、安全にデータを共有することが可能になる。
箇条書きで整理すると以下の通りである。
- マスキング:氏名や電話番号を記号で置き換える
- 仮名化:一意のIDに変換し、元データとの紐付けを制限
- k-匿名性:同一グループ化により特定を防止
- 差分プライバシー:統計的に個人を識別できないノイズを付加
**PII除去は「防御策」ではなく、データ活用の前提条件である。**適切に処理されたデータは、研究機関や外部パートナーとの連携を容易にし、社内の部門間での共有も可能にする。これは、サイロ化されたデータを解放し、協調的な価値創造を促進するための基盤である。
特に日本では、2025年改正個人情報保護法のもとで「匿名加工情報」や「仮名加工情報」の活用が強調される見通しである。PII除去技術の精度と適用範囲が、企業のデータ戦略の成否を左右することになるだろう。
コア技術の全貌:GAN・差分プライバシー・k匿名性の実力と課題
合成データとPII除去を支えるのは、AIとプライバシー保護の両立を可能にする先進的な技術群である。これらの技術の特性を理解することは、企業がユースケースごとに最適な選択を行うために不可欠である。
代表的な生成モデルとして、敵対的生成ネットワーク(GAN)が挙げられる。GANは「生成者」と「識別者」が競い合いながら学習し、最終的に本物と見分けがつかないほど精巧なデータを生成する。特に画像や複雑な表形式データの生成で高い性能を発揮しており、MOSTLY AIやTonic.aiといった海外ベンダーが採用している。ただし「モード崩壊」と呼ばれる多様性の欠如が課題とされる。
一方で、プライバシー保護の分野では差分プライバシーが注目されている。これは「個人が含まれても結果がほとんど変わらない」状態を保証する数学的枠組みであり、分析結果に意図的にノイズを加えることで再識別リスクを防ぐ。GoogleやAppleもすでに導入しており、日本でも研究や実装が進みつつある。
表にまとめると以下のようになる。
| 技術 | 特徴 | 強み | 課題 |
|---|---|---|---|
| GAN | 本物に近いデータ生成 | 高忠実度、応用範囲広い | モード崩壊リスク |
| k-匿名性 | グループ化で識別困難化 | 実装容易、国内で普及 | 均一性攻撃に脆弱 |
| 差分プライバシー | ノイズ付加で統計的保証 | 数学的に堅牢 | 有用性と保護のトレードオフ |
さらに、k-匿名性は日立やNECの国内製品に採用されており、規制準拠と導入容易性が強みである。しかし一部の攻撃手法には脆弱性が残る。一方で差分プライバシーは理論的に最も堅牢だが、ノイズを加えることでデータの精度が低下するリスクを伴う。
**企業にとって重要なのは単一技術に依存するのではなく、ユースケースやリスク許容度に応じてこれらを適切に組み合わせることである。**例えば社内テストにはk-匿名性で十分だが、外部研究機関との共有には差分プライバシーが必須となる。この柔軟な組み合わせこそが成熟したデータ戦略の証と言える。
日本市場の成長予測と2025年改正個人情報保護法のインパクト
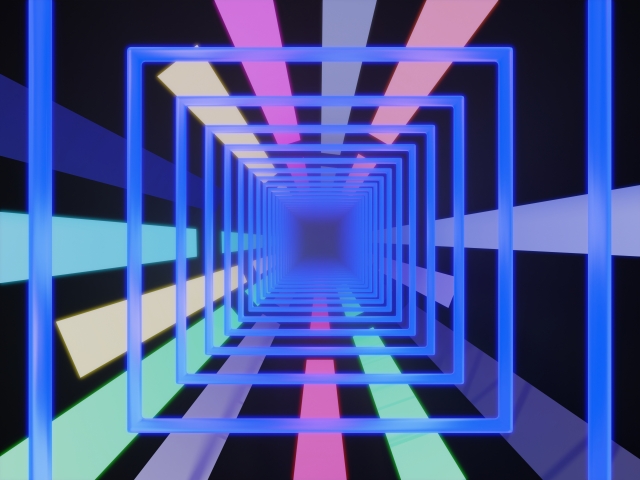
日本における合成データとPII除去市場は、AI活用の本格化と規制強化の双方を背景に急速な成長が見込まれている。富士キメラ総研の調査では、国内生成AI市場は2024年度に4,291億円に達し、2028年度には1兆7,394億円へ拡大すると予測されている。これはAI市場全体の約6割を占める規模であり、生成AI関連技術が主役の座を確立しつつあることを示している。
一方で、グローバル市場では合成データ生成が2030年に約5,200億円規模に成長するとされ、日本市場もこの潮流に乗ることは不可避である。国内の合成データ生成市場は2024年時点で約27億円規模と小さいが、2035年には約1,600億円へと拡大し、年平均成長率45%を超える予測が示されている。
こうした成長を後押しするのが2025年の改正個人情報保護法である。この改正では、AI開発や統計目的であれば一定条件下で本人同意なく個人情報を利用できる仕組みが導入される見込みだ。これは企業にとって大きな追い風となるが、その代わりに透明性確保や目的外利用の禁止といった厳格なガバナンスが求められる。
また、改正法において「匿名加工情報」や「仮名加工情報」の活用は一段と重要性を増す。単なるマスキング処理では法的要件を満たさず、規定されたガイドラインに沿った厳密な加工が必要となる。結果として、国内ベンダーが提供する匿名化ソリューションや、グローバルプラットフォームの高度な機能に対する需要は加速していく。
**法改正は企業に二つの道を提示する。**ひとつは同意緩和を活かして実データを直接利用する「高速レーン」、もうひとつは外部共有や高リスク領域における合成データ活用という「安全レーン」である。先進企業は両者を組み合わせたデュアルトラック戦略を採用し、法規制と成長機会を両立させることになるだろう。
国内外主要ベンダー比較:日立・NEC・AWS・MOSTLY AIの戦略分析
合成データとPII除去の分野では、国内大手ITベンダー、グローバルクラウド事業者、そして海外専門スタートアップがそれぞれ異なる強みを持ち、日本市場で競合している。
国内勢では日立ソリューションズ、NEC、NTTテクノクロスが代表的存在である。日立の「プライバシー情報匿名化ソリューション」やNECの「データ匿名化ソリューション」は、k-匿名性を基盤とした技術を採用し、金融や自治体など規制遵守が必須の業界で支持を集めている。国内拠点による日本語サポートや法規制への適合性が最大の強みであり、安定性を求める企業にとっては安心感のある選択肢となる。
一方で、グローバル勢はクラウド基盤を武器に拡張性と先進性で優位に立つ。AWSは「AWS Glue」にPII検出・マスキング機能を組み込み、データパイプラインに自然に統合できる環境を整えている。Google Cloudの「DLP」も同様に、テキストや画像から個人情報を自動検出し匿名化する強力な機能を提供している。これらは既存クラウドインフラを利用する企業にとってシームレスな導入が可能である。
さらに、MOSTLY AIやTonic.aiといった海外専門ベンダーは、高度なGANモデルを活用した高忠実度の合成データ生成を実現している。MOSTLY AIは「TabularARGN」と呼ばれる独自技術により、統計的忠実度を担保したデータ生成が可能であり、金融や保険の分野で注目を集める。AWSやGoogleに比べ市場シェアは小さいものの、技術的先進性と柔軟性において存在感を示している。
| ベンダー | 主な特徴 | 強み | 課題 |
|---|---|---|---|
| 日立・NEC | 国内法規制準拠、オンプレ中心 | 日本語対応、信頼性 | グローバル展開力に課題 |
| AWS・Google Cloud | クラウド統合、拡張性 | 既存基盤との親和性 | 国内商習慣への適応 |
| MOSTLY AI | 高精度合成データ | 技術革新、柔軟性 | サポート体制の限定性 |
**結局のところ、万能な解決策は存在しない。**規制遵守が最優先の基幹業務では国内ベンダーが有利であり、迅速なAI開発を志向する企業はクラウド基盤を選び、先進的なデータ活用を模索する企業は海外専門ベンダーに投資する。日本企業はこれらを組み合わせ、ユースケースに応じた最適なツールポートフォリオを構築することが競争力の鍵となる。
金融・医療・自動車・小売にみる実用事例と新しいビジネス価値

合成データとPII除去技術の真価は、抽象的な理論ではなく実際の産業応用に現れる。日本においても金融、医療、自動車、小売といった主要産業で具体的な活用事例が広がりつつある。これらの事例は単なるデータ保護手段を超え、ビジネス価値の創出に直結している。
金融業界では不正検知モデルの高度化が顕著である。横浜銀行はAIを導入し、不正調査対象口座を30〜40%削減したと報告されている。従来は個人情報が含まれる取引データを直接利用できなかったが、合成データを生成することで顧客のプライバシーを侵害することなく高精度のモデルを訓練可能になった。これにより、調査業務の効率化と信頼性向上を同時に実現している。
医療分野では、合成患者記録の利用が進んでいる。電子カルテや遺伝子情報は研究に不可欠だが、機微性の高さから活用に制約がある。合成データを用いることで、疾患の進行パターンや治療効果を再現しながらも、個々の患者を特定できない形で安全に研究が行える。富士フイルムや国立精神・神経医療研究センターが推進するAI研究の背景には、こうした技術の存在がある。
自動車業界では、自動運転AIの学習に合成データが決定的な役割を果たしている。現実には収集が困難な「エッジケース」、例えば悪天候下での歩行者飛び出しや急な障害物回避などをシミュレーション環境で生成することにより、数百万通りのシナリオをAIに学習させられる。これにより、物理的な走行テストだけでは不可能な安全性強化が実現する。
小売業界ではID-POSデータの匿名加工や合成データ化により、メーカーとの安全なデータ共有が可能になっている。さらに、特定の顧客セグメントの購買行動を模倣した合成データを活用すれば、新商品の効果検証や販促施策のシミュレーションがリスクなく行える。
**産業界の事例が示すのは、合成データの価値が単なる代替ではなく「未知のデータを創造する力」にあるという点である。**金融は潜在的な不正取引を、医療は未検証の治療効果を、自動車は未体験の走行環境を、小売は未来の購買行動を合成データから学ぶことが可能になる。これは企業が過去ではなく未来を基盤に意思決定を行うことを意味し、競争力の源泉となる。
2026年以降の展望:マルチモーダル合成データと国家戦略
今後のデータ戦略において注目されるのがマルチモーダル合成データである。これは表形式データに加え、テキスト、画像、動画、音声といった異なる形式を統合したデータセットを生成する技術である。例えば購買履歴(表データ)、商品レビュー(テキスト)、店舗内行動(映像)を組み合わせれば、顧客体験をより包括的に分析できる。これによりAIモデルは従来以上に高精度で実用性の高い結果を導き出せる。
同時に、自律的に学習・行動するAIエージェントの台頭により、合成データの役割は単なるデータ供給から「合成環境」へと進化する。製造業のロボット操作訓練、金融市場の取引シミュレーション、都市交通の最適化など、デジタルツインと呼ばれる仮想空間でAIを育成する仕組みが拡大すると考えられる。
さらに「Data-as-Code」という新しい概念も台頭している。これは合成データの生成プロセスをコードとして管理し、バージョン管理やCI/CDパイプラインに統合するアプローチである。これにより再現性と一貫性が担保され、データがソフトウェア開発ライフサイクルの一部として扱われるようになる。
日本の国家戦略との連動も無視できない。政府はG7議長国として「広島AIプロセス」を主導し、国際的なAIガバナンス形成を牽引している。東京大学の松尾豊教授も指摘するように、データ基盤の整備は国家的課題であり、合成データとPII除去はその中心的役割を担う。
**日本企業が2026年以降に取るべき行動は明確である。**第一に、全社的なデータガバナンス組織を設立し、法規制対応とイノベーション推進を両立させること。第二に、国内外のベンダーを組み合わせたツールポートフォリオを構築し、用途に応じた最適な技術を活用すること。そして第三に、PoCから着手し、短期間で成果を示すことで社内の理解と投資を拡大させることである。
合成データとPII除去は、防御のための技術から攻めのデータ戦略を実現する中核技術へと進化している。マルチモーダル化や国家戦略との連動を背景に、2026年以降の日本はデータ駆動型社会において国際競争力を確立する岐路に立っている。

