日本の情報システム部門、いわゆる情シスは、かつてない危機に直面している。人材不足は慢性的な課題として長年指摘されてきたが、2025年に入り状況は一段と深刻化し、帝国データバンクの調査では情報サービス業の正社員不足率が72.5%と全業種中で突出する結果が示された。情シス担当者の採用難は事業継続リスクに直結し、既に人手不足を理由とした倒産が過去最多を記録している。この構造的な問題に対し、経営層からはセキュリティ強化とAI活用という二大命令が突き付けられ、情シスは従来の「守り」の役割から「攻め」の戦略部門への変貌を迫られている。
同時に、AI技術は急速に進化を遂げている。市場調査によれば、国内AIOps市場は2029年度まで年平均20%以上の成長が予測され、生成AI市場も2028年度には1兆7千億円規模に拡大する見通しである。こうした背景のもと、IT資産管理、ヘルプデスク自動化、セキュリティ運用の三大領域において、最新のAIツールが次々と登場している。本記事では、国内外の導入事例や市場データを基に、情シスが直面する課題を打開する具体的なソリューションを分析し、次の一手となる戦略的示唆を提示する。
情シスを襲う人材不足と経営からの二大命令
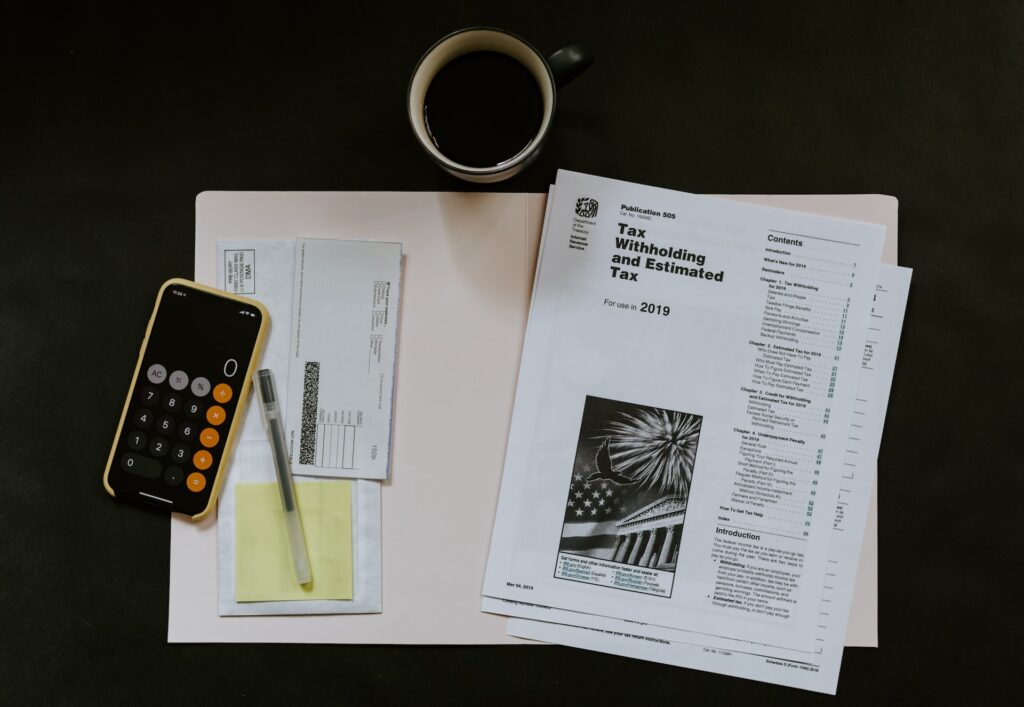
日本の情報システム部門は今、歴史的な人材不足の渦中にある。ソフトクリエイト社が2025年に実施した調査では、73.5%の企業が情シス人材不足を実感しており、4社に3社が恒常的なリソース不足に直面しているという結果が示された。この傾向は特定業界に留まらず、帝国データバンクの調査では「情報サービス」業種の正社員不足率が72.5%に達し、全業種中で最も高い水準を記録している。つまり、情シスの人材不足は一時的な問題ではなく、日本全体の構造的課題となっている。
さらに深刻なのは、この不足が事業継続そのものを脅かしている点である。2024年には人手不足倒産が過去最多を更新し、システム運用の継続性が企業の存続に直結する現実が浮き彫りになった。従来のように中途採用で人材を補充する戦略は、採用競争の激化や給与条件の制約から機能不全に陥っている。結果として、多くの企業は「外部調達」から「内部育成」へと舵を切り、32.1%の企業が社内人材のスキルアップを主要施策として掲げている。
このような状況下で、経営層から情シス部門に突き付けられた二大至上命令が「セキュリティ強化」と「AI活用」である。IDC Japanの調査によれば、情シスが経営に貢献すべき優先課題としてこの二つが上位を占めており、守りの運用部門から攻めの戦略部門へと変革を迫られている。現場の担当者自身も、今後強化したいスキルとして「生成AIの業務活用」と「セキュリティ運用」を最優先に挙げており、経営層と現場の意識が一致している点は注目すべきである。
箇条書きで整理すると次の通りである。
- 人材不足を実感する企業は73.5%
- 情報サービス業の正社員不足率は72.5%で全業種トップ
- 採用戦略は機能不全、内部育成が32.1%で最多
- 経営層の二大命令は「セキュリティ」と「AI活用」
- 現場も同様の課題認識を持つ
情シス部門は単なるIT運用の裏方ではなく、事業継続性と競争力を左右する中核機能に進化することが求められている。
爆発的に拡大するAIOps市場と生成AIの成長シナリオ
人材不足を背景に注目を集めるのが、AIをIT運用に活用するAIOps市場である。ITRの最新レポートによると、国内のAIOpsおよび運用自動化市場は2024年度に売上高86億4800万円を記録し、前年から19.8%成長した。さらに2025年度も18.9%増の成長が予測されており、今後数年間で年平均20.4%という驚異的なCAGRを達成する見込みである。これは運用管理14分野の中で最も高い成長率であり、構造的な人材不足を背景に企業がAIに救いを求めている実態を物語っている。
特に目立つのはSaaS型ソリューションの急伸である。2024年度の市場規模は約42億円に達し、2025年度には従来のパッケージ型を上回ると予測されている。CAGRは25.5%と高く、クラウドへのシフトが一層加速している。オンプレミス中心の運用から脱却できない企業にとっても、この流れは避けられない大潮流となっている。
一方、AI市場全体を俯瞰すると、富士キメラ総研の試算では生成AI市場が2028年度に1兆7397億円規模へと成長し、2023年度比で12.3倍に拡大すると予測されている。これはAI市場全体の約6割を占める規模であり、生成AIが単なる実験的技術から社会インフラに昇華することを示している。AIOpsと生成AIは、情シス部門の省力化だけでなく、企業全体の競争戦略に直結する基盤技術へと進化しているのである。
表に整理すると以下の通りである。
| 項目 | 2024年度実績 | 2025年度予測 | CAGR(2024-2029) |
|---|---|---|---|
| AIOps市場規模 | 86億4800万円 | +18.9%成長 | 20.4% |
| SaaS型市場 | 約42億円 | パッケージを上回る | 25.5% |
| 生成AI市場規模 | 約1.4兆円(2023年度比) | 1兆7397億円(2028年度) | 12.3倍成長 |
この急成長の背景には、システムの複雑化と人材不足がある。企業は少ない人員で複雑化するシステムを安定運用するため、AIによる自動化を導入せざるを得ない。もはやAIは効率化のオプションではなく、事業継続と競争力維持のための必須インフラとなりつつある。
IT資産管理の革新:LANSCOPE、ジョーシス、SKYSEAの最新動向

IT資産管理は従来、Excelやオンプレミスの台帳を基盤とした手作業が中心であり、ヒューマンエラーや属人化が大きな課題となっていた。デバイスの購入からキッティング、廃棄までライフサイクル全体を管理する必要がある一方で、情シス部門のリソース不足が深刻化し、効率化とセキュリティ強化の両立が求められている。この状況を打開する存在として、AIを活用した最新の資産管理ツールが急速に普及し始めている。
主要な国内ベンダーの動向を整理すると次の通りである。
| 製品名 | 提供形態 | 主なAI機能 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| LANSCOPE (エムオーテックス) | クラウド | Copilotによる自然言語検索、操作ログ分析 | 国内シェア26%、デファクト標準的存在 |
| ジョーシス (Josys) | クラウド | SaaSアカウント発行・削除の自動化、シャドーIT検知 | SaaS管理に特化、アンカー・ジャパンでコスト75%削減 |
| SKYSEA Client View | オンプレ/クラウド | 詳細なログ収集を基盤に将来的なAI強化 | 官公庁や金融機関で広範な導入 |
| AssetView (ハンモック) | オンプレ/クラウド | モジュール単位導入、SaaS利用状況データ活用 | 中堅・中小企業で実績多数 |
特に注目されるのがジョーシスの事例である。アンカー・ジャパンでは、従業員数の急増に伴うデバイスとSaaSの管理負担が大きな課題となっていた。同社はジョーシスを導入し、複数ベンダーで分散していたプロセスを一元化。結果として外部委託費と不要ライセンス費用を削減し、IT管理コストを75%削減する成果を挙げた。また、業務の自動化により従来2名必要だった管理業務を1名で対応可能にし、人材リソースの最適化も実現した。
LANSCOPEもまた、AIアシスタント「Copilot」によって利用状況の検索や不正操作の検知を効率化し、管理者の工数削減に寄与している。例えば「先月USBにデータを書き出したユーザーは誰か」といった自然言語での質問に即応できる機能は、セキュリティ運用の強化に直結する。
このように、AIを取り入れた資産管理は単なる効率化ではなく、セキュリティやコスト削減を同時に実現する次世代型の経営インフラとなりつつある。情シス部門は、資産管理を戦略的活動へと変革するフェーズに入ったと言える。
ゼロタッチ応答で変わるヘルプデスク:ServiceNow、Ivanti、Copilot事例分析
ヘルプデスク業務は、情シス部門が最も多くの時間を費やす領域の一つである。パスワードリセットやアプリの操作方法など定型的な問い合わせが殺到し、本来注力すべき戦略的業務を圧迫してきた。この課題を解決する手段として、AIと自動化を活用した「ゼロタッチ応答」が急速に広がっている。
代表的なプラットフォームの特徴を比較すると以下の通りである。
| 製品名 | 自動化思想 | 主なAI機能 | 国内事例 |
|---|---|---|---|
| ServiceNow Predictive AIOps | 予知・予防型 | Health Log Analytics、根本原因分析、イベントノイズ削減 | デンソー:月間1,250時間の工数削減 |
| Ivanti Neurons | 自己修復型 | エンドポイント常時監視、問題の自動検知・修復 | 日本データセンター開設、国内展開強化 |
| Microsoft Copilot for Service | 業務支援型 | ケース要約、回答案生成、CRM連携 | 住友商事:全社員9,000人導入で年間12億円削減 |
| ChatPlus | 自己解決促進型 | FAQベース自動応答、Teams/Slack連携 | 国内チャットボット市場シェアNo.1 |
デンソーはServiceNowを導入し、全社のITサポート窓口を一元化。FAQを活用してユーザーの自己解決を促し、問い合わせ1件あたりの対応時間を平均5分短縮した。その効果は月間で1,250時間の工数削減に相当し、担当者7人分の稼働時間を解放する成果を上げている。
また、住友商事はMicrosoft 365 Copilotを全社員に導入し、情報検索や資料作成などの定型業務を効率化。従業員1人あたり月4時間の業務削減を実現し、全社換算で年間12億円規模のコスト削減につなげた。これは、AI導入をトップダウンで全社展開することで生まれるスケールメリットを象徴する事例である。
Ivanti Neuronsは、問い合わせが発生する前にエンドポイントを自動修復する「自己治癒」型のアプローチを採用し、チケット発生を根本から抑制する点で独自性が高い。日本市場専用のデータセンター開設は、国内企業のデータガバナンス要件にも対応した動きとして注目されている。
ゼロタッチ応答は、単なる省力化ではなく情シスの役割を再定義し、ユーザー体験と業務効率を同時に向上させる新たな基盤である。
SOCの未来を形作る次世代セキュリティ運用:Splunk、Sentinel、Cortex XDRの競争軸

サイバー攻撃の巧妙化とアラートの氾濫により、SOC(セキュリティオペレーションセンター)のアナリストはかつてない負荷に直面している。ファイアウォールやエンドポイントなど多様なシステムから日々膨大なログが発生し、その中から真に重要な脅威を抽出する作業は極めて困難である。この課題に対し、次世代SIEMやXDRと呼ばれるAI駆動型プラットフォームが登場し、競争の軸は「個別製品」から「統合プラットフォーム」へと移りつつある。
主要ベンダーの特徴を比較すると以下の通りである。
| 製品名 | 提供ベンダー | 中核AI機能 | 主な成果 | 国内導入事例 |
|---|---|---|---|---|
| Splunk Enterprise Security | Splunk (Cisco) | AI Assistantによる自然言語クエリ生成、UEBA | 調査時間短縮、SOAR連携 | 官公庁 |
| Microsoft Sentinel | Microsoft | Fusionエンジンによる相関分析、脅威インテリジェンス連携 | マルチステージ攻撃の検出 | NTTコミュニケーションズ |
| Cortex XDR | Palo Alto Networks | エンドポイント・ネットワーク横断分析 | アラートの98%削減 | 日本航空(JAL) |
| CrowdStrike Falcon | CrowdStrike | AI/MLによるゼロデイ検知、ID保護 | プロアクティブ防御 | NEC |
Splunkは生成AIを活用し、自然言語での質問から即座に分析結果を提示できる点が画期的である。Microsoft Sentinelはマルチクラウドに対応し、低忠実度のアラートを組み合わせて高精度のインシデントを生成する機能を持つ。Cortex XDRはアラート疲れの問題を解消し、アナリストの調査負担を98%削減する成果を示している。さらにCrowdStrikeは単一エージェントで多機能を統合し、軽量かつ迅速な導入で支持を集めている。
これらの動向は、SOCの運用が従来の「検知と対応」から「統合と自動化」へと移行していることを意味する。情シス部門が取るべき戦略は、最良の個別ツールを選ぶことではなく、最適な統合プラットフォームを選択し、限られた人材の生産性を最大化することにある。
先進企業の成功事例に学ぶ導入効果と展開の技術
AIソリューションの導入において重要なのは、優れたツールを選ぶこと以上に、それをどのように社内に浸透させ、成果を可視化するかである。先進企業の事例は、その展開手法における共通の成功要因を示している。
まず注目されるのは、住友商事によるMicrosoft 365 Copilotの全社導入である。同社は派遣社員を含む9,000人全員に一斉導入するという大胆な意思決定を行い、月間平均で従業員1人あたり約4時間の業務削減を達成した。年間換算で約12億円のコスト削減効果となり、トップダウンによる全社展開の威力を証明した。
デンソーはServiceNowを導入し、月間15,000件の問い合わせ対応時間を平均5分短縮することで、1,250時間もの工数を削減した。これは担当者7人分の労働時間に相当し、AIによるナレッジ活用と問い合わせ窓口の一元化が業務効率化に直結することを示した。
また、アンカー・ジャパンはジョーシスを用いてデバイスとSaaS管理を統合し、IT関連コストを75%削減した。従来2名で行っていた業務を1名で対応可能にするなど、人材リソースの最適化も実現している。
これらの事例から導かれる成功要因は以下の通りである。
- 経営層によるトップダウンのコミットメント
- 全社的な展開によるスケールメリット
- 推進役(チャンピオン)の任命による現場浸透
- 効果測定と数値化による投資対効果の可視化
AI導入は単なる効率化ではなく、組織文化や働き方を変革する経営施策である。成功の鍵はツールそのものではなく、その展開の技術にこそある。
自律的AIエージェント時代に向けたロードマップと日本企業への提言

現在のAI活用は、人間の業務を補助する段階に留まっている。しかし、GartnerやIDCの最新調査が示す通り、AIは自律的に意思決定を行い、タスクを実行する「エージェント型AI」へと進化しつつある。この新たな潮流は、企業がAIを単なるツールではなく、新たな従業員として迎え入れる未来を現実のものにしようとしている。日本企業にとっても、数年先に訪れるこの変化を前提とした準備が急務である。
まず必要なのは、AIエージェントが活動できる基盤の整備である。部門ごとに分断されたデータ環境では、AIは横断的な分析や自律的な判断を行うことができない。そのため、データを統合し、全社的にアクセス可能なプラットフォームを構築することが第一歩となる。また、属人的な業務を標準化し、AIが実行可能なワークフローへと変換する取り組みも欠かせない。
次に重要なのは、AIの自律的な判断を適切に監督するガバナンス体制の構築である。AIエージェントは大量の業務を迅速に処理できる一方で、誤った判断が大規模なリスクにつながる可能性を持つ。したがって、人間がAIの行動を監督し、必要に応じて介入できる「ヒューマン・イン・ザ・ループ」体制を整えることが求められる。特に日本企業においては、コンプライアンスや品質保証の文化と整合させた導入が不可欠である。
さらに、全社的なAIリテラシー向上も避けて通れない課題である。住友商事が9,000人規模でMicrosoft Copilotを導入した際には、各部門に「Copilot Champion」を任命し、現場レベルでの知識共有を促進した。こうした推進役の存在が、AIの活用を一過性の取り組みで終わらせず、持続的な業務変革へとつなげたのである。
箇条書きで整理すると以下の通りである。
- データ統合基盤の構築
- 業務プロセスの標準化とワークフロー化
- ヒューマン・イン・ザ・ループ体制による監督
- 部門横断の推進役育成とリテラシー向上
AIエージェント時代を迎えるにあたり、最も重要なのは「技術」そのものではなく、それを活かすための組織的な準備である。 幻滅期を恐れず、自社課題に根差した基盤整備を今から着実に進めることこそ、日本企業が次世代の競争環境を生き抜く唯一の道筋となる。

