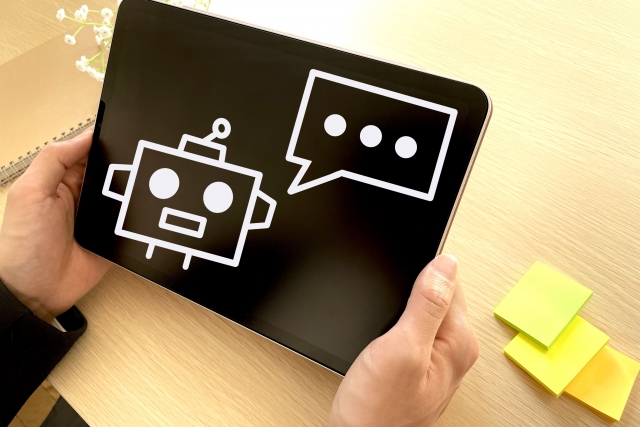生成AIの進化は、資料作成の常識を一変させた。特にプレゼンテーション分野では、Tomeの登場が象徴的であった。プロンプトを入力するだけで、瞬時に複数ページのスライドを自動生成し、画像やデザインまで一体的に仕上げるその仕組みは、まさに「ストーリーテリングの自動化」であった。教育者から企業の営業チーム、スタートアップ創業者まで幅広い層が熱狂的に支持し、利用者は瞬く間に2,000万人を突破した。
しかし2025年4月、Tomeは中核機能である「Tome Slides」の終了を発表し、多くのユーザーを驚愕させた。背景には無料ユーザーに偏った収益構造、高額なAI運用コスト、そして「Tomeらしい見た目」と揶揄された生成品質の限界があった。さらに同社は、営業CRM特化型の「Lightfield」へと事業転換し、汎用プレゼン市場から撤退した。
だが市場が空白になったわけではない。Gamma、Beautiful.ai、Plus AI、MagicSlidesといった強力な代替ツールが登場し、各自が異なる強みを武器にユーザーを獲得している。本稿ではTomeの栄枯盛衰を振り返りつつ、ポストTome時代に最適な選択肢を提示する。AIツール選びは単なる利便性ではなく、ビジネス成果を左右する戦略的な意思決定である。
Tomeが切り拓いたAIストーリーテリングの衝撃

Tomeが登場したとき、その革新性はプレゼンテーションの歴史を大きく書き換えた。従来、資料作成には数時間から数日を要し、デザイン調整や構成の考案に多大な労力が割かれていた。しかしTomeは、短いテキストを入力するだけで、自動的に数ページに及ぶプレゼン資料を生成し、文章・画像・デザインを一体化して提示した。この「Prompt-to-Presentation」という仕組みは、生成AIを実務に活かす代表例として広く注目を浴びた。
実際、Tomeの技術はOpenAIのGPT-3やGPT-4による自然言語処理と、DALL-E 2による画像生成を組み合わせ、数秒で物語性のあるスライドを完成させた。さらに、MiroのホワイトボードやYouTubeの動画など外部コンテンツを埋め込むことができ、従来の静的スライドを超えたインタラクティブな体験を実現した。
以下はTomeの中核機能を整理した表である。
| 機能 | 特徴 | 利点 |
|---|---|---|
| Prompt-to-Presentation | プロンプトからスライドを自動生成 | 作業時間を大幅短縮 |
| マルチメディア埋め込み | 動画・3Dモデルを統合 | 動的で説得力のある資料 |
| レスポンシブデザイン | デバイスごとに自動最適化 | デザイン負担を軽減 |
| ビデオナレーション | 音声・映像を資料に追加 | 非同期プレゼンに対応 |
このような革新性により、スタートアップの投資家向けピッチや企業営業の提案資料、教育現場での授業設計など多岐にわたる分野で活用された。結果として、ユーザー数はわずか数年で2,000万人を突破し、Tomeは「AI時代のPowerPoint」と呼ばれる存在にまで成長した。
また、その利用者層の幅広さも特筆に値する。学生や個人クリエイターがポートフォリオを作成する一方、企業チームはプロフェッショナルな資料を迅速に仕上げる手段として導入した。市場調査によれば、AIプレゼンツール市場は今後も年平均成長率15%以上で拡大すると見込まれており、Tomeはその先駆けとして確固たる地位を築いたのである。
AIがストーリーテリングを自動化し、人間の創造力を補完するという新しい概念を示した点で、Tomeの衝撃は極めて大きかった。この成功は一時代を象徴するものとなり、次世代ツールの開発競争を加速させる契機となった。
なぜTomeはサービス終了に追い込まれたのか
華々しい成功を収めたTomeであったが、2025年4月に突如として中核サービスである「Tome Slides」の終了を発表した。この決断の背景には、急成長したAIスタートアップ特有の課題が凝縮されていた。
第一の要因は収益化の壁である。Tomeは2,000万人を超える利用者を獲得したが、その大半は無料プランのユーザーであった。提供された500クレジットで十分に活用できるため、有料プランに移行する動機が乏しかった。一方で、GPT-4やDALL-E 2の運用には膨大な計算コストが発生し、利用が増えるほど赤字が膨らむ構造に陥った。「ユーザー数の拡大が必ずしも収益性につながらない」というジレンマが、Tomeの最大の弱点であった。
第二の要因は品質問題である。ユーザーの間では「Tomeらしい見た目」という揶揄が広がり、生成されるスライドが似通っていることが指摘された。AIは自動操縦(Autopilot)的には便利であったが、専門家と共に成果物を高める副操縦士(Co-pilot)としての役割を果たせなかった。特に営業提案や経営会議など、高い成果が求められる場面では、汎用的なコンテンツでは不十分であり、結局は人間が大幅な修正を加える必要があった。
第三の要因は戦略的なピボットである。Tomeは汎用的なプレゼンツール市場から撤退し、営業組織に特化したAIセールスCRM「Lightfield」へと転換した。これにより、無料ユーザー主体の不安定なモデルを捨て、明確な支払い意思を持つ企業顧客層に集中する戦略を選択したのである。
要因を整理すると以下のようになる。
- 収益化の壁:無料ユーザー依存と高コスト構造
- 品質の天井:生成物の均質化と独自性不足
- 戦略的必然性:営業CRM市場への転換
このように、Tomeの終了は単なる失敗ではなく、AIスタートアップが直面する構造的課題の象徴であった。急成長と持続可能性のバランスをいかに取るかが、今後のAIビジネスの成否を左右する。Tomeの事例は、生成AIツールの未来を占う上で重要な教訓を残しているのである。
事業転換の先に見えた「Lightfield」の狙い

Tomeがプレゼンテーション市場から撤退した後に打ち出したのが、営業組織特化型のAIセールスCRM「Lightfield」である。これは単なるブランド変更ではなく、生成AIの知見を営業分野に集中させた大きな戦略的転換であった。
Lightfieldの特徴は、営業担当者が直面する具体的な課題に直結している。従来のCRMはデータ入力が煩雑で、営業活動の記録が属人化する問題があった。Lightfieldは会議の議事録、メール、サポート履歴、製品利用ログといった非構造化データを自動的に収集し、顧客ごとの「継続的メモリ」として統合する。これにより引き継ぎの漏れや情報の断絶を防ぎ、営業活動の一貫性を確保できる。
さらに、AIはこのデータを分析し、会議後のフォローアップメール作成や提案書の骨子生成、リスク予測などを自動で提示する。ユーザーは自然言語で「この案件の最大の課題は何か」と質問すれば、AIが根拠とともに答えを示す。営業担当者が行うべき判断を支援する「能動的CRM」としての機能を備えている点が革新的である。
以下は従来型CRMとLightfieldの比較である。
| 項目 | 従来型CRM | Lightfield |
|---|---|---|
| データ入力 | 手作業中心 | 自動収集・自動構造化 |
| 非構造化データ活用 | 困難 | メール・会議録をAI解析 |
| フォローアップ | 担当者依存 | AIが自動生成 |
| 情報の一貫性 | 属人化リスク高 | 継続的顧客メモリを構築 |
営業組織にとって、時間のかかる事務作業を削減し、データ駆動型の意思決定を支援することは直接的な成果向上に結びつく。特に急成長を目指すテクノロジー企業にとって、Lightfieldは必須の基盤となり得る。
Tomeが汎用ツールから撤退し、営業組織という高価値市場に特化したことは、持続可能な収益モデルを築くための必然的な選択であった。この動きは、生成AI企業が広く直面する「無料ユーザー依存からの脱却」という課題を象徴する事例である。
ポストTome時代の有力候補:主要ツール徹底比較
Tomeの撤退は、AIプレゼンテーション市場に大きな空白を生んだ。しかし、その後継を狙うツールはすでに複数登場しており、それぞれが異なる強みを持っている。中でも注目されるのが「Gamma」「Beautiful.ai」「Plus AI」「MagicSlides」の4つである。
| ツール | 特徴 | 強み | 弱み |
|---|---|---|---|
| Gamma | ウェブネイティブでカード型のインタラクティブ資料 | 創造的な表現力、共同編集の柔軟性 | PPTXエクスポート時のレイアウト崩れ |
| Beautiful.ai | 「スマートスライド」によるデザイン自動化 | ブランド統一、企業利用に強い | デザイン自由度が低い |
| Plus AI | GoogleスライドやPowerPointに直接統合 | ネイティブファイル生成、セキュリティに強み | 無料プランなし |
| MagicSlides | PDFやURL、動画から高速生成 | 多様な入力対応、低コスト | 内容が簡素化されやすい |
Gammaは、Tomeのストーリーテリング思想を色濃く継承し、ウェブサイトのような動的なプレゼンを実現する。一方で、既存のPPT形式に依存するユーザーにとっては使い勝手に課題が残る。
Beautiful.aiは企業利用に特化しており、ブランドガイドラインを徹底して守れることが評価されている。社員がデザインスキルを持たなくても高品質な資料を作れる点は大企業に適しているが、クリエイティブな表現を求める個人には制約が強い。
Plus AIは、GoogleスライドやPowerPointという既存ワークフローにAIを組み込む戦略を取っている。新しい操作を覚える必要がなく、セキュリティ面でもSOC 2認証を取得しているため、大企業での導入が進んでいる。ただし無料プランが存在せず、導入コストがネックとなる。
MagicSlidesは、多様なソースからの高速変換を武器にしている。URLやPDFを瞬時にスライド化できるため、ドラフト作成や学習用途に適している。しかし生成内容は汎用的になりやすく、本格的な商談用資料には追加編集が不可欠となる。
ポストTome時代においては、ユーザーがどのような場面でAIプレゼンツールを利用するかが選択の決め手となる。企業チームでの統一性を重視するならBeautiful.ai、既存のワークフローとの親和性を求めるならPlus AI、創造性を重視するならGamma、コストと速度を優先するならMagicSlidesが適している。
ユーザータイプ別:最適なツールの選び方

ポストTome時代のAIプレゼンツール選びにおいては、ユーザーが置かれている状況や目的によって最適解が異なる。各ツールはそれぞれ異なる強みを持ち、用途に応じて使い分けることが成果の最大化につながる。
まず、企業チームに適しているのはBeautiful.aiである。ブランドの一貫性を自動的に維持する「スマートスライド」機能は、社員のデザインスキルに依存せず高品質な資料を量産できる点で大きな利点を持つ。特に広告代理店や大手メーカーなど、数十人単位で営業資料を扱う組織においては、社内外のブランド統一性が競争力の一部となる。
一方で、GoogleスライドやPowerPointを既に活用しているプロフェッショナルにとっては、Plus AIが最も自然な選択肢となる。新しいソフトを学習する必要がなく、既存のワークフローの中にAIを組み込むだけで効率が飛躍的に向上するからである。セキュリティ面でSOC 2認証を取得している点も、金融機関や大企業での導入を後押ししている。
教育者やクリエイターにとってはGammaの柔軟性が魅力となる。ウェブネイティブの設計思想により、単なるスライドではなくインタラクティブな物語表現が可能であり、授業計画やポートフォリオ作成に適している。特に教育分野においては、学生の関心を引きつけるためのインタラクティブ性が成果を左右する。
さらに、個人ユーザーや学生にはMagicSlidesが有効である。URLやPDFから瞬時にスライドを生成できるため、ゼロから資料を作る手間を省ける。コストも低く抑えられ、学習や副業の資料作成において効率性が際立つ。
- 企業チーム:Beautiful.ai
- 大企業・プロフェッショナル:Plus AI
- 教育者・クリエイター:Gamma
- 学生・個人ユーザー:MagicSlides
自らの立場と目的を明確にしたうえでツールを選択することが、プレゼンテーションの質と効率を最大化する鍵となる。単なる機能比較ではなく、利用シーンに基づいた判断が不可欠である。
AIを「副操縦士」にするプロンプト活用術
AIプレゼンツールの真価は、プロンプトの与え方に大きく左右される。曖昧な指示では汎用的な成果しか得られず、結果として手直しに時間を要する。逆に、明確かつ戦略的なプロンプト設計を行えば、AIは単なる自動生成ツールではなく、知的パートナーとして機能する。
有効な方法として注目されているのが「PTCFフレームワーク」である。これは以下の4要素から成る。
- Persona(役割):AIに特定の専門家の視点を与える
- Task(課題):具体的に実行してほしい指示を与える
- Context(文脈):背景情報やターゲットを提示する
- Format(形式):出力の形を詳細に指定する
例えば「あなたは経験豊富な営業コンサルタントです。日本のIT企業経営者向けに、生成AI活用の提案資料を7ページ構成で作成してください。市場データを表形式で示し、結論は投資効果を強調してください」というプロンプトを与えれば、AIは単なる一般論ではなく、文脈を反映した資料を生成する。
また、プロンプトは一度で完成させるのではなく、対話を通じて磨き上げることが重要である。初稿生成の後、「3ページ目の競合分析を最新データに基づき書き直して」「全体をより説得力のあるトーンに変更して」といった追加指示を与えることで、AIは人間の知見を取り込みながら成果物を改善していく。
さらに、人間ならではの要素を加えることも欠かせない。AIは一般的な情報や論理構成に優れるが、現場経験や独自の事例を反映することは苦手である。AIの生成物を土台としつつ、人間の知見を融合させることで初めて説得力あるプレゼン資料が完成する。
プロンプト活用術は単なる効率化の手法ではなく、AIを「副操縦士」として使いこなし、成果の質を高めるための必須スキルである。今後、プロンプト設計力そのものがビジネスパーソンの競争優位を左右する時代が到来するだろう。
プレゼンの未来:AIエージェントが切り拓く新時代

生成AIの進化は、単なる自動化の枠を超えつつある。今後のプレゼンテーションは「資料を作る」行為から「知識と意思決定を支援する体験」へと進化するだろう。その鍵を握るのが、ユーザーの意図を先読みし、能動的に行動するAIエージェントである。
AIエージェントは、従来のAIツールのように入力に依存するのではなく、ユーザーの文脈や目的を理解し、自律的に提案や行動を行う。例えば営業担当者が顧客との打ち合わせを終えた直後に「フォローアップ資料を作成しておいた」「次回会議で重点的に議論すべきトピックはこれだ」と通知してくれるような世界である。これはまさに副操縦士から共同操縦士への進化であり、人間とAIが並走する未来像を示している。
進化の方向性
AIエージェントが切り拓くプレゼンの未来には、いくつかの方向性がある。
- 業界特化型AI:製薬、金融、教育など、専門領域の知識を学習したAIが登場し、より精度の高い提案を行う
- 自動リサーチ機能:市場データや競合情報をリアルタイムで収集し、スライドに反映
- 感情認識の統合:聴衆の反応をAIが解析し、話すべきトーンや補足情報を即時に提案
- マルチモーダル対応:テキストだけでなく、音声・映像・ジェスチャーを組み合わせたプレゼン生成
このような変化は、単に効率性を高めるだけでなく、プレゼンそのものの形態を根本的に変える可能性を秘めている。
データと市場予測
グローバル調査会社によれば、生成AI市場は2030年までに年間2,000億ドル規模に達すると予測されている。その中でもAIプレゼン関連市場は高い成長率を示しており、特に企業の意思決定支援領域が注目されている。マッキンゼーの調査でも、AIを導入した企業の営業生産性は平均で20〜30%向上したとされ、意思決定速度の加速が競争力を大きく左右している。
人間とAIの協働の未来
AIエージェントはあくまで補助であり、最終的な意思決定は人間が担う。しかし、AIが背景情報や代替案を即座に提示することで、意思決定の質とスピードは劇的に高まる。人間は創造性と直感を、AIは分析と自動化を担うことで、プレゼンはこれまで以上に戦略的な武器となる。
Tomeが示した軌跡とその後継者たちの台頭は、AIプレゼン市場が成熟期に入りつつあることを示している。今後の焦点は「どのAIを使うか」ではなく「AIをどう使いこなし、人間の能力と融合させるか」に移行するだろう。AIエージェントが切り拓く新時代は、プレゼンを単なる情報伝達から意思決定のエンジンへと進化させる可能性を秘めている。