人工知能(AI)の進化は今、根本的な転換点を迎えている。これまでの生成AIは「考える」「書く」ことに長けていたが、現実世界においては依然として「手を動かせない」存在であった。だが、2025年以降、AIはついに「実行する」段階へと進化している。OpenAIの「Operator」を筆頭に、AIが自ら計画を立て、ウェブ操作や意思決定を行い、タスクを完遂する時代が到来したのである。
この新しい潮流は、単なる技術的アップデートではなく、人間とAIの関係そのものを再定義するパラダイムシフトである。企業は、生成AIが担ってきた「創造」から、実行AIが担う「行動」へと戦略を転換しなければならない。
本稿では、生成AIの限界、Operatorアーキテクチャの革新性、プロダクト設計や市場構造へのインパクトを体系的に分析し、「自律する知能」がもたらす社会・経済的な変化の本質を明らかにする。
生成AIの限界と「実行AI」登場の必然性

ハルシネーション、静的知識、そして受動性。生成AIが抱えるこれらの構造的限界は、AIが次の段階──「実行AI」へと進化することを必然にした。生成AIは、確率的に最も「それらしい」言葉を並べることに優れているが、現実世界で行動する力を持たない。この欠陥が、ビジネス領域における自動化の最大の壁となっている。
とりわけ深刻なのが「ハルシネーション問題」である。実際に存在しないデータを自信満々に提示するこの現象は、AIの確率的生成構造に起因する。2025年に『Science』誌に掲載された研究によれば、AIが生成した科学的仮説の実用性は人間が考案したものに劣るとされ、その原因はAIが現実検証を欠いた推論を行う傾向にあるためだとされた。金融、医療、法務といった誤りが許されない領域では、生成AIの信頼性は依然として致命的に低い。
さらに、生成AIはトレーニング時点で知識が固定されている。つまり、時間が止まったAIである。市場や法規制の変化、天候や株価といったリアルタイム情報を取り込むことができず、常に「過去の世界」に閉じ込められている。この静的知識構造は、AIが最新の文脈に基づいて判断・実行する能力を欠く根本的な理由である。
また、AIの推論は因果ではなく相関に基づく。あるパターンを「それらしく」再現することは得意でも、なぜそうなるのかという因果理解に至っていない。このため、人間が行うような多層的推論──たとえば「AはBがCを考えていると理解している」という二次的・三次的思考──は依然として困難である。
加えて、生成AIは本質的に受動的である。ユーザーからのプロンプトがなければ動かない。つまり、「聞かれなければ動けない」AIであり、自ら目標を設定して実行する能力を欠いている。これは、企業の業務プロセスを完全に自動化するうえで致命的な制約である。
このような限界の積み重ねが、新たなパラダイム──実行AIの登場を不可避にした。生成AIが「語るAI」だったのに対し、実行AIは「動くAI」である。生成AIの出力を人間が確認し、手動で行動する段階から、AI自身が判断し、行動し、結果を評価する段階へと進化が求められているのだ。
その進化を象徴するのが、OpenAIの「Operator」に代表される実行AIアーキテクチャである。生成AIの知的な創造力と、外部環境への実行力を融合させることで、AIは初めて「タスクを完了させる存在」へと変貌する。これこそが、生成AI時代の限界を超え、AIが実世界で成果を出すための次なる必然的ステップである。
実行AIとは何か:生成AIとの本質的な違い
生成AIと実行AIの差異は、単なる機能の違いではなく、存在目的そのものの変化である。前者が「コンテンツを生み出す」ことを目的とするのに対し、後者は「目標を達成する」ことを目的とする。つまり、生成AIは「クリエイター」、実行AIは「実行者」である。
実行AIの根幹を成すのは、**自律性(Autonomy)**である。人間の介入を最小限に抑え、タスクを自ら分解し、実行計画を立て、環境に応じて行動を修正する。これまでのAIがプロンプトを待つ受動的存在だったのに対し、実行AIは目標に基づいて能動的に行動を開始する。
以下は、両者の主要な相違点を整理したものである。
| 特徴 | 生成AI(例:ChatGPT) | 実行AI(例:Operator) |
|---|---|---|
| 目的 | コンテンツ生成(テキスト・画像など) | タスク実行と目標達成 |
| 動作原理 | ユーザー入力への反応 | 自律的計画と行動 |
| 情報源 | 内部データのみ | 外部ツール・API・環境認識 |
| 人間の役割 | 指示者・編集者 | 目標設定者・監督者 |
| 代表タスク | 「文章を書いて」 | 「航空券を予約して」 |
実行AIは、内部知識だけではなく、APIや外部データベース、ウェブブラウザなどと連携し、リアルタイムで情報を取得・更新できる。この構造により、現実世界の文脈を理解し、動的に意思決定するAIが初めて実現した。
さらに注目すべきは、人間との役割分担の変化である。生成AI時代において、人間はタスクを指示し、AIの出力を評価する「プロンプター」だった。だが、実行AI時代においては、人間は詳細を指示する必要がなくなり、代わりに高次の目標──「大阪出張を最適スケジュールで組んで」など──を設定するのみでよい。人間は管理者からディレクターへ、AIは補助者からパートナーへと進化するのである。
OpenAIが発表した「Operator」は、その象徴的存在である。Operatorは、ウェブ画面を視覚的に認識し、ボタンをクリックし、フォームを入力し、確認までを完了させる。つまり、人間がブラウザで行う一連の操作を「見て」「考えて」「行動する」AIが代替する。この仕組みは、従来のAPI統合に依存しないため、あらゆるウェブサービス上でタスク実行が可能となる。
結果として、AIは単なる「支援ツール」ではなく、自ら意思決定を行うデジタルワーカーへと進化した。今後の企業競争において差を生むのは、どれだけ多くのタスクを自律的に実行できるか──すなわち、どれだけ高度な「実行AI」を活用できるかにかかっている。
Operatorアーキテクチャの革新性
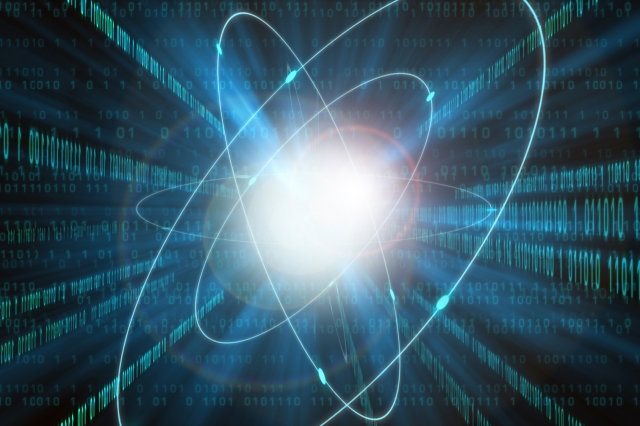
AIが「考える」段階から「実行する」段階へと進化する中で、その中心的役割を果たすのが「Operatorアーキテクチャ」である。これは単一のAIモデルではなく、複数の専門エージェントを束ねて指揮するAIの中間管理職とも呼ぶべき存在である。OpenAIが2025年に発表した「Operator」は、この概念を具現化した代表例であり、航空券予約や買い物といったオンラインタスクを自律的に完了させる能力を持つ。
Operatorの中核は「Computer-Using Agent(CUA)」と呼ばれるモデルである。CUAはGPT-4oの視覚・推論・操作の能力を組み合わせ、画面を「見て」「考え」「クリックする」ことができる。人間がブラウザ上で行う行動を模倣し、フォーム入力やチェックボックス操作を正確に再現するため、特定のAPI統合を必要とせずにあらゆるウェブサイトで動作できる点が画期的である。
Operatorは以下の4段階で動作する。
- 認識:画面の状態を視覚的に把握する
- 推論:タスクの文脈を理解し、行動を計画する
- 行動:仮想マウスとキーボードで操作を実行する
- 評価:結果を検証し、必要に応じて修正を行う
この「認識→推論→行動→評価」の連続ループにより、Operatorは人間のような実行サイクルを実現する。Googleの「ReAct」フレームワークやMetaの「Toolformer」などの先行研究で示された「推論と行動の融合」をさらに拡張し、マルチモーダル知能を通じて現実世界に適応する能力を獲得した点が特筆される。
Operatorの価値は、単にタスクをこなすだけでなく、他のAIエージェントを統括するオーケストレーターとして機能することにある。たとえば、「マーケティングキャンペーンを立ち上げて」という指示を受けた場合、Operatorは複数の下位エージェントを召喚する。リサーチを行うMarketResearchAgent、コピーを作成するCopywritingAgent、予算を管理するBudgetAgentなどが連携し、プロジェクト全体を完遂する。この構造は人間の企業組織を模倣しており、エージェント群による分業と専門化のAI化を実現している。
このアーキテクチャは、AIが「何でも屋」として機能する従来型モデルの限界を超える。単一モデルにすべての能力を詰め込むのではなく、「適材適所のエージェントを協調的に動かす」という設計思想が、複雑な業務の信頼性とスケーラビリティを高める。企業にとっては、AIを単一ツールとして導入するのではなく、組織構造そのものを再設計する戦略的インフラとして捉えることが鍵となる。
ReAct、Toolformer、Gorilla:実行AIを支える基盤技術
実行AIを支える土台には、複数の革新的研究成果が積み重なっている。これらは単独ではなく、相互に補完し合う「知的行動のスタック」を形成している。ReAct、Toolformer、Gorillaはいずれも、AIが現実世界で自律的に行動するためのコア技術として位置づけられている。
まず、Google Researchが開発した**ReAct(Reason + Act)**は、AIに「声に出して考えさせる」フレームワークである。思考と行動を交互に生成し、外部環境からのフィードバックを得ながら推論を修正することで、ハルシネーションの発生率を劇的に低減させた。たとえば、ReActでは「思考:Xを見つける必要がある→行動:Search[X]→観察:結果Y→思考:YはZを示す」といったプロセスをAI自身がループさせる。これにより、単なる内部思考(Chain-of-Thought)では不可能だった動的計画修正が可能となった。
次に、Meta AIが開発したToolformerは、AIが外部ツールを「自ら学習する」メカニズムを実現した。ToolformerはAPIコールを自己教師ありで習得し、計算機・翻訳機・カレンダーなど多様なツールを使い分けられる。結果として、小規模モデルであっても、外部知識を活用することで大型モデルを凌駕する性能を示した。これにより、AIはもはや内部知識に閉じず、外部世界と相互作用する存在へと変わった。
さらに、カリフォルニア大学バークレー校の研究チームが開発したGorillaは、実行AIの「拡張性」と「現実適応性」を飛躍的に高めた。Retriever-Aware Training(RAT)という手法を導入し、AIが最新のAPIドキュメントを検索し、内容を理解した上で最適なAPIを呼び出すことを可能にした。これにより、AIは再学習を行わずとも新しいAPIや更新仕様に対応できる柔軟性を手に入れた。
これらの技術進化は、以下のような階層構造を形成している。
| 技術 | 役割 | 主な貢献 |
|---|---|---|
| ReAct | 推論と行動の統合 | ハルシネーション削減と動的思考 |
| Toolformer | ツール利用の自己学習 | 外部情報活用とスケーラビリティ |
| Gorilla | API適応と知識更新 | 現実世界への即応性向上 |
これらが統合されることで、AIは単なる生成器から「行動主体」へと変わる。ReActが思考を外化し、Toolformerが行動の手段を獲得し、Gorillaが環境変化への適応力を与えた。結果として生まれたのが、現実世界に接続された動的な知能──すなわち実行AIの脳幹である。
今後、これらの技術がマルチモーダルモデルと融合することで、AIはテキストだけでなく、画像・音声・動画・GUIをも理解し操作する「汎用エージェント」へと進化するだろう。生成AIが「書く」時代を築いたように、実行AIは「動く」時代を切り拓く。その技術的中核は、まさにこの三層構造にある。
アプリの終焉とAX(Agentic Experience)の時代
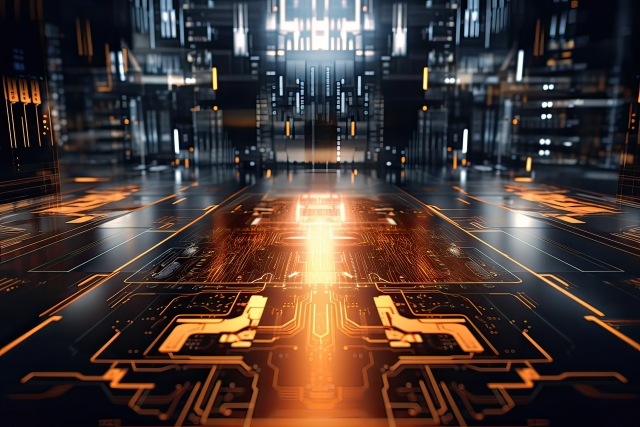
AIが実行能力を獲得することで、我々が長年慣れ親しんだ「アプリケーション」という概念自体が変わりつつある。GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)を前提とした操作は、エージェント型AIの登場によって根本的に再構築されている。いま企業の間で注目されているのは、「AX(Agentic Experience)」という新しい体験設計のパラダイムである。
人間はこれまで、マウスやタップを通じてソフトウェアを「操作」してきた。しかし、実行AIの登場によって、ユーザーは「どのように」操作するかを考える必要がなくなった。代わりに「何を達成したいか」を伝えるだけでよい。たとえば、「前四半期の売上を分析し、グラフを作って」と話しかければ、AIが自動的に必要なアプリを開き、データを取得し、レポートを生成する。つまり、ユーザーの意図がそのまま成果に変換される世界が実現しつつある。
この変化を象徴するのが、ユーザー体験の構造的転換である。従来のUXが「操作効率」を追求していたのに対し、AXは「意図理解」と「結果達成」を中心に据える。
| 比較項目 | 従来のUX | 新しいAX |
|---|---|---|
| 中心概念 | 操作のしやすさ | 意図の理解と目標の達成 |
| ユーザー行動 | クリック・入力 | 指示・会話 |
| デザイン対象 | 画面・メニュー | AIエージェントの性格と判断 |
| 成功指標 | タスク完了時間 | 結果の精度と信頼性 |
ヤコブ・ニールセン氏(UX分野の第一人者)は、AXを「アプリケーションの終焉」と呼び、今後のソフトウェアデザインはボタンではなく「人格」を設計する時代になると指摘している。
AX時代のデザイン原則として重要なのは、①AIの自律性とユーザーのコントロールのバランス、②AIの行動に対する説明責任、③信頼構築の透明性、である。特に**高リスクなタスクを自動で実行する際には、AIが理由を説明し、確認を求める「信頼チェックポイント」**が不可欠となる。
また、アプリそのものの存在意義も変化する。エージェントはGUIを介さずにAPI経由または視覚操作でシステムを制御できるため、アプリは人間向けのUIから「AIが利用するデータの供給層」へと役割を転換する。企業はこれを踏まえ、UI設計から「AIに理解されやすい情報構造設計」へと戦略をシフトさせる必要がある。
この新潮流により、企業間の競争軸も激変する。勝敗を分けるのはUIの美しさではなく、AIエージェントの賢さと信頼性である。これまでの「どのアプリを使うか」という選択は、「どのエージェントを信頼するか」へと置き換わる。まさにAXの時代は、人間中心設計から「エージェント中心設計」への歴史的転換点にある。
実世界のユースケース:DevinからOperator.aiまで
実行AIはもはや概念ではなく、すでに多くの現場で稼働している。特に2025年は「AIエージェント実装元年」と呼ばれるほど、商用プロダクトが次々に登場した年である。
まず、象徴的な存在が米Cognition AI社の**「Devin」である。Devinは「世界初のAIソフトウェアエンジニア」として発表され、GitHub上のIssue修正からテスト作成、デプロイまでを自律的に実行できる。プリンストン大学が開発したSWE-Agentも同様に、コードリポジトリを読み込み、バグを検出・修正するタスクを自動化した。GitHub Copilotが単なる補助ツールにとどまっていたのに対し、これらのエージェントは開発プロセス全体を自動化する「能動的開発者」**として機能する。
また、カスタマーサポート分野でも進化が加速している。米ASAPPの「GenerativeAgent Platform」は、人間の一次対応エージェントと同等の応答精度を持ち、顧客の問い合わせ内容を理解して返金処理や予約変更を自動で完了させる。実際に、航空会社では平均処理時間を40%以上短縮し、顧客満足度を25%向上させたと報告されている。
次に注目すべきは、OpenAIの**「Operator」**である。Operatorはブラウザを通じて画面操作を行う「実行エージェント」として設計されており、Instacartでの買い物デモでは、ユーザーが「夕食用にサーモンとサラダを注文して」と伝えるだけで購入を完了させた。特定APIを持たないウェブサイトでも、視覚理解を用いてボタンをクリックし、入力フォームを自動で操作できる点が革新的である。
さらに、ビジネスオペレーション分野ではGoogleの「Vertex AI Agent Builder」や米Gumloopなど、ノーコードでエージェントを構築できるプラットフォームが登場している。これにより、非エンジニアでも自社業務向けAIエージェントを短期間で開発できるようになった。
この流れはEコマースにも波及している。Operator.aiやShopifyのAIエージェントは、ユーザーの嗜好や在庫状況をリアルタイムで分析し、条件に合った商品を自動で提案・購入する。ユーザーが「2万円以下で防水のジャケットを探して」と言えば、AIが複数サイトを横断検索し、購入まで完了させる。これにより、消費者はもはや「検索する」ことすら不要となった。
これらの事例はいずれも、AIが構造化されたデータや明確な手順を持つ業務──つまり「論理的で反復的なタスク」──に最も強いことを示している。エージェントは単なる効率化ツールではなく、企業の生産性とROIを根本から変革する存在である。
そして次のフェーズでは、AIが創造的領域や意思決定支援に踏み込み、「補助者」から「戦略パートナー」へと進化する。DevinやOperatorは、その未来の到来を予告する実践的な前触れである。
AIエージェント市場の爆発的成長と投資動向

実行AIの登場により、世界のAI市場は「生成AIブーム」から「エージェント経済圏」へと急速に移行している。特に2024年後半以降、投資家・大手テック企業・スタートアップの資金が一斉に「AIエージェント分野」に流れ込んでおり、2025年は“AI Agent Year”として記録される可能性が高い。
米国の調査会社CB Insightsによると、2024年のAI関連スタートアップ投資総額は前年比72%増の690億ドルに達した。その中でも「AIエージェント」「AIオートメーション」「Agentic Workflow」分野への投資が全体の37%を占め、2023年の約2.5倍に拡大している。特にOpenAI、Anthropic、Adept、Inflection AIなどの大手プレイヤーが先導し、エージェント基盤を中心にAPIエコシステムを形成している点が特徴的である。
一方、日本国内でも動きは加速している。経済産業省が2025年度に創設予定の「AIエージェント推進枠」では、公共・産業分野への自律エージェント導入を国家レベルで後押しする方針が打ち出された。ソフトバンク・GMO・サイバーエージェントといった国内大手も参入を表明しており、特にソフトバンクは「Agentic Japan構想」として、企業内業務をAIエージェントに自動委任するB2B基盤を構築中である。
注目すべきは、AIエージェント市場の構造が「ツール販売型」から「稼働課金型」へと移行している点である。従来のSaaSモデルでは利用ユーザー数や期間が課金基準だったが、エージェントモデルでは「実行回数」や「成果完了数」に応じた課金へ変化している。すなわち、AIはもはや“ソフトウェア”ではなく“労働力”として扱われる時代に突入したのである。
主要市場の成長予測は以下の通りである。
| 地域 | 2024年市場規模(推定) | 2030年予測規模 | 年平均成長率(CAGR) |
|---|---|---|---|
| 北米 | 240億ドル | 1,150億ドル | 29.5% |
| 欧州 | 110億ドル | 480億ドル | 27.3% |
| アジア太平洋 | 95億ドル | 620億ドル | 36.1% |
この成長を牽引するのは、企業業務の自動化・営業支援・顧客対応・システム監視といった「反復的かつ知的」な分野である。特にAIスタートアップ「Lindy」「Hume」「Rabbit」「Character.AI」は、それぞれ異なる業種に特化したエージェントを提供し、すでに1億ドル以上のシリーズB投資を獲得している。
投資家の視点から見れば、AIエージェントはクラウドコンピューティング以来の「次なるプラットフォーム革命」と位置付けられている。生成AIが情報の“出力革命”だったのに対し、実行AIは行動の“経済革命”を起こす。この構造転換は、ソフトウェア市場の再編だけでなく、労働市場・人材戦略・教育体系にも波及していくことは間違いない。
リーダーたちのビジョン:アルトマン、フアン、孫正義
実行AIの進化を最前線で牽引しているのは、単なる技術者ではなく、新しい経済圏の設計者たちである。OpenAIのサム・アルトマン、NVIDIAのジェンスン・フアン、そしてソフトバンクの孫正義──この三人はいずれも異なる立場から「エージェント社会の未来像」を提示している。
アルトマンは2025年に発表したOperator構想で、AIを「人間の代理人」と位置づけた。彼は「コンピュータとの関係をコマンド入力から委任へ変える」と語り、AIがタスクを理解し、自律的に行動する未来を描いている。OpenAIはChatGPTの背後に実行環境「Operator」を統合し、AIがブラウザを操作し、決済やタスク管理を完了させる実験を開始した。これは、AIをアシスタントではなく“同僚”として扱う構造転換であり、個人と企業の生産性モデルを根本から変える可能性を秘めている。
一方、NVIDIAのフアンはAIの物理的基盤を提供する立場として、よりマクロなビジョンを描く。彼は「AIエージェントは次のインターネットである」と語り、GPUコンピューティングの拡張とAIエージェントの学習環境を統合した「Omniverse」構想を推進している。実際、NVIDIAは2025年に入ってから、シミュレーション環境上でAIエージェントを訓練する「AgentVerse」プログラムを発表し、企業が自社専用AIを構築・検証できる基盤を提供し始めた。**フアンにとってAIは単なるアルゴリズムではなく、現実世界を再構築する“デジタル生命体”**である。
そして、孫正義はAIエージェントを「人類史上最大の産業変換」と断言する。彼は講演で「1,000億の知能体が社会を動かす時代が来る」と語り、ソフトバンクグループの投資戦略を全面的にAIエージェント分野へシフトした。特に「Agentic Japan構想」では、自治体・医療・製造など日本の産業構造をAIエージェントで再設計する計画が進行中である。孫の狙いは、AIを輸入技術としてではなく、「社会インフラ」として日本から輸出することにある。
この三者の戦略に共通するのは、AIを“道具”ではなく“主体”として位置づけている点である。アルトマンが描く「実行AIの知的階層」、フアンが構築する「物理基盤の拡張知能」、孫が推進する「国家的エージェント構想」──これらはそれぞれ異なる軸から同じ未来を見据えている。
AIが単なる技術ではなく、新しい社会構造の中核になる時代。その未来像を、すでに彼らは設計し始めている。
信頼とリスク:自律AI社会の倫理的課題

実行AIの進化は、効率性と生産性を飛躍的に向上させる一方で、社会に新たな倫理的・法的課題を突きつけている。特にAIが「自律的に行動する存在」となった今、責任の所在、判断の透明性、そして人間の信頼構築のあり方が根本的に問われている。AIを単なるツールではなく“意思決定主体”として扱う時代において、どこまでAIに任せ、どこから人間が介入すべきかという線引きが最重要論点となっている。
AI倫理学の専門家ルシアーノ・フロリディ教授は、「AIはもはや道具ではなく“行為者(Agent)”として扱われるべき」と警鐘を鳴らす。特に実行AIは外部環境と直接やり取りを行うため、単なる誤回答では済まない。実際、2024年には米国の大手Eコマース企業がAIによる自動発注エラーで約1億ドルの損失を被る事例が発生した。AIが自ら行動を起こすようになったことで、「AIの過失」は単なる技術的問題から法的問題へと変質したのである。
この問題の本質は、「説明可能性(Explainability)」と「責任追跡性(Accountability)」の欠如にある。AIが判断を下す際、その意思決定プロセスが人間にはブラックボックス化している。とりわけ大規模モデルでは、学習データや推論経路が不明確であり、なぜその結論に至ったのかを説明することが困難である。これは医療・金融・司法といった高リスク領域でのAI活用を阻む最大の要因となっている。
欧州連合(EU)が2024年に採択した「AI Act」では、AIをリスクレベルに応じて分類し、実行AIなどの「高リスクAI」には透明性・記録保持・人間監督の義務を課した。特に自律的意思決定を行うシステムには、「人間が最終判断者として介入可能である設計」が求められている。つまり、“人間を外さない設計(Human-in-the-loop)”が信頼社会の最低条件となるのである。
加えて、AIによる誤作動や偏見も深刻な問題である。米MITの研究では、AIが採用プロセスで特定の性別・人種を無意識に排除する傾向を示すことが明らかになった。AIの学習データが社会の偏りを反映している限り、AIは「客観的な判断者」にはなり得ない。これは単なる倫理の問題ではなく、企業ブランドやコンプライアンスリスクにも直結する。
AI倫理に関する国際的議論の中で注目されているのが、「AIトラストフレームワーク」の構築である。これは、AIの設計・運用・監査を一体化し、技術・法・倫理を横断的に検証する仕組みであり、欧州ではISO/IEC 42001(AIマネジメントシステム)の国際標準化が進んでいる。日本でも総務省と経産省が共同で「信頼できるAI指針」を策定し、ガバナンス体制の整備を急ぐ。
最終的に問われるのは、AIそのものの善悪ではなく、「社会がAIとどう付き合うか」である。AIに完全な安全性を求めることは不可能だが、人間が責任を持って監督し、リスクを最小化する制度設計を構築できるかが未来の分岐点となる。
AI社会は今、利便性と信頼性の均衡を問われている。実行AIの時代を迎えた今こそ、倫理・法・技術が一体となった「AIガバナンス3.0」が求められている。

