NTTデータグループは、長年にわたり日本の社会インフラを支えてきたITサービスの雄である。その同社が、NTT Ltd.との統合とNTTによる完全子会社化という二段階の再編を経て、グローバル市場で戦う「フルスタック・プロバイダー」へと変貌を遂げた。この変革は単なる組織再編ではなく、アクセンチュアやIBMといった世界の巨人たちと真正面から競合するための、緻密な戦略的布陣である。
2025年3月期決算では、売上高4兆6,387億円、従業員数約19万8,000人という規模を誇り、その経営構造は「国内の安定×海外の成長」というデュアルエンジン体制を形成している。
本稿では、NTTデータグループの全貌を「再編」「技術」「競争」「未来戦略」という4つの軸から徹底分析し、グローバル企業としての新たな挑戦を明らかにする。
フルスタック・プロバイダーへの転生:NTTデータグループが挑む構造変革の核心
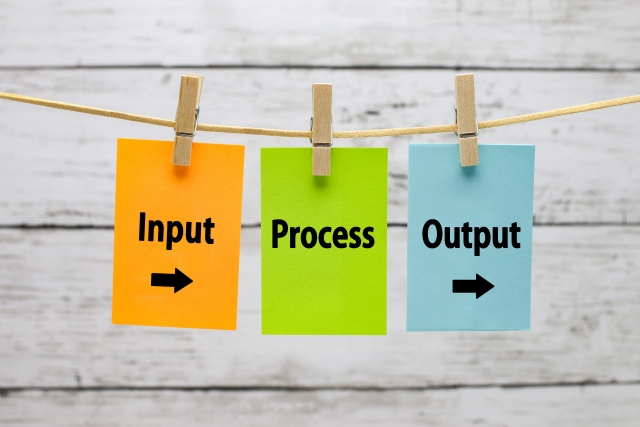
NTTデータグループは、2022年以降のグローバル再編を通じて、自らの存在意義を根底から再定義した。NTT Ltd.との事業統合とNTTによる完全子会社化という二段階の変革により、同社は「つくる力」と「つなぐ力」を融合させ、世界有数のフルスタック・ITサービスプロバイダーへと進化したのである。
この再編の狙いは単なる事業統合ではない。NTTデータが長年培ってきたアプリケーション開発やシステムインテグレーションといった「つくる力」に、NTT Ltd.が持つデータセンター・ネットワーク・マネージドサービスといった「つなぐ力」を統合することで、顧客のDXを上流の戦略設計から基盤運用まで一気通貫で支援できる体制を確立した点にある。
統合後、グローバル事業を統括する「NTT DATA, Inc.」は、欧州・北米・APACの3リージョン体制を導入し、データセンターやソリューションサービスを横断的に統合した。これにより、地域特性に応じた顧客エンゲージメントと、グローバルスケールでのコスト最適化を両立する体制が整った。
2025年3月期の業績では、売上高4兆6,387億円、営業利益3,430億円を記録。特に海外事業では、**GTSS(Global Technology and Solution Services)部門が増収増益(売上+816億円、EBITA+95億円)**を達成し、統合効果が数字として表れている。SAP移行やデータセンター需要の拡大がこの成長を支え、同社の海外事業構造における中核を形成している。
表:2025年3月期主要セグメント別実績(単位:億円)
| セグメント | 売上高 | 前期比 | 営業利益/EBITA | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本セグメント | 19,770 | +1,763 | 2,130 | +340 |
| 海外セグメント | 29,480 | +963 | 1,440 | ▲118 |
| GTSS | 4,100 | +322 | 310 | +147 |
このフルスタック体制の確立により、NTTデータはインフラだけ、アプリだけといった従来の縦割りを超え、顧客に対して包括的かつ高品質なDXソリューションを提供する唯一の日本発グローバル企業としての地位を固めつつある。
佐々木裕社長は「日本の高品質実装力をグローバルに展開する」と語る。国内で磨かれた信頼性と堅牢性の技術を武器に、NTTデータは次なる成長段階へと舵を切ったのである。
NTT完全子会社化の衝撃:巨大M&Aを見据えた非上場戦略
2025年9月、NTTデータグループは東京証券取引所への上場を廃止し、NTTの100%子会社となった。この決断は、単なる親子上場問題の解消ではなく、グローバル戦略を加速させるための「資本構造改革」である。
佐々木社長は「完全子会社化の最大の狙いは巨大M&Aだ」と明言している。つまり、非上場化によって市場の短期的評価に縛られず、NTT本体の資金力を活かして、数兆円規模のグローバルM&Aを迅速に実行するための布石なのである。
この構造転換により、経営判断のスピードが劇的に向上した。従来は親子上場ゆえに生じていた資本政策上の制約がなくなり、NTTグループのR&Dリソースと連携した長期投資が可能となった。
特に注目すべきは、M&A戦略の方向性である。同社はアクセンチュアやTCSなどと同等の規模感を目指し、アジアや欧州を中心に高付加価値領域(AI、クラウド、データセンター)への買収投資を検討しているとされる。これにより、単なるSIerではなく、「戦略コンサル×クラウド×AI」を統合する新たなビジネスモデルへの転換を狙う。
箇条書きで整理すると、この完全子会社化の効果は次の通りである。
・親子上場の解消による迅速な意思決定
・NTT資金を活用した大型M&A実行力の確保
・上場企業特有のガバナンス制約からの解放
・グループR&Dとの統合による技術的優位性の強化
この動きは国内外のIT業界でも注目を集めている。アナリストの間では「アクセンチュア型のM&A主導モデルへ進化する可能性」が指摘されており、NTTデータが今後どの企業を買収対象とするかが、市場の大きな関心事となっている。
完全子会社化によって得られる最大の資産は、**「長期的ビジョンに基づく攻めの経営」**である。短期的な株主価値よりも、グローバル覇権を見据えた投資戦略が可能になったことで、NTTデータは世界市場における真の競争者として再び歩み始めたのである。
国内事業の真価:社会インフラを支える「日本型実装力」の競争優位

NTTデータグループの国内事業は、単なる収益源ではなく、同社のブランド価値と信頼性を形づくる根幹である。官公庁、金融、法人の三本柱がそれを支え、いずれも日本社会の根幹を支えるミッションクリティカルなシステムを担っている。
官公庁・自治体分野では、国の運営を支える中枢システムを長年にわたり構築・運用してきた。自動車登録データを一元管理する「自動車登録検査システム(MOTAS)」、全省庁の会計業務を統合する「官庁会計システム(ADAMS)」などがその代表例である。近年では、行政手続きをオンライン化する「マイナポータル(ぴったりサービス)」の開発を手掛け、デジタル庁の推進する行政DXの中核を担っている。
金融・決済分野では、日本のキャッシュレス化を支えてきたクレジットカードネットワーク「CAFIS」が象徴的だ。35年以上にわたり、全国の銀行・カード会社・小売事業者を結ぶ決済基盤として稼働し続けている。また、インターネットバンキングの基盤を築いた「ANSER」は、今や全国の銀行で不可欠なインフラであり、同社の高い信頼性と継続的なメンテナンス力を示している。
さらに三菱UFJ銀行やりそな銀行のデジタル戦略策定支援、法人向けクラウド会計連携システム「AnserDATAPORT」など、金融DX分野での伴走型支援も拡大している。
法人領域では、製造・流通・サービスなど多様な産業に向けたDX支援を展開している。トヨタ紡織の社内DX展示会「DX EXPO」の支援や、旭化成におけるグローバルマーケティング改革プロジェクトなど、業務とシステムを一体化した伴走型の変革支援が特徴だ。
**これらの国内実績が示すのは、単なる技術力ではなく「運用品質における世界基準」**である。公共インフラを無停止で支える経験から生まれた「日本型実装力」は、グローバル展開において品質を象徴するブランド資産となっている。佐々木裕社長は「国内事業は品質のショーケースであり、グローバル市場での信頼の礎だ」と語る。
表:主要国内事業分野と代表プロジェクト
| 分野 | 主なシステム | 特徴 |
|---|---|---|
| 官公庁・自治体 | MOTAS、ADAMS、マイナポータル | 社会基盤のデジタル化推進 |
| 金融 | CAFIS、ANSER、AnserDATAPORT | キャッシュレス・決済基盤を支える |
| 法人 | トヨタ紡織DX支援、旭化成データ統合 | 業務改革とDX人材育成の支援 |
NTTデータの国内事業は、安定的な収益を生み出す一方で、同社が海外で競合他社と戦う上での「信頼の証明」であり、日本的品質を武器にしたグローバル戦略の起点でもある。
海外事業の成長ドライバー:データセンターと生成AIが牽引する新時代
グローバル再編を経て、NTTデータグループの海外事業は同社の成長エンジンとして急速に存在感を高めている。中でも中核を成すのが、データセンター事業とAI関連ソリューションである。
NTTデータは、NTT Ltd.との統合により世界3位のデータセンター事業者としての地位を確立した。生成AIの普及やクラウドシフトの加速により、計算資源への需要は世界的に急増しており、データセンターはその要となっている。GTSS(Global Technology and Solution Services)部門は、2025年3月期において売上4,100億円、EBITA310億円を記録し、海外全セグメント中で最も高い成長を示した。
システム開発からインフラ運用までをワンストップで提供できる「フルスタック・モデル」は、他のグローバルSIerにはない強みである。特に生成AIを利用する大規模案件では、膨大なデータ処理を担うデータセンターが不可欠であり、アプリケーションとインフラを統合的に提供できるNTTデータの価値が急上昇している。
一方で課題も明確だ。アジア太平洋地域(APAC)では不採算案件の影響でEBITAが▲102億円となり、プロジェクト管理やコスト統制が急務とされている。これは統合後のPMI(Post-Merger Integration)の最終段階であり、地域ごとの経営ガバナンス強化が今後の成長の鍵となる。
海外での成功事例としては、欧州の大手製造業におけるクラウド移行支援や、米国企業との共同によるAI主導のサプライチェーン最適化プロジェクトが挙げられる。これらは「つくる」と「つなぐ」を融合したNTTデータ独自の提供モデルの有効性を示している。
表:2025年3月期 海外セグメント主要実績(単位:億円)
| 地域 | 売上高 | 前期比 | EBITA | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| North America | 11,180 | +351 | 590 | AI・クラウド案件が好調 |
| EMEAL | 11,100 | +230 | 530 | データセンター需要増 |
| APAC | 3,100 | +60 | 10 | 不採算案件の影響 |
| GTSS | 4,100 | +322 | 310 | 増収増益を達成 |
海外事業の成長は、単に規模拡大ではなく「収益性のあるグローバル化」を実現するかどうかにかかっている。佐々木社長は「AIとデータセンターを両輪とする新たな事業モデルで、海外事業の質的転換を進める」と強調する。
この発言が示す通り、NTTデータはもはや日本企業という枠を超え、世界のデジタルインフラを支える中核プレイヤーとしての責任と野心を明確に掲げているのである。
生成AI投資が生む生産性革命:1,000億円投資の狙いと実装力の進化

NTTデータグループは、生成AIの導入を単なる業務効率化の手段ではなく、事業構造そのものを再定義する成長エンジンと位置づけている。2026年までにAI関連領域へ1,000億円規模の投資を行う計画を掲げ、開発プロセスの自動化と顧客向けソリューション創出の両輪で改革を進めている。
同社のAI戦略は明快である。第一に、「社内生産性の飛躍的向上」。システム開発における工数の大半を占めるプログラミングやテスト工程に生成AIを組み込み、人件費構造を抜本的に変えることを狙う。社内ではGitHub Copilotを全社導入し、開発者の生産性が平均40〜70%向上するという成果を得ている。特にJavaバージョンアッププロジェクトでは、コード生成とテスト自動化のAI連携により従来の半分以下の期間で納品可能となった。
第二に、**「顧客業務へのAI適用」**である。東京海上日動火災保険では、保険金支払い説明書類を自動生成するAIシステムを構築。担当者の負担を削減し、顧客対応の迅速化を実現した。また、ライオン株式会社では熟練技術者の暗黙知をAIで形式知化し、製造現場の品質維持と人材育成を支援している。
さらに、NTT研究所が開発した日本語特化型大規模言語モデル「tsuzumi」を活用し、国内産業の特性に最適化したAIサービスを展開している点も特筆に値する。社内開発環境「LITRON」では、AIによるドキュメント解析やナレッジ抽出が可能となり、開発の質的向上とナレッジ共有の効率化を同時に実現した。
箇条書きで整理すると、NTTデータの生成AI戦略の要点は次の通りである。
・開発効率を40〜70%改善する内製AIツール導入
・大企業顧客における生成AIソリューションの商用展開
・日本語特化型LLM「tsuzumi」による独自AIプラットフォーム構築
・AI人材育成と倫理ガバナンスの強化による社内文化転換
**AIによる自動化は単なる効率化ではなく、品質保証・コスト最適化・顧客価値創出を同時に満たす“第四の生産革命”**として位置づけられている。佐々木裕社長は「AIは人の仕事を奪うのではなく、人の価値を拡張する技術」と語る。NTTデータの生成AI活用は、単なる技術導入を超え、企業文化・経営構造そのものを変革するプロジェクトに進化している。
IOWN構想が切り拓く次世代インフラ戦略:光技術が変えるデータセンターの未来
NTTデータグループの競争優位性を根底で支えるのが、親会社NTTが主導する次世代通信基盤「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)」構想である。これは、通信・コンピューティング・データ処理のすべてを光ベースで統合することで、情報伝達の効率を飛躍的に高める世界的プロジェクトである。
同構想の中核技術である「オールフォトニクス・ネットワーク(APN)」は、従来の電子伝送から光伝送への全面移行を目指しており、電力効率100倍、伝送容量125倍、通信遅延1/200という圧倒的性能を実現する。これにより、データセンター間を超高速で接続し、地理的距離に制約されない「分散型超低遅延ネットワーク」が可能となる。
佐々木社長はこの技術を**「データセンター事業の競争構造を根底から変える鍵」**と位置づける。従来、AIモデルの学習やクラウド処理ではデータセンター間の距離が遅延コストとしてボトルネックとなっていた。しかしAPN導入により、遠隔地のセンター同士をまるで隣接しているかのように連携させることができ、分散処理性能を飛躍的に高められる。
このIOWN連携は、NTTデータのデータセンター事業の差別化要素として極めて大きい。競合するアクセンチュアやIBMが他社インフラに依存するのに対し、NTTデータは**自社グループ内でネットワークからコンピューティング層まで垂直統合できる「アンフェア・アドバンテージ」**を持つ。
また、環境面でもIOWNは持続可能な成長を支える。光通信を活用した省電力化は、データセンター全体のCO2排出量を最大40%削減できるとされ、カーボンニュートラル経営への寄与も大きい。NTTデータはこれを「グリーン×デジタル」の象徴として位置づけ、持続可能なITインフラモデルの国際標準化を狙っている。
表:IOWN構想の主要技術要素と事業インパクト
| 技術要素 | 主な効果 | 影響領域 |
|---|---|---|
| オールフォトニクス・ネットワーク(APN) | 低遅延・高帯域通信 | データセンター運用 |
| デジタルツインコンピューティング(DTC) | 大規模シミュレーション | 都市・交通・製造 |
| コグニティブファウンデーション | 自律制御による最適化 | ネットワーク運用 |
IOWNを活用した次世代インフラ戦略は、単なる技術革新ではなく、NTTデータが“世界の情報流通の基盤企業”へ進化するための国家規模プロジェクトである。
この光ネットワークを軸に、生成AI・クラウド・データセンターの三領域を統合することで、NTTデータは世界のデジタル経済を支える「次世代の社会OS」を構築しようとしている。
競争環境とNTTデータのポジショニング:世界6位から狙う次のステージ

NTTデータグループは、グローバル再編と完全子会社化を経て、かつての「国内SIer」から脱皮し、世界の巨大ITサービス企業と真正面から競合する立場に立った。現在、同社はガートナーのITサービス売上高ランキングで世界第6位に位置しており、アクセンチュア、IBM、TCSといったトッププレイヤーの背中を視界に捉えている。
一方で、国内市場における競争も熾烈を極める。IDC Japanによる2024年の調査では、国内ITサービス市場でNTTデータは第4位。首位の富士通、急成長する日立製作所、NECが上位を占め、わずかな差で順位が入れ替わる構図となっている。日立製作所は前年比13.3%の売上増を記録し、社会インフラ×デジタル事業の統合が奏功した。NTTデータにとっても、国内市場での収益基盤を維持しつつ、海外での成長を加速させる「二正面戦略」が必須の局面を迎えている。
表:主要ITサービス企業の市場ポジション(2024年時点)
| 市場 | 順位 | 企業名 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 世界 | 1位 | アクセンチュア | コンサル+実装型のモデルを確立 |
| 世界 | 2位 | IBM | AI・クラウドへの再集中 |
| 世界 | 6位 | NTTデータ | フルスタック統合で急成長 |
| 日本 | 1位 | 富士通 | 官公庁・社会基盤で圧倒的地位 |
| 日本 | 4位 | NTTデータ | 公共・金融領域で強みを維持 |
競合環境の中で注目されるのは、NTTデータが**「コンサルからインフラまでを内製できる唯一の日本企業」**である点である。アクセンチュアが外部クラウドやパートナー企業を組み合わせるのに対し、NTTデータはNTTグループの通信・データセンター・AI技術を垂直統合している。これが同社の最大の差別化要素であり、いわば「日本発の総合テック企業モデル」の実証である。
さらに、完全子会社化によってM&A戦略の自由度が高まったことで、世界市場での競争力強化が現実味を帯びている。特に、欧米の中堅IT企業や生成AI関連企業を対象とした**「戦略的買収による非連続成長」**が注目される。
SWOT分析で見ると、同社の立ち位置は以下のように整理できる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 強み | フルスタック・プロバイダー構造、日本型品質、NTTの研究力 |
| 弱み | 海外利益率の低さ、PMI(統合作業)の難度 |
| 機会 | AIとデータセンター市場の拡大、巨大M&Aによる成長余地 |
| 脅威 | グローバル競争の激化、地政学・為替リスク |
アクセンチュアやIBMが生成AIやサステナビリティを中心に事業変革を進める中で、NTTデータは「技術と品質」を核にした日本型成長モデルを提示しつつある。
今後の焦点は、グローバル統合を収益化し、海外事業の利益率をどこまで引き上げられるかである。世界市場でトップ5入りを狙う戦略的転換期に、NTTデータはかつてない注目を集めている。

