かつてカセットテープやCDで世界を席巻したTDKは、いまや全く異なる顔を持つ。記録メディアの象徴から脱却して10年以上、同社はフェライト技術を起点に、エナジー(EX)とデジタル(DX)の双方向変革を推進する“社会課題解決型企業”へと劇的な進化を遂げた。
齋藤昇CEOが掲げた長期ビジョン「TDK Transformation」は、単なるスローガンではない。EXでは全固体電池の実用化、DXではMEMSセンサや磁気ヘッドによるデータ社会支援と、二大潮流の交差点で新たな価値を創出している。
同社の強みは、材料・プロセス・評価・生産という「フェライトツリー」と呼ばれる未財務資本の融合にある。これにより、M&Aで獲得した多様な技術群を有機的に接ぎ木し、事業のエコシステム化を実現。さらにESG経営の深化とROIC重視の財務戦略により、「技術×人材×持続性」を軸に企業価値を最大化する姿勢を明確に打ち出した。
本稿では、EXとDXの双発変革を中心に、TDKがどのように未来社会を支える技術と経営モデルを構築しているのかを、多角的に分析する。
フェライトのDNAから「社会変革企業」へ―TDKの進化軌跡
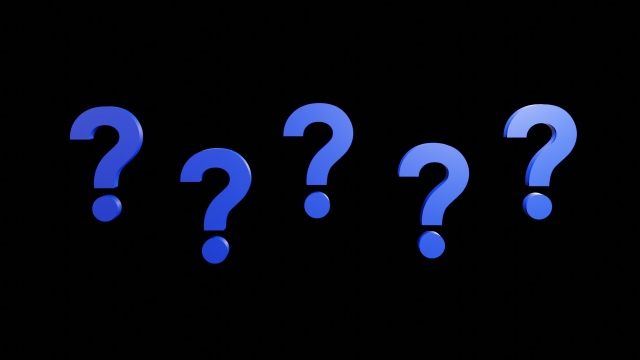
TDKという企業名に、かつて多くの人々は「カセットテープ」や「CD-R」といった記録メディアの象徴を思い浮かべた。しかし、今日のTDKはもはやその面影を残さない。同社は10年以上前に記録メディア事業から完全撤退し、磁性材料フェライトを核とする技術を基盤に、社会変革のソリューション企業へと生まれ変わった。
その変革を牽引したのが、歴代経営陣による戦略的なM&Aである。上釜健宏元社長は自動車電子化の波を捉えて車載事業を強化し、続く石黒成直前社長はIoT時代を見据えたセンサ分野への投資を加速。さらに、2022年に就任した齋藤昇CEOのもとで、M&Aで獲得した多様な事業群を「収益化から融合へ」と導く第二章の変革が始まった。
齋藤CEOは就任時に「人が全て」と明言し、組織の多様性を成長の源泉と位置づけた。この理念は、後に発表される長期ビジョン「TDK Transformation」の核心である「未財務資本の強化」に直結している。技術、知識、顧客基盤、そして人材といった目に見えない資産こそが、同社の持続的な競争優位を形成するとの哲学だ。
TDKの事業構造も劇的に変化している。現在の収益基盤は、以下の4つの柱で構成されている。
| 事業セグメント | 主な製品 | 成長ドライバー |
|---|---|---|
| 受動部品 | コンデンサ・インダクタ | EV化・再エネ |
| センサ応用製品 | TMR・MEMSセンサ | IoT・自動運転 |
| 磁気応用製品 | HDDヘッド・マグネット | 生成AI・データセンター |
| エナジー応用製品 | 二次電池・電源 | スマホ・蓄電システム |
**祖業の磁性材料が「電気を操る力」へ、センサが「世界を感じ取る力」へ、電池が「社会を動かす力」へと進化している。**これらの事業が相互に結びつくことで、TDKはもはや単なる部品メーカーではなく、DX(デジタル変革)とEX(エネルギー変革)の両輪を駆動するプラットフォーム企業へと変貌を遂げている。
この変革の方向性は、AppleやTeslaのように未来社会の基盤を構築する「イネーブラー」への道である。すなわち、製品を供給するのではなく、社会構造そのものを変える存在になること。TDKはその新たな使命を「TDK Transformation」という名で具現化しつつある。
長期ビジョン「TDK Transformation」と新中期経営計画の核心
2024年、創業90周年を目前にしてTDKが打ち出したのが、**初の長期ビジョン「TDK Transformation」**である。このビジョンは、単なる経営スローガンではなく、企業としての存在意義を再定義する羅針盤である。
その中心にあるのが、「社会の変革に貢献するTDK」と「自らを変革し続けるTDK」という二重のトランスフォーメーション思想だ。DX・EXの時代において、社会の要請に応えるだけでなく、自らが未来を創り出す主体となることを明確にした点に特徴がある。
齋藤CEOはこの理念を具体化するため、2025〜2027年度を対象とする新中期経営計画を策定した。期間を「事業基盤強化の3年間」と定義し、以下の3本柱を掲げている。
- キャッシュ・フロー経営の強化:フリーキャッシュフロー最大化を最優先課題とし、資金の生産性を高める。
- ROIC経営による資本効率の徹底:事業ROA(ROIC)8%以上を目標に、投資回収力を基準とする経営を推進。
- フェライトツリーによる未財務資本の強化:技術・人材・顧客基盤などの無形資産を「見える化」し、組織横断で再配置する。
とりわけ注目すべきは、フェライトツリーという独自の経営フレームワークである。これは、TDKの材料技術・生産技術・評価技術を有機的に接続し、M&Aで獲得した技術を“接ぎ木”して成長させる仕組みだ。
この概念により、電池技術がコンデンサ開発に活かされ、磁気ヘッドの薄膜技術がセンサ開発に応用されるなど、部門を超えた技術融合が進む。技術の生態系を企業内部で形成することで、イノベーションの再現性を高める構造的な強さを実現した。
さらに、TDKは2027年3月期に以下の数値目標を掲げている。
| 指標 | 目標値 | 背景 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2兆5,000億円 | 年平均成長率約5% |
| 営業利益率 | 11%以上 | 高付加価値事業比率の拡大 |
| ROE | 10%以上 | ROIC経営の定着 |
同社はこの目標を達成するため、3年間で1,500億円の戦略投資を実施し、特にエナジー応用製品・受動部品・センサ領域に集中投下する計画である。
「ハードの拡大からソフトの融合へ」――齋藤体制のTDKは、技術の統合と人材の多様性を武器に、企業の新陳代謝を続ける。 それこそが、真の意味での「Transformation」の実践である。
4つの事業セグメントが描く成長ポートフォリオの全貌

TDKの現在の競争力は、単一事業への依存を脱し、複数の成長エンジンを並行稼働させる多層的な事業ポートフォリオにある。「受動部品」「センサ応用製品」「磁気応用製品」「エナジー応用製品」という4つの柱が、景気循環や技術トレンドの変化に柔軟に対応する構造を支えている。
まず、エナジー応用製品は全社売上の約半分を占める最大セグメントであり、スマートフォン向け小型二次電池で世界首位級のシェアを誇る。子会社ATLが供給するリチウムポリマー電池は、Appleをはじめとする主要スマートフォンメーカーに採用されており、ICT市場の動向が業績に大きく影響する。さらにTDKは中型電池事業を「第二章」と位置づけ、CATLとの合弁会社を通じてEVや家庭用蓄電池市場への本格参入を進めている。全固体電池の研究開発も加速し、EX(エネルギートランスフォーメーション)領域での存在感を一段と高めている。
次に、センサ応用製品はIoT時代の“感覚器官”を担う事業である。TMR(トンネル磁気抵抗)センサやMEMS(微小電気機械システム)センサが主力で、2022年に黒字化を達成して以降、安定的な収益確保を目指す第二段階に入っている。自動車の電動化・自動運転、産業IoT、ウェアラブルデバイスなど、現実世界をデジタル化する最前線に位置する事業として期待が高い。
また、磁気応用製品は祖業フェライト技術を継承する事業群であり、HDD用磁気ヘッドを中心に展開している。データセンターのHDD需要は生成AIの普及で再び拡大傾向にあり、TDKは東芝やWestern Digitalと連携しながら、HAMR(熱アシスト磁気記録)とMAMR(マイクロ波アシスト磁気記録)の両技術を開発する。記録密度100TB時代を見据えた技術革新が、データ社会の基盤を支える鍵となる。
最後に、受動部品事業は電子回路の必須インフラであり、自動車の電子化や再生可能エネルギーシステムの拡大が牽引力となる。MLCC(積層セラミックコンデンサ)やインダクタといった製品は、村田製作所などとの激しい競争の中でも高信頼性を武器に堅調に推移している。特に再エネ向け電源や産業機器向けでの需要が増加しており、TDKの材料技術が高温・高圧環境でも安定動作を実現する強みを発揮している。
4事業セグメントの特性をまとめると以下の通りである。
| セグメント | 売上構成比 | 主な市場 | 成長ドライバー |
|---|---|---|---|
| エナジー応用製品 | 約50% | ICT・EV・ESS | スマホ更新・再エネ化 |
| 受動部品 | 約24% | 自動車・産業 | EV・再エネ需要 |
| センサ応用製品 | 約10% | IoT・車載 | DX・自動運転 |
| 磁気応用製品 | 約16% | データセンター | 生成AI・HDD需要 |
このように、TDKの事業群はEXとDXのメガトレンドに緻密に対応しており、短期的な市場変動に強く、長期的な成長を描ける構造的ポートフォリオを確立している。
EX(エネルギートランスフォーメーション)を牽引する全固体電池革命
TDKの全固体電池は、エネルギー産業の構造を根底から変える可能性を秘めた「次世代バッテリー革命」である。2024年6月、同社は従来製品比100倍となるエネルギー密度1,000Wh/Lを達成した新材料を発表し、業界に衝撃を与えた。酸化物系固体電解質とリチウム合金負極を組み合わせることで、可燃性電解液を使わず高い安全性と高出力を両立した点が画期的である。
TDKはこの技術のターゲットをまずウェアラブルデバイスに定め、ワイヤレスイヤホン、補聴器、スマートウォッチなど、身体装着型デバイスへの搭載を視野に入れる。**「発火しない電池」「極小でも長寿命」**という特性は、これまで設計制約の多かったマイクロデバイス市場に新たな地平を開く。さらに、EUの環境規制により、使い捨て一次電池から充電可能な二次電池への転換が求められており、同技術は環境負荷低減にも貢献する。
TDKが全固体電池で優位に立つ最大の理由は、**電子部品分野で培ったセラミック多層化技術の存在である。**セラミックコンデンサ製造で磨いた微細積層・焼結技術をそのまま応用できるため、量産化への移行スピードとコスト競争力で他社をリードする。
開発ロードマップでは、まずマイクロセル型製品を量産化し、次段階としてウェアラブル・IoT分野への供給拡大を計画。さらに中長期的には、モビリティ・エネルギーストレージ向けの大型化にも挑戦する。TDKは全固体電池を**「デバイスの設計思想そのものを変えるプラットフォーム技術」**と位置づけており、単なる部品供給を超えて新産業創出に寄与しようとしている。
アナリストの間では、この技術が商業化されればTDKのバリュエーションを根底から押し上げる「ゲームチェンジャー」になるとの見方が強い。安全性・高エネルギー密度・環境適合性を兼ね備えた全固体電池は、EX時代における最重要インフラのひとつとなる可能性が高い。
DX(デジタルトランスフォーメーション)を支えるセンサ・磁気技術の最前線

TDKの成長を支えるもう一つのエンジンが、デジタル社会の中枢を担うセンサおよび磁気応用技術である。TDKは、現実世界の物理現象をデータ化する“感覚器官”としてのセンサ群と、情報を保存・流通させる“神経系”としての磁気技術を両輪に、DX時代の基盤を形成している。
とりわけ注目されるのが、グループ会社InvenSense社が開発した特許製法「Nasiriプロセス」である。これは、MEMS構造を形成したウエハをCMOS回路上に直接封止することで、従来のワイヤボンディングを不要にした革新的工法だ。これにより、センサの小型化・高信頼性・低コスト化を同時に実現。スマートフォンのモーション制御やAIスピーカーの音声認識、さらにはウェアラブル血圧計など、多様なIoTデバイスに搭載されている。
TDKはまた、センサにAI処理機能を搭載する「エッジAI」技術を強化している。これにより、センサが自律的にデータ解析を行い、クラウドに送信する情報量を最適化できる。デバイスの省電力化、通信遅延の削減、個人情報保護という三大課題を同時に解決する点で、TDKのMEMSセンサは世界市場でも高い評価を受けている。
磁気応用技術では、生成AIの普及により爆発的に増加するデータを支えるHDD用磁気ヘッド分野が焦点となる。TDKは、HDD記録密度を飛躍的に向上させるHAMR(熱アシスト磁気記録)およびMAMR(マイクロ波アシスト磁気記録)の両技術開発を推進中である。レーザーやマイクロ波を用いて記録媒体の保磁力を一時的に低下させることで、より細かな磁区にデータを記録することを可能にしている。
特に、HAMR技術では東芝やレゾナックと共同で32TB級HDDの開発に成功しており、MAMRではWestern Digitalと連携して量産化フェーズに入っている。TDKの磁気ヘッド技術は、データセンターや生成AI向けのストレージ需要拡大に不可欠な存在となっている。
さらに、TDKはこれらの技術を車載領域にも応用している。車載用ホールセンサや角度センサは、自動運転やADAS(先進運転支援システム)の精密制御において欠かせない要素であり、同社は自動車1台あたりのセンサ搭載数増加を背景に、長期的な成長余地を確保している。
| 技術領域 | 主な用途 | TDKの強み |
|---|---|---|
| MEMSセンサ | スマホ・IoT・車載 | Nasiriプロセスによる小型高精度化 |
| 磁気ヘッド | データセンター・AI | HAMR/MAMR両対応の開発体制 |
| エッジAIセンサ | ウェアラブル・産業IoT | 低消費電力とプライバシー保護 |
TDKのDX技術は単なる電子部品の集合ではなく、「感知・解析・記録」というデータ社会の根幹を支える知的インフラである。
同社が描く未来は、センサが世界の情報を“感じ取り”、磁気がそれを“記憶する”——この連動こそが、デジタル文明の心臓部を形成している。
サステナビリティとESG経営が生む企業価値の新方程式
TDKの経営哲学の中核には、「環境と共に成長する企業」という強固な信念がある。サステナビリティは同社にとってCSR(企業の社会的責任)ではなく、事業戦略そのものである。
2024年度に発表された「TDK United Report」は、統合報告書を超える戦略的ドキュメントとして位置づけられ、取締役会での審議対象にもなっている。ここで明示されたのが、「サステナビリティと企業価値の融合」である。TDKはESG経営を財務・非財務の両面から定量的に管理し、経営戦略へ組み込む体制を確立している。
具体的には、「TDK環境ビジョン2035」のもと、製品ライフサイクル全体でのCO2排出原単位を2035年までに50%削減する目標を掲げている。さらにSBTi(Science Based Targets Initiative)による認定を受け、Scope3(サプライチェーン全体)排出量の25%削減を2030年度までに達成する計画である。
注目すべきは、TDKが自社製品のCO2削減貢献量を定量的に開示している点だ。2024年度の削減貢献量は703.8万トン(前年比35.2%増)に達し、**製品売上の77.5%が「環境貢献型製品」として定義されている。**この透明性の高い報告姿勢は、日経統合報告書アワードで3年連続優秀賞を受賞するなど、社外からも高い評価を得ている。
TDKのESG評価は世界的にも高水準である。CDPの「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に5年連続選出され、EcoVadisでは評価対象企業上位1%のみが得られるプラチナ評価を獲得。MSCIやFTSE4Goodなど、主要ESG投資インデックスにも採用されている。これらの高評価は、資金調達コストの低減や優秀人材の確保といった実利にも直結している。
さらに、TDKはサステナブルファイナンスにも積極的である。グリーンボンドの発行や、ESG指標連動型融資を通じて、環境投資と資本効率を両立。ROIC経営の枠組みの中で、非財務指標と財務KPIを統合する先進的な経営モデルを確立している。
| 指標 | 実績/評価 | 意義 |
|---|---|---|
| CO2削減貢献量 | 703.8万トン(前年比+35.2%) | 製品が社会のEXに直接貢献 |
| ESG評価 | EcoVadis プラチナ、CDP 5年連続選定 | 国際的な信頼獲得 |
| 環境貢献製品比率 | 77.5% | 事業の持続可能性を定量化 |
サステナビリティを“コスト”ではなく“価値創造の源泉”として扱うことこそ、TDKの真の革新である。
EX・DXの両軸で社会課題を解決しながら、環境配慮と利益成長を両立させる姿勢は、まさに「技術で世界を良くする企業」の理想形と言える。
株主還元・ROIC経営に見る「成長と規律」の両立戦略

TDKの成長戦略を支える根幹は、「ROIC経営による資本効率の徹底」と「株主価値の最大化」を両立させる企業統治モデルにある。近年、グローバル投資家の評価軸は「利益水準」から「資本の使い方」へと移行しており、TDKはこの潮流を先取りして経営方針を刷新した。
同社が掲げる数値目標は明快である。2027年3月期までにROE10%以上、事業ROIC8%以上、営業利益率11%以上を達成すること。これを実現するため、キャッシュフロー経営を強化し、投資配分を高収益領域に集中させている。資本を“働かせる”経営への転換が、旧来の規模拡大型から質的成長型へのシフトを象徴している。
財務面での健全性も際立つ。2025年3月期の連結売上高は2兆2,048億円、税引前利益2,378億円、親会社株主に帰属する純利益1,671億円を記録。営業活動によるキャッシュフローは安定的に創出され、M&Aや設備投資などの成長投資を十分に支える余力を維持している。
一方で、株主還元方針も明確に強化された。配当性向の目安を30%から35%に引き上げ、3年間で1,500億円の株主還元を計画。加えて、機動的な自社株買いを実施する可能性も示唆しており、資本市場へのシグナル効果を重視する姿勢が鮮明だ。
| 項目 | 政策内容 | 意義 |
|---|---|---|
| 配当性向 | 35%目安へ引き上げ | 株主価値重視の姿勢を明確化 |
| 戦略投資枠 | 3年間で1,500億円 | 成長事業への選択的資金配分 |
| ROIC目標 | 8%以上 | 投下資本効率の向上 |
| ROE目標 | 10%以上 | 株主資本の生産性向上 |
また、資本効率指標であるROICを事業評価の基準に据え、事業ポートフォリオの再構成を進めている。採算性の低い領域については撤退・再編も辞さず、高収益事業への資源集中を断行する方針だ。
市場からの評価も高く、主要証券各社はTDK株を「やや強気」から「強気」に格上げし、目標株価を2,100円〜2,450円に引き上げている。投資家は、財務規律と成長投資のバランスが取れた経営姿勢に信頼を寄せている。
ROIC経営の本質は「事業の自己採算性を問う経営文化の定着」にある。TDKはこの考え方を経営全層に浸透させ、資本の回転効率とイノベーションの両立を図る。つまり、単なる財務指標ではなく、「組織の思考様式」としてのROIC経営を体現しつつある。
TDKの次なる挑戦―技術革新と人材多様性が切り開く未来
TDKの未来戦略を語る上で欠かせないのが、「人」と「技術」の融合による変革である。齋藤昇CEOが掲げる「人が全て」という言葉は、単なるスローガンではなく、同社の経営哲学そのものを示している。多様な人材の創造性を最大限に引き出し、技術革新と経営改革を両輪で進めることが、TDKの成長の本質である。
TDKは全世界で約10万人の従業員を抱え、60を超える国・地域に拠点を展開している。近年では、グローバル人材の登用を加速させ、経営幹部層における外国籍人材比率を高めている。これにより、意思決定の多角化と市場対応力の向上を図っている。
人材戦略の柱となるのが、「フェライトツリー」に象徴される未財務資本の強化である。TDKは、技術・知識・人材・顧客基盤といった無形資産を「組織的知」として可視化し、横断的に活用することで、M&Aで獲得した多様な企業文化や技術群を有機的に統合している。
教育・研修制度もグローバル基準で整備されており、AI・データサイエンス・環境技術といった次世代スキルの育成を重視。女性技術者比率も年々上昇しており、ジェンダーダイバーシティの推進がイノベーション創出に寄与している。
さらに、TDKはオープンイノベーションにも積極的である。大学やスタートアップとの共同研究を通じ、量子材料、ナノプロセス、エッジAIなどの先端技術を探索。特に、京都大学や東京工業大学との連携では、次世代電池材料や環境エネルギー素子の実用化に向けた研究が進行中である。
| 成長基盤 | 重点領域 | 具体的施策 |
|---|---|---|
| 人材多様性 | 女性・外国人比率向上 | グローバル登用制度の強化 |
| 技術革新 | 全固体電池・MEMS・パワーエレクトロニクス | 産学連携・オープンイノベーション |
| 組織文化 | 未財務資本の可視化 | フェライトツリー経営の深化 |
TDKの未来は、既存の技術を磨くだけでなく、「人が創る新しい価値の体系」をいかに育てるかにかかっている。齋藤CEOが強調する「多様性がもたらす可能性の最大化」は、AIやエネルギー技術だけでなく、経営そのものをアップデートする指針である。
EXとDXの融合、そして人間の創造性。この三つの軸が噛み合ったとき、TDKは“未来を定義する企業”へと進化する。
その変革は、単なる企業成長ではなく、日本の製造業が再び世界の中心へ返り咲くための象徴的なモデルケースとなるだろう。

