アサヒグループホールディングスは今、創業以来最大の転換点に立っている。
かつては日本の代表的ビールメーカーであった同社は、欧州・オセアニア・東南アジアを含む世界4極の事業体を統合し、真のグローバルプレイヤーへと変貌を遂げようとしている。年間売上収益2.9兆円を超え、100億リットル以上の飲料を世界で提供する同社の成長を支えるのは、「プレミアム化」と「グローカル経営」という二本柱である。
その背後には、企業理念「Asahi Group Philosophy(AGP)」と、社外取締役が過半を占める先進的なガバナンス体制がある。さらに、M&A後の統合を成功させた実行力、そして「スマートドリンキング」「サステナビリティ」「DX」「R&D」を結合した長期戦略が、持続的成長の基盤を形成している。
本稿では、アサヒグループが「各事業の総和を超える価値」を創造するために進める構造改革の全貌を明らかにし、経営理念、事業戦略、財務体質、ブランド革新、そして未来への展望を多角的に読み解く。グローバル経営の最前線で進む「第二の創業」の実像に迫る。
世界を統合するアサヒの「第二の創業」

アサヒグループホールディングスは、単なる日本の飲料メーカーという枠を超え、真のグローバル企業へと進化を遂げつつある。創業から100年以上を経た今、同社は「地域事業体の集合」から「統合されたグローバル経営体」への転換という、第二の創業とも言うべき大改革の最中にある。
この変革の核心にあるのが、「グローカル価値創造企業」というビジョンである。グローバルな経営基盤を持ちながらも、各地域市場の文化や嗜好に深く根ざした価値を生み出すという発想だ。これにより、世界の多様な市場でプレミアムブランドを確立しながら、地域消費者との共感的な関係を築いている。
アサヒグループは現在、欧州・オセアニア・東南アジア・日本の4つの地域統括会社(RHQ)による分権体制から、CxO(最高責任者)を中心とした統合経営モデルへ移行している。2025年には、各地域CEOが経営中枢に参画する「Executive Committee(執行委員会)」を設立し、グループ全体での意思決定スピードと実行力を強化した。この新体制は、地域の独自性とグローバル規模の効率性を両立するための設計思想に基づいている。
さらに、同社が2024年に掲げた中長期方針では、「おいしさと楽しさで“変化するWell-being”に応える」というコンセプトを中心に据えている。これは、単なる飲料の提供を超え、人々の心身の健康や社会的幸福を支える企業へと進化する決意の表明である。
財務面でも、売上収益2.9兆円、事業利益2,851億円という過去最高の実績を記録し、海外事業比率は売上の50%超に達した。アサヒグループは今や「日本企業の国際化成功モデル」として、経済産業省や金融機関からも高く評価されている。
その一方で、課題も明確だ。特に、オセアニア市場の競争激化や為替影響による利益圧迫など、グローバル事業拡大に伴うボラティリティリスクが浮上している。だが同社は、こうした課題を単なる障害ではなく「経営高度化の契機」と捉え、リスク管理・資本配分・ESG統合経営の三位一体化を進めている。
アサヒの第二の創業期は、「規模の拡大」ではなく「価値の統合」に焦点を当てた知的進化である。その中核にあるのは、各事業の総和を超える企業価値の創造という理念であり、この方向性こそが、次の10年を決定づける羅針盤となる。
理念とガバナンスが支えるグローバル経営の骨格
アサヒグループの進化を根底で支えるのは、「Asahi Group Philosophy(AGP)」と呼ばれる共通理念と、グローバル基準のコーポレートガバナンスである。AGPは単なるスローガンではなく、世界の従業員約3万人を一つに束ねる経営思想の共通言語として機能している。
AGPは以下の4要素で構成される。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| Mission | 「期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造」 |
| Vision | 「高付加価値ブランドを核として成長する“グローカルな価値創造企業”」 |
| Values | 「挑戦と革新」「最高の品質」「感動の共有」 |
| Principles | ステークホルダー全体との共創による企業価値向上 |
この理念を現場レベルに浸透させる仕組みとして、「AGP AWARDS」による表彰制度が存在する。世界各地の従業員が自発的に理念を体現する取り組みを共有し、全社的に称えることで、理念を“生きた文化”として根付かせている。
ガバナンス面では、アサヒグループは国内企業の中でも先進的な体制を誇る。社外取締役比率は過半を超え、女性取締役が5名、外国籍取締役が2名と多様性に富む。特に2025年3月には「指名委員会等設置会社」へ移行し、監督と執行を完全に分離する構造へと刷新した。これにより、経営判断の透明性と迅速性が大幅に高まった。
また、取締役会長とCEOの役割分離、独立した社外委員長による報酬・指名委員会の運営など、グローバル水準の統治構造を確立。M&Aや投資判断の際には、欧州CEO経験者やM&A専門家が社外取締役として助言し、リスクテイクとガバナンスのバランスを最適化する経営モデルを構築している。
特筆すべきは、ガバナンスを「防御」ではなく「攻めの経営基盤」として活用している点である。多様な視点を持つ取締役が議論に参加することで、戦略決定の質が高まり、国際M&Aなど高リスク案件でも迅速な意思決定が可能になっている。
このように、理念の共有とガバナンスの進化が相まって、アサヒグループは「挑戦と革新」を持続可能な形で推進する企業体へと成熟している。AGPが精神的な羅針盤なら、ガバナンスはその実行を支える骨格であり、両者の融合こそが、アサヒが世界で勝ち続けるための経営インフラとなっている。
プレミアム戦略と5大ブランドによる成長エンジン
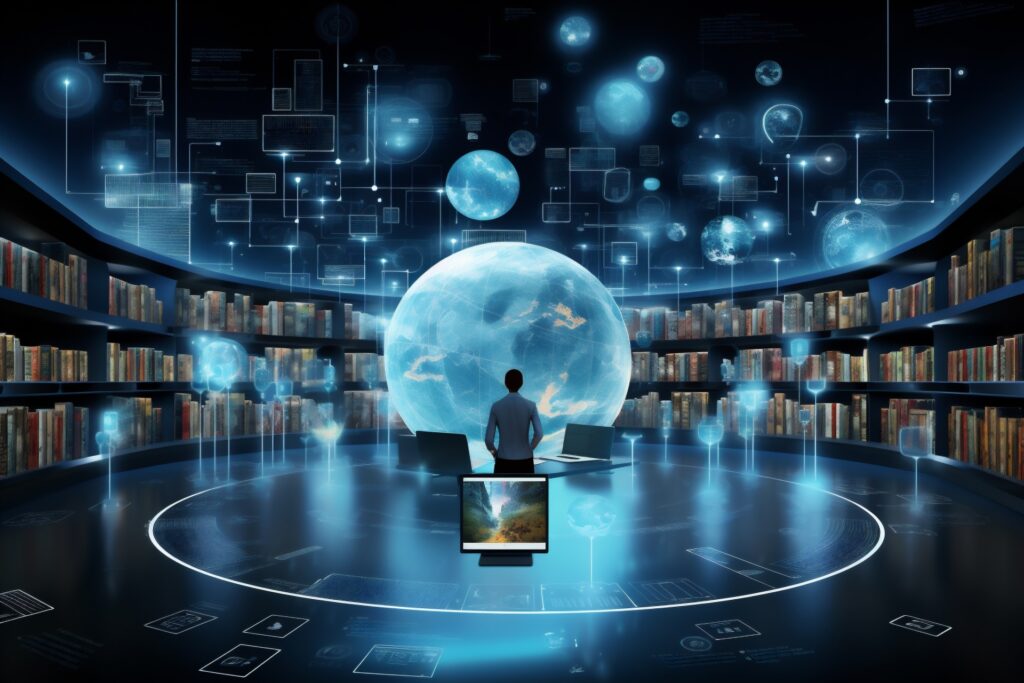
アサヒグループホールディングスの成長を牽引する最大の原動力は、明確に定義された「プレミアム戦略」である。これは、単に高価格帯の商品を販売するということではなく、ブランド体験そのものを通じて消費者に特別な価値を提供する経営戦略である。
同社が世界的に展開する5つのグローバルブランド——『Asahi Super Dry』『Peroni Nastro Azzurro』『Pilsner Urquell』『Grolsch』『Kozel』——は、その象徴的存在だ。これらは単なる輸出ブランドではなく、現地生産・現地流通を徹底し、各国市場に適応する形で成長している。特に『Asahi Super Dry』は、欧州を中心に現地醸造体制を構築し、輸送コスト削減と鮮度保持を両立。ラグビーワールドカップやシティ・フットボール・グループとのパートナーシップを通じ、グローバルブランドとしての地位を不動のものとした。
以下の表は、2020年から2023年にかけてのグローバル5ブランドの販売成長率を示すものである。
| ブランド名 | 主な市場 | 年平均成長率(CAGR)2020-2023 | 主な施策 |
|---|---|---|---|
| Asahi Super Dry | 欧州・アジア | +10% | 現地生産化・スポーツマーケティング |
| Peroni Nastro Azzurro | 欧州・北米 | +8% | プレミアムポジショニング・デザイン刷新 |
| Pilsner Urquell | 欧州 | +6% | チェコ本拠地醸造強化 |
| Grolsch | 欧州北部 | +4% | クラフト志向消費層の獲得 |
| Kozel | アジア | +9% | 新興市場向け展開 |
特に注目すべきは、『Asahi Super Dry』がグローバル全体で年平均9%の販売成長を維持し、同社のプレミアム戦略を牽引している点である。2024年には欧州で前年比10%の販売増を記録し、同社売上の中核を担った。
また、アサヒグループは「グローカル(Global × Local)」の考え方を徹底し、地域文化に根ざしたブランド戦略を展開している。オーストラリアでは「Great Northern Zero」、東南アジアでは乳製品や清涼飲料における健康志向ブランドを育成し、ローカル市場特性を尊重した成長モデルを構築した。
これらのブランド戦略の根底には、「消費者体験価値の最大化」という一貫した理念がある。高付加価値な製品ポートフォリオを核に、“飲むことの体験”そのものを再定義するプレミアム化の深化が、アサヒを他社との差別化へ導いている。
M&Aと統合力が生んだグローバル・シナジー
アサヒグループのグローバル化を決定づけたのは、2016年から続く一連の大型M&Aである。特に、2020年に完了したオーストラリアのCUB(Carlton & United Breweries)買収は、企業史上最大規模のディールであり、同社の事業構造を一変させた。
アサヒはM&Aを単なる買収拡大ではなく、「経営統合を通じた価値創造」と位置づけている。CUB買収後のPMI(Post Merger Integration:統合プロセス)では、想定していたコストシナジーを2年前倒しで達成し、驚異的なスピードでシナジー創出を実現した。統合後、メルボルンとシドニーに分散していた拠点をWeWorkシドニーへ統合し、部門横断のコラボレーションを促進。文化の融合と意識改革を同時に進める“ソフト統合”の成功例として、欧州のビジネススクールでも研究対象となった。
M&Aの実績を俯瞰すると、アサヒの戦略的眼力が際立つ。
| 年 | 買収案件 | 取得金額(億円) | 主な効果 |
|---|---|---|---|
| 2016 | SABミラー欧州事業 | 約12,000 | 欧州市場進出の足掛かり |
| 2019 | カールトン&ユナイテッド・ブリュワリーズ(CUB) | 約12,000 | オセアニア市場の主導権確保 |
| 2020 | Peroni・Pilsner Urquell等のブランド権益 | 約7,000 | プレミアムブランド群の取得 |
一方で、統合後の課題も浮き彫りとなっている。2024年度の決算では、欧州事業が価格改定とプレミアム化で好調を維持する一方、オセアニア事業は市場競争の激化で減益に転じた。特に『Great Northern』『Victoria Bitter』といった主力ブランドが豪州市場の景気動向に大きく依存しており、市場縮小リスクとブランド構造の脆弱性が露呈した。
しかし、アサヒはこれを成長の「再設計期」と捉え、低アルコール市場やゼロビールなどの新カテゴリー開発に注力。『Great Northern Zero』のような革新的ブランドを投入し、次世代型市場創造に挑んでいる。
M&Aによって得た規模の経済、現地生産体制、グローバル調達ネットワークは、今や同社の競争優位の中核にある。さらに、欧州とオセアニアで培った統合ノウハウは、今後の新興国展開や新規M&Aにおいて重要な経営資産となる。
アサヒのM&A戦略は、単なる拡大ではなく、「統合による革新」こそが企業成長の本質であるという経営哲学の体現であり、これが他の日本企業にはない真のグローバル競争力を生み出している。
財務健全化と株主還元方針に見る経営の成熟

アサヒグループホールディングスは、過去数年にわたる大型M&Aで拡大した事業ポートフォリオを統合し、財務健全性の回復と株主還元の強化という二つの成果を同時に実現した。2024年12月期の連結業績は、売上収益2兆9,394億円(前期比6.2%増)、事業利益2,851億円(同8.1%増)と過去最高を更新し、収益性と資本効率の両立に成功した稀有な例である。
財務体質の改善を測る代表的指標であるNet Debt/EBITDA倍率は2.49倍まで低下し、同社が掲げる中期目標レンジ(2.5~3.0倍)を下回った。これは、欧州・豪州買収に伴う負債の圧縮をほぼ完了させたことを意味する。背景には、年平均2,530億円という安定したフリーキャッシュフロー(FCF)の創出がある。アサヒは、事業利益を着実に現金化できるビジネスモデルを確立し、「稼ぐ力」に裏打ちされた財務の健全性を取り戻した。
以下は、直近5年間の主要財務指標の推移である。
| 決算期 | 売上収益(億円) | 事業利益(億円) | 事業利益率 | Net Debt/EBITDA倍率 | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 20,297 | 1,819 | 8.9% | 3.9倍 | 34.0% |
| 2021年 | 22,361 | 2,137 | 9.6% | 3.4倍 | 36.2% |
| 2022年 | 25,974 | 2,438 | 9.4% | 2.9倍 | 38.5% |
| 2023年 | 27,691 | 2,637 | 9.5% | 2.7倍 | 39.8% |
| 2024年 | 29,394 | 2,851 | 9.7% | 2.49倍 | 40.6% |
注目すべきは、配当性向が40.6%に達し、2025年に目標としていた「配当性向40%」を1年前倒しで達成した点である。さらに、DOE(株主資本配当率)4%以上を目安とした累進配当方針を導入し、自己株式取得を柔軟に組み合わせる姿勢を明確にした。
株主還元の強化は、単なる利益の分配ではない。経営陣が中長期の収益安定性に確信を持っている証左である。M&A期を経て、財務の安定とキャッシュ創出力を取り戻した今、アサヒは投資・還元・成長の好循環を描き出しつつある。
また、海外事業が利益の6割を占める中で、為替リスクや原材料価格の変動にも柔軟に対応するリスクヘッジ体制を構築。財務の“守り”と株主への“攻め”を両立させることで、資本効率経営を深化させている。アサヒは、財務基盤の強化を単なる数値改善にとどめず、「成長を支える経営戦略そのもの」として再定義したと言えるだろう。
サステナビリティとスマートドリンキングの融合
アサヒグループは、「サステナビリティを経営そのものに統合する」という明確なビジョンを掲げ、環境・社会・ガバナンスを貫くESG経営を深化させている。その中でも注目すべきは、**サステナビリティと飲酒文化変革を融合させた“スマートドリンキング(スマドリ)戦略”**である。これは、飲む人も飲まない人も共に楽しめる社会の実現を目指す、アサヒ独自の革新的取り組みだ。
同社は、2025年までにアルコール度数3.5%以下の商品構成比を20%に引き上げる目標を設定し、2023年時点で10.5%に到達。低アル・ノンアル領域を中核成長分野として位置付けた。象徴的成功例が、2023年に172万箱を販売したノンアルコールビールテイスト飲料『アサヒゼロ』である。従来のノンアルに満足できなかったビール愛好層に対し、独自の脱アルコール製法により「本物のビールに近い味わい」を実現し、市場を刷新した。
さらに、同社は「SUMADORI-BAR SHIBUYA」を開設し、消費者にスマドリ文化を体験させるリアル拠点を展開。飲酒量を可視化するアプリ提供や大学との啓発活動など、飲酒を「健康と社会的調和の中で再定義」する試みを多面的に進めている。
スマドリ戦略は、サステナビリティ経営と密接に連動している。アサヒは気候変動対策として、2040年までにバリューチェーン全体でCO₂排出量ネットゼロを達成する目標を掲げ、SBTi(科学的根拠に基づく目標設定イニシアチブ)から国内初の「FLAG排出量を含むネットゼロ認定」を取得した。また、2030年までにPETボトルを100%リサイクル素材またはバイオ素材に切り替える「3R+Innovation」戦略も推進中である。
| 主要目標 | 2030年または2040年目標 | 2023年進捗 |
|---|---|---|
| CO₂削減(Scope1,2) | 2030年までに70%削減(2019年比) | 32%削減 |
| PETボトル環境配慮素材比率 | 2030年までに100% | 25% |
| 低アル・ノンアル構成比 | 2025年までに20% | 10.5% |
このように、アサヒは「環境」と「人の健康」を二軸に据え、飲料企業から“ウェルビーイング創造企業”へ進化しようとしている。スマドリはその象徴であり、同社のR&D・サステナビリティ・DXの各戦略を接続する“ハブ”として機能している。
アサヒのサステナビリティ経営は、もはやCSRの延長ではなく、**「持続可能性を利益の源泉とする経営モデル」**である。この変革こそが、次世代の成長エンジンとして世界市場での競争優位を生み出している。
研究開発とDXが牽引する「健康×体験」価値創造

アサヒグループホールディングスの成長を内側から支えるのが、独自の研究開発(R&D)力とデジタルトランスフォーメーション(DX)による新価値創造である。ビール醸造や「カルピス」に代表される発酵研究を源流とし、同社は100年以上にわたり微生物や発酵科学の知見を蓄積してきた。このR&D資産が、いま「健康」「ウェルビーイング」「デジタル体験」という次世代の成長軸と結びついている。
特に注目されるのが、乳酸菌「ラクトバチルス・ガセリCP2305株」や「ラクトトリペプチド」の研究成果である。これらは、睡眠の質改善、ストレス緩和、血圧低下といった健康効果が科学的に実証されており、同社の機能性商品群『カルピス由来の乳酸菌科学』『ディアナチュラ』などに応用されている。R&Dによるエビデンスの蓄積は、アサヒを単なる飲料メーカーから「健康価値を科学的に提供する企業」へと転換させた。
また、同社はR&DとDXを融合し、「データ駆動型商品開発」の実現に挑んでいる。AIを活用した味覚設計システムでは、発酵過程の微細な変化を数値化し、最適な風味バランスを導き出す。さらに「AIクリエーターシステム」では、消費者の嗜好データをもとにパッケージデザインを自動生成し、人間では発想しにくいデザインを創出。これにより、ブランドごとに異なる世界観をデジタルで再現することが可能になった。
経営面でも、取締役会レベルでAI解析を導入し、過去の質疑応答履歴から想定問答を生成。意思決定プロセスの質を高め、ガバナンスと経営スピードの両立を実現している。さらに、AIカメラや生体データを用いた実証実験では、個人の状態に合わせたパーソナライズド飲料提案を行い、将来的には「健康と嗜好のデータ連携プラットフォーム」構築を視野に入れている。
| 項目 | 主な取組内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 発酵・微生物研究 | 乳酸菌機能研究(CP2305株、ガセリ菌等) | 健康価値の創出 |
| AI味覚設計 | 醸造データ解析による最適風味開発 | 商品差別化と品質安定 |
| デザインDX | AIパッケージ生成・評価 | ブランド体験の刷新 |
| 経営DX | 取締役会AI分析・想定問答生成 | 意思決定の迅速化 |
アサヒのR&DとDXは、単なる技術導入ではなく、「人間の幸福(Well-being)」という哲学を基軸にしている。研究成果を消費者体験へと還元し、飲む行為そのものに“意味”を与えることで、同社は**「健康×体験」という新たな市場価値の創造者**として進化を遂げている。
ブランド再生力が示す革新のDNA
アサヒグループの強さは、時代の変化に応じてブランドを再定義し、再生させる「革新のDNA」にある。その象徴が、2022年に実施された『アサヒスーパードライ』のフルリニューアルである。発売から36年目にして初の全面刷新となったこの改革は、単なる製品改良ではなく、ブランドマネジメントの成功事例として国内外で高く評価されている。
リニューアル前、『スーパードライ』はユーザー数が年率4%減少し、ブランドの成熟化による市場停滞が続いていた。しかし、アサヒは「辛口」というブランドアイデンティティを守りながら、中味処方を一新。「キレの良さ」に加えて「飲みごたえ」を強化し、若年層や女性層にも響くバランス型ビールへと進化させた。
リニューアル直後、2022年3月の販売数量は前年同月比40%増を記録し、購入者数は10年ぶりに2,000万人を突破。長期低迷からの完全復活を果たしたこの事例は、ブランド資産の再構築モデルとして異例の成功といえる。
成功の背景には、徹底したマーケティングDXの活用がある。年間35,000GRPというテレビCM史上最大級の投下に加え、SNS・デジタル広告・体験型イベントを融合させたオムニチャネル戦略を展開。AI解析によって消費者の情緒データをリアルタイムで分析し、広告クリエイティブの最適化を図った。
さらに、同社は『スーパードライ』の成功体験を他ブランドにも展開している。
- 『十六茶』では「差し入れ」をテーマにした共感マーケティングを導入し、無糖茶市場で前年比112%の販売増を達成。
- 『カルピス THE RICH』では北海道産乳原料を使用し、健康とプレミアム感を両立。
- 『ミンティア+MASK』では、コロナ禍後の新生活習慣に即した“機能性ミント”市場を開拓した。
| ブランド | 戦略キーワード | 結果 |
|---|---|---|
| アサヒスーパードライ | 辛口×飲みごたえの再定義 | 販売数量+40%(2022年3月) |
| 十六茶 | 共感型マーケティング | 売上前年比112% |
| カルピス THE RICH | 健康×高付加価値 | 大人層の新規獲得 |
| ミンティア | ニューノーマル対応 | 売上前年比123% |
これらの成功に共通するのは、「消費者インサイトを科学的に読み解き、ブランド価値を再設計する力」である。アサヒは、データと感性を融合させたマーケティング革新によって、ブランドを“守る”のではなく“進化させる”企業文化を確立している。
『スーパードライ』の再生は、AGP(Asahi Group Philosophy)に掲げる「挑戦と革新」の実践そのものであり、この文化がある限り、アサヒのブランドは常に時代の先を走り続けるだろう。
次の10年を決めるリスクとチャンス

アサヒグループホールディングスが直面するリスクとチャンスは、今後の10年の企業価値を左右する決定的な要素である。特に、地政学的リスク・為替変動・原材料高騰といった外部要因が同社のグローバル事業に与える影響は大きい。一方で、ノンアルコール・ウェルネス市場の拡大やDXによる新価値創造の機会も急速に広がっている。
まず、最大の短期リスクはオセアニア事業にある。豪州市場では、ビール消費量が2010年代比で約15%減少しており、特に若年層のアルコール離れが進んでいる。加えて、輸送費高騰や為替影響が収益圧迫要因となっている。2024年度は欧州事業が価格改定とプレミアム化で増益を確保した一方で、オセアニアは減益に転じた。こうした市場構造の違いが、今後の地域戦略を見直す契機となっている。
また、グローバルサプライチェーンの分断も中長期的な課題である。ビール・飲料業界ではホップや麦芽、アルミ缶といった主要原料の調達先が限られており、気候変動による農産物価格の乱高下が経営リスクを増大させる。アサヒはこれに対応するため、欧州と日本の原材料調達を統合し、サプライヤーとの長期契約や代替素材開発を進めている。
一方で、機会の面では、ノンアル・低アル市場の急拡大が挙げられる。世界のノンアルコール飲料市場は2024年に1,300億ドル規模に達し、年平均成長率は6%を超える見通しである。アサヒが先行して進める「スマートドリンキング」戦略は、このトレンドの中心に位置しており、将来的にグループ全体の売上構成を変える可能性がある。
また、DXによる新たな顧客接点の創出もチャンスである。AIカメラやウェアラブルデータを用いた「個人最適型飲料提案」など、消費者の健康状態やライフスタイルに寄り添う“体験型ブランド”への進化が進んでいる。
さらに、サステナビリティ対応の進展が長期的な成長ドライバーとなる。2040年のCO₂ネットゼロ達成目標は、欧州の競合大手よりも早い時期に設定されており、国際的なESG投資家からの評価を高める要因となっている。
アサヒのリスクマネジメントの特徴は、防御的ではなく「変化を先取りする攻めの姿勢」である。リスクを機会へ転換するこの経営哲学こそが、今後10年の企業価値を規定する最大の武器となる。
アサヒが目指す「各事業の総和を超える価値」
アサヒグループホールディングスが掲げる中長期ビジョンの核心は、**「各事業の総和を超える価値の創造」**にある。これは単なるスローガンではなく、グローバル企業としての統合経営によって新たな付加価値を生み出すという実践的な方針である。
アサヒはこれまで、日本・欧州・オセアニア・東南アジアという4極体制のもと、各地域が独立した収益構造を持つ分権型モデルで成長してきた。しかし、今後はそれらを横断的に結合し、グローバルシナジーを最大化する「統合型経営」へ移行している。
その象徴が、グループCxO(最高責任者)職と地域CEOが参画する「Executive Committee(執行委員会)」の設置である。各地域の知見を集約し、調達・物流・ブランド開発をグローバル視点で最適化することで、従来の地域最適を超えた経営効率を実現している。
たとえば、欧州のプレミアムビール事業と日本のR&Dを組み合わせ、欧州限定『Asahi Super Dry 0.0%』の開発を実現した。これは単なる商品連携ではなく、地域横断型の知識融合による新市場創造の成功例である。
加えて、グローバル共通基盤としての「デジタル・サプライチェーン」構築も進む。調達データ、販売データ、環境データを一元管理し、AIで最適生産量や輸送経路を算出。結果として、在庫ロス削減とCO₂排出抑制を同時に達成している。
| 項目 | 目的 | 進捗 |
|---|---|---|
| グローバル調達統合 | コスト最適化と安定供給 | 欧州・日本間で実施済 |
| ブランド横断R&D | 新市場創出 | ノンアル製品群で成果 |
| デジタルサプライチェーン | 環境負荷削減・効率化 | 主要工場で導入完了 |
また、アサヒは「人材の多様性」を統合価値創造の重要要素として位置付けている。取締役会では女性比率40%超、外国籍取締役2名を擁し、多様な視点を経営に反映している。これにより、グローバルM&A後の統合や事業戦略策定において、**文化・市場・価値観の差異を活かす“人材ポートフォリオ経営”**が実現している。
アサヒの挑戦は、「規模の経営」から「知の経営」への転換である。地域、ブランド、人材、技術を有機的に結びつけることで、同社はもはや飲料企業の枠を超えた「グローカル価値創造企業」へ進化しつつある。
この統合経営が完成したとき、アサヒグループの企業価値は、まさにその理念通り——“各事業の総和を超える”新たな成長段階へと到達するだろう。

