テルモ株式会社は、創業から100年以上にわたり日本の医療を支えてきたグローバル・メドテック企業である。1921年に国産体温計の製造から始まった同社は、いまや世界160カ国以上で事業を展開し、売上高9,000億円を超える規模に成長した。その根底には「医療を通じて社会に貢献する」という不変の理念がある。だがテルモはいま、医療機器メーカーの枠を超えた「ソリューション企業」への進化を加速させている。
その象徴が、中期経営計画「GS26」と英国OrganOx社の買収である。前者は「デバイスからソリューションへ」という企業変革を明確に打ち出し、後者は臓器保存という未開拓市場への参入を意味する。さらに、AIや再生医療、ESG経営といった次世代のキーワードが戦略の中核を占める。モノづくりの精度とグローバル戦略を兼ね備えたテルモは、今まさに第二の創業期を迎えている。本稿では、同社の事業構造・成長戦略・M&A・技術革新を多面的に分析し、テルモが描く医療の未来像を解き明かす。
医療の未来を変えるテルモの挑戦:100年企業の次なる転換点

テルモ株式会社は、創業から100年を超える歴史の中で、単なる医療機器メーカーから「医療イノベーション企業」へと進化を遂げてきた。その歩みは、技術革新と社会的使命を両立させる日本型メドテックの理想像を体現している。
1921年、北里柴三郎ら医学界の重鎮が「高品質な国産体温計の製造」を目的に創業して以来、テルモは医療現場の課題解決に正面から取り組んできた。1964年には日本初のディスポーザブル注射器を発売し、院内感染リスクを劇的に減少させた。その後も血液バッグや輸液システムなど、医療安全の基盤を支える製品を次々に開発。1984年には水銀体温計の生産を停止し、環境負荷への配慮をいち早く示した。このような決断力こそが、テルモのDNA=「医療を通じて社会に貢献する」精神である。
現在のテルモは、世界160カ国以上で事業を展開し、グループ従業員数3万人超、売上高9,219億円(2024年3月期)を誇る。以下の表が、同社の成長規模を端的に示している。
| 指標 | 数値(2024年3月期) |
|---|---|
| 売上収益 | 9,219億円 |
| 営業利益 | 1,414億円(調整後) |
| 時価総額 | 約3兆6,000億円 |
| 従業員数 | 30,591名 |
この規模は単なる数値の拡大ではない。心臓血管領域での世界的シェア、CDMO事業による製薬支援、再生医療・臓器保存といった次世代医療分野への拡張など、医療の質そのものを変革する「総合的ソリューション企業」への進化を意味する。
特に注目すべきは、同社が単に製品を供給するだけでなく、「医療プロセス全体」を改善する視点を持つ点である。カテーテル治療におけるアクセスから止血までの一貫ソリューション、薬剤充填型デバイスによる製薬支援、AIを活用したサプライチェーン最適化など、製品ではなく“治療体験そのもの”を革新する企業へと脱皮している。
このような進化の背後には、「短期的利益よりも長期的信頼を重視する」経営哲学がある。患者、医師、医療機関、そして社会全体との共生を軸に据えたテルモの姿勢は、国内外のメドテック業界における稀有な存在として、今後さらにその価値を高めていくであろう。
テルモの3カンパニー体制がもたらす収益構造と競争優位
テルモの強みは、その緻密に設計された3カンパニー体制にある。この構造は、事業の安定性と成長性を両立させる経営モデルとして高く評価されている。
テルモは、主要事業を以下の3部門に分けて運営している。
| カンパニー | 売上構成比(2023年度) | 主な領域 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 心臓血管カンパニー | 60% | カテーテル・ステントなど | 世界シェア75%以上のガイドワイヤー技術 |
| メディカルケアソリューションズカンパニー | 21% | 注射器・輸液・CDMO事業 | 製薬企業との長期協働モデル |
| 血液・細胞テクノロジーカンパニー | 19% | 血液分離・再生医療装置 | アフェレーシス技術で世界をリード |
この3本柱はそれぞれ独立しながらも、相互に補完し合うポートフォリオ戦略として機能している。例えば、メディカルケアソリューションズが安定したキャッシュフローを生み出し、心臓血管や血液・細胞テクノロジーのR&D投資を支える。一方で、成長セグメントが企業全体の収益性を押し上げ、再投資を可能にする循環構造を形成している。
心臓血管カンパニーは、特に冠動脈治療用ガイドワイヤーで世界75%以上のシェアを占める圧倒的な存在である。この技術的優位性は、参入障壁を築くだけでなく、テルモブランドへの医師の信頼を世界規模で醸成している。また、カテーテル治療の「アクセスから止血」までを包括的に提供する戦略は、競合の模倣を許さないビジネスモデルである。
一方、CDMO事業を中核とするメディカルケアソリューションズは、製薬企業の新薬開発段階からデバイス開発・薬事承認・商用化までを一貫支援する。これにより、単なる供給者ではなく「開発パートナー」としての地位を確立している。
そして、再生医療を担う血液・細胞テクノロジーカンパニーは、血漿採取装置「Rika」などを通じて持続的な収益を生み出す新たなビジネスモデルを構築。**未来医療の基盤を創る“次世代エンジン”**として存在感を増している。
この3カンパニー体制こそが、テルモを単なる医療機器メーカーではなく、医療ソリューションの総合企業へと進化させる構造的ドライバーである。
心臓血管カンパニーの圧倒的市場支配と技術力の本質
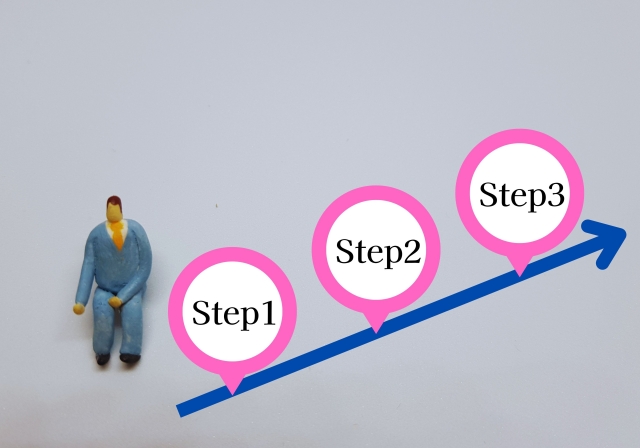
テルモの収益の柱を形成するのが、全体売上の約60%を占める心臓血管カンパニーである。この部門は、同社の技術的優位性とグローバル支配力を象徴する存在であり、テルモの持続的成長のエンジンとなっている。
中核事業であるカテーテル治療領域では、特に冠動脈治療用ガイドワイヤーにおいて世界シェア75%超という圧倒的な地位を確立している。この市場支配は単なる数量的成果ではなく、医師からの高い信頼に裏打ちされた臨床的実績の積み重ねである。ガイドワイヤーは血管内を通過させる“医師の指先そのもの”と呼ばれるほど繊細な操作性が求められる。テルモは、ワイヤーの表面コーティングやトルク伝達性を極限まで高める独自技術を確立し、他社が模倣できないレベルの精密加工と一貫製造体制を構築してきた。
また、テルモが世界で初めて普及させた「経橈骨動脈インターベンション(TRI)」も特筆すべき成果である。従来の大腿動脈からのアプローチに比べ、患者の負担が少なく、出血リスクを大幅に軽減できるこの手技は、患者QOLと医療コスト双方の改善を実現する低侵襲治療の象徴として世界的に採用が進んでいる。テルモはTRI関連製品群を早期に整備し、「アクセスから止血まで」を包括的にサポートする製品体系を築いた。
| 主な製品群 | 技術的特徴 | 医療効果 |
|---|---|---|
| ガイドワイヤー | 世界最高レベルの操作性・耐久性 | 血管損傷リスクの低減 |
| カテーテルシステム | 高精度ポリマーチューブ技術 | 治療精度・安全性の向上 |
| 止血デバイス | 患者負担を軽減するワンタッチ構造 | 出血合併症の抑制 |
これらの製品群がもたらすのは単なる製品価値ではなく、「治療の流れ」そのものを最適化する包括的ソリューションである。テルモは心臓だけでなく、下肢動脈、大動脈、脳血管といった領域にも事業を拡大し、今後はAIを活用した手技支援やデジタル連携型デバイスへの進化も進めている。
市場調査会社ストレイツ・リサーチによると、世界のカテーテル市場は2033年までに年平均成長率(CAGR)6.2%で拡大するとされる。このなかで、テルモは自社技術と臨床ネットワークを基盤に、「品質」「安全」「操作性」の三位一体で競争優位を維持している。まさに、心臓血管カンパニーはテルモのブランド信頼を支える中核的存在である。
CDMOで変わる医療の価値連鎖:メディカルケアソリューションズの進化
メディカルケアソリューションズカンパニーは、テルモの売上の約2割を占める基盤事業でありながら、近年は「安定収益源」から「成長ドライバー」へと役割を変化させている。その中心にあるのが、製薬企業との協業によるCDMO(開発製造受託)ビジネスモデルである。
テルモはこれまで、注射器や輸液システムといった日常的医療機器を提供してきた。しかし、プレフィルドシリンジ(薬剤充填済み注射器)やドラッグデバイス一体型製品の需要拡大に伴い、医薬品開発の上流工程に踏み込む戦略を採用した。これは、製薬企業とともに**「薬×デバイス×品質管理」を統合した総合ソリューション**を構築することを意味する。
このCDMOモデルは、医薬品メーカーにとっても大きな利点をもたらす。テルモが提供するシリンジ設計、滅菌、薬事承認支援、生産ライン構築の一貫プロセスにより、開発コストと上市期間の大幅短縮が実現できる。さらに、テルモの世界的な生産拠点(日本、ドイツ、米国など)を活用することで、グローバル同時供給体制の構築も可能になった。
| 項目 | テルモCDMOの特徴 | 製薬企業にもたらす効果 |
|---|---|---|
| 製造範囲 | 開発初期~商用化までの一貫支援 | 研究から量産までの時間短縮 |
| 品質保証 | 医療機器GMP+医薬品GMPの統合管理 | 国際基準適合による信頼性強化 |
| 技術領域 | プレフィルドシリンジ・オートインジェクターなど | 投与効率・患者利便性の向上 |
この戦略転換は、単なる委託製造ビジネスではなく、テルモの本質である「医療の品質を高める」という理念に直結している。薬剤とデバイスを一体で最適化することで、治療の安全性・効率性・患者体験を同時に向上させる仕組みが構築されている。
特に欧州市場では、テルモが買収したドイツ工場を拠点にCDMO事業を拡大しており、将来的にはバイオ医薬や遺伝子治療薬への応用も視野に入れている。医療機器メーカーが製薬の価値連鎖を変えるという構造転換は、まさに「デバイスからソリューションへ」というGS26戦略の具現化である。
メディカルケアソリューションズは、安定事業から戦略的収益源へと進化しつつある。その成長の本質は、製品ではなく“関係性”を提供する企業への転換にある。テルモは医療の裏方から、医療の未来を共創する存在へと確実に歩を進めている。
血液・細胞テクノロジー事業が切り拓く再生医療の新潮流

テルモの成長を牽引するもう一つの柱が、血液・細胞テクノロジーカンパニーである。この事業は売上構成比こそ19%にとどまるが、再生医療や細胞治療といった次世代医療を支える中核分野として、同社の将来を決定づける重要なポジションを占めている。
同カンパニーの核となるのは、血液中の特定成分を分離・採取するアフェレーシス技術である。テルモはこの分野でグローバルリーダーの地位を築いており、世界中の血液センターや病院に導入されている。特に注目されるのが、米国市場で急速に普及している血漿採取装置「Rika」である。Rikaは血漿採取の効率と安全性を両立させ、装置の販売とディスポーザブル製品の継続使用によって安定した収益を生む“サブスクリプション型”のビジネスモデルを実現している。
| 主力製品 | 主な導入先 | 収益構造 |
|---|---|---|
| Rika(血漿採取デバイス) | CSL Plasma社(約330施設) | 本体販売+消耗品供給による継続収益 |
| セルプロセシング装置 | 製薬・再生医療研究機関 | 自動化・無菌化による製造効率向上 |
再生医療の進展に伴い、細胞を利用した治療法の実用化が加速している。テルモはこの潮流を的確に捉え、細胞培養や分離工程の自動化技術を強化している。従来、細胞治療製品の製造は人手に依存しており、品質のばらつきやコスト増が課題だった。テルモは**「クリーンベンチからロボティクスへ」**という方向転換を進め、製造工程を統合制御する自動化システムを開発。これにより、再生医療の商業化に向けた最大の障壁を技術的に克服しつつある。
さらに、テルモは世界的な血液関連技術企業「テルモBCT」を通じて、細胞治療製品のスケールアップ支援を進めている。研究段階の技術を臨床・量産レベルへ引き上げるこの仕組みは、グローバル製薬企業との連携拡大にもつながっている。血液テクノロジーから再生医療へという技術の連続性を持つ点が、テルモの競争優位の根源である。
世界の細胞治療市場は2030年までに約600億ドル規模に達すると予測されており、この分野は今後のメドテック業界の主戦場となる。テルモはその中心で、“医療の未来インフラ”を構築する企業へと進化を続けている。
OrganOx買収が示す「血液技術×臓器保存」の戦略的多角化
2025年8月、テルモは英国の医療機器メーカーOrganOx社を約2,200億円で買収すると発表した。この大型案件は、同社が臓器移植分野という新たな成長領域に踏み出す決定的な一手であり、テルモ史上最大の戦略的転換点と評されている。
OrganOx社は「常温機械灌流(Normothermic Machine Perfusion:NMP)」技術のパイオニアである。従来の静的低温保存とは異なり、NMPは臓器を体温に近い温度で血液や酸素を循環させることで、臓器の代謝を維持しながら保存できる。これにより、移植前に臓器機能をリアルタイムで評価でき、移植成功率の向上と臓器廃棄率の低減を同時に実現する。世界的に移植用臓器が不足するなか、この技術は医療現場に革命をもたらす可能性を秘めている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 買収金額 | 約15億米ドル(約2,200億円) |
| 核心技術 | 常温機械灌流(NMP) |
| 主な対象臓器 | 肝臓・腎臓・心臓 |
| 期待される効果 | 臓器利用率向上・移植成功率の改善 |
テルモにとってこの買収は、単なる事業多角化ではない。人工心肺装置で培った体外循環技術、血液ポンプ、酸素化器、流路設計といったコア技術が、OrganOxのNMP技術と高い親和性を持つ。つまり、テルモが長年積み重ねてきた「血液を体外で制御する力」を臓器保存に応用することで、臓器移植という未踏領域を自社技術の延長線上に取り込む戦略的関連多角化を実現しているのである。
この技術融合によって、臓器移植の前後プロセスを包括的に支援する「血液循環ソリューション」の構築が可能となる。テルモは、OrganOxの技術と自社製品群を統合し、移植医療全体を最適化するプラットフォームの確立を目指している。
また、この買収によりテルモは欧州市場での存在感を一段と高め、世界規模での医療ネットワークを強化した。今後は、心臓・肝臓・腎臓など多臓器への適用拡大が期待されており、医療機器業界でも類を見ない長期的なシナジーが見込まれる。
OrganOx買収は、テルモが単なる医療機器企業から**「生体機能の維持・再生を支援するメドテック企業」へと進化する象徴的事例**である。血液技術と臓器工学の融合が、次の100年を見据えたテルモの新たな医療価値を創出しようとしている。
「デバイスからソリューションへ」GS26が導くテルモの成長モデル

テルモが掲げる中期経営計画「GS26」は、単なる数値目標ではなく、事業構造そのものを変革する長期ビジョンである。その核となるメッセージが「デバイスからソリューションへ(From Devices to Solutions)」であり、これは製品提供型企業から課題解決型企業への進化を意味している。
従来のテルモは、医療機器という「モノ」を通じて医療現場に価値を提供してきた。しかしGS26では、製品にデータ・サービス・プロセスを統合し、医療現場全体の効率化と患者アウトカムの最適化を支援する「ソリューション型企業」への転換を明確に打ち出した。
たとえば心臓血管カンパニーでは、「アクセスから止血まで」を網羅する包括的治療プロセスを整備し、単一製品販売ではなく**“治療全体の最適化パートナー”**としての立ち位置を確立した。また、メディカルケアソリューションズカンパニーでは、CDMO事業を通じて「薬剤開発支援から商用化まで」を担うトータルパートナーシップを展開。これはGS26の本質的な理念である「患者と医療従事者双方のベネフィットを最大化するソリューション」の具体的実践である。
| GS26の主要要素 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| デバイスからソリューションへ | 製品+データ+サービスの統合提供 | 医療現場の課題を包括的に解決 |
| One Terumoアプローチ | 3カンパニーの連携による価値共創 | 組織間のシナジー最大化 |
| 医療デジタル化の推進 | AI・IoT活用による治療精度と運営効率の向上 | 医療現場の生産性革新 |
さらにGS26では、**営業利益率20%、売上収益1兆円(2027年3月期)**という明確な財務目標を掲げ、同時にESGやDE&Iを経営の中核に組み込んでいる点が特徴である。これによりテルモは、利益成長と社会的価値創出を両立する「サステナブル・メドテック企業」への進化を狙っている。
特筆すべきは、テルモがこの変革を「既存事業の延長線」ではなく、「新しい企業文化の再構築」として位置づけていることである。GS26は、製品開発、営業、R&D、そして人材育成までを貫く経営哲学となっており、**“医療現場とともに成長する企業”**というテルモの次世代像を明確に描いている。
AIとデジタルヘルスの融合が変えるテルモのR&Dと現場医療
テルモのR&D戦略は、単なる技術開発にとどまらず、**デジタル・AI・データを中核に据えた「医療の再設計」**へと進化している。同社は現在、世界22拠点に研究開発センターを展開し、地域特性に応じたイノベーションを推進しているが、その中枢を担うのが「TERUMO R&D Way」という共通理念である。これは、グローバルで一貫した技術開発プロセスと知識共有を促進する枠組みであり、分散型R&Dを“連携型知識ネットワーク”に変える仕組みである。
テルモは近年、デジタルヘルス分野への投資を本格化させている。特にAIを活用した需要予測システムは、同社の5万点を超える製品群の在庫管理を最適化し、サプライチェーン効率とキャッシュフローの改善を実現している。また、IoT技術を応用した遠隔モニタリングでは、患者の状態データを医療従事者がリアルタイムで共有できる仕組みを構築し、在宅医療・慢性疾患ケアの分野でも成果を上げている。
| 主要領域 | 活用技術 | 成果・効果 |
|---|---|---|
| 需要予測・在庫管理 | AI・機械学習 | 欠品リスク削減・供給安定化 |
| 手技支援・画像解析 | AI画像認識 | カテーテル治療の精度向上 |
| 遠隔モニタリング | IoT・クラウド | 在宅医療の効率化・データ連携強化 |
特に心臓血管治療分野では、AIが術中映像を解析し、カテーテル操作の最適ルートを提案する「インテリジェント・サポート・システム」の開発が進行している。これにより、経験の浅い医師でも熟練医同等の精度で施術が可能となり、医療の地域格差是正にも寄与する。
さらに、テルモは再生医療分野でもデジタル技術を導入し、細胞培養工程の自動制御や品質管理AIの活用を進めている。これは、再生医療の商業化を加速させるとともに、「デジタル×バイオ×医療機器」の融合による新産業創出の布石ともいえる。
テルモのR&D戦略は、従来の製品開発型企業とは一線を画す。そこにあるのは、デジタル技術を使って医療現場を“再構築”するという発想である。AIやIoTを手段としてではなく、「医療体験そのものを変える仕組み」として位置づけている点が、他社との差別化の核心である。
テルモは今後、AIを搭載したカテーテルやデジタル連携型臓器保存装置など、次世代医療機器の市場投入を予定している。こうした動きは、GS26で掲げた「ソリューション企業」への転換を技術面から支えるものであり、テルモが“デジタル×医療”の未来を牽引する存在へと進化していることを明確に示している。
ESGとDE&Iを軸にした企業価値の再構築:サステナブル経営の中核

テルモが中期経営計画「GS26」の中で強調しているのが、ESG(環境・社会・ガバナンス)とDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)を経営の基盤に据えることである。これらを単なるCSR活動ではなく、事業戦略の中核に位置づけた点が、テルモの経営の成熟度を示している。
まず、環境面(Environment)では、テルモは2040年までにカーボンニュートラルを達成するという明確な目標を掲げている。科学的根拠に基づく排出削減目標(SBT)を設定し、2030年までに温室効果ガス排出量を大幅に削減する計画を公表した。国内外の製造拠点では再生可能エネルギーの導入が進んでおり、2024年時点で全電力使用量の約60%が再エネ由来に転換されている。
社会面(Social)では、DE&Iを「経営戦略そのもの」として位置づけている点が特徴的である。テルモは多様性を単なる理念ではなく「イノベーションの源泉」と捉え、世界各地の人材が共通の価値観のもとで連携できる仕組みを整備した。2021年にはグローバルDE&Iカウンシルを発足し、「帰属意識」「インクルーシブなリーダーシップ」「キャリア機会の公平性」の3分野を重点課題に設定。2026年度末までに日本国内の女性管理職比率13%を達成する目標を掲げている。
| ESG/DE&Iの重点領域 | 取り組み内容 | 数値目標 |
|---|---|---|
| 環境(E) | 再エネ導入・温室効果ガス削減 | 2040年カーボンニュートラル |
| 社会(S) | 女性・外国人リーダー育成 | 管理職に占める女性比率13% |
| ガバナンス(G) | グローバル人事制度・倫理強化 | すべての地域で統一的ガイドライン運用 |
さらに、テルモのガバナンス強化は「透明性」と「説明責任」の両面で進化している。社外取締役比率は50%を超え、国籍・性別の多様性を意識した取締役会構成を採用。グローバル人事制度の下で、役員報酬にESG目標の達成度を連動させる「インセンティブ連動型ガバナンス」も導入している。
このような取り組みの根底には、「社会からの信頼なくして企業成長はあり得ない」という哲学がある。ESGとDE&Iを通じて社会課題の解決を利益創出と両立させることこそ、テルモが次の100年に向けて掲げる新たな競争優位の核なのである。
グローバル競争を勝ち抜くための次の一手:テルモが挑む未来図
テルモは今、グローバルメドテック業界における「次の主役」として、さらなる成長局面に突入している。世界市場を見渡せば、メドトロニック、ジョンソン・エンド・ジョンソン、シーメンス・ヘルシニアーズといった巨大企業がしのぎを削るなか、テルモは**“選択と集中による特化型グローバルリーダー”**という独自ポジションを築きつつある。
テルモの最大の強みは、規模よりも「深さ」にある。ガイドワイヤーやアフェレーシス装置といったニッチながら高付加価値な領域で圧倒的なシェアを誇り、その精密技術が他事業への波及効果を生んでいる。また、世界160カ国に広がる販売・流通ネットワークは、各国の医療制度に即したきめ細やかな展開を可能にし、**“ローカル適応型グローバル戦略”**を実現している。
| 成長の柱 | 内容 | 競争優位性 |
|---|---|---|
| 心臓血管事業 | ガイドワイヤー・ステント・TRI製品群 | 世界シェア75%超、技術的参入障壁 |
| 血液・細胞事業 | 再生医療・血漿分離装置 | 研究~商業化まで一貫支援 |
| 臓器保存分野 | OrganOx買収による新市場参入 | 臓器移植成功率向上・新収益源創出 |
一方で、世界的な競争環境は急速に変化している。医療費抑制政策、規制強化、地政学的リスク、そしてAIを中心とする技術革新が業界構造を再編している。テルモに求められるのは、これら外的変化を単なるリスクではなく「変革の機会」として捉える柔軟性である。
実際、同社は「AI×バイオ×デバイス」を融合した次世代R&Dへの投資を加速しており、デジタル臓器保存やAI支援カテーテル治療といった**“医療の未来を実装する技術群”**の開発が進行中である。これらの技術は、単なる製品拡張ではなく、患者の生存率や医療コスト削減といった社会的価値を創出するものとなる。
さらに注目されるのが、テルモがアジア・中南米などの新興国市場を「次の成長エンジン」として再定義している点である。人口増加と高齢化が進むこれらの地域では、医療インフラの拡充ニーズが高まっており、テルモの低侵襲・高品質な製品群が高い親和性を持つ。**“先進国の品質を新興国価格で”**という戦略的供給モデルは、持続的な収益拡大のカギを握る。
テルモの次の10年は、デジタル技術、再生医療、臓器保存、そして新興国戦略という4本の軸で描かれるだろう。そこに共通するキーワードは「生命の価値を最大化する技術」である。製品ではなく「医療の未来」そのものをデザインする企業として、テルモは日本発の真のグローバル・メドテックリーダーへと進化を遂げようとしている。

