オリンパス株式会社は、かつて「世界のオリンパス」と称された日本光学技術の象徴であった。しかし、2020年代に入り同社は大胆な構造転換を断行し、カメラという原点を手放してまで「グローバル・メドテック・リーダー」への道を選んだ。この決断は、単なる事業再編ではなく、100年企業が再び世界をリードするための生存戦略である。
スマートフォンの普及により映像事業が急速に衰退するなか、オリンパスは「選択と集中」を掲げ、医療技術という成長分野に経営資源を集約した。その結果、現在では消化器内視鏡で世界シェア約70%を誇る圧倒的王者として君臨している。だがその歩みは順風満帆ではない。中国市場の逆風、米国での競争激化、そして新製品サイクルの谷間といった複数の試練が同社の真価を問う。
それでもなお、オリンパスの変革は世界的に注目されている。AI・クラウド・データ分析を駆使した「インテリジェント内視鏡エコシステム」の構想は、ハードウェア企業からデジタル医療プラットフォーム企業への進化を意味する。本稿では、同社の戦略転換の全貌と、真のグローバル・メドテック・リーダーへと飛躍するための条件を徹底分析する。
日本の象徴から世界の医療巨人へ:オリンパスの第二の創業

オリンパスは、かつて「カメラのオリンパス」として世界中に名を馳せた。しかし、いまや同社はその象徴的な映像事業を手放し、医療機器分野に経営資源を集中させることで、世界的なメドテック企業へと再生を遂げつつある。
この変革の出発点は、デジタルカメラ市場の急激な縮小にあった。スマートフォンの台頭により、一般消費者向けカメラの需要は急落。2019年度から2020年度にかけて、映像事業は約400億円の売上に対し、100億円を超える営業損失を計上した。13年間のうち10年が赤字という構造的な不採算事業を抱えたままでは、企業としての持続性が失われるのは明白だった。
そこでオリンパスは「選択と集中」という明確な指針のもと、象徴的であった映像部門を2020年に日本産業パートナーズ(JIP)へ売却。さらに2022年には黒字だった科学事業も譲渡し、医療機器事業にすべてを注ぎ込む決断を下した。2024年には整形外科事業も売却し、経営資源を消化器・泌尿器・呼吸器の3領域に集中させる体制を整えた。
この徹底した構造改革は、単なるリストラではない。オリンパスは中核である医療事業を通じて、**「光学から生命科学へ」**という新たな使命を掲げた。現在、同社の売上の約85%は医療事業が占めており、その変貌ぶりは日本企業の再編史における象徴的事例とされている。
経営哲学も大きく変化した。かつての感情的なレガシー重視経営から脱却し、ROIC(投下資本利益率)や長期株主価値を軸とした資本効率経営へと移行した。投資家はこの決断を高く評価し、株価は2020年から2025年の間でおよそ1.5倍に上昇している。
財務体質の健全化に加え、グローバル戦略の舵取りを担うのが、メドトロニック出身のCEOボブ・ホワイトである。彼の下でオリンパスは、米国市場に照準を定め、**「日本発の世界企業」から「世界基準の日本企業」**へと進化しつつある。この第二の創業こそ、オリンパス再生の真の核心である。
カメラを捨てて医療に賭けた決断:「選択と集中」の真意
オリンパスの事業転換は、国内外の経営学者や投資家から「日本企業の合理化モデル」として注目を集めている。感情的価値の高いカメラ事業を切り離した背景には、冷徹な財務分析と長期的視点に基づく戦略的判断があった。
オリンパスは、カメラや科学事業の売却を通じて得た資金を、研究開発と医療機器のグローバル展開に再投資した。特に、内視鏡分野での世界シェア約70%という圧倒的優位性を活かし、技術革新と地域拡大を両立させる構造へと変貌したのである。
以下の表は、主要事業の再編過程を整理したものである。
| 売却年度 | 対象事業 | 売却先 | 売却理由 | 影響 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 映像事業 | 日本産業パートナーズ | 不採算部門からの撤退 | 財務負担軽減 |
| 2022年 | 科学事業 | Evident(分社化後売却) | シナジー低さ・資本効率改善 | 医療集中強化 |
| 2024年 | 整形外科事業 | ポラリス・キャピタル・グループ | 慢性赤字部門の整理 | 中核領域明確化 |
このようにして同社は「光学機器の総合メーカー」から「医療機器専業企業」へと再定義された。
この転換の成果は数字にも表れている。2025年3月期の営業利益は1624億円と過去最高を記録し、営業利益率は16.3%へ上昇。ROEは15.62%と、製造業としては極めて健全な水準に達している。特に北米市場ではEVIS X1内視鏡システムの販売が好調で、消化器内視鏡売上が前年同期比44%増という成長を見せた。
一方で、短期的な課題も存在する。中国市場では反腐敗運動の影響で医療機器投資が停滞し、販売減少が顕著となった。また、整形外科事業の売却に伴う一時的な収益減も避けられない。
それでもオリンパスの経営陣は、この決断を**「痛みを伴うが回復への唯一の道」**と位置づける。経済産業省の「医療機器産業ビジョン2024」でも、同社の戦略転換は日本企業における構造改革成功例として紹介されており、非中核資産の売却による集中経営は、今後の企業ガバナンスの標準となりつつある。
つまり、オリンパスの「選択と集中」は過去の象徴を捨てる行為ではなく、未来の競争力を選ぶ決断であった。カメラを手放したその瞬間、オリンパスは世界の医療を握る新しいレンズを手にしたのである。
消化器内視鏡で世界70%シェア:圧倒的王者の技術力と臨床優位
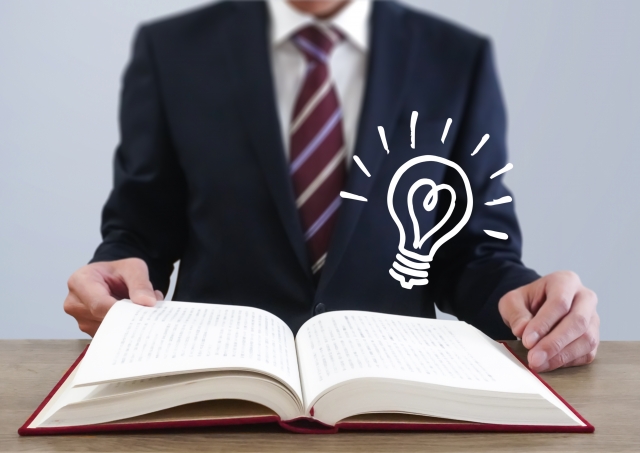
オリンパスの医療事業の中心に位置するのが、消化器内視鏡ソリューション(GIS)である。同社はこの分野で約70%という圧倒的な世界シェアを誇り、まさに「内視鏡のグローバルスタンダード」を確立している。この市場支配力の源泉は、光学技術の蓄積だけではなく、臨床現場における課題解決に直結する画像技術と医師主導の開発体制にある。
主力製品であるEVIS X1内視鏡システムは、テクスチャー強調技術TXIや狭帯域光観察NBI、赤色二色成像RDIといった多層的な画像モダリティを搭載している。特にTXIは、2023年に『Gastroenterology』誌に掲載された多施設共同ランダム化比較試験において、腺腫発見率を従来の白色光内視鏡より13.61%有意に向上させたと報告されており、その臨床的有効性が科学的に裏付けられている。
さらにNBI技術は血管構造を明瞭に可視化し、早期がんの見逃しを防ぐだけでなく、手技の短縮にも寄与している。医師は生検箇所を正確に特定できるため、不要な侵襲を減らし、患者の負担を軽減する。このようにオリンパスの技術は、「検出率の向上」と「手技効率化」という二重の価値」を同時に実現している。
地域別に見ると、北米が同社の最大の収益源となっており、2025年度第2四半期には消化器内視鏡の売上が前年同期比44%増と急伸した。一方、中国では政府の反腐敗キャンペーンの影響で病院設備投資が抑制され、販売が減少した。しかし、欧州・インド・中東などの新興市場では堅調な需要が続いており、地域ポートフォリオの多様化がリスク緩和に寄与している。
オリンパスの強みは、単なるハードウェア販売に留まらない。全世界で数十万台規模の設置基盤を活かし、修理・保守契約、消耗品供給といったサービス事業を拡充している。この「装置+サービス」モデルが、安定的で高利益率な収益を支えている。
また、医師教育や学会との共同研究にも積極的である。日本消化器内視鏡学会との共同プログラムや、米国・欧州での臨床評価ネットワークを通じて、実際の診療現場のフィードバックを製品設計に反映させている。これにより、オリンパス製品は**「医師が求める臨床解決力」を持つブランド**として定着している。
結果として、オリンパスは単なる機器メーカーを超え、医療プロセス全体を支えるプラットフォーマーとして進化している。消化器疾患の診断・治療・追跡を一貫して支援するそのエコシステムは、今後の医療DX時代において最も堅固な参入障壁となる。
外科・泌尿器・呼吸器領域の拡張:SIS事業が描く成長戦略
オリンパスの外科・インターベンションソリューションズ(SIS)事業は、同社の次なる成長エンジンとして注目されている。従来の診断中心のGIS事業に対し、SISは**「治療への拡張」**を担う事業であり、低侵襲医療の潮流を背景に高い成長ポテンシャルを持つ。
この部門は泌尿器科、呼吸器科、耳鼻咽喉科、一般外科といった複数の専門分野を横断しており、特に泌尿器分野での成長が顕著である。腎結石治療用の「SOLTIVE SuperPulsed Laser System」や前立腺肥大症(BPH)向けデバイス群が売上を牽引している。また、前立腺治療用の「iTind」デバイスは欧米で急速に普及し、BPH市場での地位を強化している。
呼吸器領域では、肺がん診断で使用される超音波気管支鏡(EBUS-TBNA)向けデバイスが堅調に拡大。これにより、がんの早期診断と正確な病期分類が可能となり、臨床ニーズが急速に高まっている。
一方、外科領域では次世代手術内視鏡システム「VISERA ELITE III」を日米中で展開し、手術映像の高精細化とAI支援の導入を進めている。これにより、手術中の血管視認性が向上し、出血リスクを低減できるなど、医療安全性の観点からも高く評価されている。
| 主な製品 | 医療領域 | 特徴・臨床価値 |
|---|---|---|
| SOLTIVE Laser | 泌尿器科 | 結石破砕効率の向上、低侵襲化 |
| iTind | 泌尿器科 | BPH治療の非永久的インプラント |
| VISERA ELITE III | 外科 | 高精細映像・AI画像支援 |
| SecureFlex | 消化器内視鏡(EUS-FNA) | がん診断用シングルユース生検針 |
2025年には新製品「SecureFlex」の投入により、膵臓がんや胆管がんの診断精度を高める取り組みも始まっている。単回使用デバイスの拡充は、感染対策や品質保証の観点から世界的に需要が高まっており、オリンパスはこの市場トレンドを的確に捉えている。
また、GISとSISは独立した事業ではなく、相乗効果を生むエコシステムとして機能している。病院がEVIS X1などの内視鏡システムを導入すれば、その周辺で使用する治療用具(スネア、鉗子、SecureFlex針など)もオリンパス製品が選ばれる確率が極めて高い。この「ハード+消耗品」モデルが、高利益率かつ継続収益を生む構造的強みである。
さらに、オリンパスはM&Aや技術提携を通じてポートフォリオ拡大を進めている。2025年10月には米国のW. L. Gore & Associates社と提携し、胆道ステントの販売契約を締結。これにより、消化器治療領域での製品群を拡張し、臨床シーンでの包括的ソリューション提供が可能になった。
SIS事業の拡大は、オリンパスが**「診断から治療までをカバーするトータルメドテック企業」**へと進化するための核心的な要素である。低侵襲治療とAI統合という二つの潮流を制した企業だけが、次世代医療の主導権を握ることになる。
数字で読み解く企業再生:財務健全化と株主還元の実像

オリンパスの「選択と集中」戦略は、事業ポートフォリオの刷新だけでなく、財務体質の抜本的な再構築にも直結している。かつてのカメラ事業が慢性的な赤字を生み出していた時期と比較すると、現在の同社は高収益・高ROE型のメドテック企業へと劇的に転換した。
2025年3月期における売上高は9,973億円、営業利益は1,624億円と過去最高を記録。営業利益率は16.3%、ROEは15.62%と、医療機器業界でもトップクラスの水準を示した。とりわけ、2022年に黒字であった科学事業を売却したことが資本効率の改善に寄与し、ROIC(投下資本利益率)重視の経営へと明確に舵を切った。
以下は直近の主要財務指標である。
| 会計年度 | 売上収益(億円) | 営業利益(億円) | 純利益(億円) | 営業利益率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 9,258 | 514 | 2,426* | 5.6% | 34.7% |
| 2025年度 | 9,973 | 1,624 | 1,179 | 16.3% | 15.6% |
| 2026年度(予測) | 9,980 | 1,360 | 940 | 13.6% | – |
*注:2024年度は科学事業売却益を含む
2025年度の営業利益率は前年から約3倍へと急上昇しており、これはコスト構造改革と高収益医療製品へのシフトの成果である。特に北米市場における消化器内視鏡の好調な販売が収益を牽引した。一方で、2026年度は通期予想が下方修正され、純利益は940億円へ減少する見込みとなった。要因は北米での新製品切り替えに伴う一時的な販売抑制と、中国市場の反腐敗政策による投資停滞である。
しかし、これらの短期的逆風にもかかわらず、同社のキャッシュフロー創出力は依然として強固である。営業活動によるキャッシュフローは年間1,200億円規模を維持しており、安定的な資金源を背景に積極的な株主還元策を展開している。
2026年度の年間配当は1株あたり30円と、前年度比で50%増配を予定。さらに500億円規模の自社株買いプログラムも実施中である。これにより経営陣の「自社株価は割安」との確信が市場に伝わり、投資家の信認強化につながっている。
オリンパスの財務改革は、単に利益を増やすことではなく、「安定・成長・還元」の三位一体経営モデルの構築にある。これは、グローバル市場でのプレゼンス拡大を支える財務的土台であり、メドテック業界における持続的競争力の証左でもある。
デジタル×AIで挑む新戦略:「インテリジェント内視鏡」構想の全貌
オリンパスが次に描く未来は、ハードウェア中心の医療機器メーカーから、データとAIを統合した**「インテリジェント・メドテック企業」**への進化である。その象徴が「インテリジェント内視鏡エコシステム」構想であり、同社のデジタル戦略の中核に位置づけられている。
この構想の第一歩が、2024年に開始したクラウド基盤サービス「Health Cloud for Clinical」である。これにより、医療機関は内視鏡の稼働状況や手技データをクラウド上で一元管理できるようになった。今後、このプラットフォームを通じてAI解析やリアルタイム診断支援を組み込み、臨床ワークフローの最適化を図る計画である。
さらに、2026年度には米国およびEMEA地域で、AIを活用したポリープ自動検出アルゴリズムを搭載した診断支援ソフトウェアの提供を予定。これは、富士フイルムなど競合が進めるAI内視鏡の領域で、オリンパスが**「診断精度と操作効率の両立」**を目指す試みである。
この取り組みを支えるのが、NTTとのクラウド連携実証実験である。両社は医療データを安全に共有し、遠隔診療や臨床支援に応用できるプラットフォームの開発を進めており、これは日本発の医療DXモデルとして国際的にも注目されている。
| 年度 | 主要施策 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024年度 | Health Cloud導入 | 内視鏡データ可視化・運用最適化 |
| 2025年度 | AI解析機能追加 | 臨床画像のリアルタイム診断支援 |
| 2026年度 | SaaS展開 | 米欧でAI診断ツールを商用化 |
このデジタル転換の狙いは、従来の「一度きりの装置販売」モデルを超え、SaaS型サブスクリプション収益の拡大を実現することにある。病院がオリンパスのクラウドシステムを導入し、AI診断や運用分析機能を日常業務に組み込めば、その利用継続が新たな安定収益を生む。
また、このデジタルエコシステムは防御的側面も強い。医療データとAI解析が病院のITインフラに深く統合されることで、他社製品への切り替えコストが急上昇し、オリンパスのプラットフォーム依存度が高まる。つまり、デジタル化は新収益源の創出であると同時に、**「競争優位を強固にするデジタルの堀」**でもある。
オリンパスはこの構想を通じ、医療機器メーカーからデータ駆動型ソリューション企業へと脱皮しようとしている。AIによる臨床支援、クラウドによる医療運用効率化、そしてSaaSによる持続的収益モデル――そのいずれもが、次の10年の競争地図を塗り替える中心にオリンパスの名を刻むだろう。
富士フイルム、HOYAとの激戦:内視鏡市場の覇権争い

オリンパスが主戦場とする消化器内視鏡市場は、実質的に日本の3大メーカーによる寡占構造にある。すなわち、オリンパス(約70%)、富士フイルム(約20%)、HOYA傘下のPENTAX Medical(10%未満)である。これほど高い市場集中度を誇る医療機器分野は稀であり、技術・ブランド・サービス網の三位一体による参入障壁の高さが、オリンパスの牙城を守ってきた最大の要因である。
この市場構造の中で、最も積極的に挑戦を仕掛けているのが富士フイルムである。同社はAIとITソリューションを融合させた戦略を推進し、「診断精度の可視化」を武器にオリンパスの優位に迫っている。特に「CAD EYE」システムは、AIによる大腸ポリープ検出をリアルタイムで支援するものであり、欧州・米国で高い臨床評価を獲得している。また、富士フイルムは2030年までに医療システム事業の売上を倍増させる方針を掲げ、AI診断を中核としたメドテック領域への投資を加速させている。
一方、HOYAのPENTAX Medicalは、戦略的にニッチ領域へ特化している。特に感染防止対策を重視したシングルユーススコープ(単回使用内視鏡)分野で存在感を発揮しており、再処理工程の簡略化や院内感染リスクの低減といった社会的価値を訴求している。さらに、HOYAグループの光学技術と資本力を背景に、欧州を中心としたライフケアポートフォリオとの連携を進めている。
以下は、主要プレイヤーの戦略比較である。
| 企業名 | 世界シェア | 主な強み | 成長戦略 |
|---|---|---|---|
| オリンパス | 約70% | 内視鏡の臨床優位・世界最大の設置基盤 | 医療AI・クラウド統合でデジタルプラットフォーム化 |
| 富士フイルム | 約20% | 画像処理技術・AI診断支援 | 医療DX・AI内視鏡で攻勢、2030年までに売上倍増目標 |
| HOYA(PENTAX) | 約10%未満 | 感染対策・シングルユーススコープ | 特定領域特化とグループ内シナジー活用 |
富士フイルムのAI戦略、HOYAの衛生・安全重視路線に対し、オリンパスは自社の「医師ネットワークとブランド信頼」に基づく実装力で応戦する。特に、同社が開発を進めるAI支援型「インテリジェント内視鏡」は、画像診断からデータ解析、クラウド連携までを包括する統合プラットフォームであり、単なる内視鏡メーカーではなく“医療データ企業”としての新たな地位を狙っている。
この三つ巴の競争は、内視鏡を単なる医療機器から「データを生む医療インフラ」へと昇華させる転換点である。誰が次世代医療の標準を定義するか——オリンパスの牙城をめぐる覇権争いは、今後10年のメドテック産業の勢力図を決定づけるだろう。
ESG経営とグローバル人材改革:信頼と持続性を支える新リーダーシップ
オリンパスの変革は、事業や財務の再構築にとどまらず、経営の基盤そのものを支えるガバナンス改革へと拡大している。現在、同社を率いるのはメドトロニック出身のボブ・ホワイト社長兼CEOであり、その就任はグローバル経営への本格的な転換点となった。彼は世界最大の医療市場である米国での経験を活かし、企業文化を「国内主導から国際標準へ」刷新している。
経営執行体制も国際的に再編され、CSOのガブリエラ・ケイナーやCFOの泉竜也など、多国籍の経営陣が戦略を牽引している。こうした「多様性経営」は、製品開発や市場戦略の迅速化に寄与し、グローバル展開を支える意思決定の質を高めている。
同時に、オリンパスはESG(環境・社会・ガバナンス)を企業戦略の中心に据えている。環境分野では、2040年までにスコープ1~3の温室効果ガス排出量をネットゼロとすることを宣言し、再生可能エネルギー100%化を目指す。この目標はSBTi(科学的根拠に基づく目標イニシアチブ)により正式認定されており、医療機器業界における環境先進企業としての地位を確立している。
社会面では、医療アクセス格差の解消に向けた教育支援を推進。新興国の医師や医療従事者に対して内視鏡技術のトレーニングを提供し、「医療の公平性」を企業の社会的使命として具体化している。また、製品包装の再生素材化など、循環型経済の構築にも取り組み、2026年には約100種類のディスポーザブル製品を再生可能資源素材へ切り替える予定である。
さらに、ガバナンス面では取締役会議長が最高ESG責任者を兼任し、取締役会直下に「ESG委員会」を設置。これにより、経営判断とサステナビリティ戦略を連動させる体制を整備している。こうした枠組みが、CDP「Aリスト」選出やダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス(DJSI World)への4年連続選定といった国際的評価につながっている。
ESGの取り組みは単なるCSR活動ではなく、リスクマネジメントとブランド資産形成の両輪である。医療は信頼の上に成り立つ産業であり、ESG経営の深度がそのまま企業価値を左右する。
オリンパスのESG戦略は、投資家からの評価を高めるだけでなく、医師・患者・規制当局といった全ステークホルダーとの信頼構築を支える基盤である。
結果として、同社の「グローバル人材×ESG経営」モデルは、日本企業が世界市場で持続的に存在感を高めるための先行事例となった。技術だけでなく、倫理と信頼を武器とする新しいメドテックリーダー像を、オリンパスは現実のものとしつつある。

