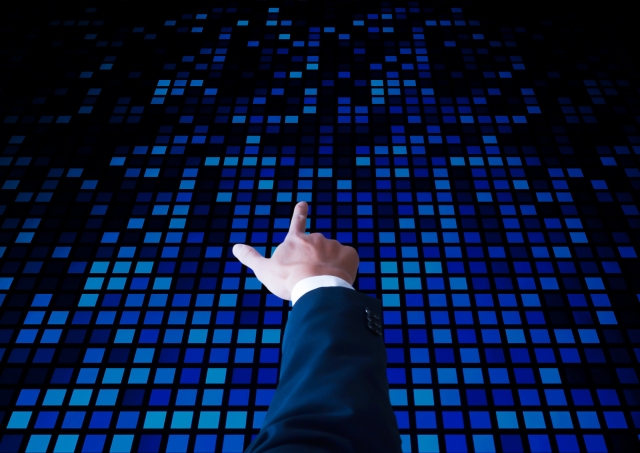デジタルとグリーンの潮流が加速する中、日立製作所が静かに、しかし確実に「製造業の枠」を超えた存在へと変貌している。100年以上にわたり重電・インフラを支えてきたこの企業は、今やデータとテクノロジーを駆使して社会課題を解決する「社会イノベーション事業」の旗手として、世界的な注目を集めている。
この変革の中心にあるのが、ITとOTを融合させたデジタルプラットフォーム「Lumada」と、GX(グリーントランスフォーメーション)を牽引するエネルギー・モビリティ事業である。さらにGlobalLogicやThalesといったグローバル企業の買収によって、日立はデジタル人材と技術の両面で世界水準に躍り出た。
本稿では、日立の進化を支える経営理念からLumadaの実像、3セクター体制の戦略、M&Aの真価、財務実績、そしてサステナビリティ経営までを体系的に分析する。社会インフラの再定義に挑むこの企業の軌跡は、日本産業の新たな未来像を映し出している。
社会イノベーションの原点:創業理念と経営哲学の進化

日立製作所の変革を支える最大の原動力は、100年以上前に創業者・小平浪平が掲げた「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する」という理念にある。この理念は単なる企業スローガンではなく、**「和・誠・開拓者精神」**という創業の精神として全社に受け継がれ、現代の「社会イノベーション事業」へと昇華している。
この思想は、「社会課題をテクノロジーで解決する」という日立のビジネスモデルの中核に位置づけられている。従来の電機メーカー的なモノづくりから脱却し、IT(情報技術)とOT(制御・運用技術)を融合させ、インフラ・エネルギー・都市交通・ヘルスケアなど社会の基盤領域における問題解決を目的化した。この転換こそが、日立が世界の中で独自のポジションを築く決定的な要素である。
さらに、グループ全体の価値観を明確化した「日立グループ・アイデンティティ」は、**MISSION(社会に貢献する理念)・VALUES(創業の精神)・VISION(未来像)**の3層構造で成り立つ。27万人に及ぶ従業員がこの共通言語を持つことで、グローバル規模の一体感を維持しつつ、地域や文化を超えた協働が可能となっている。
表:日立グループ・アイデンティティの3要素
| 要素 | 内容 | 役割 |
|---|---|---|
| MISSION | 優れた自主技術・製品を通じ社会に貢献 | 存在意義の明示 |
| VALUES | 和・誠・開拓者精神 | 行動規範 |
| VISION | 社会イノベーションでより良い社会を創造 | 将来像の共有 |
日立の経営はこの理念を軸に、「社会に必要とされ続ける企業」を目指すという明確な方向性を持つ。単なる利益の最大化ではなく、**「社会価値・環境価値・経済価値の三位一体経営」**を掲げ、事業活動を通じて地球環境や人々の幸福に寄与することを使命としている。この理念の実践が、デジタル化や脱炭素化といった時代の潮流においても揺るがぬ企業軸を形成している。
創業精神を現代経営に融合させる日立の姿勢は、単なる伝統の継承ではない。むしろ、100年企業としての経験を、新しい社会課題解決型モデルの源泉へと変換した結果であり、その哲学的な一貫性が国内外の投資家や顧客からの信頼の基盤となっている。
デジタル変革の中核「Lumada」:データが導く価値創造の最前線
日立のデジタル戦略の象徴である「Lumada(ルマーダ)」は、同社を従来型の製造業からデータ主導型ソリューション企業へと転換させた中心的存在である。その名は“Illuminate(照らす)”と“Data(データ)”を組み合わせた造語であり、**「データに光をあて、経営や社会の課題を解決する」**という思想を体現している。
Lumadaは単一の製品やソフトウェアではなく、IT・OT・プロダクトを統合した「課題解決の仕組み」そのものである。つまり、顧客や社会が抱える複雑な問題を、データ分析とAIを通じて可視化し、最適なソリューションへ導く包括的プラットフォームである。
2024中期経営計画では、Lumada事業の売上収益を2021年度の1.4兆円から2024年度に2.7兆円へ倍増させる目標を掲げた。実際に2023年度時点で2.33兆円に達し、年平均成長率24%という驚異的な伸びを実現している。収益率も16%近くに上昇し、グループ全体の利益を牽引する「稼ぐ中核」へと進化した。
表:Lumada事業の成長推移
| 年度 | 売上収益(兆円) | Adjusted EBITA率 | 全社比率 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.38 | 12% | 21% |
| 2022 | 1.96 | 14% | 26% |
| 2023 | 2.33 | 15% | 27% |
| 2024見通し | 2.65 | 16% | 29% |
Lumadaの特徴は、**「協創(Co-Creation)」**を軸に顧客と共に価値を創り出す点にある。製造業ではニチレイフーズの生産計画自動化、モビリティ領域ではイタリア・ジェノバ市のMaaS統合プラットフォーム構築など、具体的成果が多数生まれている。これらは単なるシステム提供ではなく、顧客企業の事業構造そのものを変革する取り組みである。
また、Lumadaは社内文化の変革にも寄与している。縦割りだった事業部門を横断し、データを基軸に全社の知見を融合させる「One Hitachi」体制を生んだ。**技術だけでなく、組織や思考の変革を促す“企業OS”**として機能している点が、他のDXソリューションとは一線を画す。
このLumadaを軸に、日立は「製造業発のデジタル企業」という新たなカテゴリーを確立しつつある。今後は生成AIや量子技術を取り込み、データの価値を社会インフラ全体に拡張することで、世界の社会イノベーションをリードする存在へと成長していくだろう。
3セクター体制の戦略:デジタル・グリーン・インダストリーの融合モデル

日立製作所が掲げる「社会イノベーション事業」を実現するための中核が、**3セクター体制(デジタルシステム&サービス、グリーンエナジー&モビリティ、コネクティブインダストリーズ)**である。この構造は、単なる事業分割ではなく、DX(デジタルトランスフォーメーション)とGX(グリーントランスフォーメーション)の双方を推進するための戦略的なエコシステムとして設計されている。
2023年度の実績では、この3セクターが全社Adjusted EBITAの約9割を生み出し、日立の成長を牽引した。2025年にはエネルギーとモビリティの分離により、より専門性の高い4セクター体制へ移行しているが、根底にある構想は変わらない。**「IT×OT×プロダクトの融合」**を通じて、社会システム全体の最適化を目指す点にある。
表:日立の主要セクター別業績(2023年度)
| セクター | 売上収益(億円) | 前年比 | Adjusted EBITA率 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| デジタルシステム&サービス(DSS) | 26,118 | +9% | 12.9% | DX推進の司令塔、GlobalLogic・Hitachi Vantaraを傘下に保有 |
| グリーンエナジー&モビリティ(GEM) | 27,946 | +24% | 7.4% | HVDC送電・原子力・鉄道システム・MaaSが成長エンジン |
| コネクティブインダストリーズ(CI) | 30,579 | +3% | 10.5% | ビルシステム・産業機器・半導体装置・環境ソリューションを展開 |
この3セクター体制の最大の強みは、DSSが開発するAI・クラウド技術を中核に、GEMとCIが実社会での運用・実装を担う連携構造にある。IT企業が持たない現場の深い知見(OT)と、製造・設備インフラという膨大なアセットを自社グループ内で循環させることにより、持続的に価値を創出できる。
特に注目されるのは、GEMにおける高圧直流送電(HVDC)事業の急成長である。日立エナジーは欧州・インド・米国などで20億ユーロ規模の案件を次々と受注し、世界の再エネ送電市場でトップクラスの地位を確立した。これにより、日立は**「脱炭素インフラを支える日本発の中核プレイヤー」**となっている。
CIセクターでは、エレベーターや空調、産業機器などのインストールベースを「デジタライズドアセット」として捉え、稼働データを活用した予兆保全・遠隔監視サービスを展開。ビジネスモデルのリカーリング化(継続収益化)を進めている。
このように、デジタルによる分析・最適化と、リアルなインフラ提供を一体で行う日立の構造は、「デジタルが社会を動かす」時代に最も適した統合モデルとして進化を遂げつつある。
GlobalLogicとThales買収:時間と人材を買う経営戦略
日立製作所がグローバルリーダーへの飛躍を遂げた背景には、「時間と人材を買う」戦略的M&Aがある。2021年の米GlobalLogic社買収、2024年の仏Thales社鉄道信号事業(GTS)買収はいずれも約1兆円規模の大型投資であり、その意図は明確だった。自社育成では追いつけないデジタル人材・技術基盤を一気に獲得し、変革スピードを世界水準へ引き上げることにあった。
GlobalLogicはUX/UI設計、アジャイル開発、エクスペリエンスデザインに強みを持つ米国発のデジタルエンジニアリング企業であり、買収によって日立は顧客起点のデジタル変革力を獲得した。GlobalLogicの専門家集団は、社内各事業部のDX推進を支援する「デジタル頭脳」として機能し、Lumadaのグローバル展開を加速させた最大の要因である。
実際、米ヘイガーズタウン工場ではGlobalLogicとEricssonが協業し、5GネットワークとAIを活用したデジタルツイン工場を構築。安全性と生産効率を同時に高める「次世代スマートファクトリー」のモデルケースを実現した。また、水処理事業のHitachi Aqua-Techでは、クラウド基盤「MIZU LINK」を共同開発し、開発工数を50%削減。こうした具体的成果がPMI(統合プロセス)の成功を裏付けている。
一方、Thales社のGTS部門買収は、鉄道信号事業を中心に欧州市場を一気に掌握するものだった。ドイツ、フランス、カナダなどで強固な顧客基盤を持つ同社の買収により、日立レールは**「信号と車両を一体で提供するターンキープロバイダー」**へと進化した。
この結果、日立レールの売上規模は約1.2兆円、信号関連が収益の6割を占める高収益構造へ転換。さらに約9,000人の高度なデジタル技術者が加わり、欧州全域でのMaaS・スマートモビリティ事業展開が加速している。
箇条書きで整理すると、これらのM&Aがもたらした主要成果は以下の通り。
- Lumada事業のグローバル展開力を強化
- 顧客起点型デジタル開発(アジャイル型)の内製化
- 欧州モビリティ市場でのプレゼンス拡大
- 約9,000人のデジタル人材獲得
- 車両・信号・制御を統合した高収益ビジネスモデル確立
これらの買収は単なる事業拡張ではなく、「変革の時間を買う」戦略的な先行投資であった。デジタル人材の獲得競争が激化する中、日立はM&Aを通じて自らの変革スピードを劇的に高め、世界のデジタル・インフラ市場で「One Hitachi」としての存在感を確立しつつある。
財務から読み解く競争優位:中期計画達成と市場評価

日立製作所の財務実績は、構造改革の集大成として極めて堅調である。2024年3月期決算では売上収益10兆8,812億円、営業利益(Adjusted EBITA)9,322億円を記録し、営業利益率は8.6%と過去最高水準を維持した。これは2021年度比で約1.6倍の利益成長に相当する。
さらに注目すべきは、キャッシュ創出力の向上である。フリーキャッシュフローは6,000億円を超え、自己資本比率も約38%に上昇。大規模なM&Aを実施しながらも健全な財務体質を保ち、**「攻めと守りを両立する経営構造」**を実現している点が特筆される。
表:主要財務指標の推移(単位:億円)
| 指標 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度(実績) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 87,275 | 102,049 | 107,585 | 108,812 |
| Adjusted EBITA | 6,045 | 7,735 | 8,803 | 9,322 |
| Adjusted EBITA率 | 6.9% | 7.6% | 8.2% | 8.6% |
| フリーキャッシュフロー | 4,425 | 5,271 | 5,874 | 6,103 |
2024中期経営計画において掲げた「社会イノベーション事業を中心とする成長基盤の確立」はほぼ達成された。3セクター(DSS、GEM、CI)がそれぞれ安定的な収益源として機能し、Lumadaを軸にしたデジタルソリューション事業の利益貢献が大きい。
一方で、2025年以降の課題として、グローバル市場での為替影響や欧州鉄道事業におけるコスト高騰が指摘されている。しかし、アナリストの見解は概して強気であり、みんかぶ・株予報Proなど複数の調査機関は**「目標株価5,200円、レーティング強気」**を維持している。
財務面の安定性と事業ポートフォリオの多角化が、日立の株式市場での高評価を支えている。ROIC(投下資本利益率)は10%台を維持し、資本効率性の面でもグローバル企業基準を満たす。**「稼ぐ力」「投資する力」「持続する力」**の3軸がバランスした経営基盤こそが、日立の競争優位の根源である。
サステナビリティ経営の深化:GX×DXで描く未来社会
日立製作所は、サステナビリティを企業戦略の中心に据え、**「環境・社会・経済の三価値の同時実現」**を掲げている。その実行力は、ESG評価機関からの高い評価に裏づけられている。
具体的には、MSCI ESGレーティングで「AA(リーダー)」を獲得し、CDP(気候変動分野)では4年連続で最高評価「Aリスト」に選定されている。また、ISS ESGの「Prime」認定を受けるほか、FTSE4GoodやFTSE Blossom Japan Indexなど主要ESG投資指数にも継続的に採用されている。
表:日立製作所の主なESG評価実績
| 評価機関 | 評価内容 | 評価結果 |
|---|---|---|
| MSCI ESG Rating | 総合ESG評価 | AA(リーダー) |
| CDP | 気候変動・情報開示 | Aリスト(4年連続) |
| ISS ESG | Corporate Rating | Prime認定 |
| FTSE4Good / Blossom Japan | 投資指標選定 | 継続採用 |
環境分野では、「カーボンニュートラル2050」を視野に自社・顧客・社会全体の排出削減を推進。特にエネルギー事業でのHVDC(高圧直流送電)技術や、都市交通分野での電化モビリティ事業がGX(グリーントランスフォーメーション)の実践例となっている。
加えて、デジタル技術を活用したサステナビリティの可視化も進む。Lumadaを活用した環境データ分析や循環経済ソリューションが、企業や自治体の脱炭素経営を支援している。**「DXを通じてGXを加速させる」**という一貫した戦略は、他社が模倣しにくい競争力を生んでいる。
人材面でも、多様性と包摂性を重視する経営文化を形成しており、女性管理職比率の引き上げ、外国籍役員の登用、グローバル人材育成プログラムの拡充が進む。こうした取り組みは、単なるCSRではなく、経営の中核的価値として組み込まれている。
総じて、日立のサステナビリティ経営は、単なる「環境配慮型企業」ではなく、社会システムそのものを変革するGX×DX企業への進化モデルである。ESG投資が加速する世界市場において、この方向性は長期的な企業価値創造の最大の基盤となるだろう。
生成AIと日立の次世代構想:「Inspire 2027」が描く未来

日立製作所が掲げる新中期経営計画「Inspire 2027」は、単なる数値目標ではなく、生成AIを核とした次世代社会インフラ構築の青写真である。その中心に据えられているのが、「人とデジタルの協創による持続可能な社会の実現」というビジョンであり、同社が長年培ってきたOT(制御技術)とIT(情報技術)の融合を次のステージに引き上げるものとなっている。
この構想の骨子は三つある。第一に、生成AIや量子技術を含む先端デジタルの社会実装。第二に、カーボンニュートラルを超えた**「ネットポジティブ経営」**への転換。第三に、企業内外のデータを結合し、産業横断型のソリューションを創出するエコシステム形成である。
表:Inspire 2027の主要テーマ
| テーマ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 生成AI活用 | Lumada+生成AIによる自動設計・意思決定支援 | 人とAIの協働による生産性向上 |
| GXの深化 | エネルギー・交通・都市を脱炭素化 | ネットゼロからネットポジティブへ |
| データ連携基盤 | 産業・行政データの相互運用を促進 | 社会全体の効率化 |
特に生成AI分野では、Lumadaの分析・予測モデルに加え、自然言語生成技術を導入することで、設備メンテナンス報告や設計仕様書の自動生成など、**「知識労働の自動化」**を本格化させている。Hitachi Vantaraを中心に、米国・インドのデジタル拠点でAIガバナンス体制を整備し、信頼性・透明性を確保したAI実装を進めている点も特徴である。
さらに、量子アニーリング技術を用いた社会シミュレーションにも着手。交通渋滞や電力負荷など都市全体の最適化をリアルタイムに行う「量子・AI複合システム」の実証を進めており、東京・ロンドン・バンガロールで共同プロジェクトが動き始めている。
人材面では、GlobalLogicと連携した「AIエクスペリエンスデザインセンター」を開設。ここではAIによるUI/UX設計自動化や、顧客対話型生成モデルの開発が進む。これにより、顧客がプロトタイプを提示すれば、AIが代替案を瞬時に生成し、開発期間を大幅に短縮する新しい業務スタイルが浸透しつつある。
日立のInspire 2027は、DXの次に来る「HX(Human Transformation)」を見据えた戦略でもある。AIが人間の判断を置き換えるのではなく、人間の創造性を拡張するパートナーとして機能させる発想である。これこそが、日立が目指す「人中心のテクノロジー経営」であり、社会イノベーションを次の世紀へと導く原動力となる。
生成AIを軸にしたこの変革は、単に技術的進化ではなく、社会・産業・人材を包摂する全方位の再設計である。Inspire 2027は、日立が「テクノロジー企業」から「社会変革企業」へと進化することを象徴する旗印であり、その波は日本の産業構造全体にも波及していくことになるだろう。