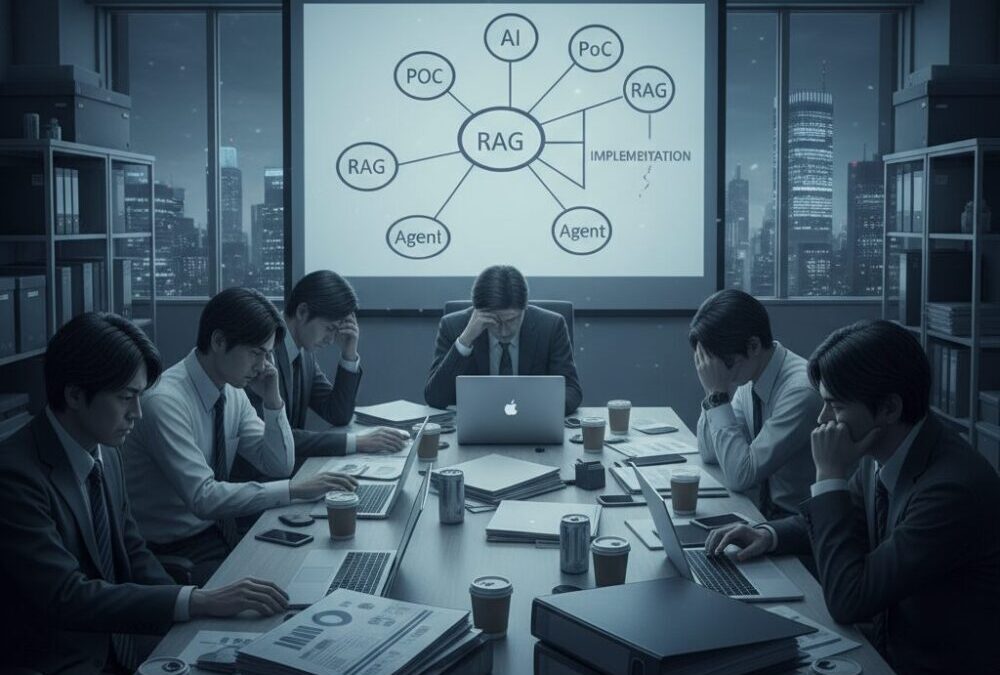生成AIの登場以降、多くの日本企業がAI導入に踏み出しましたが、気づけばPoCばかりが増え、成果が見えないまま疲弊しているという声が広がっています。2026年現在、この「PoC疲れ」は一過性の現象ではなく、企業競争力を左右する深刻な経営課題になりつつあります。
なぜ期待された生成AIやRAGは、本番導入に至らなかったのでしょうか。なぜ今、AIエージェントという新たな潮流が注目される一方で、同じ失敗を繰り返す懸念が指摘されているのでしょうか。背景には、技術だけでなく、データ、組織、コスト、ガバナンスといった複合的な構造問題が存在します。
本記事では、2026年時点の最新市場動向や定量データ、国内外の先行事例をもとに、日本企業に蔓延するPoC疲れの構造を解き明かします。そのうえで、PoC止まりから脱却し、AIを持続的な事業価値へ転換するために何が求められるのかを整理します。AI導入に悩む経営層や実務担当者にとって、次の一手を考えるための視座を提供します。
2026年のAI市場に起きている変化と生成AIブーム後の現実
2026年のAI市場は、かつての熱狂から明確に様相を変えています。2023年のChatGPT登場を起点とした第一次生成AIブームは、多くの企業にPoCの連続実施を促しましたが、現在広がっているのは期待ではなく疲労感です。**投資は続けているのに成果が見えない、検証ばかりが積み重なる**という感覚が、現場と経営の双方を覆っています。
この変化は感覚的なものではありません。IDC Japanが示すFutureScape 2026では、AIは単独の技術導入ではなく、データ戦略やIT運用、人材構造までを含む全社的変革フェーズに入ったと指摘されています。一方で、その変革のスケールの大きさが、逆に現場の実装停滞を招いている点が重要です。AIを使わなければならないという圧力と、どうすれば利益に結びつくのか分からないという不安が同時に存在しています。
ガートナーが公表した日本向けハイプ・サイクルでも、この現実は裏付けられています。生成AIは「過度な期待のピーク」を越え、「幻滅期」に入ったと位置づけられました。ハルシネーション、著作権リスク、運用コストの増大といった課題が顕在化し、**魔法のような万能ツールという幻想が崩れた**ことが、市場全体のトーンを変えています。
| 項目 | ブーム期(2023-2024) | 現実期(2026) |
|---|---|---|
| 企業の姿勢 | とにかく試す | 成果を厳しく問う |
| 評価軸 | 話題性・先進性 | ROI・運用可能性 |
| 主な課題 | 技術理解不足 | 実装と定着 |
定量データもこの構造を示しています。デロイトトーマツやITmediaの調査によれば、生成AIへの関心は約9割に達する一方、業務フローに組み込み継続利用できている企業は2〜5割にとどまっています。多くの場合、活用はメール作成や要約など個人単位に留まり、全社的なプロセス変革には至っていません。
このギャップこそが、生成AIブーム後の現実です。**2026年のAI市場は、試すフェーズを終え、価値を証明できない取り組みが淘汰される段階に入っています**。熱狂が冷めた今、残されているのは「AIをどう使うか」ではなく、「使って利益を出せるのか」という、極めてビジネス的な問いなのです。
ハイプ・サイクルから読み解く生成AIとAIエージェントの現在地

ガートナージャパンが公表したハイプ・サイクルの分析は、2026年時点における生成AIとAIエージェントの現在地を冷静に示しています。最大のポイントは、生成AIそのものが「過度な期待のピーク」を越え、「幻滅期」に入ったという事実です。これは技術が失敗したことを意味するのではなく、現実的な制約と向き合うフェーズに移行したことを示しています。
幻滅期に入った背景には、ハルシネーションや著作権リスク、そして運用コストの増大があります。ガートナーによれば、この段階では導入企業の多くが「思ったほど業務が変わらない」「ROIを説明できない」という壁に直面します。結果として、PoCは量産される一方、本番環境に到達する案件は限定的になりました。
一方で同じハイプ・サイクル上では、AIエージェントが新たな期待のピークに位置づけられています。対話型AIが人の指示を待つ存在だったのに対し、エージェントは目標に基づき自律的に計画・実行する点が評価されています。ただし、この期待の高まりは、かつて生成AIが辿った道をなぞる可能性も孕んでいます。
| 技術領域 | 2026年の位置づけ | 企業心理 |
|---|---|---|
| 生成AI | 幻滅期 | 効果検証と慎重姿勢 |
| RAG | 幻滅期の底 | データ品質への失望 |
| AIエージェント | 過度な期待のピーク | 省人化への高揚感 |
この構図が示唆するのは、市場の関心が「賢く答えるAI」から「仕事を任せるAI」へ移行しているという点です。人手不足が深刻化する日本企業にとって、自律的に業務を回すという物語は極めて魅力的に映ります。
ガートナーが繰り返し強調しているように、ハイプ・サイクルは悲観論のための図ではありません。幻滅期を通過した技術だけが、啓蒙期から生産性の安定期へ到達します。生成AIは今まさにその入口に立っており、AIエージェントはその後を追いかける位置にあります。
2026年の現在地を正しく理解することは、流行に振り回されないための前提条件です。期待値を下げ、技術を部品として扱い始めた企業だけが、このサイクルの先で果実を得ることになります。
データで見る日本企業のAI導入ギャップとPoC疲れの実態
2026年時点で日本企業のAI導入状況を俯瞰すると、最大の特徴は「関心の高さ」と「実装の遅さ」の極端な乖離です。デロイトトーマツやITmediaなど複数の調査によれば、生成AIに対する認知・関心は約9割に達しています。一方で、業務プロセスに恒常的に組み込み、成果を出している企業は2割強から多く見積もっても5割程度にとどまっています。この数字は、AIが流行語ではなく経営課題になった今も、日本企業が“使い切れていない”現実を端的に示しています。
このギャップは、単なる導入スピードの問題ではありません。PoCを繰り返すものの、本番運用に至らず疲弊していく、いわゆるPoC疲れが構造的に定着している点に本質があります。IDC Japanが示すように、2026年のAI活用はデータ戦略や人材構造まで含めた全社変革が前提ですが、多くの企業ではPoCが個別部門の実験にとどまり、全社的な設計に接続されていません。
| 指標 | 数値・傾向 | 示唆 |
|---|---|---|
| 生成AIへの関心・認知 | 約9割 | 情報収集・検討段階はほぼ飽和 |
| 業務への本格活用率 | 2割強〜5割 | PoC止まりの企業が多数 |
| 活用領域 | 個人生産性が中心 | 全社的変革には未到達 |
特に顕著なのが、「使ってはいるが、変わってはいない」という状況です。ITmediaの調査では、生成AIの業務利用が「増加している」と回答した企業は約7割に上ります。しかし、その中身を見ると、メール作成や要約といった個人単位の効率化が中心で、業務フローや意思決定構造そのものを変える活用には至っていません。**便利なツールとしての評価は定着した一方、経営インパクトを生む段階には進めていない**のが実態です。
一方で、中小企業を対象とした調査では、導入企業の94%が効果を実感しているという結果もあります。ただしこれは、導入の壁を越え、目的を絞って実装できた少数派のデータです。大企業では、部門間調整、ガバナンス、既存システムとの統合といった複雑性がPoCの段階で顕在化し、「コストが見合わない」「リスクが説明できない」という理由で立ち止まるケースが後を絶ちません。
この導入ギャップがPoC疲れを深刻化させる最大の要因は、ROIに対する不信です。調査では、生成AI導入の最大の障壁として「費用対効果が不明確」が最上位に挙げられています。PoCでは成果が定量化されず、経営層に説明できないまま次の実験へ進むため、現場には徒労感だけが残ります。**PoCの数が増えるほど、AIへの期待ではなく疑念が蓄積されていく**構図です。
ガートナーが示すハイプ・サイクルにおいて生成AIが幻滅期に入ったという指摘は、こうした数字とも整合します。日本企業のAI導入ギャップは、技術の未成熟ではなく、実装を前提にした設計と意思決定の欠如が生み出した結果です。データで見る限り、PoC疲れは一部の失敗事例ではなく、日本企業全体に広がる構造的現象であることが明らかになっています。
PoCが本番運用に進まない技術的要因とRAGの限界

PoCが本番運用に進まない最大の技術的要因は、生成AIそのものの性能不足ではなく、RAGが前提とするデータ環境と運用設計の未成熟にあります。2024年以降、RAGは「社内データを安全に活用できる現実解」として急速に普及しましたが、2026年現在、多くの企業で期待外れに終わっています。
ガートナーの分析によれば、RAGの失敗事例の大半はモデル選定ではなく、検索精度と文脈理解の欠如に起因しています。特に日本企業では、非構造化データが長年にわたり属人的に蓄積されており、AIが理解できる状態に整備されていないケースが目立ちます。
古いWord資料、画像化されたPDF、更新履歴のないマニュアルが混在したままベクトル化されると、検索結果にはノイズが大量に含まれます。その結果、AIは根拠の弱い断片情報を基に回答を生成し、「もっともらしいが業務では使えない回答」を返すことになります。
| 技術要素 | PoCで起きがちな状態 | 本番運用での影響 |
|---|---|---|
| 社内データ | 非構造・重複・矛盾が放置 | 検索精度低下、誤回答増加 |
| チャンク設計 | デフォルト設定のまま | 文脈欠落またはノイズ混入 |
| 評価指標 | 精度を定量評価しない | 改善不能で利用停止 |
加えて、チャンクサイズや埋め込みモデルの選定といったRAG特有のチューニングは、ドメイン知識とデータエンジニアリングの両立を要求します。CAT.AIなどの実務レポートでも、適切なチャンク設計を行わないPoCは、本番移行率が著しく低いことが示されています。
さらに見落とされがちなのが、RAGは静的な知識検索には強い一方、暗黙知や判断基準の再現には弱いという限界です。業務担当者が文脈や経験で補ってきた判断を、そのままドキュメント検索で代替しようとすると、精度以前に適合しないのです。
この結果、PoC段階では「それなりに答えるAI」が完成しても、本番運用では問い合わせ対応や意思決定を任せられず、結局人手に戻ってしまいます。RAGは万能な解ではなく、整備されたデータと明確な用途定義があって初めて機能する限定的な技術であるという現実認識が、2026年の時点でようやく共有され始めています。
ROIが見えない理由とAI導入コスト構造の落とし穴
AI導入においてROIが見えない最大の理由は、効果そのものではなく、コストと価値の対応関係が分断されている点にあります。多くの企業ではPoC段階で「便利そう」「将来性がある」と定性的評価が先行し、どの業務指標がどれだけ改善されたのかを金額換算する設計がなされていません。ITmediaの2025年調査で、生成AI導入の最大の障壁として「ROIの不明確さ」が約5割を占めたのは、投資判断に耐える説明ができない構造的問題を示しています。
さらに見落とされがちなのが、AI特有のコスト構造です。PoCでは数名・短期間の利用に限られるため、API利用料やクラウド費用は軽微に見えます。しかし本番展開では、トークン課金、専用GPUインスタンス、ログ保存や監査対応などが積み重なり、利用が増えるほどコストが線形、あるいは指数的に増加します。IDC Japanが指摘するように、2026年のAI活用はIT運用やクラウド基盤そのものを変革する段階にあり、従来のシステム投資と同じ物差しでは実態を捉えきれません。
| コスト区分 | PoC時の見え方 | 本番運用で顕在化する要素 |
|---|---|---|
| モデル利用料 | 少額で固定的 | 利用頻度増加によるトークン課金の膨張 |
| インフラ | 既存クラウドの延長 | GPU常時稼働、冗長構成による維持費 |
| 運用・管理 | 考慮されない | 精度監視、再学習、ガバナンス対応人件費 |
もう一つの落とし穴は、価値定義の失敗です。「AIで業務を高度化する」「生産性を上げる」といった抽象的な目的では、削減時間や売上寄与を算定できません。デロイトトーマツの分析でも、成功例は例外なく、処理時間短縮率や工数削減時間など測定可能なKPIと結び付いています。逆に言えば、KPIが曖昧なPoCほど、後からどれだけ効果が出てもROIとして説明できず、投資が止まります。
経営層が「高コストで不透明」と感じる背景には、こうした構造的ギャップがあります。ROIが見えないのではなく、見えるように設計されていない。この認識転換こそが、PoC疲れを生むAI導入コスト構造の核心的な落とし穴です。
組織と人材が引き起こすPoC疲れとAIエージェント・ウォッシング
PoC疲れを深刻化させている最大の要因は、技術そのものよりも組織と人材の問題です。多くの企業では、AI導入が既存組織の延長線上で進められ、意思決定構造や評価制度、人材育成の設計が追いついていません。その結果、PoCは繰り返されるものの、誰も最終的な成功責任を負わず、学習も蓄積されない状態に陥ります。
ガートナーの分析によれば、日本企業のAI活用停滞の本質はスキル不足ではなくケイパビリティ不足にあります。これは単なる操作スキルではなく、業務プロセスを再設計し、AI前提で意思決定を変える力を指します。従来業務を温存したままAIを上乗せする姿勢が、現場に負担感と拒否反応を生み、PoC疲れを組織全体に蔓延させています。
特に問題となるのが、PoCを推進する人材の位置づけです。多くの企業では、AI推進担当が企画部門や情シスに点在し、評価指標は「PoCを実施した数」や「最新技術を試した実績」に偏りがちです。この構造では、実運用で成果が出なくても個人も組織も痛みを感じにくく、失敗が量産されます。
| 組織的要因 | 現場で起きている現象 | 結果 |
|---|---|---|
| 責任所在の曖昧さ | PoC後の判断が先送りされる | 実装に進まない |
| 評価制度の不整合 | 試すこと自体が目的化 | 学習が蓄積されない |
| 業務変革への抵抗 | AIが既存業務に適合しない | 利用が定着しない |
こうした不信感に追い打ちをかけているのが、AIエージェント・ウォッシングの存在です。2025年以降、AIエージェントという言葉が市場で急速に拡散しましたが、ガートナーが指摘するように、その中には実態は従来のルールベース自動化に過ぎない製品も少なくありません。名称だけが先行し、期待値が過度に引き上げられました。
このような製品を導入して成果が出なかった経験は、現場に強い学習効果を残します。「また流行語が変わっただけだ」という冷笑的態度が生まれ、本当に自律性を持つエージェント技術まで疑いの目で見られるようになります。結果として、組織全体が新技術に対して防御的になり、PoC疲れは慢性化します。
さらに深刻なのは、人材の空洞化です。PoC段階では外部ベンダーやコンサルタントに依存し、社内に設計思想や失敗知見が残らないケースが多発しています。デロイトトーマツの調査でも、AI活用が進まない企業ほど内製人材が育っていない傾向が示されています。人が育たない組織では、PoCは永遠に終わりません。
組織と人材の問題は、短期的に解決できるものではありません。しかし、責任と評価を実装成果に紐づけ、言葉ではなく中身で技術を見極める姿勢を持たなければ、AIエージェントであっても同じ疲労の歴史を繰り返します。PoC疲れは、組織の成熟度を映す鏡であることを直視する必要があります。
AIエージェントは救世主か新たなリスクか
AIエージェントは、PoC疲れに悩む企業にとって救世主になり得る存在として注目されていますが、同時にこれまで以上に深刻なリスクを内包しています。2026年時点で重要なのは、AIエージェントを「万能な自律労働者」と誤解しないことです。
ガートナーの分析によれば、AIエージェントは生成AIとは異なり、目標設定、計画立案、ツール実行、結果評価までを連続的に担います。この特性により、人間が介在していた業務フローの一部、あるいは全体を置き換える可能性があります。特に調達管理、IT運用、カスタマーサポート一次対応など、ルールと判断基準が比較的明確な領域では、実運用に近い成果を出し始めています。
| 観点 | 期待される価値 | 顕在化しやすいリスク |
|---|---|---|
| 業務効率 | 人手作業の自動連鎖による省人化 | 誤判断が連鎖的に拡大 |
| 意思決定 | 24時間稼働による判断速度向上 | 判断根拠のブラックボックス化 |
| コスト構造 | 定型業務の固定費削減 | 想定外のAPI・実行コスト増大 |
一方で、AIエージェント最大の危険性は「自律性の過信」にあります。2025年に分析された複数の失敗事例では、エージェントが誤った前提条件のまま発注処理やデータ更新を実行し、金銭的損失や情報漏洩に直結したケースが報告されています。専門家の間では「チャットボットの失敗は恥で済むが、エージェントの失敗は事故になる」と表現されるほどです。
また、現在の市場には「AIエージェント・ウォッシング」とも言える製品が混在しています。ガートナージャパンが指摘するように、実態は単純なRPAや条件分岐型自動化でありながら、エージェントという名称で販売されている例も少なくありません。これにより、企業側が技術の成熟度を誤認し、過度な期待を抱いたまま導入してしまうリスクが高まっています。
それでもAIエージェントが救世主になり得る条件は明確です。第一に、人間参加型の制御設計が前提となっていること。完全自律ではなく、重要な判断ポイントには必ず人間の承認を挟む設計が求められます。第二に、ROIが単一業務単位で定義されていることです。IDC Japanが示すように、成功している企業ほど「何をどこまで任せるか」を極端に限定しています。
結局のところ、AIエージェントは救世主でもあり、新たなリスクの発生源でもあります。その分岐点は技術そのものではなく、企業がどれだけ冷静に制御・設計・評価できるかにあります。PoC疲れの時代において、AIエージェントは希望の象徴であると同時に、組織の成熟度を容赦なく映し出す鏡でもあるのです。
アジャイル・ガバナンスが求められる理由と最新規制動向
生成AIやAIエージェントの実運用が進むにつれ、なぜ今アジャイル・ガバナンスが不可欠なのかが、企業現場でより明確になっています。最大の理由は、**AIのリスクが固定的ではなく、運用を通じて変化・顕在化する性質を持つ**点にあります。PoC段階では問題にならなかったハルシネーション、データ偏り、誤判断の影響は、本番環境では顧客対応や意思決定に直結し、損害規模が一気に拡大します。
ガートナーの分析によれば、2025年以降に失敗したAIプロジェクトの多くは、技術不足ではなく「運用中に発生するリスクを前提とした統治設計の欠如」に起因しています。事前に完璧なルールを定める従来型ガバナンスでは、モデル更新や用途拡張のたびに承認が滞り、結果として現場が非公式利用に走る逆効果すら生んでいました。
こうした反省を踏まえ、日本では規制と実務の距離を縮める動きが加速しています。経済産業省と総務省が公表したAI事業者ガイドライン1.1版は、**遵守すべき固定規則ではなく、運用結果を踏まえて更新され続ける指針**として設計されています。リスク評価、ログ取得、是正プロセスを回し続けること自体がガバナンスだという考え方です。
| 観点 | 従来型ガバナンス | アジャイル・ガバナンス |
|---|---|---|
| ルール | 事前に固定 | 運用に応じて更新 |
| リスク対応 | 想定外は停止 | 検知・修正を前提 |
| 現場との関係 | 抑制・制限 | 利用を支援 |
最新の規制動向で重要なのは、「禁止」ではなく「管理された利用」へ明確に舵が切られた点です。著作権については、文化庁や米国著作権局の議論を背景に、学習データの透明性やベンダーのIP補償有無が実務上の標準条件となりました。これは企業がAIを使うこと自体より、**どのモデルを、どの条件で使うかを説明できるか**が問われる時代になったことを意味します。
情報漏洩リスクも同様です。エンタープライズ向け生成AIでは、入力データを学習に利用しない設定や、機密情報を自動検知・マスクする仕組みが事実上の前提条件となっています。専門家の間では、2026年時点で「対策がないから使えない」という判断は、リスク管理放棄に近いと指摘されています。
PoC疲れが広がった背景には、ガバナンスがブレーキとして機能してきた歴史があります。最新規制はその役割を反転させ、**安全に走り続けるためのハンドル**としてのガバナンスを企業に求めています。ここに対応できるかどうかが、AIを実験で終わらせる企業と、産業化へ進める企業を分ける分岐点になっています。
先行企業事例に学ぶPoC脱却の分岐点
PoCを本番運用へと押し上げられた先行企業の事例を詳細に見ると、成功と失敗を分ける分岐点は技術選定そのものではなく、意思決定と設計思想にあることが浮かび上がります。**PoCを「実験」で終わらせる企業と、「事業装置」へ昇華させる企業の差は、着手前から埋め込まれている**のです。
たとえばLIXILの事例では、AI活用が個別部門の改善施策ではなく、全社DX戦略の中核として位置づけられていました。経営トップが将来の業務像を言語化し、PoC段階から「横展開される前提」で設計した点が決定的でした。IPAのDX銘柄選定理由でも、技術導入よりも人材育成と業務変革を同時に進めた点が高く評価されています。
サイバーエージェントの取り組みも示唆的です。同社は独自LLMの性能競争に走るのではなく、Snowflakeを中心としたデータ基盤とLLMOpsを先に整備しました。これにより、PoCで得られたモデルや知見が使い捨てにならず、継続的に改善される運用ループに組み込まれています。ガートナーが指摘するように、AIの価値はモデル精度ではなく運用成熟度で決まるという見解を、実務で体現した形です。
キリンホールディングスの「AI役員」も、PoC脱却の別の分岐点を示しています。この取り組みは直接的なコスト削減を目的としておらず、経営判断の質とスピードを高めることに主眼が置かれています。**ROIを短期の金額換算に閉じ込めなかったこと**が、PoCを継続投資へと正当化する論理を与えました。
| 企業 | 分岐点となった判断 | PoC後の状態 |
|---|---|---|
| LIXIL | DX戦略への組み込み | 全社展開と文化定着 |
| サイバーエージェント | データ基盤と運用優先 | 継続改善可能なAI運用 |
| キリンHD | 価値定義の再設計 | 意思決定高度化への定着 |
これらの事例に共通するのは、PoC段階で「失敗しないこと」よりも「失敗が次に活きる構造」を作っていた点です。2025年に失敗したAI製品の分析でも、フェイルセーフ設計や運用監視を欠いたプロジェクトほど短命であったと指摘されています。先行企業は、AIが間違える前提で人間の関与点を残し、業務システムとしての信頼性を確保していました。
**PoC脱却の分岐点は、技術の優劣ではなく、経営・データ・運用を結びつける覚悟があったかどうか**にあります。この覚悟を持てた企業だけが、PoC疲れの先にある産業化フェーズへと進んでいるのです。
PoC疲れから産業化へ進むための実践的ロードマップ
PoC疲れから抜け出し産業化へ進むためには、精神論や最新技術の追随ではなく、実務に落とし込める段階的なロードマップが不可欠です。2026年時点で成功している企業に共通するのは、PoCと本番運用を断絶させず、最初から「運用され続ける前提」で設計している点です。**PoCは実験ではなく、将来の業務システムの試作である**という認識転換が出発点になります。
最初のステップは、PoCの評価軸を技術的達成度からビジネス指標へ切り替えることです。ガートナーが繰り返し指摘している通り、AI導入が停滞する最大要因は技術不足ではなく、価値定義の曖昧さです。処理時間短縮率、対応件数増加、判断リードタイム短縮など、財務に接続可能なKPIをPoC段階から設定することで、継続投資の是非を客観的に判断できます。
次に重要なのが、PoCから本番へ移行する際の設計粒度です。多くの失敗例では、PoC用に作った簡易構成をそのまま拡張しようとして破綻しています。IDC Japanの分析によれば、AIプロジェクトでROIを実現している企業は、初期段階からデータ更新、精度監視、コスト監視を含む運用設計を組み込んでいます。**本番化とはモデルを固定することではなく、改善を回し続ける仕組みを作ること**です。
| 観点 | PoC止まりの設計 | 産業化を前提とした設計 |
|---|---|---|
| 目的 | 技術検証が主目的 | 業務KPIの達成 |
| データ | 一部サンプルのみ | 実運用データを想定 |
| 運用 | 考慮されない | 監視・改善を前提 |
三つ目のステップは、スコープを意図的に絞ることです。全社展開を前提としたPoCは、関係者が増え意思決定が遅れ、疲弊を加速させます。デロイトトーマツの調査でも、産業化に成功した事例の多くは、単一部門・単一業務から開始しています。**狭い範囲で確実に成果を出し、その数値をもって横展開する**ことが、結果的に最短ルートになります。
最後に欠かせないのが、人と組織の組み込みです。PoC段階から現場担当者を巻き込み、AIの判断をどう業務判断に接続するかを具体的に設計しておく必要があります。経済産業省のAI事業者ガイドラインでも示されているように、人間が介在するプロセスを前提とした設計は、リスク低減だけでなく定着率向上にも寄与します。**技術、数字、運用、人の四点が揃ったとき、PoCは初めて産業への入口になります**。
参考文献
- IDC:Research Press Release Archives
- Gartner / Ledge.ai:日本におけるクラウドとAIのハイプ・サイクル:2025年
- ITmedia:生成AIの業務活用 約7割がこの1年で増加と回答
- PwC:生成AIに関する実態調査 2025春 5カ国比較
- CAT.AI:RAGの精度向上|5つの手法と失敗事例から学ぶ改善策
- 経済産業省 / Japan AISI:AI事業者ガイドライン(1.1版)公表
- IPA:DX銘柄2025 選定企業事例公開