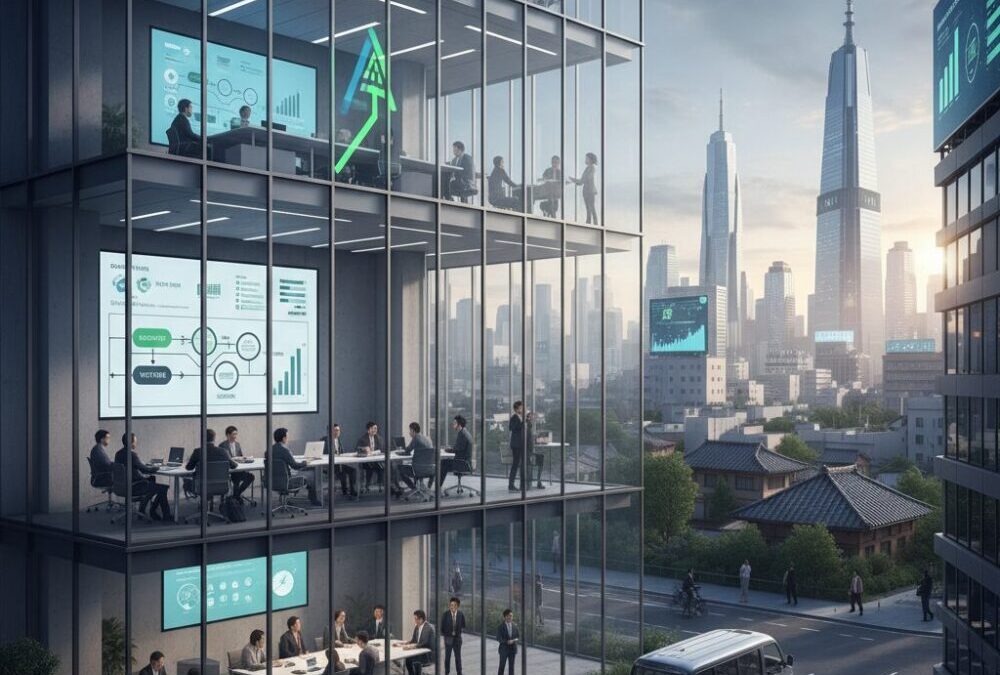「社内起業」や「イノベーション創出」という言葉に、かつてのブーム的な熱狂は感じられなくなりました。補助金やアクセラレータープログラムが乱立した時代を経て、日本企業はいま、本気で成果を問われる局面に立っています。
2026年現在、政策は官主導から民間主導へ、投資環境は拡大から選別へ、企業の取り組みは実験から社会実装へと明確に移行しています。その一方で、多くの企業が「アイデアはあるのに動かない」「最後までやり切れる人材がいない」という深刻な壁に直面しています。
本記事では、出向起業制度の民間移行、スタートアップ投資の構造変化、カーブアウト・スピンオフの最新動向、そして90%の企業が不足を訴える実行人材の問題までを一気通貫で整理します。トヨタ、三菱地所、リコー、パナソニックといった先進企業の実例や、調査データ、学術的な知見を交えながら、2026年以降に日本企業が取るべき現実的な選択肢を読み解いていきます。
社内起業を検討している経営者・事業責任者の方はもちろん、制度設計や人材育成に関わる専門家にとっても、現在地を俯瞰するための羅針盤となる内容です。
2026年、日本のイノベーションは何が変わったのか
2026年の日本におけるイノベーションは、これまでの延長線上では語れない明確な変化点を迎えています。最大の特徴は、**イノベーションの重心が「支援される挑戦」から「自律的に実装される事業創造」へと移行したこと**です。2020年代前半に象徴的だった補助金やアクセラレーター主導の取り組みは一定の役割を終え、企業自身の戦略意思と実行力が厳しく問われる局面に入っています。
この変化を象徴するのが、経済産業省が推進してきたスタートアップ育成5か年計画の中間評価です。2026年時点では、創業数や支援プログラム数といった量的目標は概ね達成されつつある一方で、**社会実装や事業化に至る割合、いわゆる転換率の低さが課題として共有されるようになりました**。内閣官房や経済産業省の進捗資料でも、単発のPoCに終わらず、事業として継続成長する案件をいかに増やすかが次の焦点とされています。
また、制度設計の思想そのものも変わっています。かつては「国がリスクを肩代わりする」設計が中心でしたが、2026年の制度は市場規律を前提としています。出向起業制度において、出向元企業の株式保有比率を20%未満とする要件が厳格に運用されているのはその象徴です。**スタートアップとしての独立性を確保し、外部投資家の目に耐える事業でなければ生き残れない**というメッセージが、制度を通じて明確に示されています。
| 観点 | 2020年代前半 | 2026年時点 |
|---|---|---|
| 主導主体 | 政府・補助金中心 | 民間・企業戦略中心 |
| 評価軸 | 挑戦数・参加数 | 事業化・実装度 |
| 起業の位置づけ | 実証的な試み | 本業を左右する経営課題 |
投資環境の変化も、この潮流を後押ししています。INITIALやPitchBookなどの分析によれば、国内スタートアップへの資金総額は横ばいで推移する一方、投資件数は減少し、1社あたりの調達額は増加しています。これは、**アイデア段階への分散投資から、実績や技術的優位性を持つ企業への集中投資へと市場がシフトした結果**です。企業にとっては、構想段階の新規事業ではなく、成長曲線を描ける事業だけが評価される時代に入ったと言えます。
こうした環境下で、日本のイノベーションは「できるかどうか」ではなく「やり切れるかどうか」が問われています。研究開発や企画力そのものが劇的に向上したわけではありません。しかし、**実行を前提に制度・投資・組織が再設計され始めたことこそが、2026年における日本のイノベーションの本質的な変化**であり、多くの専門家がこの点を転換点として捉えています。
出向起業制度の転換点:補助金終了とJISSUI認定の意味

出向起業制度は2025年を境に、大きな転換点を迎えました。経済産業省が主導してきた補助金事業が2024年度で終了し、2025年度からは一般社団法人社会実装推進センター(JISSUI)による民間主導の認定・助成金制度へと移行しています。これは単なる財源変更ではなく、日本型イントレプレナーシップの成熟度が問われる局面に入ったことを意味します。
経済産業省によれば、補助金終了は「普及啓発フェーズの完了」を示す発展的解消と位置づけられています。実際、2020年代前半の補助金期には、制度を試行する企業数が急増し、出向起業という概念自体は大企業の経営企画層に広く認知されました。一方で、補助金を前提とした取り組みでは、事業の持続性や市場適合性が十分に検証されないまま終わるケースも少なくありませんでした。
JISSUI認定制度の核心は「独立性の厳格化」にあります。とりわけ象徴的なのが、出向元企業の株式保有比率を20%未満とする要件です。これは、スタートアップが連結子会社や持分法適用会社として扱われることで、大企業特有の意思決定プロセスやリスク管理が過度に持ち込まれることを防ぐためです。市場からの資金調達と第三者の目による規律を前提に、真に自律した経営を促す設計だと評価できます。
| 項目 | 補助金事業(~2024年度) | JISSUI認定制度(2025年度~) |
|---|---|---|
| 制度主体 | 国(経済産業省) | 民間第三者機関 |
| 資金の性格 | 税金による直接支援 | 民間資金+認定価値 |
| 企業姿勢 | 制度活用型 | 戦略内製型 |
この移行により、企業側の意思決定にも変化が求められています。従来は「補助金があるから試す」という発想が一定程度許容されていましたが、現在は「自社の中長期戦略として成立するか」が厳しく問われます。JISSUI認定は単なるお墨付きではなく、外部投資家やパートナーに対する信頼シグナルとして機能するため、事業構想やガバナンス設計の質がそのまま評価に跳ね返ります。
実務家の間では、JISSUI認定を取得した出向起業案件は、ベンチャーキャピタルとの初期対話が明らかにスムーズになるという指摘もあります。第三者認証があることで、企業都合の社内プロジェクトではなく、市場志向のスタートアップとして扱われやすくなるためです。これは、官主導から民間エコシステムへの橋渡しとして、制度が果たす新しい役割と言えるでしょう。
補助金終了は支援の後退ではなく、選別と自律の始まりです。出向起業は「守られた挑戦」から「市場で試される挑戦」へと進化しました。この変化を前向きに捉え、自社戦略に組み込める企業だけが、2026年以降の出向起業を成長エンジンとして活用できる段階に入っています。
スタートアップ育成5か年計画の進捗と見えてきた限界
スタートアップ育成5か年計画は、2026年時点で後半戦に入り、量的拡大という初期目標については一定の成果が確認されています。内閣官房や経済産業省の公表資料によれば、スタートアップ数や投資家との接点創出、海外派遣人材の規模といった指標は、当初計画をおおむね前倒しで達成しています。
象徴的なのが、J-StarXに代表される海外派遣プログラムです。2024年末時点で累計673名が派遣され、2026年には1,000名目標を超えるペースで進行しています。**グローバルな起業家ネットワークへの接続という点では、日本の政策として過去に例のない規模感**であり、国際比較でも見劣りしない水準に到達しました。
| 指標 | 当初目標 | 2026年時点の状況 |
|---|---|---|
| 海外派遣人材数 | 累計1,000人 | 前倒し達成見込み |
| 事業会社のスタートアップ投資 | 投資裾野の拡大 | 件数は横ばい、選別は厳格化 |
一方で、進捗が明確になるにつれ、計画の限界も可視化されてきました。最大の論点は、派遣や支援を受けた人材が、その後どれだけ起業や新規事業創出に結びついたかという転換率です。文部科学省やAMEDと連携した調査・議論では、**海外経験そのものが成果を生むのではなく、帰国後の環境設計が成否を分ける**ことが繰り返し指摘されています。
特に大企業所属人材の場合、帰国後に既存組織へ戻った途端、権限や時間、評価制度の壁に直面し、学びを十分に生かせないケースが少なくありません。これは政策の不足というより、企業側の受け皿が整っていない構造的問題だと言えます。経済学者や政策評価の専門家の間でも、「人材投資と組織改革が分断されている点」が日本特有の弱点として語られています。
また、オープンイノベーション促進税制の運用厳格化も、計画の次段階を象徴しています。取得価額の25%控除という強力な制度は維持されたものの、3年以上の株式保有や継続的協業が求められるようになり、形式的な出資は実質的に排除されました。**数を増やすフェーズから、関係性の深さを問うフェーズへ移行した**ことを意味します。
こうした動きを総合すると、スタートアップ育成5か年計画は「政策で環境を整える段階」には成功した一方で、「成果を自走させる段階」には踏み切れていないことが分かります。2026年時点で見えてきた限界は、支援の不足ではなく、政策と企業経営、そして個人のキャリアが十分に接続されていない点にあります。
このギャップを埋められるかどうかが、計画後半の実質的な評価軸になります。**これから問われるのは、新たな施策の追加ではなく、既に育てた人材と制度を、どれだけ実装へ導けるか**という一点に集約されつつあります。
スピンオフ・カーブアウトが経営アジェンダになった理由

スピンオフやカーブアウトが2026年において経営アジェンダの中枢に位置づけられるようになった最大の理由は、「やった方がよい施策」から「やらなければ価値が毀損する選択肢」へと性格が変わった点にあります。背景には、制度・資本市場・人材という三つの外部環境の同時変化があります。
第一に、制度面での転換です。2024年4月に施行されたパーシャルスピンオフ税制の要件緩和により、親会社が一定の持分を保有したまま事業を切り出す場合でも、条件を満たせば課税が繰り延べられるようになりました。経済産業省の手引によれば、この改正によって「完全に手放すか、社内に抱え続けるか」という二択から脱し、戦略的に外部資本を呼び込みながら育てる選択肢が現実的になったとされています。
| 観点 | 従来 | 2026年の変化 |
|---|---|---|
| 税務リスク | 部分保有は課税リスク大 | 一定条件で課税繰延 |
| 経営裁量 | 社内規律に強く拘束 | 独立性と影響力の両立 |
| 外部資本 | 導入が困難 | VC・CVC参画が容易 |
第二に、資本市場の要請です。IPO市場の停滞が長期化する中、PitchBookなどの分析でも、投資家は上場一本足の成長ストーリーに慎重になっています。その代替として、事業会社からのカーブアウトやスピンオフを出口や成長加速の起点として評価する動きが強まっています。既に技術や顧客を持つ事業を独立させる方が、ゼロからのスタートアップよりリスクが低いという合理的判断が共有されつつあります。
第三に、人材とガバナンスの問題です。PwCの調査が示す通り、多くの企業は新規事業を「実行」できる人材を社内に十分持っていません。一方で、社内に閉じたままでは意思決定の遅さや過剰なコンプライアンスが足かせとなります。法人格を分け、評価軸と責任を明確にすること自体が、実行人材を惹きつける装置として機能し始めています。
2026年のスピンオフ・カーブアウトは、成長戦略であると同時に、資本効率と人材戦略を立て直すための経営インフラになっています。
デロイトなどの専門家も、コングロマリット・ディスカウントを受け続けるより、事業ごとの価値を可視化し、市場に委ねる方が中長期の企業価値向上につながると指摘しています。こうした評価軸の変化が、経営層にとってスピンオフやカーブアウトを「先送りできないテーマ」に押し上げているのです。
資金調達環境の現実:拡大の時代から厳選の時代へ
2026年の資金調達環境を語る上で最も重要な変化は、かつての「拡大ありき」の局面が終わり、厳密な選別を前提とした資本配分の時代へ完全に移行した点にあります。INITIALやPitchBookの分析によれば、国内スタートアップの資金調達総額自体は2025年上半期で約3,400億円と横ばいを維持していますが、その内実は大きく変質しています。
調達件数は減少する一方で、1社あたりの調達額中央値は上昇しています。これは投資家が「数を打つ」戦略を捨て、既に売上、顧客、技術検証といったトラクションを示している企業に資金を集中させているためです。特にシード・アーリー期では、プロダクト構想や社会的意義だけでは不十分で、初期顧客の存在や再現性ある成長仮説が厳しく問われています。
この変化を象徴するのが、IPO市場の停滞です。2026年時点でも上場環境は回復途上にあり、短期的なIPO益を前提とした投資モデルは成立しにくくなっています。PitchBookのレポートでも、投資家の関心がIPO一択から、M&Aやカーブアウトを含む複線的な出口戦略を描ける企業へ移っていることが示されています。
| 観点 | 拡大の時代 | 厳選の時代 |
|---|---|---|
| 投資判断 | 将来性・ストーリー重視 | 実績・検証データ重視 |
| 調達件数 | 多い | 減少 |
| 出口戦略 | IPO中心 | M&A・カーブアウト併用 |
CVCの動きも同様です。ベンチャーエンタープライズセンターの統計では、2025年のCVC投資額は前年同期比で減少しましたが、これは撤退ではなく「戦略なき投資」の整理と解釈できます。トヨタのWoven CapitalやSBI系ファンドのように、自社事業との接続点が明確な案件には引き続き資金と人材が投入されています。
結果として、資金調達はもはやスタート地点ではなく、事業の進捗を証明した企業だけが通過できる関門となりました。拡大の時代に通用した横並びの事業計画ではなく、限られた資本をどう使い、どの市場で勝つのかという具体性こそが、2026年の資金調達環境における最大の通行証となっています。
CVCは何を失い、何を得たのか
2026年時点でCVCは、量的拡大の時代に享受していた「自由さ」を明確に失いました。かつてはオープンイノベーションの名の下、戦略的意義が曖昧なままでも投資が成立し、社内的にも挑戦として許容されてきました。しかし、投資環境が「冬の時代」から「厳選の時代」へ移行する中で、CVCには財務的妥当性と事業的必然性の両立が強く求められるようになっています。
ベンチャーエンタープライズセンターの2025年第2四半期データによれば、国内CVC投資金額は前年同期比で減少しました。この数字は単なる縮小ではなく、**お付き合い投資の終焉**を示しています。投資件数を維持することよりも、投資後に何を実装できたのかが、経営層や市場から厳しく問われる局面に入ったのです。
一方で、CVCが得たものも非常に大きいと言えます。最大の変化は、CVCが「財布」から「事業共創の中核装置」へと再定義された点です。トヨタ自動車のWoven CapitalやSBIグループのCVCは、投資先を単に財務ポートフォリオとして扱うのではなく、自社の事業開発部門と密接に連動させ、技術の社会実装まで踏み込んで支援しています。
| 観点 | 従来型CVC | 2026年型CVC |
|---|---|---|
| 投資目的 | 関係構築・情報収集 | 事業共創・実装 |
| 評価軸 | 件数・話題性 | 実装成果・事業KPI |
| 社内位置づけ | 周辺機能 | 事業開発の中核 |
この変化により、CVC担当者には投資スキルだけでなく、事業開発や組織調整の高度な能力が求められるようになりました。デロイトなどの専門家が指摘するように、CVCは単独で完結する組織ではなく、研究開発、営業、経営企画を横断するインターフェースとして機能する必要があります。
結果としてCVCは、短期的な投資の自由度を失う代わりに、**企業変革に直接関与できる実効性**を手に入れました。投資先スタートアップの成長と自社の事業進化が同期するかどうかが、CVCの存在価値を左右する時代に入ったと言えるでしょう。
ディープテックとカーブアウトに資金が集まる背景
2026年にかけて、投資マネーがディープテックとカーブアウトに集まっている背景には、単なる流行ではなく、資本市場と企業戦略の構造変化があります。最大の要因は、スタートアップ投資が「拡大」から「回収可能性重視」へと明確に転換したことです。IPO市場の停滞が長期化する中、投資家は短期的な成長ストーリーよりも、技術的優位性や既存事業との接続可能性を厳しく見極めるようになっています。
INITIALやPitchBookの分析によれば、2025年以降の国内投資では件数が減少する一方、1件あたりの調達額は増加しています。これは、SaaSのように模倣されやすいモデルよりも、研究開発に時間と資本を要するディープテックに資金を集中させる動きの表れです。自動運転や宇宙、医療といった分野は政策とも連動しやすく、官民ファンドや大企業CVCが長期資金を供給しやすい点も追い風となっています。
カーブアウトへの資金流入も、この文脈で理解できます。既に大企業の中で技術検証や顧客実績を積んだ事業を切り出すモデルは、ゼロから立ち上げるスタートアップに比べて不確実性が低く、M&Aや持分売却といったIPO以外の出口を描きやすいと評価されています。経済産業省のスピンオフ・カーブアウト税制の整備も後押しとなり、2025年以降、具体案件が増加しています。
特に投資家が評価しているのは、カーブアウト企業が持つ「初期トラクション」です。親会社の顧客基盤や製造・品質管理ノウハウを活用できるため、事業の立ち上がりが早く、資金の使途も明確になります。Chambers and Partnersが指摘するように、日本市場ではこのモデルがコングロマリット・ディスカウント解消の手段としても注目されています。
| 観点 | 従来型スタートアップ | ディープテック・カーブアウト |
|---|---|---|
| 参入障壁 | 低〜中 | 高(技術・知財) |
| 初期不確実性 | 高い | 相対的に低い |
| 想定出口 | IPO依存 | M&A・部分売却も現実的 |
このように、2026年時点でディープテックとカーブアウトに資金が集まるのは、景気循環の結果ではなく、資本市場が成熟し、失敗確率を構造的に下げる投資対象を選別している結果です。企業側にとっても、研究開発や非中核事業を外に切り出し、外部資本とともに育てることが、最も合理的な成長戦略として認識され始めています。
トヨタ・三菱地所・リコーに学ぶ社会実装型イノベーション
社会実装型イノベーションの象徴的な事例として、2026年時点で特に示唆に富むのがトヨタ自動車、三菱地所、リコーの取り組みです。3社に共通するのは、技術やアイデアを社内に留めず、実際の生活者・顧客・社会の現場に持ち出すことを前提に設計している点にあります。
トヨタのWoven Cityは、その最前線に位置づけられます。経済産業省やCESでの公式発表によれば、2025年にフェーズ1が竣工し、2026年には約2,000人規模の居住者を迎える実稼働都市へ移行しました。ここでは自動運転、水素エネルギー、ロボティクスが“実験”ではなく“日常”として使われ、住民の行動データが継続的に収集・改善へと還流します。都市そのものをプロダクトと見なし、社会実装をR&Dの中核に据えた点は、従来の実証実験型イノベーションと一線を画します。
三菱地所のアプローチは、不動産という物理アセットを基盤にした実装です。DX銘柄2025に選定された背景には、丸の内を中心とした街区全体でのデータ連携と、スマートホームサービスHOMETACTの外販化があります。公式資料によれば、同サービスは自社物件に限定せずB2B2Cモデルで展開され、居住後の生活データを活用した継続収益モデルを志向しています。街を「売る」企業から、街を「運営し続ける」プラットフォーマーへの転換が、社会実装型イノベーションとして評価されています。
リコーのTRIBUSは、実装の距離感をさらに縮めた好例です。2025年度は「中小企業の人材課題」という明確なテーマを掲げ、全国の顧客基盤をスタートアップと社内起業家に開放しました。リコーの発表によれば、採択チームはPoCで終わらず、製品化や販売チャネルへの接続まで支援を受けます。アクセラレーターを“選抜イベント”ではなく“事業化装置”として再設計した点に、成熟した社会実装志向が表れています。
| 企業 | 実装の場 | 特徴的な価値 |
|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 実居住都市 | 生活データを前提とした都市R&D |
| 三菱地所 | 都市・住宅 | 不動産×デジタルの継続サービス化 |
| リコー | 中小企業の現場 | 顧客接点を活かした即時事業化 |
ハーバード・ビジネス・スクールの研究でも、イノベーションの成功確率は「技術の新規性」より「実装環境への適合度」に強く依存すると指摘されています。3社の事例は、日本企業が2026年以降、アイデア創出の巧拙ではなく、社会に根づかせる設計力こそが競争力になることを明確に示しています。
最大のボトルネック「実行人材不足」という構造問題
日本企業の社内起業やイノベーション創出において、2026年時点で最大のボトルネックとなっているのが「実行人材の構造的不足」です。制度や資金、外部パートナーが整備される一方で、事業を実際に動かし、顧客を獲得し、継続的に改善する担い手が決定的に足りていません。この問題は個々の企業努力では解消しにくい、産業構造レベルの課題へと発展しています。
PwCコンサルティングの「新規事業開発の取り組みに関する実態調査2025」によれば、新規事業の全工程で9割以上の企業が人材不足を感じており、特に実行フェーズで「大幅に不足している」と回答した企業は46.2%に達しています。アイデア創出やPoCまでは到達しても、売上創出やスケールに進めない、いわゆるPoC死が常態化しているのが現実です。
| 工程 | 人材不足を感じる企業割合 | 主な停滞要因 |
|---|---|---|
| 企画・構想 | 約90% | 事業化経験の不足 |
| 実行・運営 | 約90% | 現場推進力・権限不足 |
| スケール | 約95% | 収益化・組織設計の未経験 |
この不足は単なる人数の問題ではありません。大企業に多いのは、調整や稟議に長けた人材は豊富でも、不確実な状況で仮説検証を高速に回し、意思決定を連続させる経験者が極端に少ないというミスマッチです。スタートアップ経験者や事業責任者経験者は市場価値が高く、社内に留まりにくいことも拍車をかけています。
さらに、若手人材の価値観変化も実行人材不足を深刻化させています。リクルートマネジメントソリューションズの調査では、若手が重視するのは「成長」と「貢献」であり、過度な競争や政治的調整を伴う役割を避ける傾向が明確です。結果として、事業を前に進めるために不可欠な泥臭い交渉や失敗を引き受ける人が不足します。
専門家の間では、この問題に対し「育成」だけでなく構造の再設計が必要だと指摘されています。デロイトや組織学会の議論でも、実行人材を個人の資質に帰すのではなく、権限委譲、評価制度、外部人材との混成チームといった仕組みで補完すべきだとされています。実行人材不足は、日本企業のイノベーションが次の段階へ進むために避けて通れない、最重要の経営課題です。
若手人材の価値観変化とキャリアオーナーシップ経営
2026年の日本企業において、若手人材の価値観は明確な転換点を迎えています。リクルートマネジメントソリューションズの新入社員意識調査2025によれば、仕事で重視する要素の上位は「成長」と「貢献」で占められ、「競争」は3%と最下位でした。勝ち抜くことより、意味ある経験を通じて社会や他者に価値を返したいという志向が、若手の主流になりつつあります。
この変化は、社内起業や新規事業にとって追い風である一方、従来型マネジメントとの摩擦も生みます。競争や根性論を前提とした選抜型の制度では、優秀な若手ほど早期に距離を置いてしまうからです。実際、働きたい職場像として「お互いに助け合う」が約7割を占める一方、情緒的な結束を想起させる表現は支持を失っています。ドライだが相互に尊重し合うプロフェッショナルな関係性が求められています。
| 項目 | 従来型 | 2026年の若手志向 |
|---|---|---|
| 仕事の動機 | 競争・昇進 | 成長・社会への貢献 |
| 組織観 | 会社主導 | 個人主導と相互支援 |
| 評価の期待 | 結果重視 | 挑戦プロセスも重視 |
こうした背景で注目されているのがキャリアオーナーシップ経営です。パーソルキャリアが提唱するこの概念は、キャリアの主体を個人に置き、企業はその挑戦を支援する立場に回ります。2025年のキャリアオーナーシップ経営AWARD受賞企業では、社内起業や越境学習を「特別施策」ではなく、日常的な選択肢として制度化している点が共通しています。
重要なのは、自由放任ではなく「選択と責任」を明確にすることです。心理的安全性の研究で知られる組織学会やHR分野の実践事例では、挑戦を歓迎する一方、KPI未達の場合は撤退を判断する仕組みが成果を生んでいます。自分で選び、自分で学び、必要ならやめるという一連の経験そのものが、若手にとっては成長実感となり、企業にとっては実行力を備えた人材育成につながっています。
学術研究が示す組織変革とナラティヴの重要性
組織変革が停滞する最大の要因は、制度や人材の不足ではなく、組織内で共有されている意味づけや語りの断絶にあることが、近年の学術研究から明らかになっています。組織学会の高宮賞受賞研究や、リクルートワークス研究所の報告によれば、既存事業と新規事業の対立は、利害衝突そのものよりも、互いの文脈が理解されないまま固定化されることで深刻化します。
この文脈で注目されるのがナラティヴ・アプローチです。宇田川元一氏らの研究によれば、組織とは戦略や構造の集合体ではなく、日々の対話を通じて編まれる「物語のネットワーク」として捉えるべきだとされています。新規事業が失敗する多くのケースでは、挑戦の合理性が語られないまま「例外」や「異物」として扱われ、周囲の協力を得られなくなっています。
| 視点 | 従来型アプローチ | ナラティヴ・アプローチ |
|---|---|---|
| 問題の捉え方 | 個人の能力や意欲 | 関係性と語りのズレ |
| 解決手段 | 評価制度・権限付与 | 対話による意味の再構築 |
実務への示唆は明確です。社内起業やカーブアウトを進める際には、KPIや投資額の説明だけでなく、なぜ今この挑戦が必要なのか、既存事業にどんな価値をもたらすのかを言語化し、対話を重ねる必要があります。ある製造業の事例では、新規事業チームが定期的に既存事業部門と失敗談を共有する場を設けたことで、協力部署が増え、PoC止まりだった案件が事業化に進みました。
学術研究が示すのは、組織変革とはトップダウンの号令ではなく、複数の物語を接続し直すプロセスだという点です。ナラティヴを意識的にマネジメントすることが、2026年以降の日本企業におけるイノベーション実装力を左右する重要な分岐点となっています。
参考文献
- 経済産業省:出向起業の促進
- 一般社団法人社会実装推進センター:2025年度 出向起業「認定・助成金」
- 内閣官房:「スタートアップ育成5か年計画」の進捗状況について
- Deloitte:オープンイノベーション促進税制の申請(2025年度)
- INITIAL:Growth Prospects for Trends in Japanese Startup Deals in First Half of 2025
- PwC:新規事業開発の取り組みに関する実態調査 2025年
- トヨタ自動車:モビリティのテストコースToyota Woven Cityで、本日実証を開始