建設・鉱山機械の巨人コマツが、いま新たなステージへと踏み出している。2025年度から始まる中期経営計画「Driving value with ambition」は、従来の“重機メーカー”という枠を超え、顧客の現場全体を最適化するソリューションプロバイダーへの転換を明確に示すものである。世界的な脱炭素化、労働力不足、地政学リスクという三重苦の時代において、同社はデジタル技術とクリーンエネルギーを両輪に、事業構造の再定義を進めている。
特に注目されるのが、バッテリー電動化と水素燃料電池という「脱炭素の二刀流」戦略である。米国ABS社の買収による垂直統合と、GMとの燃料電池共同開発という外部連携を組み合わせることで、サプライチェーンの強靭化と技術優位を同時に実現する構図だ。さらに、AHS(無人ダンプトラック運行システム)やSmart Constructionといったデジタルソリューションが、現場の安全性・生産性を革新している。
一方、財務面では3年間で1兆円のフリー・キャッシュ・フロー(FCF)創出を掲げ、自己資金による成長投資と株主還元の両立を図る。ESGガバナンスの透明性強化も進み、非財務指標を含めた企業価値創造の基盤を確立しつつある。技術・財務・ガバナンスを統合するこの戦略こそ、次世代コマツの企業像を象徴している。
変革期を迎えるコマツ:製造業からソリューション企業への進化

建設・鉱山機械の代名詞として知られるコマツが、いま大規模な構造転換に踏み出している。2025年度から始まる新中期経営計画「Driving value with ambition」は、「安全で生産性の高いクリーンな現場を実現するソリューションパートナー」への再定義を掲げ、従来の「モノづくり企業」から「現場価値を提供するプラットフォーマー」への進化を鮮明にしている。
この変革の背景には、世界的な脱炭素化の潮流、労働人口の減少、そして地政学リスクの高まりという三重の課題がある。コマツはこれらを単なるリスクではなく、技術革新と事業モデルの刷新によって新たな成長機会に変換する構想を描いている。
特に注目されるのが、収益の軸を「モノ価値」から「コト価値」へと移行する方針である。つまり、単なる機械販売ではなく、AI・IoT・自動化技術を駆使した現場全体の生産性向上サービスを提供する事業モデルへの転換だ。この構造転換によって、景気循環に左右されにくい安定収益源の確立を目指している。
コマツの戦略的進化の概要
| 項目 | 従来の姿 | 新戦略の方向性 |
|---|---|---|
| 事業モデル | 建機・鉱山機械の製造販売中心 | ソリューション提供型への転換 |
| 収益構造 | モノ価値(製品販売) | コト価値(デジタル・サービス) |
| 技術投資 | 機械性能向上 | AI・DX・クリーンエネルギー技術 |
| 顧客接点 | 製品納入後サポート中心 | データ連携によるライフサイクル支援 |
この変革の象徴的存在が、**鉱山用無人ダンプトラック運行システム(AHS)**である。すでに世界5カ国25カ所の鉱山に896台が稼働しており、AIによる運行最適化や安全制御技術で圧倒的なデータ資産を築いている。この蓄積された膨大な稼働データは、次世代の完全自律運転技術や予測保全(Komtrax)の高度化を支える「知的資本」として機能している。
また、同社は建設現場向けの「Smart Construction」事業を拡大し、遠隔操作・自動施工・クラウド管理を統合したデジタルソリューションを展開している。これは、少子高齢化による人手不足や安全性向上といった社会課題の解決と直結しており、単なる業務効率化に留まらず、建設産業そのものの再構築を牽引する基盤技術となっている。
さらに、地政学的なリスクの増大に対しては、サプライチェーン可視化や基幹システム刷新など、DXによる経営インフラ強化を推進している。製造業の枠を超え、社会インフラ全体の持続性に貢献する企業へと進化することこそが、コマツの次世代ビジョンの核心である。
新中期経営計画「Driving value with ambition」が描く未来像
コマツの新中期経営計画(2025–2027年度)は、単なる数値目標ではなく、**企業の存在意義を再定義する「構造変革ロードマップ」**として設計されている。計画の中核は、「イノベーション」「成長性・収益性」「経営基盤革新」という三本柱から構成されている。
第一の柱であるイノベーションでは、水素燃料電池やリチウムイオンバッテリーなど、複数の動力源を柔軟に活用する「脱炭素の二刀流」戦略が推進されている。特に米GMとの水素燃料電池共同開発や、米ABS社の買収による大型バッテリー技術の内製化は、エネルギー転換期における供給網リスクの低減と技術主権の確保を意味する。
第二の柱である成長性と収益性の追求では、アジア・アフリカといった新興市場の拡大に加え、アフターマーケット(メンテナンス・データ解析サービス)の収益化を重視する。これにより、建設・鉱山機械の販売サイクル依存から脱却し、景気変動に強いバリューチェーンビジネスモデルへの進化を目指している。
第三の柱は、経営基盤の革新である。AIを活用した生産・調達・販売データの一元管理や、代理店向けのソリューションプラットフォーム開発など、グループ全体のDX推進によって迅速な意思決定と経営レジリエンスを高める構造を構築中である。
コマツの新中期経営計画の三本柱
| 戦略領域 | 主な施策 | 期待効果 |
|---|---|---|
| イノベーション | 水素燃料電池開発、ABS買収、AI技術投資 | 技術優位性確立・脱炭素化の推進 |
| 成長・収益性 | アフターマーケット拡大、新興市場強化 | 安定収益・地域多角化 |
| 経営基盤 | DX・AIによる業務統合と迅速化 | 経営レジリエンスの向上 |
また、同社は財務面で3年間で1兆円のフリー・キャッシュ・フロー創出という高い目標を掲げている。これは外部資金に頼らず、自己資金で革新投資を継続する強固な資本規律を示すものだ。
こうした一連の施策は、単なる経営改善ではなく、企業体質の再構築と持続的な競争優位の確立を狙うものである。モノからコトへ、そして現場から社会全体へ──コマツは、産業の境界線を越える新たな価値創造企業へと進化している。
二刀流の脱炭素戦略:バッテリー内製化と水素燃料電池の協業モデル

コマツの脱炭素戦略は、単一技術への依存を避けた「デュアル・アプローチ(Dual Approach)」に特徴がある。すなわち、バッテリー電動化による垂直統合と、水素燃料電池による外部協業の両立である。これにより、エネルギー源の多様化と技術リスクの分散を同時に実現している。
まず、バッテリー電動化の要となるのが、米国のアメリカン・バッテリー・ソリューションズ(ABS)の買収である。2023年に実施されたこの買収により、コマツは大型リチウムイオンバッテリーを自社開発・製造できる体制を確立した。ABSは商用車や重機向けの高出力バッテリーで実績を持ち、ミシガン州・オハイオ州に最新鋭の生産拠点を保有している。これにより、コマツは電動鉱山機械のバッテリー設計から量産までを一貫して行う能力を獲得した。
この戦略は単なる技術開発ではなく、サプライチェーン全体の再構築を意味する。外部供給に依存していたキーコンポーネントを内製化することで、供給リスク・価格変動リスクの低減を実現し、さらに性能・安全性・熱管理などを自社最適化できるようになった。ABS製のバッテリーを搭載した電動鉱山機械は、まず北米・南米市場への投入を予定しており、脱炭素化需要の高い地域で市場優位を築く狙いである。
一方で、水素燃料電池の分野では、米ゼネラルモーターズ(GM)と共同開発を進めている。両社は、2MW(メガワット)以上の高出力を持つ「ハイドロテックパワーキューブ」を基盤とした燃料電池システムを鉱山用ダンプトラックに搭載する計画を発表した。燃料電池は軽量で補給が迅速なため、長時間稼働と積載量の確保が求められる鉱山機械に最適である。
特に鉱山車両は一つの鉱山で長期間稼働するため、水素ステーションの設置や供給ラインを限定的な範囲で整備でき、インフラ投資コストを最小化できる利点がある。GMが持つ燃料電池の量産ノウハウとコマツの重機開発力の融合により、実用化コストの大幅削減も見込まれている。
コマツの脱炭素技術アプローチ
| 技術領域 | 主なパートナー | 対象機種 | 特徴・戦略意義 |
|---|---|---|---|
| バッテリー電動化 | ABS(買収) | 建設機械・中型鉱山機械 | 内製化による供給安定と技術最適化 |
| 水素燃料電池 | GM(協業) | 大型・超大型鉱山ダンプ | 高出力・長稼働・迅速燃料補給を両立 |
この「内製化×協業」モデルは、脱炭素化競争が激化する中で他社との差別化要因となる。単一技術に賭けるのではなく、市場ごと・用途ごとに最適解を提供する柔軟な戦略こそが、次世代エネルギー市場での生存戦略である。
デジタルソリューションの深化:AHSとSmart Constructionの相乗効果
コマツが次世代の競争優位を築くもう一つの柱が、デジタルソリューションの拡張と統合である。同社は「AHS(無人ダンプトラック運行システム)」と「Smart Construction」を両輪とし、建設・鉱山現場の生産性と安全性を抜本的に高めている。
AHSは2008年に世界初の商用化に成功して以降、2025年時点で世界5カ国25鉱山に896台が導入されている。これにより、競合が容易に追随できない圧倒的な稼働データを蓄積しており、同データはAIによる予測保全や自律運転技術の学習に活用されている。これが、**「データ資本を基盤とした差別化戦略」**の中核をなしている。
さらに、AHSの進化系として、鉱山全体のオペレーションを最適化する「FMS(Fleet Management System)」の開発も進む。これは機械・設備・作業員の動きを統合的に管理し、最短ルートでの運搬や待機時間削減を実現するもので、生産性向上とGHG排出削減を同時に実現する仕組みである。
一方、建設現場向けのSmart Constructionでは、遠隔操作技術「Teleoperation」を核に、1人のオペレーターが複数台の建機を遠隔制御できる体制を構築した。これにより、危険区域での作業を安全に行いながら、労働力不足にも対応できる。ブラジルのAnglo American社との提携事例では、鉄鉱山の急斜面におけるICTブルドーザー遠隔操作の実証が進み、作業効率と安全性が飛躍的に向上した。
主要ソリューションの概要
| ソリューション | 技術内容 | 導入実績 | 効果 |
|---|---|---|---|
| AHS | 無人ダンプ運行制御 | 世界25鉱山・896台 | 安全性向上・燃費最適化 |
| FMS | 鉱山オペレーション統合管理 | 開発中(複数鉱山で実証) | 効率最適化・GHG削減 |
| Smart Construction Teleoperation | 遠隔建機操作 | 建設・鉱山現場で実装 | 労働力不足対策・安全確保 |
これらのデジタルプラットフォームは、単体で機能するのではなく、データを共有・統合することで現場全体の最適化を実現するエコシステムへと進化している。AIによる学習データが蓄積されるほど精度が高まり、利用企業にとっての付加価値が増大する「ネットワーク効果」も生まれている。
コマツが描く未来像は、単なる機械メーカーではなく、“データドリブンな現場最適化企業”としての地位確立である。AHSとSmart Constructionの融合は、世界のインフラ現場のデジタル化を先導する次世代産業モデルの象徴と言える。
サプライチェーンDXとAI経営基盤が生む経営レジリエンス

コマツの中期経営計画における最大の特徴は、AIとDXを中核とした経営インフラの再構築にある。従来の生産効率化を超え、サプライチェーン全体をデジタルで可視化・統合することで、地政学リスクや為替変動に強い経営構造を実現しようとしている。
近年、ウクライナ危機や中東情勢の不安定化、物流混乱などにより、重機メーカーは調達・生産・販売のあらゆる段階で不確実性に直面している。こうした状況下で、DXによる迅速な再構築能力こそが競争力の源泉となる。コマツはこのリスクを「機会」に転換すべく、AIを活用した経営基盤改革を加速させている。
AIと統合データ基盤による意思決定の高速化
コマツはグローバル全拠点の生産・販売・在庫データを一元管理する「統合データ基盤」を構築中である。この仕組みは、販売代理店や生産拠点のリアルタイムデータをAIが解析し、需要変動に応じた最適生産・物流計画を自動生成する。
これにより、材料調達から納入までのリードタイムを短縮し、突発的な市場変動にも迅速に対応できるようになる。特にアジアやアフリカなどの新興市場では、需給バランスの変化が激しいため、AI主導の需要予測モデルが経営の俊敏性と利益率の両立を支えている。
代理店プラットフォームによるデジタル連携
さらに、販売代理店向けのソリューションプラットフォームも刷新された。これは、代理店が顧客データ、メンテナンス履歴、部品需要などを即時に共有できるシステムであり、**現場情報を経営に直接反映させる「循環型データ構造」**を形成する。
この仕組みは、機械の稼働状況を監視する「Komtrax」と連携し、修理・保守・更新時期をAIが予測。部品在庫を自動調整することで、稼働率を最大化する。結果として、代理店・顧客・本社の三位一体型オペレーションが実現し、グローバルに均質なサービス品質を担保できるようになった。
レジリエンス経営への転換
このようなDXの進化は、単なる効率化にとどまらない。サプライチェーンの可視化は、為替変動や資材価格上昇、地政学リスクといった外的ショックへの即応力を高める。2025年度第1四半期には、調達コストの低下と物流改善によってセグメント利益が前年同期比で増益を達成しており、DX投資が実際の利益安定化に寄与していることが実証されている。
コマツのAI×DX戦略は、製造業の「データ経営化」の最前線を走るものであり、同時に地政学的変動をもビジネスチャンスに転じる強靭な企業体質を築きつつある。
1兆円FCF目標の意味:成長投資と株主還元の両立
コマツが掲げる「3年間で1兆円のフリー・キャッシュ・フロー(FCF)」という目標は、単なる数字ではない。これは、イノベーション投資・財務規律・株主還元を同時に成立させる企業体質への挑戦である。
FCFとは、事業活動によって得たキャッシュから設備投資などを差し引いた残余資金を指す。つまり、企業の「自己資金による成長能力」を示す指標である。コマツはこれを2025〜2027年度の3年間で累計1兆円とする目標を設定した。
投資と還元を両立する資本政策
この巨額のFCFは、電動化・DX・M&Aなどの戦略投資を外部資金に依存せずに実行できる体制を示す。特にABS買収などの大型案件を自己資金で賄うことは、資本コストを抑えつつ長期的な企業価値を最大化する戦略的判断である。
さらに、コマツは配当性向40%以上を維持しつつ、機動的な自己株式取得も実施する方針を明示。これにより、株主還元と内部留保をバランスさせた「安定かつ成長志向の財務政策」を展開している。
資本効率と成長性を両立させる仕組み
ROE(自己資本利益率)についても10%以上を継続目標とし、**資本効率を犠牲にせず成長投資を続ける「高収益循環モデル」**を構築している。リテールファイナンス事業ではD/Eレシオを6倍以下に緩和し、成長市場の販売機会を最大化する方針を打ち出した。
コマツの資本政策概要
| 項目 | 目標値・方針 | 意義 |
|---|---|---|
| FCF | 3年累計1兆円 | 自己資金での成長投資・還元の両立 |
| 配当性向 | 40%以上 | 安定的な株主還元の維持 |
| ROE | 10%以上 | 資本効率と成長投資の両立 |
| D/Eレシオ | 6倍以下 | 販売ファイナンス事業の柔軟化 |
財務戦略の持続可能性
コマツの財務体制は、短期利益の最大化ではなく、長期の企業価値創造に焦点を当てている。調達コストの削減や金利収入の増加など、収益安定化施策が実を結び、直近の決算では増益を達成した。
1兆円のFCF創出は、単なる目標ではなく、「自律成長できる財務エンジン」への転換宣言である。内部資金で研究開発・M&A・還元を循環させるこの構造こそ、外部環境に左右されない経営の持続性を担保するものであり、コマツの次なる成長段階の礎となる。
ESG経営と非財務KPIによる透明性強化
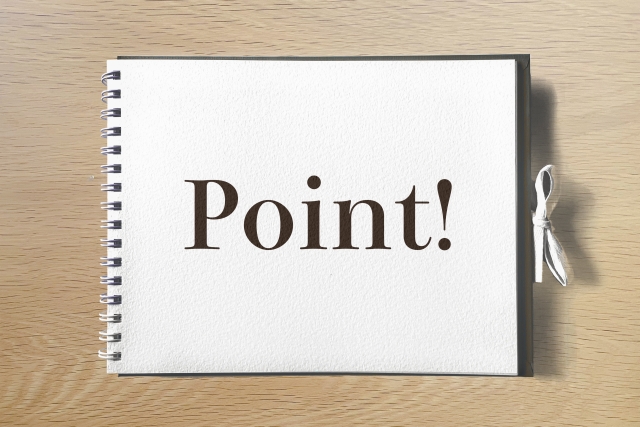
コマツは、財務指標だけでなく、ESG(環境・社会・ガバナンス)領域を企業価値創造の中核に据える経営改革を進めている。特に2025年度からの中期経営計画では、ESG活動を可視化するための「非財務KPI(重要業績評価指標)」を30項目設定し、サステナビリティ経営の定量化を明確に打ち出した。
この動きの背景には、グローバル投資家によるESG情報開示要求の高まりがある。欧州ではCSRD(企業サステナビリティ報告指令)が施行され、米国でもSECが気候関連開示を義務化する方向に動いている。こうした潮流の中で、ESGの透明性は資本市場における信頼性の核心指標となりつつある。
環境負荷低減への数値目標化
環境分野では、コマツは2030年にCO₂排出量を2010年比で50%削減、2050年にはカーボンニュートラルを実現する長期目標を掲げている。脱炭素技術への投資は、電動化や水素燃料電池に加え、再生可能エネルギーの導入、工場のエネルギー管理システム(EMS)最適化などにも及ぶ。
特に注目されるのは、グローバル全工場での再エネ比率の引き上げと、物流・生産のCO₂排出量削減である。2024年度時点で再エネ使用率は約40%に達しており、今後は主要拠点での太陽光発電自家消費モデルの導入により、さらなる拡大が見込まれている。
社会的価値創造と人材戦略
社会分野では、労働安全・ダイバーシティ推進・地域貢献を柱としたKPIを策定。特に「安全で生産性の高い現場」を実現するため、死亡災害ゼロ運動を全世界で展開している。また、女性管理職比率やグローバル人材登用率といった人材関連指標を定期開示し、持続的成長を支える人的資本経営の強化を進めている。
さらに、建設・鉱山分野における人材不足に対応するため、リモート操作や自律施工技術を活用した「安全教育プログラム」を展開。これは、現場での熟練度格差をデジタル技術で補完し、労働力不足と安全性を同時に解決する社会的価値創造の象徴といえる。
ガバナンスの高度化とIR戦略
ガバナンス面では、ダブル・マテリアリティ(財務・非財務両面の重要課題)に基づく経営体制を採用。監査・指名・報酬の各委員会を強化し、社外取締役比率を50%超に維持するなど、透明性と説明責任を重視するガバナンス構造を整備している。
また、非財務情報の開示に関しては、統合報告書にESG関連データを詳細に掲載し、投資家との対話を深化させている。これにより、ESG投資家からの信頼獲得と資本コスト低減の両立を図る姿勢が鮮明である。コマツのESG経営は、もはや「社会的責任」ではなく、企業価値を高める戦略的資本政策へと進化している。
技術・財務・ガバナンスが融合するコマツの次世代企業モデル
コマツの企業変革は、技術革新・財務戦略・ガバナンス体制の三要素を有機的に結び付ける点に最大の特徴がある。単なるモノづくり企業を超え、「データ×脱炭素×ガバナンス」で企業価値を創造する統合型モデルへと進化しているのである。
テクノロジー主導の持続的成長モデル
コマツの成長エンジンは、AHS(無人ダンプトラック運行システム)とSmart Constructionを中心とするデジタルソリューション群である。これらはAI・IoT・自動化技術を融合し、現場データを経営に直結させる「インテリジェントオペレーションモデル」を形成している。
さらに、バッテリー電動化と水素燃料電池の両軸による脱炭素戦略が、持続的な環境価値と市場優位性を同時に生み出している。こうした技術群は、製品そのものよりも「データと稼働情報」から利益を創出する構造を実現しつつある。
財務健全性と投資スピードの両立
3年間で1兆円のフリー・キャッシュ・フロー創出という目標は、自己資金による成長投資と株主還元の両立を意味する。外部借入に頼らずにイノベーション投資を継続できる点は、財務の健全性と成長速度の両方を確保する稀有な事例である。
また、調達コストの最適化とサプライチェーンDXの成果により、為替変動などの外部要因を吸収しながら安定した収益構造を維持している。これにより、短期利益に偏らない「長期的企業価値の創造」が可能になっている。
統合的経営による未来志向型企業像
ESG指標の明確化、AI基盤の構築、財務規律の徹底──これらを一体化することで、コマツは「技術と資本と倫理」を融合させた新しい企業モデルを提示している。その結果、社会的課題と経済的利益の両立を図る「価値共創型経営」が実現している。
この構造的変革は、建設・鉱山機械業界にとどまらず、製造業全体における持続可能な経営のベンチマークとして注目を集めている。脱炭素とデジタルの交差点に立つコマツは、テクノロジーとガバナンスの融合によって、次世代の産業構造そのものを再定義する企業へと進化しつつある。

